
「悪質クレーマーなどへの対応で接客スタッフのストレスがたまり、皆かなり疲れているように見える。どう対処すればいいんだろう?」
あなたは接客業務から生じる自社スタッフの精神的な疲労をなんとかしたいと思っているのかもしれませんね。
サービス業など直接人と接する仕事に要求されるのが「感情労働」です。例えば、体に不調がある場合でも、笑顔で接客しなければならないなど、文字通り自分の感情をコントロールしながら業務にあたらねばならない仕事を指します。
この記事では、感情労働の詳しい定義、感情労働が必要な職種、感情労働が引き起こす問題とその対処法などについてお伝えしていきます。
1.感情労働とは

感情労働とは、アメリカの社会学者であるA・R・ホックシールドが提唱した概念で、仕事をするうえで常に自分の感情をコントロールすることが求められ、我慢したり、明るくふるまわねばならない働き方を指します。
感情労働において求められるのは、表面上、相手に好まれる表情や仕草をすることです。一方で、相手にとって好ましく見えるように、怒りや悲しみといった負の感情は抑え、喜びや楽しみといった明るく前向きな感情を表現するなど、自分自身の感情をコントロールする必要があります。そしてそれにより報酬を得ます。
肉体労働や頭脳労働と並ぶ労働のカテゴリーの一種とされています。
2.感情労働が必要な職種
一般に感情労働が多い職種は、3次産業(サービス業)に分類されます。なかでも特に割合が多いと思われる職業を紹介します。

2-1. 接客業
接客業やサービス業は顧客である他人と接してサービスを提供することで報酬を得ます。そこでは顧客を満足させる態度や仕草が求められ、感情労働の割合が高くなります。
2-2. 客室乗務員
感情労働という言葉が使われるようになってから、その代表的な職業として挙げられてきた客室乗務員ですが、その業務においては、狭い空間で長時間にわたり乗客からの無理な要求にも笑顔で対応しなくてはなりません。
2-3. テレフォンオペレーター
クレーム対応などで、なんらかの不満やトラブルを抱えた顧客に対応することが多い職種です。ネガティブな感情を持った人を相手にすることから、精神的な負担が大きくなります。また、表情や仕草が使えないので、他の職種と比べて表現できることの幅が狭く、それもストレスの原因にもなります。
2-4. 看護師や介護士
病院の患者や福祉サービスの利用者またはその家族などは、専門的な技能とともに接する職員の応対も評価の対象にします。看護師や介護職の人には専門的な知識、十分な体力も必要であり、頭脳、肉体、そして感情という3つの労働カテゴリーすべてに当てはまる職業です。
2-5. 教師や講師
学校教育などでは、生徒である子供はもちろん、その親への対応も重要です。近年では保護者からのクレームにも対応せねばならない場面も多く、感情を多く使う仕事の割合が増えています。
3.社内の人間関係にも感情労働は発生する

対外的な労働だけでなく、社内で上司や同僚に対して過剰な気遣いをせねばならない場合も感情労働に含めるケースがあります。
例えば、上司からパワハラやセクハラまがいのことをされても毅然とした態度で抗議できなかったり、機嫌を損ねるのがこわくて自分の意見をはっきりと言えなかったりといったケースがそれに当たります。
特に女性の場合は、お茶くみをするのが当然と思われたり、いつも明るく笑顔でいることを望まれたり、「女らしく」丁寧な仕事をするよう期待されたりという場面がまだまだ多いのが実情です。
職場で女性であるがゆえに我慢したり、軽んじられることに耐えなくてはいけない場面があるとしたら、それも感情労働です。
4.感情労働により引き起こされがちなメンタルの問題

感情労働に従事する労働者は、自身の感情をコントロールして、顧客を不快な気分にさせないように常に笑顔で接したり、相手を立てたりすることを期待されます。
仮に顧客から理不尽な要求をされたり、屈辱的な言葉をかけられたりしても、労働者は感じた怒りをそのまま表現することは許されず、反対にそのネガティブな感情を抑えて顧客と接することを期待されます。
感情を無理にコントロールすることで、労働者には大きな精神的な負担がかかります。抑圧状態が長く続くことで、バーンアウト(燃え尽き症候群)やうつ病、アルコール依存症、ギャンブル依存症などさまざまな病状に悩まされる人も少なくありません。
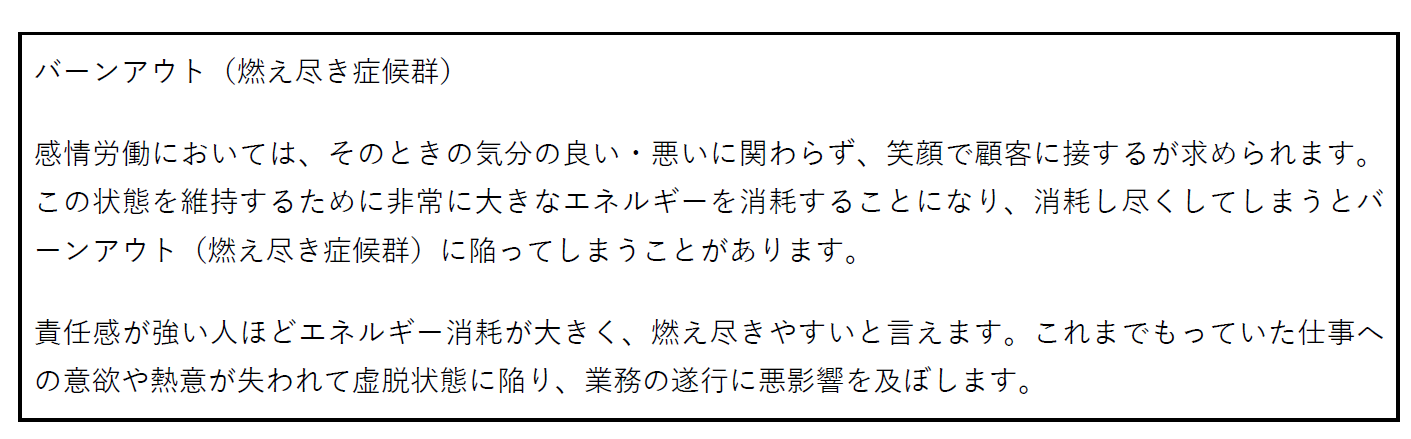
5.感情労働が引き起こす問題への対処法

感情労働が労働者のメンタルヘルスに悪い影響を及ぼさないよう企業サイドが講じるべき対策と、労働者サイドが取り入れたい対処法があります。
5-1. 企業が行うべき対処法
感情労働の多い職種はもちろんのこと、そうでない職種であっても、先に書いた通り感情労働は存在します。よって、組織全体として、感情労働によるメンタル面の不調を出さないような施策を講じたり、また出てしまった場合の従業員のケアについて対処する必要があります。
精神面で不調を抱えた労働者がいると、企業としての生産性や収益性にも影響を及ぼします。感情労働対策は、社員に対する福利厚生が第一ですが、事業に貢献する取り組みとしても大切な要素です。
5-1-1. ストレスチェック制度を導入する
メンタルの不調を未然に防ぐために、全従業員を対象としたストレス状況のチェックをする機会をもうけます。そこで問題を抱えた人がわかれば、すみやかにケアを行うようにします。
日本では、2015年12月に労働安全衛生法の一部が改正され、50人以上の労働者を抱える事業所で年1回のストレスチェック実施が義務付けられました。実施しなくても罰則はありませんが、労働安全衛生法第100条で労働基準監督署への報告が義務付けられています。
ストレスチェック制度では、事業者に対して以下の3つの事柄について義務づけています。
①ストレスチェックの実施
事業者は、従業員に対して、医師、保険師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を定期的に実施しなければなりません。
ストレスチェックを実施することで、企業は労働者のストレス状況について把握することができ、労働者自身も自らのストレス状況について理解することができ、対処に役立てることができます。
なお、厚生労働省が提供している職業性ストレス簡易調査票(57項目) は以下よりダウンロードしていただけます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/dl/stress-check_j.pdf
また、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が事業者にて円滑に導入できるよう、厚生労働省が「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料で配布しています(囲み記事参照)。
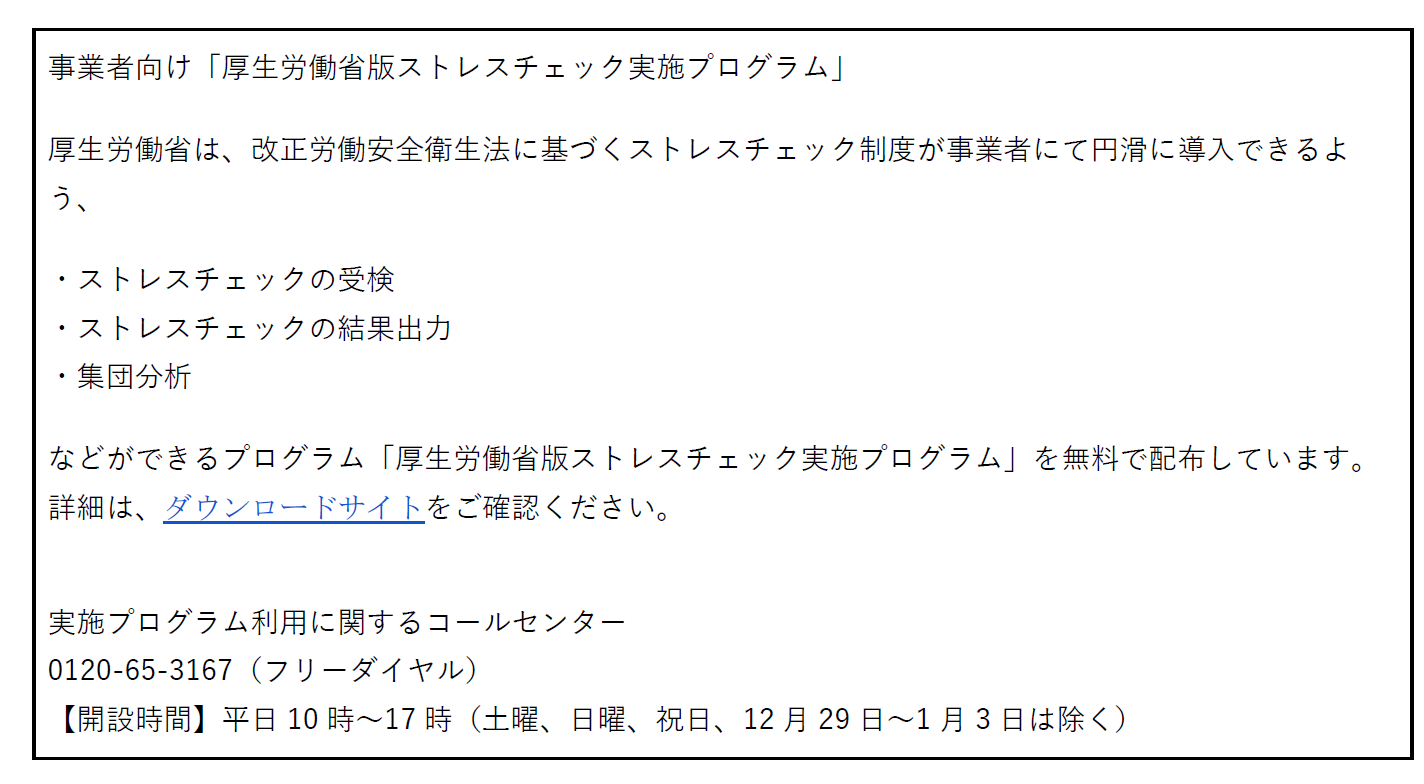
②結果に基づく医師の面接指導
ストレスチェックの結果、「高ストレス」などの要件に該当し、労働者から申し出があった場合は、医師の面接指導を実施しなければなりません。事業者は医師の意見を聞いた上で、必要に応じて勤務時間を制限するなど就業上の措置を講じなければなりません。
③結果の集団ごとの集計・分析(努力義務)
事業者は、ストレスチェックの結果を受けて、職場のストレス状況、その他の職場環境から、改善の必要性が認められる場合には、集団ごとに分析を実施し、その結果に基づいて職場環境の改善に取り組むことも努力義務とされています。
なお、ストレスチェック制度の詳細については、以下のサイトをご覧ください。
厚生労働省:ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
こころの耳:ストレスチェック制度について
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/#head-1
5-1-2. アンガーマネジメント研修などを導入する
ストレスをためていないかどうかを確認することも大切ですが、ストレスを蓄積しにくい考え方を身につけることも大切です。その方法の一つが アンガーマネジメントです。
アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで生まれたとされる、怒りの感情と上手に付き合うための心理教育、心理トレーニングです。怒らないことを目的とするのではなく、怒る必要のあることはうまくその気持ちを相手に伝えることができ、怒る必要のないことには怒らなくてもすむようになることを目標としています。
アンガーマネジメントのスキルを身につけると、以下のようなメリットが得られます。
- 価値観の多様性に対して寛容になれる
- 怒りの感情をうまくコントロールできるようになり、モチベーションの維持・向上に役立つ
- 怒りの原因を整理して適切に対処できるようになる
- 自分の怒りを相手が納得しやすい表現で伝えられるようになる
従業員にストレスを溜めないスキルを身につけてもらうために、アンガーマネジメント研修を導入するのも良いでしょう。
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会では、個人向けの講座とともに、アンガーマネジメントの企業研修も行なっています。詳細は下記の協会サイトをご覧ください。
一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会
https://www.angermanagement.co.jp/training
5-1-3. ワークライフバランスを実現する
ワークライフバランスとは、仕事とプライベートとの調和のことであり、上手に両者のバランスをとることで健康で豊かな生活を目指します。
ワークライフバランスという概念のもとでは、次のような社会を目指します。
①働く機会を得て経済的自立が可能な社会
②健康で豊かな生活のための時間を持てる社会
③多様な働き方や生き方を選べる社会
企業においては、特に②③が大切になってきます。
それでは、ワークライフバランスを推進するために企業取り組むべきこととは何なのでしょうか?
①業務の標準化を図り無駄な作業を減らす
無駄な業務を整理するためには、業務内容を見直して、社員のスキルや能力に応じて適切な仕事を割り振ることが大切です。また、特定の社員以外でも対応ができるように業務のマニュアルを作成するなどして業務の標準化を進めるとよいでしょう。
②生産性を高めて労働時間を短縮する
長時間労働は、従業員の生産性を低下させ、モチベーション低下による離職につながる恐れもあります。一方、企業にとっては、長時間労働と生産性が比例しなければ、コストが増加します。このような長時間労働によるリスクを小さくするには、時間当たりの労働生産性を高める工夫が必要です。
労働生産性を高めるには、従業員の仕事量を見直して適切な業務分担を行うことが有効です。それにより無駄な残業を無くし、仕事以外の時間を充実させることで身に付けたスキルやアイデアなどを仕事で発揮してもらえば、生産性向上に貢献します。
③フレックスタイムの活用で働き方の柔軟性を高める
フレックスタイム制を導入している場合は、フレキシブルタイムをうまく活用することで働き方の柔軟性を高めて、仕事と質の高い生活との両立を図ることができます。例えば、子供や被介護者の送り迎えが無理なくできたり、通勤ラッシュを避けられるほか、自己研鑽を行うなどプライベートとの両立が無理なく実現できます。
④テレワークの導入で働き方の幅を広げる
テレワークは、情報通信端末を利用してオフィス以外の場所で業務を行うことです。在宅勤務、モバイルワーク、施設利用型勤務の3形態があり、これらの導入によって時間や場所に縛られずに業務を進めることができるようになるため、働き方の幅がグンと広がります。ただし、導入にあたっては、職場のチーム内で業務が円滑に進められるように工夫することが必要です。
5-1-4. 顧客の声や社内の良いニュースを共有する
感情労働は、顧客満足追求のために行っている側面があります。よって、自分の行いが顧客満足につながったのか、自社は顧客にどう評価されているのかについての顧客からの声を知ることは、自身の行った業務に対する一番のフィードバックになります。
また、会社における従業員の良い行いなどをニュースとして社内に共有したり、お互いがほめ合う仕組みなどを取り入れることで、さらに仕事のやりがいを見つけられる機会が増えるでしょう。
社員同士で感謝を贈り合うことで働きがいを向上させる〜Unipos(ユニポス)のご紹介〜

(出典:https://unipos.me/)
Uniposは、従業員同士がスマートフォンやパソコンで、日頃の仕事の成果や行動に対しての感謝や賞賛するメッセージとともに、ポイントを送りあえるウェブサービスです。ポイントは、成果給(ピアボーナス®)として従業員に還元する他、Amazonギフト券やお菓子など各社自由な形でご設定いただけます。
Uniposは従業員エンゲージメントや働きがいを高めます〜そのメリット〜

Uniposの特徴
①全員が見るオープンなタイムライン
リアルタイムに賞賛の言葉が全社にシェアされます。オープンな場で個人の貢献が可視化され、働きがいやモチベーションアップにつながります。
②気楽にエールを送れる拍手
共感する投稿に拍手をすることで気軽にエールが送れます。個人の貢献を共に喜び合う組織カルチャー醸成につながります。
③行動指針を浸透させるハッシュタグ
投稿に行動指針やバリューをハッシュタグを紐づけることができ、賞賛される行動内容が可視化されることで、企業の価値観浸透に役立ちます。
Unipos公式サイト
5-2. 個人が行うべき対処法
以上、企業サイドが行うべき施策について紹介しましたが、こちらでは個人で行うストレス対処法をお伝えします。
5-2-1. ネット上のストレスチェックを受ける
個人でできるストレス対策としてまず挙げられるのは、自分のストレス耐性がどれくらいのものなのかをチェックするためにインターネット上の診断テストを受けるということです。
現在では、ネット上でさまざまなチェックリストや無料でできる診断テストが公開されています。これらを活用すれば、自分がどれだけストレスに抗える力を持っているのかを知ることができます。
以下は株式会社ジャパンEPAシステムズが提供している「ストレス度チェック(不知火式)」です(計40問)。ご自身の今のストレス度合いが無料で判断できますので、ぜひご活用ください。
https://www.jes.ne.jp/self-check/stress.html
5-2-2. ストレスを解消する
診断テストによってストレスの度合いが高いと出た場合、ストレスを発散させる必要があります。
まずすべきことは、仕事を忘れて他のことに没頭できる時間を作ることです。多忙な方やストレスを蓄積しやすい仕事の方こそ、そういう時間を確保することが大切です。
仕事を忘れる時間が確保できたら、その時間を自分の感情が開放されることに使います。
例えば、
- 好きなスポーツをして思いきり体を動かす
- 趣味に没頭して楽しむ
- 旅行に出てリフレッシュする
- マッサージや入浴などでリラックスする
- 無理に何かをするのではなく良質な睡眠や十分な休養をとる
以上のような時間にします。これらの行為がストレスを緩和します。仕事をしているときとは違って感情を抑制しないことがポイントです。
5-2-3. 常に完璧を目指さない
ストレスを溜め込みやすいタイプは完璧を目指す方が多いという傾向があります。
しかし、どのような仕事であれ失敗はつきもの。「完璧にできなかった」と深く落ち込むと、感情労働の際に精神により強く負荷がかかり、精神が不安定な状態となります。完璧を求めずに働くことは心身の健康を守ることにつながります。
また、感情労働をする場所と時間を決めてしまうという方法もあります。「感情労働をする場」を離れたら、感情労働からも離れられるという状況をつくるのです。そうすることで感情労働に過剰に振り回されなくてすみます。
6.職場で起きた感情労働についての相談先

感情労働に従事する従業員に対するケアの一環としてカウンセラーを設置する企業も増えています。しかし、なかなか専従者を設置することは難しいもの。そこで、感情労働を強制されている、パワハラまがいの指導を受けているといった職場での問題で困ったときは、公的な機関の利用をおすすめします。
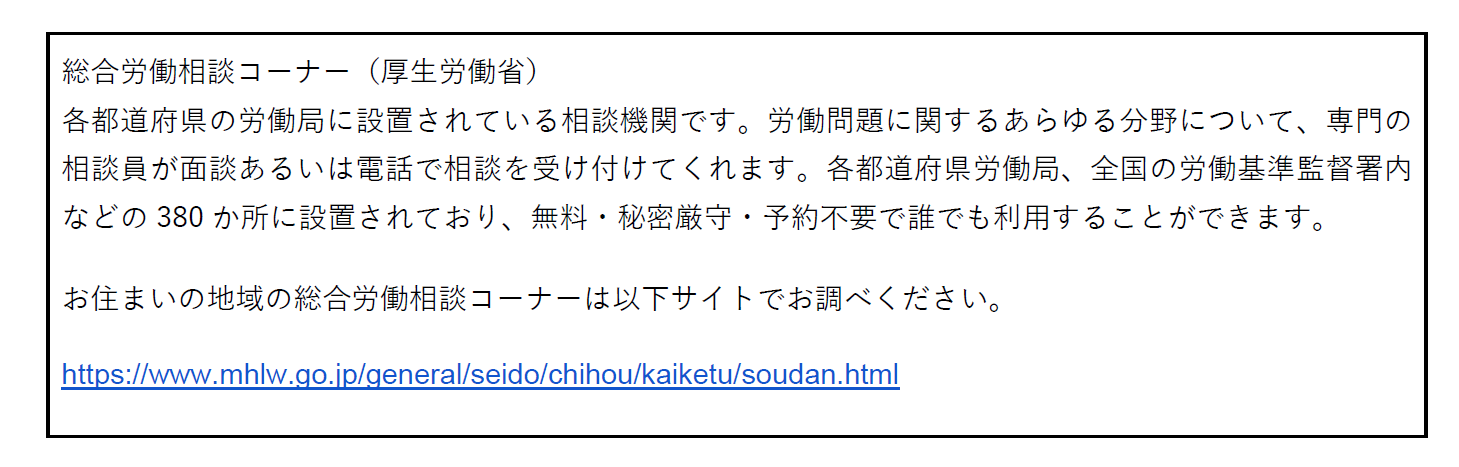
まとめ
最後に、感情労働の定義を再度確認しておくと、「仕事をするうえで常に自分の感情をコントロールすることが求められ、我慢したり、明るくふるまわねばならない働き方」のことでしたね。
感情を無理にコントロールすることで、労働者に大きな精神的な負担がかかり、抑圧状態が長く続くことで、バーンアウト(燃え尽き症候群)やうつ病、アルコール依存症・ギャンブル依存症などのさまざまな病気や症状に悩まされる人が出てくるのは見てきた通りです。
こういった感情労働が引き起こす諸問題への対処法としては、以下がありました。
企業が行うべき対処法
- ストレスチェック制度を導入する
- アンガーマネジメント研修などを導入する
- ワークライフバランスを実現する
- 顧客の声や社内の良いニュースを共有する
個人が行うべき対処法
- ネット上のストレスチェックを受ける
- ストレスを解消する
- 常に完璧を目指さない
感情労働は特定の職種だけに生じるものではなく、社内の業務や人間関係においても生じる労働です。
現代では誰もが感情労働の強いストレスにさらされているわけですから、しっかりと対策を講じておきたいものですね。
この記事が有効な感情労働対策を検討するお役に立てば幸いです。


