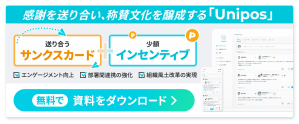やる気のない社員の特徴とは

やる気のない社員は、職場でどのような特徴を示すのでしょうか。
一般的に、やる気のない社員は、以下の4つの特徴が挙げられます。
①無気力で覇気がない
やる気のない社員の特徴として、最もよく挙げられるのが、無気力で覇気がないということです。仕事に意欲的ではなく、やる気が感じられません。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 仕事のスピードが遅い
- 仕事への責任感が薄い
- 積極的に仕事に取り組もうとしない
無気力で覇気がない人は、仕事に対するモチベーションが低下している可能性があります。仕事のやりがいや目標が見いだせていない、仕事の環境や人間関係に問題がある、心身の不調を抱えているなど、さまざまな原因が考えられます。
②会社や周りの人の愚痴や文句、批判ばかり言う
やる気のない社員は、会社や周りの人の愚痴や文句、批判ばかり言う傾向があります。自分の仕事や成果に対する不満、上司や同僚に対する不満などを、周囲に吐露します。
会社や周りの人の愚痴や文句、批判ばかり言う人を改善するためには、まずその原因を特定することが重要です。
③言われた仕事の最低限のことしかやらない
やる気のない社員の特徴として、よく挙げられるのが、言われた仕事の最低限のことしかやらないということです。仕事に積極的に取り組まず、指示されたこと以外は何もしません。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
-
指示された仕事以外のことは一切やらない
-
指示された仕事も最低限の労力で済ませようとする
-
仕事に責任感がなく、ミスをしても反省しない
言われた仕事の最低限のことしかやらない人は、仕事に対するモチベーションが低下している可能性があります。
④仕事が雑でミスが多く、人のせいにする
やる気のない社員は、仕事の成果に責任感がありません。仕事で失敗しても、自分のせいだと認めようとせず、他人や環境のせいにします。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
-
仕事の段取りが悪く、ミスを頻発する
-
ミスしても反省せず、言い訳ばかりする
-
ミスを人のせいにする
仕事が雑でミスが多く、人のせいにする人を改善するためには、まずその原因を特定することが重要です。
やる気のない社員の本心と原因

やる気のない社員は、仕事に対するモチベーションが低下している可能性があります。その本心や原因を理解することは、やる気を取り戻し、組織に貢献できる人材に成長させていくために重要です。
やる気のない社員の本心は、大きく分けて以下の4つが挙げられます。
①目標設定が高すぎるから
目標設定が高すぎることは、やる気のない社員の大きな原因の一つです。
目標設定が高すぎると、以下のようなことが起こります。
・達成が困難で、達成感や自信が得られない
・目標達成のために過度な努力やストレスを強いられる
・目標達成が難しいことにより、仕事に意味を見いだせず、やる気が失われる
目標設定が高すぎると、社員は達成が難しいことに不安や焦りを感じ、やる気を失ってしまいます。
また、目標達成のために過度な努力やストレスを強いられることで、心身に不調をきたし、やる気が失われることもあります。
さらに、目標達成が難しいことにより、仕事に意味を見いだせず、やる気が失われることもあります。
目標設定が高すぎると、このようにさまざまな悪影響を及ぼすため、注意が必要です。
②仕事で良い結果が出ないから
仕事で良い結果を出せないと、社員は達成感や自信が得られず、やる気を失ってしまいます。
また、自分の能力や将来に不安を感じ、周囲からの評価が得られず、仕事で良い結果を出せないと、このようにさまざまな悪影響を及ぼすため、注意が必要です。仕事で良い結果を出すためには、まず社員の能力や経験、状況などを把握し、適切な指導やサポートを行うことが重要です。
また、社員が仕事に意欲的に取り組めるように、仕事のやりがいや意味を感じられるようにすることも大切です。仕事で良い結果を出すことで、社員のやる気を引き出し、モチベーションの向上につなげることができます。
③頑張っても報われないから
頑張りが報われないと、社員は努力や成果が認められないことに不満や無力感を感じ、やる気を失ってしまいます。
頑張りが報われないと、以下のようなことが起こります。
- 努力や成果が認められず、やる気が失われる
- 自分の能力や将来に不安を感じ、やる気が失われる
頑張りが報われないと、自分の能力や将来に不安を感じ、やる気を失ってしまうこともあります。
さらに、仕事に対するモチベーションが下がり、やる気を失ってしまうこともあります。
このようにさまざまな悪影響を及ぼすため、注意が必要です。
頑張りが報われるためには、まず社員の努力や成果を適切に評価し、フィードバックすることが重要です。
また、社員が仕事にやりがいを感じられるように、目標や評価制度を明確にすることも大切です。
頑張りが報われることで、社員のやる気を引き出し、モチベーションの向上につなげることができます。
④評価されず、待遇が悪いから
評価されず、待遇が悪いことも、やる気のない社員の大きな原因の一つです。社員は自分の能力や貢献が認められないことに不満や無力感を感じ、仕事に対するモチベーションが下がりやる気を失ってしまいます。
例えば、以下のようなことが起こります。
- 自分の能力や貢献が認められず、やる気が失われる
- 自分の将来に不安を感じ、やる気が失われる
- 仕事に対するモチベーションが下がり、やる気が失われる
評価されず、待遇が悪いと、このようにさまざまな悪影響を及ぼすため、注意が必要です。
評価され、待遇が良くなると、社員のやる気を引き出し、モチベーションの向上につながることができます。
具体的には、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
- 社員の努力や成果を適切に評価し、フィードバックすること
- 昇進や昇給などの形で、社員の貢献を報いること
- 福利厚生や待遇を充実させること
評価され、待遇が良くなると、社員は自分の能力や貢献が認められ、自分の将来に安心感を抱き、仕事に対するモチベーションを高めることができます。
なお、評価や待遇は、社員のやる気を高めるためには重要な要素ですが、それだけがすべてではありません。
仕事のやりがいを感じたり、職場の人間関係を良好に保ったりすることも、社員のやる気を高めるためには大切なことです。
Uniposは、従業員同士が「貢献に対する称賛×少額のインセンティブ」を送り合うピアボーナス®の仕組みを使って「組織を変える行動を増やす」webサービスです。
Uniposを導入することで、社員の頑張りを可視化し、称賛しやすくなります。
やる気のない社員を改善する4つの施策

やる気のない社員を抱えている企業は少なくありません。やる気のない社員は、仕事のパフォーマンスが低下したり、職場の雰囲気を悪化させたりするため、早急な改善が求められます。
①コミュニケーションのあり方を見直す
コミュニケーションが不足すると、社員同士の信頼関係が築けず、仕事のやりがいやモチベーションが低下します。定期的な1on1ミーティングを実施したり、社内SNSやチャットツールを活用したりすることで、社員同士のコミュニケーションを活性化させましょう。
②定期的な1on1の実施で社員の悩みや不安を聞く
1on1ミーティングは、上司と部下が1対1で面談を行うことで、仕事の進捗状況や課題、キャリアプランなどを話し合う機会です。1on1ミーティングを定期的に実施することで、上司と部下間の信頼関係を築き、仕事に対するモチベーションを高めることができます。
③社員のつながりを深める、コミュニケーションツールの活用
社員のつながりを深めるためには、コミュニケーションツールの活用が有効です。コミュニケーションツールを活用することで、社員同士が気軽にコミュニケーションをとることができ、信頼関係を築き、仕事のやりがいやモチベーションを高めることができます。
④社員の頑張りを評価し、称賛する文化をつくる
社員の頑張りを評価し、称賛する文化をつくることは、組織の活性化に欠かせません。「日々の仕事を認められている実感」が得られ、従業員の挑戦・貢献意欲を高め、仕事のやりがいを向上させます。また、社員同士のコミュニケーションも活性化し、職場の雰囲気を明るくします。
Uniposのピアボーナスを活用することで、社員の頑張りを可視化し、称賛しやすい環境を整え、称賛の文化を浸透させることができます。
社員の頑張りを評価し、称賛する文化をつくるためには、社員の頑張りを可視化し、称賛しやすい環境を整え、称賛の文化を浸透させることが重要です。Uniposのピアボーナスを活用することで、これらを実現することができます。
Uniposを導入した企業では、以下のような効果が得られています。
- 社員のモチベーションが向上した
- 仕事のやりがいが高まった
- 職場の雰囲気が明るくなった
- 離職率が低下した
Uniposの導入を検討することで、社員の頑張りを評価し、称賛する文化をつくることができ、組織の活性化につなげることができます。
やる気のない社員を減らすために!事業プランの見直し

やる気のない社員を減らすためには、事業プランを見直すことが有効です。事業プランが明確で、社員一人ひとりが自分の仕事がどのように貢献しているのかを認識できていれば、仕事に対するモチベーションを高めることができます。
社員の意見を積極的に反映する
社員の意見を積極的に反映することで、社員が会社に対して主体性や帰属意識を持つことができます。社員の意見を反映するためには、以下の方法を検討しましょう。
- 社員アンケートやヒアリングを実施する
- 社内ワークショップやプロジェクトを開催する
- 社員の意見を反映するための仕組みを構築する
社員の意見を反映することで、事業プランがより社員にとって納得感のあるものになり、やる気のない社員を減らすことにつながります。
具体的な事例
ある企業では、社員アンケートやヒアリングを実施し、社員の意見を事業プランに反映しました。その結果、社員のモチベーションが向上し、やる気のない社員が減少したという効果が得られました。
やる気のない社員を減らすためには、事業プランの見直しを検討しましょう。その際には、社員の意見を積極的に反映することが重要です。
社員の目標達成を支援するための研修やOJTを実施
やる気のない社員を減らすためには、事業プランの見直しを行うとともに、社員の目標達成を支援するための研修やOJTを実施することも有効です。社員が自分の目標を達成できれば、仕事に対するやりがいを高めることができます。
研修やOJTを実施する際には、以下のポイントを押さえましょう。
- 社員の目標を明確にする
- 社員のスキルや能力を把握する
- 社員のニーズに合わせた研修やOJTを実施する
社員の目標を明確にする
社員の目標を明確にすることで、研修やOJTの目的を明確にすることができます。社員の目標を明確にするためには、以下の方法を検討しましょう。
- 社員と面談を行い、目標をヒアリングする
- 社員に目標設定シートを記入させる
- 社員の目標をチームや部門の目標と連動させる
社員のニーズに合わせた研修やOJTを実施する
社員のニーズに合わせた研修やOJTを実施することで、社員の満足度を高めることができます。社員のニーズを把握するためには、以下の方法を検討しましょう。
- 社員アンケートやヒアリングを実施する
- 社員の職務経歴やスキルシートを分析する
- 社員のOJT担当者にヒアリングする
研修やOJTを実施することで、社員の目標達成を支援し、やる気のない社員を減らすことにつながります。
具体的な事例
ある企業では、社員の目標達成を支援するために、社員一人ひとりに目標設定シートを記入してもらい、目標達成に必要な研修やOJTを実施しました。その結果、社員のモチベーションが向上し、やる気のない社員が減少したという効果が得られました。
やる気のない社員を減らすためには、事業プランの見直しとともに、社員の目標達成を支援するための研修やOJTを実施することも重要です。
評価制度を見直す
やる気のない社員を減らすためには、評価制度を見直すことも有効です。評価制度が明確で、社員が納得できるものであれば、仕事に対するモチベーションを高めることができます。
評価制度を見直す際には、以下のポイントを押さえましょう。
- 評価の基準を明確にする
- 評価の公平性を確保する
- 評価結果をフィードバックする
評価の基準を明確にする
評価の基準が明確になっていないと、社員は自分の成果がどのように評価されるのかがわかりません。評価の基準を明確にすることで、社員は自分の目標を達成するために何をすべきかを理解し、モチベーションを高めることができます。
評価の基準を明確にするためには、以下の方法を検討しましょう。
- 評価項目を明確にする
- 評価項目の重み付けを明確にする
- 評価基準を社員に周知する
評価の公平性を確保する
評価の公平性が確保されていないと、社員は評価制度に不満を抱き、やる気を失う可能性があります。評価の公平性を確保するためには、以下の方法を検討しましょう。
- 評価者を複数にする
- 評価方法を多様化する
- 評価結果を定期的に検証する
評価結果をフィードバックする
評価結果をフィードバックすることで、社員は自分の成果を把握し、改善点を見つけることができます。評価結果をフィードバックするためには、以下の方法を検討しましょう。
- 評価者から直接フィードバックを受ける機会を設ける
- 評価結果を社員に開示する
- 評価結果をフィードバックするための仕組みを構築する
評価制度を見直すことで、社員のモチベーションを向上させ、やる気のない社員を減らすことにつながります。
具体的な事例
ある企業では、評価制度を見直し、評価の基準を明確にし、評価の公平性を確保しました。その結果、社員のモチベーションが向上し、やる気のない社員が減少したという効果が得られました。
やる気のない社員を減らすためには、評価制度を見直すことも重要です。評価制度の見直しを検討する際には、上記のポイントを参考にしましょう。
社内SNSやチャットツールを活用
やる気のない社員を減らすためには、社内SNSやチャットツールを活用することも有効です。社内SNSやチャットツールを活用することで、社員同士のコミュニケーションを活性化し、仕事に対するモチベーションを高めることができます。
社員のニーズを把握することで、社員にとって使いやすいツールを選ぶことができます。社員のニーズを把握するためには、以下の方法を検討しましょう。
- 社員アンケートやヒアリングを実施する
- 社員の意見を反映するための仕組みを構築する
社内SNSやチャットツールを活用することで、社員同士のコミュニケーションを活性化し、やる気のない社員を減らすことにつながります。
具体的な事例
ある企業では、社内SNSを導入し、社員同士のコミュニケーションを活性化しました。その結果、社員のモチベーションが向上し、やる気のない社員が減少したという効果が得られました。
やる気のない社員を減らすためには、社内SNSやチャットツールを活用することも重要です。社内SNSやチャットツールの導入を検討する際には、上記のポイントを参考にしましょう。
やる気のない社員を改善し、組織活性化へ

やる気のない社員を改善し、組織活性化を図るためには、コミュニケーションが鍵となります。Uniposを活用することで、社員同士のコミュニケーションを活性化し、やる気のない社員を改善し、組織活性化を図ることができます。
Uniposは感謝や称賛・激励の気持ちを伝えやすくし、チームの心理的安全性を高めます。
Uniposを活用することで、以下のような効果が期待できます。
- 社員の頑張りや貢献を可視化することで、称賛しやすい環境を整える
- 社員のモチベーションを高め、仕事のやりがいを向上させる
- 職場の雰囲気を明るくし、コミュニケーションを活性化する
Uniposを導入することで、社員同士のコミュニケーションを活性化し、やる気のない社員を改善し、組織活性化を図ることができます。
まとめ
やる気のない社員がいると、組織全体の活力が低下します。やる気のない社員を改善し、組織活性化を図るためには、以下のポイントが重要です。
- やる気のない社員の原因を特定する
やる気のない社員には、さまざまな原因があります。心身の不調や家庭の事情など、個人的な原因が考えられます。また、仕事のやりがいや目標が見い出せないなど、仕事上の原因が考えられます。やる気のない社員の原因を特定することで、適切な対策を講じることができます。
- やる気を引き出すための環境を整える
やる気のない社員は、仕事に対するモチベーションが低下しています。そのため、やる気を引き出すための環境を整えることが重要です。具体的には、以下の施策が考えられます。
- 社員一人ひとりに寄り添う
やる気のない社員には、一人ひとりに事情があります。そのため、社員一人ひとりに寄り添い、理解しようとすることが重要です。具体的には、以下の施策が考えられます。
* 面談や1on1ミーティングを実施する
* 社員の声を反映する仕組みを構築する
* メンター制度やコーチング制度を導入する
コミュニケーションが鍵
やる気のない社員を改善し、組織活性化を図るためには、コミュニケーションが鍵となります。社員同士がコミュニケーションをとることで、お互いの理解が深まり、仕事のやりがいや目標を見いだしやすくなります。
これらのポイントを踏まえて、コミュニケーションを活性化することも有効です。Uniposなどのピアボーナス®を活用することで、社員同士のコミュニケーションを活性化し、やる気のない社員を改善し、組織活性化を図ることができます。