
近年は、働き方改革や新型コロナウィルスの影響により、多様な雇用のあり方が模索されるようになりました。
その一つが、大手企業を中心に導入が進む「ジョブ型雇用」です。
「名前は聞いたことがあるけど詳しい特徴を知らない」という企業担当者も多いのではないでしょうか。今回は、注目を集める「ジョブ型雇用」について、基礎知識からメリット・デメリット、注意点や具体的な導入事例などを幅広く解説していきます。
欧米で普及する「ジョブ型雇用」とは?

ジョブ型雇用とは、業務を細分化・明確化し、個々の業務に対して必要な能力を持っている人を採用する雇用形態のことです。
業務の内容や必要なスキル、勤務地といった労働条件を明確に定めた「職務記述書(ジョブディスクリプション)」を作成し、その条件に見合う人材を探します。
例えば、関東地方限定の営業職として採用された場合、マネジメントや事務など営業以外の業務には携わらず、関東以外の地域への転勤もありません。何年も同じエリアで営業の業務のみをこなし、営業スキルを高めていくことになります。
このように、求人の時点で具体的な業務内容や勤務地などを明確に提示し、「仕事に人を割り振る」スタイルは欧米諸国では一般的です。しかし、日本ではあまり見られません。
従来の日本は、年功序列制や終身雇用制が一般的で、まず「人」の採用ありきで業務を割り振っていくスタイルが主流でした。特定の業務への能力よりも「いかに長く働くか」が評価される傾向にあり、実力がなくても長く勤めさえすれば、ある程度昇進することもできたのです。
しかし、このようなスタイルでは、専門的な高いスキルを持つ人材が育ちにくくなります。オールラウンドな人材ももちろん重要ですが、専門性がなければ生産性が落ちてしまうこともあるでしょう。
そこで、大手企業を中心として特定の仕事に人を割り振り、専門性を高めるジョブ型雇用を導入する動きが活発になってきたのです。ジョブ型雇用は、労働時間や勤続年数などではなく、能力や仕事の成果によって評価される実力主義的な雇用制度ともいえるでしょう。
ジョブ型雇用が注目される3つの理由

大企業を中心に導入が進むジョブ型雇用ですが、そもそもなぜこのように注目を集めるようになったのでしょうか。主な理由は、以下の3つです。
①生産性の向上
ジョブ型雇用が注目されるようになった理由として、まず挙げられるのが生産性の向上を図ることです。
従来の日本に多かった年功序列制や終身雇用制は、景気が安定し若い労働力も豊富に確保できた時代には合理的なやり方でした。ところが、現代の日本は少子高齢化の影響により、労働人口が徐々に減少しています。
将来的には、求人の場において売り手市場となり、必要な人材を確保できず競争力や生産性が低下する企業も増えるでしょう。
このような状況で生き抜くには、すでに雇用している従業員の能力を高めることが必須です。
たとえ従業員数が減ったとしても、個々の従業員が高いパフォーマンスを発揮すれば、生産性を維持または向上が期待できます。
このことから、能力をあまり重視しない従来の年功序列制や終身雇用制ではなく、特定の業務に高い専門性を持つ人材を育成できるジョブ型雇用の必要性が増したのです。
②国際的な競争力の向上
ジョブ型雇用は、高い専門技術を持つ人材の育成により、国際的な競争力を高めることを目的として導入する企業も多い傾向です。
従来の日本では、大学を卒業したばかりの若者を新卒として一括採用する企業が一般的でした。新卒は、特別なスキルを持たない状態で入社し、さまざまな業務を経験しながらどこでも働けるオールラウンドな人材として育てられることが多かったのです。
しかし、このように業務に浅く広く接するだけでは、専門性を高めるのは難しくなります。その結果、グローバル化が進む現代において、国際的な競争力の低下が顕著になってしまったのです。
スイスのビジネススクールの国際経営開発研究所が2020年に公表した「世界競争力年鑑」によれば、日本の国際競争力は34位という結果でした。
バブル期には1位を獲得していた日本が、1997~2018年までは17~27位まで落ち込み、2020年には過去最低の34位にまで後退してしまったのです。
特に、ITやデジタル系で高いスキルを持つ人材の確保が難しくなっており、優秀な人材が外資系企業に取られるケースも珍しくありません。これでは、ますます国際競争力が落ちてしまうため、このような状況を打開するべくジョブ雇用型を導入して人材を育成する企業も増えています。
③多様化する働き方への対応
ジョブ型雇用へ注目が集まる理由には、多様化する働き方に対応することも挙げられます。
働き方改革などの影響により、日本でもテレワークを導入する企業が増えました。しかし、テレワークは従業員が働いている様子を上司が直接確認できません。進捗や取り組み方などを把握しにくくなり、従業員同士で協力して進める業務などに支障が出ることもあります。
一方、ジョブ型雇用は業務の範囲を限定し、それを達成したかどうかをチェックするだけで済みます。周囲との連携や進捗管理などの必要性がぐっと減るため、テレワークに適した雇用形態として注目を集めるようになったのです。
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いは?

メンバーシップ型雇用とは?
従来の日本で採用される雇用形態といえば、「メンバーシップ型雇用」と呼ばれるものが主流でした。
メンバーシップ型雇用は、採用や入社の段階ではどこに配属されるかが決まっておらず、研修や経験を通じて適性を見極めながら配属先を決めるのが特徴です。
一般的には、入社後数年おきに部署や業務を異動し、時には転勤も交えながらジョブローテーションを繰り返します。これにより、さまざまな業務のキャリアを積み重ね、企業の将来を担う人材を中長期的な視点で育成していくのです。
この特徴を見ると、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用は、まさに対極にあるような雇用形態であることがわかるでしょう。
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の3つの違い
ジョブ型雇用と従来の日本で主流だったメンバーシップ型雇用には、主な違いが3つあります。それぞれにどのような違いがあるのか、具体的に見ていきましょう。
1.採用基準
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の1つ目の違いは、採用基準です。
業務に対して人を割り振るジョブ型雇用に対し、メンバーシップ型雇用は人に対して業務を割り振ります。
ジョブ型雇用は、学歴や年齢などよりも採用する時点で業務をこなす能力があるかどうかが重視される傾向です。
一方でメンバーシップ型雇用の場合、学歴や年齢、人柄なども含めた総合的な潜在能力が重視されます。
そのため、ジョブ型雇用では即戦力となる人材や中途採用が多く、メンバーシップ型雇用は将来性を期待した若者の採用が多くなる傾向です。大学を卒業したばかりの新卒の場合、スキルがほとんどないことが多いため、ジョブ型雇用だと厳しくなるかもしれません。
2.評価方法
2つ目の違いは、評価方法の違いです。ジョブ型雇用では、「特定の業務をこなすための能力やスキルを持っているか」「どの程度成果を出せたか」という結果部分が評価されます。
一方のメンバーシップ型雇用は、中長期的な雇用や育成を前提としているため、勤続年数が長いほど自然に評価が高くなる傾向です。
3.教育制度
3つ目の違いは、教育制度です。ジョブ型雇用では、採用の時点で能力のある人材を選んでいるため、企業側が一律の研修や教育を行うケースはあまり見かけません。
採用後は、業務をこなしながら自主的に専門性を磨き、より高い評価を目指します。
一方、メンバーシップ型雇用では採用した人材に一律で同じ内容の研修を受けさせた後、上述したようにジョブローテーションが行われることが多い傾向です。長い年月をかけ、多分野に優れた人材の育成を目指します。
【企業からみた】ジョブ型雇用のメリット・デメリット

企業にとってのメリット
ジョブ型雇用を導入することで、人材の確保や評価の面でメリットが期待できます。詳しい内容をそれぞれに見ていきましょう。
専門的スキルを持つ人材を確保できる
ジョブ雇用型は、職務記述書で定めた明確な基準によって採用する人材が決まるため、企業が求める人材をほぼ確実に探すことができます。
まったくスキルのない人材をゼロから育てるのと比べてコストもかからず、即戦力としてすぐに活躍してもらえるため非常に効率的です。
また、業務の内容や勤務地、労働時間などの範囲が限定されていることで、従業員とのミスマッチも防ぎやすくなります。「期待していた能力がない」「思ったような仕事ではない」などのミスマッチが起きると、企業と従業員双方にとって悲劇です。
すぐに、従業員が退職してしまえば、新たな人材を採用するためのコストや時間も余計にかかってしまいかねません。これを防ぐためにも、最初から労働条件を明確に提示できるジョブ型雇用は双方にとって大きなメリットになります。
評価がしやすい
従来の人事評価制度では、評価する上司の主観や好悪感情によって評価が左右されるケースもありました。
一方、ジョブ型雇用では基本的に職務記述書で定められた業務を達成できたかどうかで評価が決まるため、評価基準が明確でわかりやすいです。
従業員の能力に基づいた客観的かつ正当な評価が可能になれば、人事戦略や組織運営にも役立つでしょう。評価に対する従業員の納得も得られやすいため、高いモチベーションで業務にあたり、生産性を高められる可能性もあります。
企業にとってのデメリット
企業がジョブ型雇用を導入する場合、メリットだけでなくデメリットもあるため、注意しなければなりません。主なデメリットを紹介するので、導入前に正しく理解しておきましょう。
臨機応変な配置が難しい
ジョブ型雇用は、業務内容や勤務地の範囲が限られるため、人手不足の部署への応援に回したり、キャリアアップのための異動をさせたりするのが難しい傾向です。
どうしても異動させたい場合は、その都度契約をやり直すことになりますが、従業員が同意するとは限りません。柔軟な配置ができなかった結果、ビジネスチャンスを失ったり生産性が低下したりするリスクもあると覚えておきましょう。
導入時の環境整備に手間と時間がかかる
雇用形態を従来のものから新しいものへ切り替える場合、さまざまな準備が必要です。
例えば、企業が求める能力に満たない従業員は給与が下がってしまう可能性もあるため、事前に従業員への十分な説明が欠かせません。
ほかにも人事や評価システムの変更や給与体系の見直し、職務記述書の作成など、さまざまな面で環境整備に取り組む必要もあります。
導入にこぎつけるまでには、手間と時間、さらにコストもかかるでしょう。専門性を持つ人材を求める以上、採用のハードルも上がって雇用が不安定になりやすい点にも注意が必要です。
【従業員からみた】ジョブ型雇用のメリット・デメリット
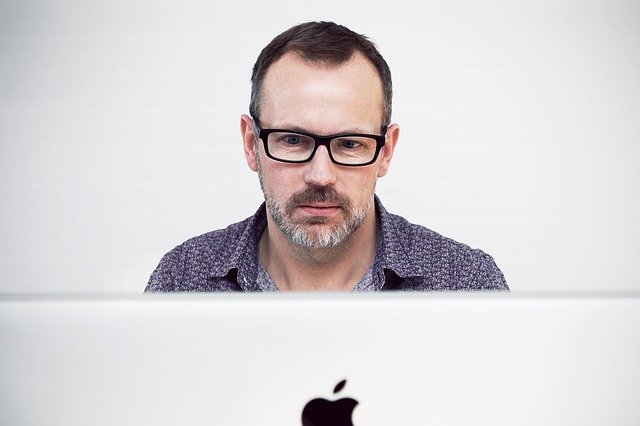
従業員にとってのメリット
ジョブ型雇用の導入でメリットが期待できるのは、企業だけではありません。従業員が得られるメリットも把握し、採用活動でアピールしてみましょう。
得意分野を活かせる
ジョブ型雇用では、特定の業務を遂行できる能力を持つ人材を採用するため、従業員は今の自分の能力を最大限に発揮することができます。
メンバーシップ型雇用の場合、ジョブローテーションにより自分の興味がない苦手な業務に携わる可能性もあるでしょう。しかし、ジョブ型雇用ではそういった心配がありません。
基本的に遠く離れた地域への転勤もないので、住み慣れた場所を離れたり単身赴任をしたりする必要もないのです。一つの地域に腰を据えて自分の得意分野、または伸ばしたい分野のみスキルを磨けば良いため、高いモチベーションで働けるでしょう。
収入アップを目指せる
ジョブ型雇用の評価は、特定の仕事に対する成果であり、学歴や年齢はほとんど関係ありません。
そのため、得意分野のスキルを磨いて高い専門的技術が身に付けば、年齢に関係なく高い給与を得ることも可能です。スキルが高まれば、より待遇の良い企業への転職もしやすくなり、充実した生活を送れるようになることが期待できます。
従業員にとってのデメリット
企業の場合と同様に、従業員にとってもジョブ型雇用のデメリットはあります。ミスマッチを防ぐためにも、従業員のデメリットも理解しておくことが大切です。
職を失うリスクがある
メンバーシップ型雇用であれば、ジョブローテーションにより幅広い業務を経験するため、一つの業務ができなくなってもほかの業務に回って働くことができます。
ところが、ジョブ型雇用は高い専門性が求められる一方で、その業務以外には経験がないため臨機応変な対応があまりできません。
そのため、景気の悪化や企業の都合などによっては、専門的な業務が必要なくなれば雇用を打ち切られる可能性もあります。
自主的なスキルアップが必要
ジョブ型雇用は、もともと専門性のある人材を採用するケースが多い傾向です。そのため、あまり企業側が研修などを行うことがありません。
つまり、より良い成果を出すためには、自分で積極的に問題点を見つけて専門スキルを磨く必要があるのです。特に、ITやデジタル分野の技術革新スピードはすさまじいため、常に情報を集めスキルを高めていかないと企業が求める能力を発揮できなくなる可能性があります。
ジョブ型雇用の報酬は、成果で決まるため、自己研さんが苦手な人は給与が下がってしまう可能性もあると覚えておきましょう。
ジョブ型雇用の導入事例3選
富士通株式会社
総合エレクトロニクスメーカー「富士通株式会社」は、2020年4月からジョブ型雇用を導入しました。
当初の対象は、管理職以上でしたが2021年4月より一般の従業員も含めた全従業員に対象を広げて2024年までの完全移行を目指しています。
職責の大きさや重要性に応じた7段階の「FUJITSU Level」という格付け制度を創設し、段階ごとに月額報酬を変化させているのが特徴です。
個人の職務遂行能力ではなく、職責によって賃金が決まることで従業員が自主的に難易度の高い業務に挑戦する風土を目指しています。
その土台として富士通が拡大したのが、「社内ポスティング制度」です。
富士通グループ全体に向けて募集ポジションを公開し、全従業員がどのポジションにも応募できる環境を整えました。この社内ポスティング制度を活用すれば、従業員は自身の選択で異動や昇進することも可能です。
能力を発揮する機会を増やすことで、従業員の自主性や向上心を育む効果も生まれています。
株式会社ニトリ
インテリア小売業大手の「株式会社ニトリ」では、ジョブ型雇用を適用する従業員と適用しない従業員を混在させる雇用形態を運用しています。
一般的には、ジョブ型雇用を導入するなら最終的に全従業員を対象とするのですが、ニトリは適用対象とそうでない職種を明確に分けたのです。
もともと、ニトリでは数年単位で幅広い業務を経験する「配転教育」というジョブローテーションを導入していました。これを撤廃するのではなく、デザイナーやエンジニアなど明確に業務の範囲を設定できる専門職に限ってジョブ型雇用も導入したのです。
つまり、専門職になるまでは従来のようにジョブローテーションで多分野の知識と経験を身に付け、その中から従業員自身がキャリアプランを立てられる環境を整えています。
このようなスタイルは、オールラウンドな人材と高い専門的スキルを持つ人材をどちらも育成できることになり、メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用双方の良さを両立できる制度だといえるでしょう。
株式会社資生堂
化粧品メーカー大手の「株式会社資生堂」では、生産性の低さ改善と国際競争力の強化を目指して2020年より一部従業員を対象にジョブ型雇用を導入しました。
資生堂の場合、欧米諸国で主流の完全なジョブ型ではなく、日本のメンバーシップ型雇用の特徴も含めた独自の形態になっている点が特徴です。
まず、業務に応じた20以上もの領域を設定し、一つの領域の中で働く従業員を採用します。職務記述書は、領域ごとに作成され一つの領域に複数の職務があっても、職務等級が同じなら同じ職務記述書を使用します。
これにより、業務が必要以上に細分化されて限定的になるのを防ぎ、領域内での異動もスムーズに行えるようになりました。報酬や役職なども、職務記述書で定められた目標の達成度によって決まります。
ジョブ型雇用の特徴を正しく理解して導入を検討しよう
国際競争力の低下や労働力不足が深刻化する中、高い専門性を持つ優秀な人材を育成できるジョブ型雇用の導入は企業にとって大きな意義を持ちます。
ただし、メリットだけではなくデメリットもあるため、注意しなければなりません。注目を集めているからといって飛びつくのではなく、自社に合うのかどうかも考えながら慎重に導入を検討してみましょう。



