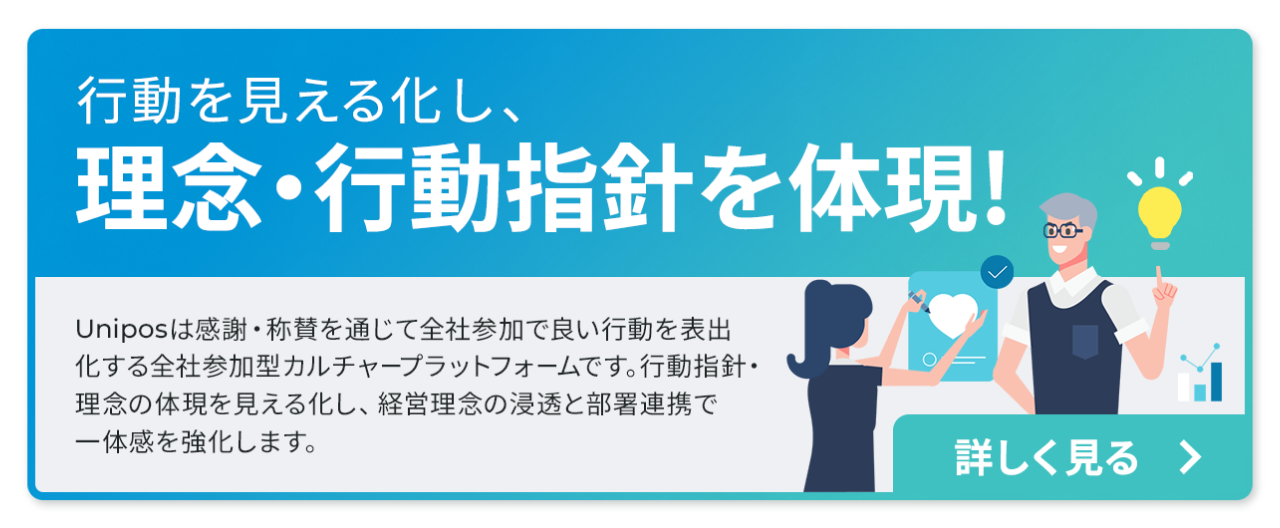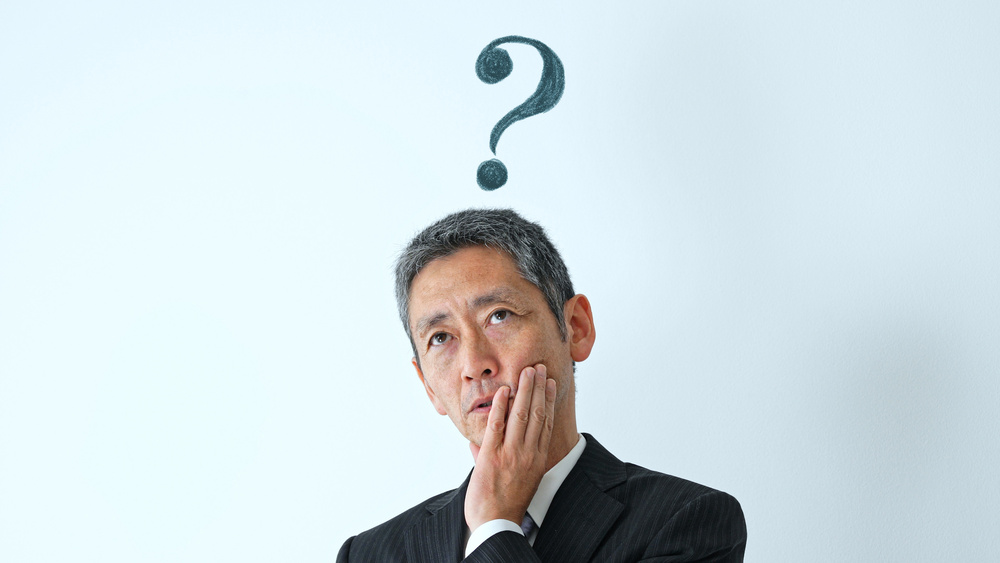
「なぜか職場に活気がない」「社員のやる気が見えない」そう感じていませんか? 企業の持続的な成長を左右する重要な要素として、組織風土への注目が近年高まっています。特に、心理的安全性が高く、従業員エンゲージメントに満ちた職場環境は、創造性や生産性の向上に不可欠であることが明らかになっています。しかし、理想的な組織風土を組織に根付かせ、停滞した現状を打破するには、具体的なステップと戦略が求められます。
本記事では、従業員のモチベーションと貢献意欲を最大限に引き出す組織風土改革について、その具体的な進め方と、Unipos導入企業における成功事例を詳しく解説します。理論だけでなく、実践的なノウハウも盛り込み、皆様の組織改革を強力に支援することを目指します。
組織風土とは?企業文化との違いと、注目される背景

企業の成長を左右する重要な要素として注目されている組織風土。これは、組織を構成するメンバー間で共通認識となっている価値観やルール、従業員の思考や行動に影響を与える職場環境の特性を指します。組織のパフォーマンスに直結するため、多くの企業でその改善が経営課題となっています。本章では、まず組織風土の基本的な定義と企業文化との違いを明確にします。その上で、なぜ今これほどまでに組織風土が注目され、改革が求められているのか、その背景についても深く掘り下げて解説していきます。
「組織風土」の定義と、行動や関係性への影響
組織風土とは、職場で従業員同士が自然と共有する「空気感」のこと。暗黙のルールや価値観が、行動や人間関係に強く影響します。
心理的安全性の高い職場では、従業員は意見を出しやすく、新しい挑戦にも前向きになれます。反対に、「失敗が許されない」風土では指示待ちや停滞が起こり、組織の成長を妨げかねません。 また、感謝や承認が行き交う職場では信頼関係が築かれやすく、部署を越えた連携も円滑になります。こうした関係性の質が、最終的に組織パフォーマンスに直結するのです。
組織風土・企業文化・組織文化の違いをわかりやすく整理
組織の状態を示す言葉には、「組織風土」の他にも「組織文化」や「企業文化」といったものがあり、これらの違いについて、分かりにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。組織をより深く理解するためには、これらの違いを明確に区別することが重要です。 まず、「組織風土」は、従業員が日々の業務や人間関係を通して肌で感じる「職場の空気」のようなものです。これは、暗黙のうちに共有される価値観やルール、習慣であり、自然発生的に形成される側面が強いと言えます。一方、「企業文化」は、経営理念、ビジョン、行動指針など、経営層が意図的に掲げ、組織全体に浸透させようとする価値観や考え方を指します。 そして、「組織文化」は、これら組織風土と企業文化の両方を包含した、組織全体の行動様式や共通認識の総体として捉えることができます。 これらの関係性を「氷山モデル」で説明すると、より分かりやすくなります。水面上に見えている、比較的明文化されやすく意識的に変えやすい部分が、理念や制度といった「企業文化」や組織構造などに当たります。そして、水面下に隠れており、目には見えにくいながらも組織の基盤として広大な部分を占めるのが、「職場の空気」や従業員間の人間関係、暗黙のルールといった「組織風土」です。
なぜ今、“良い組織風土”が経営課題になるのか?
現代のビジネス環境は、人材の流動化や変化の激しさなど、予測困難なVUCA時代に突入しています。この激変期において、単なる経済的利益追求だけでは企業は生き残れません。 企業が持続的に成長するためには、組織の内側、特に「組織風土」の質が極めて重要になっています。
-
優秀な人材の獲得と定着(リテンション)競争の激化 人材獲得競争が激化する中で、優秀な人材を惹きつけ、長く活躍してもらうためには、「働きがいのある職場」を提供できるかが企業の競争力を左右します。「働きがいのある会社ランキング」が毎年注目を集めていますが、その重要性は高まる一方です。
-
変化への迅速な適応とイノベーションの創出 予測困難なVUCA時代においては、変化への迅速な適応と継続的なイノベーションが不可欠です。従業員が失敗を恐れずに自由に意見を言い、新しいことに挑戦できる心理的安全性の高い組織風土は、まさにイノベーションの土台となります。Google社の「プロジェクトアリストテレス」でも、効果的なチームに最も重要な要素として心理的安全性が挙げられ、その有効性が実証されています。
-
多様化する働き方とエンゲージメント維持 リモートワークなど働き方が多様化し、従業員同士が直接顔を合わせる機会が減る中でも、組織としての一体感を保ち、エンゲージメント(貢献意欲や愛着)を維持することが求められています。共通の価値観や行動様式が根付いた組織風土は、離れた場所にいても従業員を繋ぐ重要な役割を担います。 このように、良い組織風土が醸成されることで従業員のエンゲージメントが高まり、それが企業の生産性や業績向上に直接的な影響を与えることが明らかになっています。そのため、「良い組織風土」の構築と維持は、多くの企業にとって経営戦略上の重要なテーマとして認識されるようになりました。
組織風土が停滞している職場に現れる3つの兆候

組織風土の停滞は、企業の成長にとって見過ごせない「静かな危機」となり得ます。従業員のパフォーマンス低下や離職率の増加を招き、イノベーションの阻害要因となるためです。では、あなたの職場の組織風土は健全でしょうか。これからご紹介する3つの兆候は、組織の健康状態を測る重要なバロメーターとなります。
心理的安全性が低く、発言や挑戦がしづらい
心理的安全性が低い職場では、従業員は他者からの評価を過度に恐れ、本音や建設的な意見を言えなくなります。これが新しいアイデアや挑戦の停滞につながります。 組織風土が停滞している職場の最初の兆候として、心理的安全性の低さが挙げられます。心理的安全性が低い状態とは、「こんな質問をしたら無知だと思われるのではないか」「このミスを報告したら無能だとレッテルを貼られるか」「異なる意見を言ったら邪魔をしていると思われるか」「懸念を伝えたらネガティブな奴だと思われるか」といった、他者からの評価に対する過度な恐れや不安から、従業員が本音や建設的な意見を言えなくなる状態です。提案や率直な意見を出すことが歓迎されない雰囲気が蔓延します。 こうした職場では、会議で誰も積極的に発言しなかったり、活発な質問が出なかったりといった具体的な行動が見られます。また、失敗を恐れるあまり、ミスやトラブルの報告が遅れたり隠蔽されたりするケースも少なくありません。従業員は萎縮し、「言っても無駄だ」「波風を立てたくない」といった心理が働き、発言を抑制するようになります。 心理的安全性が低い環境では、新しいアイデアの提案や、前例のない業務への挑戦といった建設的な行動が生まれにくくなります。現状維持を優先し、リスクを避ける空気が広がるため、組織全体の柔軟性や変化への適応力が低下します。
従業員のエンゲージメントが低下し、行動が受け身に
組織風土の停滞を示すもう一つの兆候は、従業員のエンゲージメント低下です。これは、仕事への熱意や組織への貢献意欲が失われ、受け身な行動が増える状態を指します。 従業員のエンゲージメントが低下していることも、組織風土が停滞している職場の顕著な兆候です。エンゲージメントとは、従業員の仕事への熱意や、組織の目標達成に向けた貢献意欲を指します。このエンゲージメントが低い状態が続くと、従業員の行動は自然と受け身や消極的になっていきます。 具体的には、以下のような様子が見られるようになります。
-
指示されたことだけをこなす「指示待ち」の姿勢が増える
-
業務改善に向けた自発的な提案が出なくなる
-
会議で積極的に発言しなくなる
こうした行動の背景には、自身の仕事が組織全体の成長や成果にどのようにつながっているのか、その貢献を実感しにくい状況があります。自分の働きが正当に評価されず、組織への貢献や仕事そのものにやりがいを感じられないことから、エンゲージメントが低下し、結果として行動も消極的になるという悪循環に陥りがちです。この状態は、組織全体の活力を奪い、変革への機運を失わせる要因となります。
チーム内に変化への抵抗感が広がり、成長が止まる
組織風土が停滞していると、「変化は無駄」という諦めや抵抗感が広がり、新しいアイデアが生まれず、組織全体の成長が阻害される傾向にあります。 組織風土が停滞している職場では、「どうせ何かを変えようとしても無駄だ」「現状維持が一番安全だ」といった諦めや、変化に対して及び腰になる雰囲気がチーム内に広がります。このような環境下では、新しい取り組みや業務改善の提案が出たとしても、積極的に受け入れられず、非協力的であったり、否定的な反応に直面しがちです。具体的には、次の言葉や雰囲気が見られるようになります。
-
前例がない
-
以前も試したがうまくいかなかった
-
現状で特に問題はない
-
今のやり方で十分
-
余計な仕事が増えるだけだ
こうした変化への抵抗は、従業員の成長意欲を削ぎ、新しい知識やスキルを学ぶ機会を失わせます。さらに、新しいアイデアや異なる視点を排除する文化は、チームや部署を越えた連携、そして組織全体のイノベーションを大きく阻害します。変化を拒み続ける組織は、市場の変化や技術革新に柔軟に対応できなくなり、学習・成長のサイクルが止まってしまいます。結果として、競争力が低下し、事業全体の成長を停滞させるという深刻なリスクを抱えることになります。
組織風土を改善するための7つの実践アプローチ

このセクションでは、組織風土の停滞を乗り越え、従業員が生き生きと活躍できる職場を実現するための、具体的な7つの実践アプローチをご紹介します。
前章では、組織風土が停滞している職場で現れる兆候として、心理的安全性の低さやエンゲージメントの低下などについて解説しました。このような状況を改善し、従業員が生き生きと働く組織を実現するためには、単一の施策にとどまらず、多角的な視点からのアプローチが不可欠です。組織風土の改革は、一朝一夕に成し遂げられるものではなく、組織全体で継続的に取り組むべき課題だからです。 良い組織風土を築くための具体的な実践アプローチを7つご紹介します。これらは、経営層の明確なコミットメントから、現場レベルでの日々のコミュニケーション、文化醸成に至るまで、組織のあらゆる階層と側面にわたる重要なステップです
経営層のビジョンとコミットメントを明確に伝える
組織風土改革を成功させるためには、経営層が改革の旗振り役となり、明確なビジョンと強いコミットメントを示すことが何よりも重要です。 組織風土改革は、一部の担当者や現場任せでは抜本的な変革には繋がりません。経営層が改革の必要性を深く理解し、先頭に立って推進する姿勢を示すことが、従業員全体の意識を変える第一歩となります。企業が目指す未来の姿(ビジョン)と、その実現のためにどのような組織でありたいか(理想の風土)を、従業員一人ひとりが「自分ごと」として捉えられるように、具体的かつ共感できる言葉で語りかけることが重要です。
心理的安全性を育む「対話の場」と信頼の構築
従業員が互いを理解し、安心して本音を語り合える心理的安全性の高い組織風土は、意図的に設ける「対話の場」を通じて築かれる信頼関係が土台となります。 心理的安全性の高い組織風土を醸成するためには、従業員同士が互いを理解し、安心して本音を語り合える関係性の構築が不可欠です。これを実現するためには、意図的に「対話の場」を設けることが非常に有効なアプローチとなります。こうした場を通じて、立場や部署を超えた相互理解と信頼関係を深めることが可能になります。 具体的な施策としては、上司と部下が個別の課題や成長について話し合う1on1ミーティング、チームで目標や進捗、懸念事項を共有する定例会などが挙げられます。また、部署の垣根を越えた交流を促すシャッフルランチや、特定のテーマについて自由に意見交換するワークショップなども、「対話の場」として機能します。これらの場は、それぞれの目的に応じて従業員が安心して発言し、多様な視点に触れる機会を提供します。 しかし、単に場を設けるだけでは形骸化してしまう恐れがあります。対話の場を実りあるものにするためには、いくつかの重要なポイントがあります。例えば、相手の話に真摯に耳を傾ける「傾聴」の姿勢が基本となりますし、どのような意見や質問であっても頭ごなしに否定しない、といった明確なグラウンドルールを設定することも大切です。リーダー自身が積極的に自身の考えや経験を「自己開示」することで、他のメンバーも安心して本音を話しやすい雰囲気を作ることができます。これらのポイントを意識することで、「対話の場」は心理的安全性を高め、組織内の信頼関係を育む土台となるのです。
感謝と承認を見える化し、称賛文化を育てる
日々の感謝と貢献を組織全体で「見える化」することは、称賛文化を育み、従業員のモチベーション向上とポジティブな行動を促進する上で極めて重要です。 日々の業務の中には、目に見えにくいけれど組織を支える「隠れた貢献」や、当たり前になりがちな「感謝の気持ち」が数多く存在します。これらを組織全体で共有し、誰もが見てわかる形に「見える化」することは、組織風土を改善する上で非常に重要です。貢献や感謝が可視化されることで、「どのような行動が組織内で推奨されているか」が明確になり、従業員は自信を持ってポジティブな行動を促進しやすくなります。 具体的な実践方法としては、ピアボーナスツールや社内SNS、ビジネスチャットツールなどを活用することが効果的です。例えば、Uniposのように、従業員同士が感謝や称賛のメッセージに少額のインセンティブを添えて送り合う仕組みは、貢献した人が誰か、どのような行動が評価されているかがオープンになり、相互承認の文化が育まれます。社内報や社内SNSでの積極的な情報共有も、称賛の機会を増やすことにつながります。 称賛文化を組織にしっかりと根付かせるためには、いくつかのコツがあります。まず、経営層や管理職が率先して感謝や称賛のメッセージを発信することが不可欠です。リーダーの姿勢は、従業員に大きな影響を与えます。また、プロジェクトの成功といった大きな成果だけでなく、日常のささいな協力やサポート、課題解決に向けた小さな一歩といった「スモールグッド」にも光を当て、積極的に称賛することが重要です。これにより、「自分も組織に貢献できている」という実感が高まり、組織全体の活性化につながるのです。
エンゲージメント指標を使って、職場の空気を可視化
組織風土のように目に見えづらい職場の空気を正確に把握するためには、エンゲージメントサーベイなどの客観的な指標を活用し、データとして可視化することが不可欠です。 「組織風土」は、職場の空気のように目に見えづらく、肌感覚だけで現状を正確に把握することは困難です。そのため、エンゲージメントサーベイなどのツールを活用し、組織の状態をデータとして客観的に可視化することが重要ですし、数値に基づいた分析は、勘や感覚に頼らず具体的な課題を特定し、実施した施策の効果を測定するために不可欠だからです。 エンゲージメントサーベイでは、例えば、仕事への熱意ややりがい、組織への貢献意欲や誇り、上司や同僚との人間関係の質、会社のビジョンや目標への共感度といった項目を測定できます。これらの指標を通じて、組織風土の現状や課題を把握することが可能です。 重要なのは、サーベイを単なる「調査」として終わらせないことです。定期的に実施し、得られた結果を詳細に分析します。そして、その分析結果をもとに具体的な改善アクションを計画・実行し、さらに次回のサーベイで効果を測定するというPDCAサイクルを継続的に回していくことが求められます。
挑戦と失敗を許容する“学習する組織”をつくる
組織風土の停滞を招く要因として「減点主義」の文化が挙げられます。これは失敗を恐れ、新しい挑戦が生まれにくくなる環境で、現状維持を好む結果、組織の成長が停滞します。これを打開するには、失敗を「学習の機会」と捉える「学習する組織」への転換が必要です。この組織では、失敗から得られた教訓を共有し、次に活かす文化が根付いています。
組織風土の停滞を招く大きな要因の一つに、「減点主義」の文化が挙げられます。これは、失敗に対して厳しく評価され、罰せられることを恐れるあまり、新しいことへの挑戦や、リスクを伴う提案が生まれにくくなる環境です。失敗を回避することに焦点が当てられるため、従業員は現状維持を好み、組織全体として大胆な変革に踏み出せない状況に陥りがちです。こうした「減点中毒」は、従業員の学びやモチベーションを阻害し、結果として組織の成長を停滞させてしまう弊害をもたらします。
こうした状況を打開し、持続的な成長を実現するためには、失敗を責めるのではなく、「学習の機会」と捉える「学習する組織」への転換が不可欠です。「学習する組織」とは、組織全体で継続的に学び、変化に対応しながら能力を高め、目的に向かって効果的に行動できる組織を指します。ここでは、失敗を単なるミスとして片付けるのではなく、そこから得られた教訓を組織全体の資産として共有し、次に活かす文化が根付いています。具体的には、振り返り会の実施や挑戦的な目標設定の評価制度があり、組織として学び、改善する姿勢を育みます。
この変革において、マネジメント層は極めて重要な役割を担います。部下の新しい挑戦を積極的に後押しし、たとえ失敗したとしても、「何を学んだか」「次にどう活かせるか」を問いかける姿勢を示すことが大切です。リーダー自らが自身の失敗談を共有するなど、失敗を恐れない空気感を率先して作り出すことが、挑戦と学びが循環する組織風土を築く鍵となります。
共感者を増やし、変化を“他人事”にさせない仕掛け
組織風土改革を成功させるには、従業員をプロセスに巻き込み、「自分ごと」として共感を広げることが不可欠です。McKinsey & Companyの調査によれば、組織変革の失敗原因の多くが従業員の抵抗にあるとされ、この「自分ごと化」が成否を左右します。
効果的な方法として、各部署から「アンバサダー」や「チェンジエージェント」を募り、彼らが現場のキーパーソンとして経営層の意図を伝え、現場の声を吸い上げる役割を担うことが挙げられます。また、改革によるポジティブな変化や成功事例を社内報で「ストーリー」として共有し、従業員の貢献や困難を乗り越えたエピソードを伝えることで、共感を広げます。NEC社が社長と社員の対話を通じて改革のストーリーを共有した事例は、当事者意識を育む力となります。
小さな成功を振り返る“リズム”とPDCAの習慣化
組織風土改革を持続可能にするには、日々の業務で得られる「小さな成功」を積み重ね、定期的に振り返り、次の行動に繋げるPDCAサイクルを組織の習慣とすることが重要です。大きな変革には時間がかかり、従業員のモチベーション維持が課題となるため、「スモールウィン戦略」で小さな成功を意識的に積み重ねることが必要です。これにより従業員は「自分たちも組織を変えられる」という実感を持ち、成功体験の共有を通じてポジティブな変化を実感しやすくなります。成功要因や課題を次のアクションに反映させるプロセスを定着させることで、組織は常に進化を続け、改革への当事者意識が醸成され、強力な原動力となります。成功事例の共有は他の社員の実践を促す効果も期待できます。
Uniposが支援した「組織風土改革」成功事例4選

ここまで、組織風土が停滞している兆候や、良い組織風土を築くための様々な実践アプローチをご紹介しました。ここからは、これらのアプローチをUniposの活用によって実現し、組織風土改革に成功した企業の事例を具体的にご紹介します。Uniposは、従業員同士が日々の感謝や貢献をオープンに伝え合う「称賛文化」を醸成し、相互承認を通じて心理的安全性の高い、エンゲージメントに満ちた組織づくりを支援するツールです。これからご紹介する7つの事例は、抱える課題や組織の規模も様々です。ぜひ、貴社の状況と照らし合わせながら、改革のヒントを見つけてください。これらの成功事例を通じて、組織風土改革の具体的なイメージを掴み、自社での取り組みを始める一歩としていただければ幸いです。
H3-1. 三菱電機社: 「硬直化した組織」を打破!Uniposが"称賛文化"を浸透させ、挑戦行動を劇的に増加 (https://unipos.me/ja/blog/mitsubishielectric)
三菱電機では、硬直化しがちな組織風土の課題に対し、Uniposを導入。日常的な称賛と感謝の可視化を通じて称賛文化を浸透させ、従業員の挑戦意欲と自発的な行動を大きく促進しました。
H3-2. 明電舎社: 「心理的安全性不足」を解消!Uniposの"ほめる文化"で関係性が大きく変化 (https://unipos.me/ja/blog/meidensha)
株式会社明電舎は、Uniposが育む「ほめる文化」を通じて、従業員間の心理的安全性を劇的に向上させました。これにより、率直な意見交換が活発になり、組織内の人間関係がより良好に変化したことが示されています。
H3-3. 富士製薬工業社: 「部署間サイロ化」を乗り越える!Uniposが"連携"を活性化させ、壁のない組織へ (https://unipos.me/ja/blog/fujipharma-2024)
富士製薬工業では、部署間の連携不足による「サイロ化」が課題でした。Uniposの導入により、部署を越えた感謝と貢献の可視化が進み、組織内のコミュニケーションが活性化。部門間の心理的な壁が低減し、一体感のある組織へと変革しました。
H3-4. サンワカンパニー社: 「受け身の姿勢」を変革!Uniposが"相互理解"を深め、組織の自走力を向上 (https://unipos.me/ja/blog/sanwacompany)
株式会社サンワカンパニーでは、Uniposを通じた日常的な貢献の可視化が、従業員間の相互理解を深め、主体的な行動を促しました。これにより、組織全体の自走力が向上し、従業員一人ひとりが「自分ごと」として業務に取り組む風土が醸成されました。
組織風土改革を「一過性」で終わらせないために
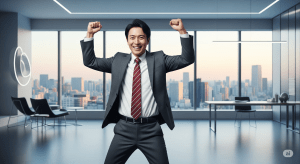
時間と労力をかけて取り組んだ組織風土改革も、残念ながら多くのケースで一時的な「イベント」として捉えられ、次第に活動が形骸化してしまう失敗が見られます。改革の目的や意義が従業員に浸透しなかったり、活動が現場のメリットにつながらなかったりすると、取り組みへの関心は薄れ、いつしか元の組織風土に戻ってしまうことも少なくありません。改革を真に組織に根付かせ、持続可能なものとするためには、特別な活動としてではなく、日々の業務の中に自然と溶け込ませる仕組みづくりが不可欠です。
改革を持続させるためには、まず組織風土の改善を「日常業務の一部」として位置づけることが重要です。例えば、定例会議で組織風土に関する簡単なテーマを議題に加えたり、1on1ミーティングで従業員の心理状態やチームの雰囲気に触れる対話を取り入れたりすることが有効です。さらに、組織の状態を客観的に把握するために、エンゲージメントサーベイや各種ツールの利用データを活用した定期的な効果測定を行い、その結果を関係者にフィードバックするサイクルを回すことも欠かせません。この「測定→共有→改善アクション」の繰り返しが、関係者のモチベーションを維持し、継続的な改善へとつながります。そして、何よりも重要なのは、経営層や管理職が改革のビジョンを継続的に発信し続け、自ら変化を体現する姿勢を示し続けることです。トップが本気でコミットしている姿勢は、組織全体に改革を推進する強いメッセージとなります。
継続的な変化を支える“共感の輪”を社内に広げる
組織風土改革を持続可能にするには、一部の担当者だけの「やらされ仕事」ではなく、全従業員が「自分ごと」として関わることが不可欠です。改革への共感が組織全体に根付かないと、一過性のイベントに終わるリスクがあります。McKinsey & Companyの調査では、組織変革の失敗原因の多くが従業員の抵抗にあるとされ、この「自分ごと化」が成否を左右します。共感の輪を広げるには、各部署から「アンバサダー」や「チェンジエージェント」を募り、彼らが現場のキーパーソンとして経営層の意図を伝え、現場の声を吸い上げる役割を担うことが有効です。また、改革によるポジティブな変化や成功事例を社内報で「ストーリー」として共有し、従業員の貢献や困難を乗り越えたエピソードを伝えることで、共感を広げます。NEC社が社長と社員の対話を通じて改革のストーリーを共有した事例は、当事者意識を育む力となります。
日常の中で“振り返りと改善”のサイクルを回す
組織風土改革を持続させるためには、施策の効果を定期的に振り返り、そこから学びを得て次へと繋げるサイクルを日常業務の中に組み込むことが極めて重要です。
組織風土改革を一過性のイベントで終わらせないためには、実施した施策を「やりっぱなし」にせず、その効果を定期的に振り返る仕組みを日常業務の中に組み込むことが非常に重要です。特別な時間を設けるのが難しい場合でも、例えば週次の定例会やプロジェクトの節目など、既存のフローの中で、短時間でも良いので、意図的に振り返りの機会を作りましょう。
振り返りのフレームワークとして有効なのが、「KPT法」です。「Keep(良かったこと)」「Problem(問題点)」「Try(次に試すこと)」の3つの視点から議論を進めます。この手法は、単に過去を評価するだけでなく、そこから学びを得て具体的な次の行動につなげることを目的としています。
振り返りの中で課題や改善案が出た際には、個人や部署を非難するのではなく、「次への学び」として捉え、ポジティブな姿勢で議論を進める文化を醸成することが不可欠です。そして、話し合った内容を必ず具体的なアクションに落とし込み、「Try」として実行に移します。この小さな改善と成功体験の積み重ねが、組織全体に「自分たちで変えられる」という実感をもたらし、改革を継続させる揺るぎない原動力となります。PDCAサイクルを回すように、この振り返りと改善のプロセスを組織の習慣として定着させましょう。
PDCAで風土改革を習慣として定着させる
組織風土改革を単発の取り組みで終わらせず、組織文化として定着させるためには、継続的なプロセスとしてのPDCAサイクルを回し続けることが不可欠です。
組織風土改革を単発の取り組みで終わらせず、文化として組織に定着させるためには、継続的なプロセスとしてPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回すことが不可欠です。このサイクルを通じて、現状を把握し、施策を実行し、効果を測定・評価し、次の改善につなげていくことで、組織は着実に、そして持続的に進化を遂げることができます。
まず、Plan(計画)の段階では、どのような組織風土を目指すのか、その理想像を具体的に定義します。そして、その実現度を測るための測定可能な目標(KPI)を設定します。例えば、従業員エンゲージメントサーベイのスコア向上や、感謝・称賛の投稿数増加、部署間の協力に関する従業員アンケート結果などがKPIとして考えられます。次に、Do(実行)の段階では、計画に基づいて具体的な施策を実行に移します。対話の場の設定やコミュニケーションツールの導入など、計画した施策を実施します。この際、従業員の反応や施策を通じて得られた具体的なエピソードなどを記録しておくことが、後の評価につながります。
続くCheck(評価)の段階では、設定したKPIの推移や従業員へのアンケート結果、現場の声を収集・分析し、施策がどの程度効果を上げているのかを客観的に評価します。良かった点、課題となっている点を明確に特定することが重要です。そして、Action(改善)では、評価結果を踏まえ、うまくいった点は継続・強化し、課題点については改善策を検討して次の計画に反映させます。このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、組織風土の改善活動は特別なイベントではなく、日々の業務に組み込まれた習慣となり、組織文化として根付いていきます。
まとめ:持続可能な成長の土台は、良い組織風土にある

本記事では、企業の持続的な成長に不可欠な要素である組織風土に焦点を当て、その定義や重要性、そして組織が停滞している際の兆候について解説しました。心理的安全性の低さやエンゲージメントの低下といった課題に対し、経営層のコミットメントや心理的安全性を育む対話、感謝・称賛の見える化など、具体的な7つの改善アプローチをご紹介しました。良い組織風土は、単なる従業員満足度の向上にとどまらず、企業の競争力を高め、変化に対応し続けるための強固な土台となります。
組織風土改革は、一朝一夕に成し遂げられる特効薬ではありません。経営層が明確なビジョンを示し、改革への強い意志を示すトップダウンのアプローチと、現場の声を吸い上げ、従業員一人ひとりが「自分ごと」として関わるボトムアップのアプローチ、その両輪を機能させることが不可欠です。そして何より、改革は継続的な取り組みであり、日々の小さな改善と、それを組織全体で共有し、称賛し合う文化を育むことが成功の鍵となります。
改革は、日常の「ありがとう」から始まる
組織風土改革は大規模なプロジェクトに思われがちですが、真の変革は日々の業務における一人ひとりの「ありがとう」という感謝の小さな行動の積み重ねから生まれます。
組織風土改革と聞くと、大規模なプロジェクトや特別な施策が必要だと考えがちです。しかし、真の変革は、日々の業務における一人ひとりの小さな行動の積み重ねから生まれます。中でも、最もシンプルでありながら強力な一歩となるのが、感謝の気持ちを言葉にして伝える「ありがとう」です。
感謝の言葉を交わすことは、職場の心理的安全性を高める上で非常に効果的です。教育コミュニケーション協会の情報にもある通り、感謝の言語化は職場の信頼関係を築き、安心感を育むことが実証されています。互いに感謝し合う文化が根付くと、「自分は認められている」「役に立っている」と感じられるようになり、積極的に発言したり挑戦したりすることへの心理的なハードルが下がります。これは、組織内に承認文化を醸成する基盤となります。
まずは、身近な同僚やチームメンバーに対し、具体的な貢献やサポートに対する感謝を「ありがとう」という言葉で伝えてみましょう。些細なことでも構いません。この小さな習慣が、職場の空気を温め、ポジティブな変化のきっかけとなります。Uniposのようなツールは、こうした日常の感謝や貢献を見える化し、組織全体で共有・称賛することを強力に後押しします。感謝や承認がオープンに交わされることで、自然と互いを認め合い、支え合う文化が育まれ、組織風土改革を加速させていくでしょう。