
企業の内部環境や人間関係を表現する言葉として、組織風土や組織文化、社風などはいずれもよく用いられる言葉です。
この3つの言葉にはそれぞれ異なる意味があり、人事や経営戦略ではこれらの意味の違いを理解した上で活用することが重要です。
それぞれの言葉の意味と関係性について詳しく見ていきましょう。
1.組織風土・組織文化・社風のそれぞれの意味

「組織風土」「組織文化」「社風」は、組織の特徴や価値観を示すワードとして用いられます。どれも似ている言葉ですが、定義や意味には違いがあります。まずは、3つの言葉の意味について理解しておきましょう。
組織風土の意味
組織風土とは、「組織内で共通認識として持たれている独自の規則・価値観」を指し、組織活動における意思決定や従業員のモチベーションに深く関わるものとされています。
組織風土は、組織や従業員のこれまでの取り組み、行動、思想などから受け継がれてきたものであり、外部からの影響を受けにくい特徴があります。
そのため、組織風土は安易に変えられるものではなく、変革には時間がかかるとされています。
組織文化の意味
組織文化とは、「組織内で共有されているルールや信念」を指します。組織の目指す方向性や仕事に対する価値観などが当てはまり、組織として判断を下す際のベースとなるものです。
組織文化は、組織や従業員の経験や伝達などによって、変化や成長を伴いながら徐々に形成されるものです。また、市場変化や競合の状況など外部からの影響も受けやすいとされています。
そのため、トップや経営層などの判断で、意図的にデザインすることも可能です。
社風の意味
社風とは、「従業員が感じる組織の雰囲気や特徴」を指します。
組織内の人間関係や労働環境、仕事のスタイルなどから、従業員一人ひとりが感じる主観的、感覚的なものです。
社風は、組織風土や組織文化からも大いに影響を受け、従業員によってさまざまな捉え方や視点が存在します。
参考:「企業風土や組織文化、社風の意味や定義の違いとは?」
https://mitsucari.com/blog/climate_culture/
2.組織風土・組織文化・社風の違いと関係性

次に「組織風土」「組織文化」「社風」の違いや関係性についてみていきましょう。
組織風土と組織文化の違いと関係性
わかりやすい言葉で例えると、組織風土は長年にわたり培われてきた「性格」、組織文化は自分の性格と周囲の環境により築かれた「価値観」と表現できます。
例えば、負けず嫌いや心配性などの個人がもつ性格は、一朝一夕には変えられないものです。しかし、何よりも仕事を優先したい、残業も厭わないなどの価値観は、結婚や子育てなど、自分を取り巻く環境の変化により柔軟に変わります。
組織においても同様で、長年の体質や伝統といった組織風土を変更するのは難しいですが、仕事のやり方や価値観などの組織文化は、時代や市場の変化により徐々に変化していく可能性が高いといえます。
組織風土と社風の違いと関係性
組織風土を「性格」と表現するならば、社風は性格と価値観から生まれた「人柄」といえるでしょう。
例えば、柔和で話しかけやすいという人柄は、人見知りをしない、社交的な性格や、人と積極的に関わることで成長できるという価値観によって築かれているものです。
組織においても、経営理念や行動規範などを基にした「組織風土」と仕事に対する価値観である「組織文化」が合わさることで、組織の「社風」が生まれます。
組織文化と社風の違いと関係性
上述した通り、組織文化は「価値観」、社風は「人柄」と表現でき、社風は組織文化と組織風土の組み合わせにより誕生します。
具体的には、革新的なアイデアやチャレンジが受け入れられやすいという「組織文化」があるため、自分の考えや意見を提案しやすい、自由度が高いといった「社風」が生まれたなどのケースが挙げられます。
参考:「企業風土や組織文化、社風の意味や定義の違いとは?」
https://mitsucari.com/blog/climate_culture/
3.良い組織風土や組織文化が醸成されることのメリット

良い組織風土、良い組織文化が組織にもたらすメリットについて詳しくみていきましょう。
良い組織風土のメリットとは
良い組織風土がもたらすメリットには以下のようなものがあります。
- 組織のビジョンや目指すべき方向性を従業員と共有できる
- 組織内の人間関係が良好になる
- 従業員にとって働きやすい職場環境を実現できる
- 従業員エンゲージメントが高まる
- モチベーションの高い人材を育成できる
- 生産性アップ、業績品質の向上が期待できる
組織風土は、組織のビジョンや目指すべき方向性を明確にしたものです。組織風土を従業員へしっかりと伝えることで、従業員はビジョンや方向性に沿った行動がとれるようになります。
また、一般的に良い組織風土は従業員のエンゲージメントを向上させるといわれています。従業員エンゲージメントとは、愛社精神や組織への思い入れと表現される言葉です。従業員エンゲージメントが高い組織では、従業員が組織の成長や発展のために、自発的に貢献しようと意欲が高まります。
それにより、定着率や生産性アップ、製品やサービスの品質向上など、組織経営にプラスの影響が期待できます。
良い組織文化のメリットとは
良い組織文化がもたらすメリットには以下のようなものがあります。
- 組織に一体感が生まれる
- 従業員のモチベーションを引き出す
- 意思決定のスピードが上がる
- 採用力強化、人材定着率の向上につながる
- 社内外へ発信する組織イメージが明確になる
組織文化を明確に打ち出すことで、目指すべき方向性や行動指針が定まり、組織に一体感が生まれ結束力も強まります。
また、良い組織文化は従業員の自発的な行動を生み出し、モチベーションややりがいを感じやすくさせます。仕事を進めていく上でも、組織文化に沿った意思決定や課題解決方法を選択するため、全体的な意思決定のスピードもアップします。
さらに、組織文化を社外へ発信することで、採用活動や組織のブランディング面でもプラスの効果が期待できます。
参考:
「組織を成功に導く風土醸成とは?具体例とともにわかりやすく解説します」
https://www.sofia-inc.com/blog/6919.html
「組織文化とは?良い組織風土を持った会社に共通する5つの要素」
https://www.training-c.co.jp/mailmagazine/hrreport26/#Toc-2
4.組織風土・組織文化それぞれの構成要素

組織風土や組織文化はさまざまな要素により構成されています。では、一体どのような要素によって成り立っているのでしょうか。詳しくみていきましょう。
組織風土を構成する要素
組織風土を構成する要素には、ハード要素とソフト要素の2種類があります。それぞれについて具体的にみていきましょう。
・ハード要素
組織のもつルールや制度など、目に見える(明文化された)ものが組織風土を構成するハード要素です。具体的には以下のような要素を指します。
経営理念(ミッション)
行動指針(バリュー)
就業規則
人事評価制度
業務プロセス
業務マニュアル
マネジメント方針
コンプライアンス規約 など
・ソフト要素
従業員一人ひとりがもつ価値観や行動基準、組織内の人間関係や信頼関係など目に見えない(明文化されていない)ものが組織風土を構成するソフト要素です。具体的には以下のような要素を指します。
コミュニケーション
チームワーク
信頼関係
人間関係
個々人のモチベーション
判断基準
組織内の独自ルール
暗黙の了解
責任の所在 など
組織文化を構成する要素
組織文化を構成する要素には以下のようなものが挙げられます。
・創業者の意志
特に創業者の意志や信念は、組織文化の醸成に深く関わる要素の1つです。創業時の想いや現在までの歴史は組織を構成する従業員へ受け継がれることで組織文化が生まれます。
・トップやマネジメント層の行動
トップやマネジメント層などの行動は、組織文化の浸透や組織にマッチする人材教育において重要です。
・組織におけるエピソードや神話
組織が苦境に陥った時にこう乗り越えたなど、身近に起きたエピソードは共感しやすく、心に響きやすいものです。こういったエピソードが語り継がれ、組織文化として定着するケースもあります。
・組織内での評価
組織文化に沿った行動や成果を上げている人が適切に評価されなければ、組織文化は浸透していきません。評価対象や評価基準も組織文化の構成には欠かせない要素です。
・採用活動
組織にマッチする人材を採用することで、組織文化はより強固なものになります。また、人材採用により組織文化を変革させることも可能です。
参考:
「組織風土とは?構成する要素や改革を進める6つのステップを紹介」
https://hygi.jp/blog/organizational-climate-innovation
「組織文化とは?良い組織風土を持った会社に共通する5つの要素」
https://www.training-c.co.jp/mailmagazine/hrreport26/#Toc-4
5.組織風土は悪い状態に陥ってしまうことがある
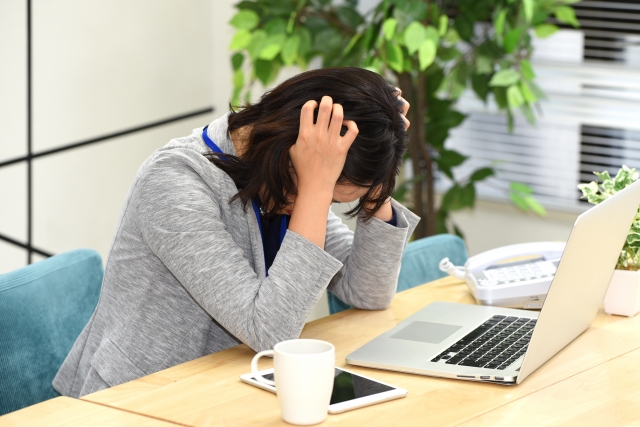
現状で何も問題がないと感じられる組織でも、気が付かないうちに悪い組織風土が蔓延する状態に陥っていたというケースも少なくありません。
ここでは、長年にわたる悪しき組織風土が従業員の不正に繋がってしまったかんぽ生命保険の事例を参考に話を進めていきましょう。
かんぽ生命保険では、高齢者など顧客に強引な勧誘を行い、不利益な契約を結ばせ成果をあげる営業手法が慣例のように行われていました。保険を売る販売員はもちろん、上司や教育を担当する職員にも、その手法を良しとする雰囲気があり、また、その手法により成果を上げた人が称賛される風土があったといわれています。
かんぽ生命の事例は、組織が目指すべきビジョンや価値観、従業員一人ひとりの意識や良心よりも、長年にわたり受け継がれてきた悪しき慣習や偏った成果主義により発生したと考えられています。
このように、悪い組織風土は表面化しづらく、気付かぬうちに病巣のように広がっていたというケースもあります。悪い組織風土は、従業員の関係性の悪化やモチベーションの低下、業績の悪化や不正につながるなど、多くのデメリットを引き起こします。また、一度根付いた悪い組織風土は取り除くことが難しく、さらに悪い組織風土が芽生えてしまう事態に陥る可能性もあります。
参考:
「組織を成功に導く風土醸成とは?具体例とともにわかりやすく解説します」
https://www.sofia-inc.com/blog/6919.html
「かんぽ生命で放置されてきた営業現場の暴走」
https://toyokeizai.net/articles/-/294533
6.組織改革は組織のどこに課題があるかを理解することが大切

社内で問題が発生した時は、その原因がどこにあるのかを的確に見極めることが重要です。問題が、組織風土、組織文化、社風のどれに起因するのかをいち早く捉えられれば、解決のための対策も打ち出しやすくなります。
・組織風土、社風に問題がある場合
問題やトラブルが組織風土や社風に起因する場合は、従業員が無意識レベルで行っている要素に手を加えてみるとよいでしょう。メールの送り方や、上司や同僚などの呼び方など、自分たちの組織内では当たり前のように行われていたことが、実は一般的ではなかったというケースは多々あります。
社内ルールや、制度、評価基準など、常態化している価値基準や行動を見直すような対策を講じることで問題が解決する可能性も高くなります。
組織文化に問題がある場合
問題やトラブルが組織文化に起因する場合は、経営層が中心となり、組織の目指す方向性や価値、目標などを見直し、改革を進めることが重要です。具体的なケースをみていきましょう。
ケース①業務スピードや作業効率に課題
価値基準や判断基準が定まっていないため、業務のスピードや作業効率が悪くなっている場合は、企業文化の見直しと従業員への発信が効果的です。
組織文化が明確であれば、さまざまな局面で組織文化に沿った迅速な判断や行動が取れるようになります。
ケース②採用面での課題
組織に合う人材が採用できない、募集をかけても適切な人材が集まらない、採用してもすぐに辞めてしまうなど、人材採用に問題がある場合は、組織文化の醸造が解決の一助となる可能性があります。
組織内だけでなく、外部に明確に組織文化を打ち出すことで、組織にマッチする人材が集まりやすくなります。また、組織文化との乖離が少ない人材であれば、必然的に定着率は上がり、結果的に採用コストや教育コストも抑えられます。
参考:「似ているようでだいぶ違う「企業文化」「企業風土」「社風」の違いを理解する!」
https://motifyhr.jp/blog/training/corporate_culture-4/#i-3
まとめ

組織風土、組織文化、社風は、似ているようで言葉の意味やニュアンスが大きく異なるものです。特に人事や経営戦略においては、この3つの言葉を適切に使い分けていくことが重要です。
組織を目指すべき方向へ成長、発展させるためにも、それぞれの言葉の本質をしっかりと捉え、従業員に適切に発信していくよう心がけましょう。


