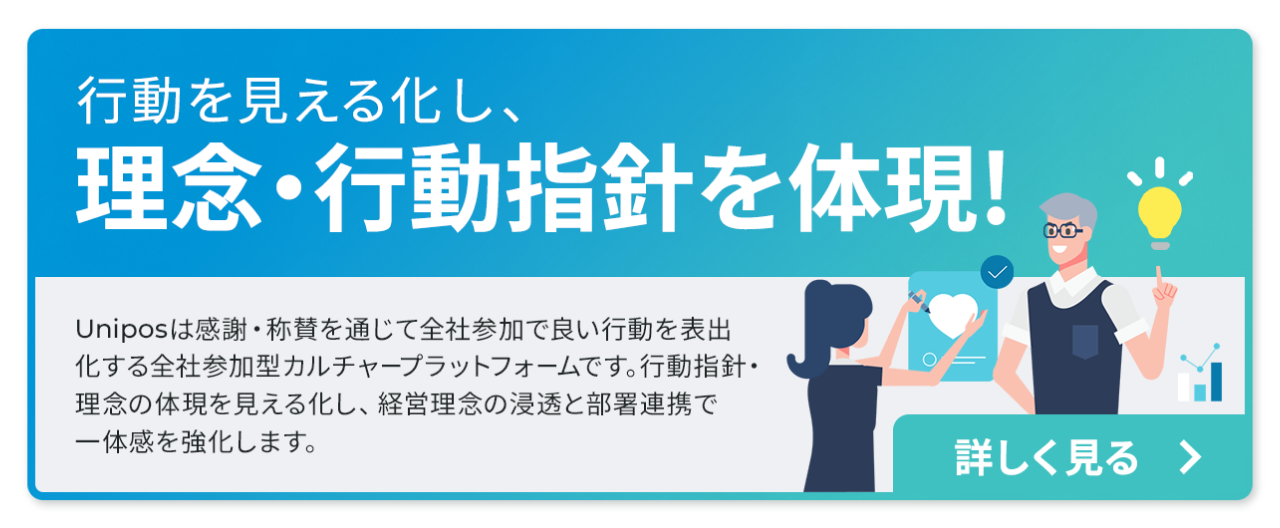企業という組織の中では周囲との関係性を重視して、大勢の意見に従わなくてはならないことがあります。このような同調圧力を「ピアプレッシャー」と呼び、強すぎる場合は過剰なストレスを感じるなど、仕事に支障をきたす恐れがあります。
しかし、ピアプレッシャーが適度に働いている場合は、同僚に対する仲間意識の向上や業務の効率アップなど、プラスに働くことがあるのです。
ピアプレッシャーをよい方向へと向けるためにも、ピアプレッシャーが持つメリットとデメリットを把握し、組織の効果的な運用に役立てることが重要だといえます。
ピアプレッシャーとは?

ピアプレッシャーとは、「仲間からの圧力」という意味です。和の精神や秩序を保つことを重視するような企業に所属していた場合、「周囲に合わせなくては」という同調圧力が、精神的なプレッシャーとして重くのしかかってきます。
ピアプレッシャーには2種類がある
ピアプレッシャーには以下の2種類が存在します。
・同調圧力としてのピアプレッシャー(相互監視)
・助け合いとしてのピアプレッシャー(相互配慮)
働き方次第で企業や社員にとってのメリットにもデメリットにもなり得るピアプレッシャー 。
まずは、それぞれの特徴を確認しましょう。
同調圧力としてのピアプレッシャー(相互監視)
同調圧力としてのピアプレッシャーは、多くの社員にとってストレスに感じてしまいます。
「他の社員が頑張っているから、自分も同じくらい頑張らないといけない」
という考え方は、立派な同調圧力です。
ピアプレッシャーは業務上の相互監視も生みます。お互いに監視しながら働いていたのでは、労働環境は劣悪なものになってしまうでしょう。同調圧力が働きすぎることでストレスの温床となり、作業効率が大幅に落ちてしまうことが懸念されます。
助け合いとしてのピアプレッシャー(相互配慮)
同調圧力であるピアプレッシャーがプラスに作用するケースもあります。相互配慮によって組織の連帯感が高まる効果が期待できるのです。
適度なピアプレッシャーはお互いに励まし合い、助け合うなど、業務を効率化できる可能性があります。社員同士が切磋琢磨できる環境づくりのためには、適度に働くピアプレッシャーが必要だといえるでしょう。
ピアプレッシャーが強すぎる際の5つのデメリット

ピアプレッシャーが強すぎると組織に問題を引き起こすことは、先述の通りです。
ここからは、ピアプレッシャーが強すぎる場合の5つのデメリットを確認しましょう。
|
1.相互監視によるストレスの増加 2.残業を断りにくくなる 3.育休などを取得しにくい 4.企業内のイベントを断りにくくなる 5.自己主張が難しくなる |
1.相互監視によるストレスの増加
ピアプレッシャーが強すぎる組織では相互監視が行われ、常に周囲の目を気にしなくてはならなくなります。そのような環境では仕事に集中することも難しくなり、過剰なストレスから生産性が下がることが考えられます。
また逆に、ピアプレッシャーをうまく活用して生産性を高められたとしても、周囲の視線を意識し常に緊張しているせいで、ストレスを感じてしまいます。
2.残業を断りにくくなる
ワークライフバランスが浸透する中、ピアプレッシャーによって「残業を断れない」「意味もなく残業している」社員がいるかもしれません。
例えば、定時を過ぎているのに部署内で数人が残業をしていると、「自分の業務は終わっていても、残って仕事をしなくてはならないのではないか?」という同調圧力が発生してしまうのです。
3.育休などを取得しにくい
企業を挙げてワークライフバランスを推進しようとしても、組織内にピアプレッシャーが強く働いている場合は、有給や育休の取得率が上がらない可能性があります。働き方改革を掲げていても、社員同士が相互監視を行なっている環境下では、「自分だけが休みをとりづらい」と感じてしまうためです。
厚生労働省が行なった「平成29年度雇用均等基本調査」によると、平成29年度における男性の育休取得率は5.14%でした。女性の場合は83.2%となっていますが、それでも取得しづらい雰囲気があるようです。
育児休暇取得率の推移
|
性別 |
平成25年度 |
平成26年度 |
平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
|
女性 |
83.0% |
86.6% |
81.5% |
81.8% |
83.2% |
|
男性 |
2.03% |
2.30% |
2.65% |
3.16% |
5.14% |
参考:厚生労働省・平成29年度雇用均等基本調査 表5 有期契約労働者の育児休業取得率
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-29r/03.pdf
4.企業内のイベントを断りにくくなる
企業によっては定期的な懇親会や社員旅行など、福利厚生の一環としてのイベントが開かれることがあります。これらのイベントを楽しく感じる人と、そうでない人がいるのは仕方がないことです。しかし、ピアプレッシャーによって、不参加が許されにくい空気ができあがってしまうことがあります。
お酒の席が苦手な人や、退勤後はプライベートを優先させたいと思う人でも、参加を強制されてしまうことがあるのです。
5.自己主張が難しくなる
ピアプレッシャーによる同調圧力が働く環境下では、自己主張することが難しくなります。周囲に足並みを揃えた意見しか許されない風潮が生まれてしまうのです。よくない流れだと思っていても、周囲に配慮して意見をいえなくなってしまうと、多様性が失われることにより組織全体の発展が阻害されてしまう可能性があります。
部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら
適切なピアプレッシャーが働く5つのメリット

ピアプレッシャーが適切に働いている場合、企業や組織にとって多くのメリットを享受できます。具体的には以下の5つです。
|
1.切磋琢磨できる環境が生まれる 2.仲間同士で助け合える 3.お互いの長所に気づける 4.連帯感により生産性の向上につながる 5.チームワークの向上 |
1.切磋琢磨できる環境が生まれる
適切なピアプレッシャーが働くことで組織に軽い緊張感が生まれ、業務上のミスが減ったり、納期を厳守したスケジュール管理ができるようになったりします。
お互いに見られているという意識が適度な緊張感を育むのです。互いに競争意識が生まれ、切磋琢磨できる環境が生まれるでしょう。
2.仲間同士で助け合える
ピアプレッシャーが働く環境下では、お互いの仕事ぶりを観察しているため、何かトラブルが発生した時には助け合うことができます。同僚の問題解決のため、同調圧力ではなく、自発的に残業することもあるでしょう。上司や同僚の期待に応えるために、自発的な行動をおこしやすくなるのです。
3.お互いの長所に気づける
ピアプレッシャーによる相互配慮は、社員一人ひとりに合わせた働き方を可能にします。お互いをよく見ながら働いていると、次第に上司や同僚の長所に気づけるようになるでしょう。
共に働く仲間のよい部分を意識することで、よい部分を吸収できます。それらの積み重ねによって、自分の仕事におけるモチベーションを高めて行くことも可能です。
4.連帯感により生産性の向上につながる
ピアプレッシャーが適切に働くと、組織内に連帯感が生まれ、生産性の向上が期待できます。
「この上司や同僚たちとなら、目標を上回ることも難しくはない」というように、社員にとってのモチベーションを常に高く維持できるからです。
管理者としては適切なピアプレッシャーをうまくコントロールして、社員同士が協力しながら生産性を高められるように、部署のモチベーションを上げていきたいところです。
5.チームワークの向上
度なピアプレッシャーが働く環境では、上司や同僚と助け合いながらも切磋琢磨できる環境が生まれます。それは次第に、組織のチームワーク向上につながります。周囲からの程よいプレッシャーを受けることで自分を律し、周囲にも目を向けることで細かな気配りを可能にするのです。
ピアプレッシャーと日本企業の関係性

日本企業とピアプレッシャーには深い関連性があります。日本企業は社員同士の「和」を大切にしてきました。そのため、同調圧力としてのピアプレッシャーが強く働く傾向にあります。
日本企業では相互監視をしながらも、助け合う関係性によって発展してきました。終身雇用制が主流だった時代は、新卒で入った企業で定年まで働くのが一般的な考え方でした。
そのため転職することが難しく、企業内で強いピアプレッシャーを感じる機会が多くあったのです。
成果主義の導入で相互監視の側面が強くなる
日本企業において、終身雇用制に代わって成果主義が主流になり始めた頃から、ピアプレッシャーの持つ意味合いも変化してきました。
昇給や昇進の基準として年功序列ではなく、個人の成果が評価されるようになったため、社員同士がお互いの働き方を強く意識するようになったのです。これにより、成果主義の環境下のほうが、ピアプレッシャーの相互監視的な側面が強く働くようになりました。
働き方改革を阻害する原因に
長時間労働の是正や個人の事情に応じた働き方を実現するために、国を挙げて取り組んでいる働き方改革。
ピアプレッシャーによって、「同僚たちが残業しているのに、定時退社するのは気が引ける」というように、周囲の残業に引き込まれる形で長時間労働が発生するケースが多くあるのは先述の通りです。
無理のない働き方を実現するためには、ピアプレッシャーが強く働きすぎないように、企業をあげて対応する必要があります。部署単位で不必要な残業をしないよう、社員一人ひとりの働き方を管理しなければならないのです。
部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら
ピアプレッシャーをうまく活用しよう

ピアプレッシャーが適度に働く環境では、社員のモチベーションがアップし、お互いに助け合えるようになります。ピアプレッシャーの活用により職場の雰囲気をよくし、生産性を高めていくこともできるのです。
ここからは、ピアプレッシャーの具体的な活用法についてご説明します。
社員同士のチームワーク向上に活かす
ピアプレッシャーが持つ相互監視の側面を、チームワーク向上のために活用します。社員同士がお互いの仕事内容を把握することで、進捗の遅れやミスに気付きやすくなり、迅速なフォローを実現するのです。
そのためには、上司が部署のメンバーの状況を把握しておかなくてはなりません。業務で困っていたり、何か問題を抱えている社員がいたら、周囲を巻き込み迅速にフォローできる体制を整えておくためです。
・業務量の多さに困っている社員
・常に何か考えごとをしている社員
上記のような社員がいたら、仕事の割り振りを見直す、悩みについてしっかりと話を聞くなどの行動に移しましょう。比較的仲のよい社員同士で相談に乗ってもらうのも効果的です。
社員の状況を知るための方法としては、定期的な面談の他に、部署内のコミュニケーションの活性化も有効です。各社員のコンディションを明確にし、同僚間で自然に助け合える状況を作り出しましょう。
★社内コミュニケーションを活性化させたい・同僚間の自然な助け合いを促したい方におすすめのツール:「Unipos(ユニポス)」
お互いにフォローし合える体制づくりをめざす
ピアプレッシャーの相互監視を適切に活用するためには、社員がお互いを過剰に監視したり、周囲からの同調圧力に支配されたりしないように、しっかりと管理することが重要です。
適度なピアプレッシャーの中では、お互いの働き方や仕事への向き合い方について注視するようになります。特に新入社員に対しては、周囲が進んで仕事ぶりを見るようになり、フォローの輪が広がることが予想されます。ピアプレッシャーが適切に働くことで、社員の離職率低下にも貢献できる可能性が高まるのです。
お互いのよい部分や改善すべき点を指摘し合える文化を作ることも大切です。社員が周囲からの視線を意識し、自分を高めていける状況を作り出せれば、健全な競争が起こる組織にできるでしょう。
適切なマネジメントが重要
上司や人事部としては、社員同士の間にピアプレッシャーが働きすぎていないかを、常に把握しておかなければなりません。強すぎるピアプレッシャーによって社員がストレスを感じていないか、常に気を配る必要があるのです。
ピアプレッシャーが全く発生しない環境はないと考えて、うまくマネジメントしていくのが重要です。ピアプレッシャーを味方につけてもらうためにも、定期的な面談により社員のモチベーションを高めて業務に励んでもらうようにしましょう。
まとめ
ピアプレッシャーは同調圧力であり、強く働きすぎるとストレスを感じるなどのデメリットが、適度に働くと切磋琢磨できるなど、多くのメリットがあることがお分りいただけたかと思います。
ピアプレッシャーが適切に働いていると、チームワークが高まり、生産性の向上が期待できます。
社員同士の関係性をきちんと把握し、ピアプレッシャーをうまくコントロールしながら、社員がストレスなく働ける環境づくりをめざしてください。
部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら