
「自社の課題を解決にうまくつなげられない」「部下が課題を認識していない」「課題があると感じているが根本的な原因をつかみきれない」と悩む管理職の方は多いのではないでしょうか。会社の持つ課題は「組織課題」と呼ばれるもので、従業員が一丸となって取り組む必要があります。会社の成長には組織課題の解決は欠かせません。そのためには適切なマネジメントが必要です。この記事では、組織課題についての情報と管理職の役割を解説します。
組織課題とは?

組織課題とは、組織が目指す姿になることや目標を達成することを妨げる要因となるものを指します。時代背景や業界の状況・競合の存在、組織に属する従業員など、会社を取り巻く環境や要素は常に変化するものです。そのため、会社の持つ組織課題も変化します。
組織課題は以下の2種類に大別できます。
・顕在化している組織課題
・潜在化している組織課題
それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。
顕在化している組織課題
組織課題には、従業員が課題の存在を既に認識している、すなわち顕在化しているものがあります。課題に対して取り組みが必要だと考えられていたり、言語化されていたりするものです。そのため、発見しやすく解決に向けで動き出しやすいという特徴があります。
ただし、顕在化しているといっても、すべての従業員が認識しているものから、一部の従業員しか認識していないものまでさまざまです。
潜在化している組織課題
従業員に認識されておらず潜在的に存在する組織課題もあります。言語化されておらず、組織の活動や行動から判明する課題です。
そもそも存在に気づいていないため、積極的に課題を発見しようと行動しなければ見つけることはできません。そのため、顕在化している組織課題に比べると解決の難しい課題です。
組織課題としてよくある事例

組織課題には具体的にどのようなものがあるのか、イメージしにくい方もいるのではないでしょうか。ここからは、よくある組織課題を紹介します。自分の会社に当てはまる課題はないか、ぜひ参考に読んでみてください。
組織全体を俯瞰して見ていない
全体を俯瞰できておらず、目の前の業務や数値目標にとらわれているという課題です。個々の業務や目標達成はできても、組織としてのまとまりがなくなり、全体的な業績の向上につなげられていない状態です。この要因には、企業理念・経営戦略の共有ができていないことや、部署内でのコミュニケーションができていないことなどが挙げられます。
日々の業務を通してどのような結果を生み出せばいいか、目標を達成することで会社がどうなることを目指しているのか、という全体を俯瞰する視点を持ってもらうことが大切です。業務や目標が会社のあるべき姿にどのようにつながるのかを理解して、行動してもらうような解決策を考えなければなりません。
プロセスの可視化が不十分
成果は見ていても、そこに至るプロセスを把握できていないケースがあります。プロセスを可視化して評価を行う仕組みがなければ、経理や総務など、バックオフィス職の正当な評価ができず、不満の元となるでしょう。また、成果だけを求める余り、人間関係をおろそかにする人が出てくる可能性もあります。
さらに、プロセスが可視化されていなければ業務の属人化が起こりやすくなります。属人化によって問題が生じるのは、その業務を担っていた人が退職や異動をしたあとであって、平時には顕在化しにくいものです。属人化しない仕組みをつくるためにも、プロセスを可視化することは大切です。
煩雑な事務作業

組織課題とは、組織が目指す姿になることや目標を達成することを妨げる要因となるものを指します。時代背景や業界の状況・競合の存在、組織に属する従業員など、会社を取り巻く環境や要素は常に変化するものです。そのため、会社の持つ組織課題も変化します。
組織課題は以下の2種類に大別できます。
・顕在化している組織課題
・潜在化している組織課題
それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。
顕在化している組織課題
組織課題には、従業員が課題の存在を既に認識している、すなわち顕在化しているものがあります。課題に対して取り組みが必要だと考えられていたり、言語化されていたりするものです。そのため、発見しやすく解決に向けで動き出しやすいという特徴があります。ただし、顕在化しているといっても、すべての従業員が認識しているものから、一部の従業員しか認識していないものまでさまざまです。
潜在化している組織課題
従業員に認識されておらず潜在的に存在する組織課題もあります。言語化されておらず、組織の活動や行動から判明する課題です。
そもそも存在に気づいていないため、積極的に課題を発見しようと行動しなければ見つけることはできません。そのため、顕在化している組織課題に比べると解決の難しい課題です。
組織課題としてよくある事例

組織課題には具体的にどのようなものがあるのか、イメージしにくい方もいるのではないでしょうか。ここからは、よくある組織課題を紹介します。自分の会社に当てはまる課題はないか、ぜひ参考に読んでみてください。
組織全体を俯瞰して見ていない
全体を俯瞰できておらず、目の前の業務や数値目標にとらわれているという課題です。個々の業務や目標達成はできても、組織としてのまとまりがなくなり、全体的な業績の向上につなげられていない状態です。この要因には、企業理念・経営戦略の共有ができていないことや、部署内でのコミュニケーションができていないことなどが挙げられます。日々の業務を通してどのような結果を生み出せばいいか、目標を達成することで会社がどうなることを目指しているのか、という全体を俯瞰する視点を持ってもらうことが大切です。業務や目標が会社のあるべき姿にどのようにつながるのかを理解して、行動してもらうような解決策を考えなければなりません。
プロセスの可視化が不十分
成果は見ていても、そこに至るプロセスを把握できていないケースがあります。プロセスを可視化して評価を行う仕組みがなければ、経理や総務など、バックオフィス職の正当な評価ができず、不満の元となるでしょう。また、成果だけを求める余り、人間関係をおろそかにする人が出てくる可能性もあります。
さらに、プロセスが可視化されていなければ業務の属人化が起こりやすくなります。属人化によって問題が生じるのは、その業務を担っていた人が退職や異動をしたあとであって、平時には顕在化しにくいものです。属人化しない仕組みをつくるためにも、プロセスを可視化することは大切です
煩雑な事務作業
事務作業に時間を取られ、ビジネスを大きくするための時間が取れなければ、会社の成長に支障をきたします。事務作業が多いとミスも発生しやすいため、業務内容を見直して無駄を省くなどの対策が必要です。
ただし、簡略化を目指すあまりに必要な工程までなくさないように注意が必要です。そのため、単に業務を減らすのではなく、ツールを導入して効率化することも視野に入れましょう。
コミュニケーションの不足
上司に相談しにくい雰囲気がある、他部署との連携が取れていないなど、コミュニケーションが不足することもよくある組織課題の一つです。必要なコミュニケーションが取れなければ仕事を進めることはできません。
認識の齟齬を正せず大きなミスにつながったり、人材育成の機会を失ったりすることもあります。その結果、共通の目標に向けて協力ができなくなってしまいます。さらに、会社の雰囲気にも影響を与え、離職につながることもあるでしょう。コミュニケーション自体は個人同士で行うものですが、組織が成果を上げるために組織全体で取り組まなければならない課題です。
人材育成が不十分
研修制度を設けていても人材が育っておらず、効果を実感できない場合もあります。この課題を解決するには、研修の対象となる従業員、研修内容、フォローアップ方法など、どこに問題があるのかを精査することが必要です。
日々の業務内容がかけ離れないように研修内容を考える、日々の業務でフォローするといった、研修と実務を結び付けるサポートを行うことが大切です。さらに人材戦略、研修の目的、研修終了後のキャリアパスや利用できる制度など、人材育成の結果となる理想像・未来の姿が周知されていなければ効果は期待できません。
また、次世代のリーダー候補となる人材が育っていない場合は、次の経営・管理職の選定に不安が残ります。組織の通常業務と育成を行う場合は十分に時間や手間をかけられないこともあるでしょう。どうやってリーダーを輩出するのか、どうやって従業員の能力を伸ばすかを考えなければなりません。
さらに、従業員に能力差がある場合はサポートを行い、差を縮めることも必要です。能力の低い人はモチベーションの維持が難しく、能力の高い人は業務負担が増えて不公平に感じてしまいます。能力差が縮まれば組織の効率性向上や成果も期待できます。モチベーションの維持もしやすく、組織としての一体感も高まるでしょう。
企業戦略などへの理解が不十分
企業戦略や経営理念を知っていても、従業員自身が自分事ととらえておらず、浸透していないケースもあります。経営層や管理職が戦略や理念を掲げていても、それらに沿った行動が伴わなければ意味がありません。実際に業務を行う従業員に、戦略や理念を浸透させることは必須といえます。
そのためには、業務において重視する価値観や行動原則に戦略や理念を落とし込み、日々の実務にどう結びつくのかを理解してもらう必要があります。そうすることで、統一感や外部からの信用、ブランドの価値向上などにつながるでしょう。
声の小さい人を軽視
声の大きい人や主張の強い人の意見は現場の声として認識されがちです。しかし、それが現場全体の意見とは限りません。立場が変われば意見も変わり、同じ役職であっても人によって感じることは当然ながら違います。現場の一意見として認識しつつも、他の人の声も聞いて客観的な判断をすることが大切です。
組織課題の見つけ方は5つ

組織課題の中でも、特に潜在的な課題は見つけようと動かなければ発見できません。顕在的な課題でも、人によって認識が異なるため、洗い出して客観的にすり合わせる作業が必要です。そのためには幅広い従業員からの意見が求められます。トップの意志と明確なメッセージを従業員に伝え、組織をよりよくするために協力を求めることが必要です。
ここでは、組織課題を見つける主な方法を5つ紹介します。さまざまな方法を組み合わせて、組織課題を見つけるための参考にしてください。
1.従業員にアンケートを実施する
従業員へのアンケートを実施することで、各従業員の認識している課題を集められます。あらかじめ質問を用意するだけでなく、自由記載欄も用意するとより詳細な情報を得られるでしょう。従業員によって、感じている課題はさまざまです。一部の人のみ認識している顕在的な課題も把握できます。また、上層部にはわからない現場の課題や思いなどを把握することにも役立つでしょう。
2.個々の従業員と面談を行う
上司や管理職が従業員一人ひとりと面談を行うことで、個々が課題と感じていることを、アンケートよりも詳しく具体的に聞き取れます。立場によって課題と感じていることは異なるため、人によって同じ課題を違うふうに捉え、別のことを原因と認識していると気づくこともあるでしょう。具体的な方法は、人事によるヒアリングや上司との面談などが挙げられます。面談を行う場合は、発言によりその従業員が不利にならないように、人事評価に影響しないこと・匿名性を確保することを保証することが大切です。
3.従業員同士の意見交換を実施する
従業員を集めてブレインストーミングを行い、意見交換することも一つの方法です。
複数人で意見交換をすることでアイデアを出しやすくなる、潜在的に感じていた違和感を言語化しやすくなるといった効果が期待できます。従業員にとっては、同じ事象を他の従業員はどう感じているかを聞ける機会にもなります。気軽に話しやすい雰囲気づくりにも努めましょう。
4.マインドマップを活用し課題を洗い出す
マインドマップとは、あるテーマから連想されるアイデアや情報を書き出し、線で繋いで思考を拡大する手法です。認識していなかった潜在課題が見つかる可能性があります。組織課題を探す初期段階において、情報の整理に役立つでしょう。
5.ITツールを活用しデータ収集・分析を行う
客観的なデータを収集・分析して課題を洗い出すためにITツールを活用することも一つの方法です。工数管理や作業時間などを可視化することで、個人の主観ではなく事実に基づいた課題の検討ができるでしょう。導入にはコストが必要となる場合もありますが、迅速な課題の発見が期待できます。
データ収集には業務日報や報告書を活用することも有効です。従業員からの報告をもとに、何をどのように行ったのか、どれくらいの工数や時間がかかったのかを把握できます。それらを客観的に分析することで、課題の発見につながるでしょう。
日常的な業務をデータとして可視化することは、日頃意識していなかった潜在的な組織課題の発掘に特に有効です。
組織課題の解決方法

組織課題を解決するには、一つひとつのステップを確実に進めていくことが大切です。組織全体の課題であるため、すぐに改善できるわけではありません。焦らずにじっくりと取り組みましょう。
1.組織課題の把握
上で紹介した方法を参考に組織課題を探してみましょう。一つの方法ではなく、あらゆる方法を組み合わせることで、組織課題を見つけるヒントを得られるでしょう。この段階では小さなこともなるべく多く洗い出すことが大切です。多くの課題を把握したうえで、のちに優先順位を付けて改善する課題を絞ります。
2.把握した組織課題の共有
組織課題を把握できたら、従業員に共有しましょう。課題を踏まえて、どのような方向に進もうとしているのかも伝えます。その際には課題を客観的に見て整理し、何を解決すべきか、どれくらいの熱量で取り組むのかを、誰にでもわかるよう客観的に言語化することが必要です。
従業員の認識統一を図り、当事者意識を持ってもらえるよう伝えましょう。
認識をすり合わせることで、同じ方向を見据えたさまざまな立場からの多角的な意見を集められます。また、課題を放置することの危険性を伝えることも当事者意識を持ってもらうことに役立ちます。
3.組織課題の原因究明と解決
表面化した課題を解決できても、その根幹にある考え方や行動原理、雰囲気など、課題の本当の原因を見つけなければ課題は繰り返し生じます。根本的・本質的な問題をとらえることが大切です。そして、どうすれば解決できるかを考えましょう。解決策をまとめたら、本当に解決できるのか再度検討します。同じ事象でも立場によって見え方が違うため、さまざまな立場の従業員が忌憚なく意見を交わして原因を特定する必要があります。そのためには、従業員が立場に関わらず率直な意見を言えるように配慮することも大切です。
4.組織課題の優先順位付け
さまざまな方法で組織課題を探すことで、複数の課題が見つかることが少なくありません。しかし、すべてを並行して進めるのではなく、何を最初にすべきかを見極めましょう。一度に複数の課題に取り組むと、中途半端に終わる可能性が高いものです。優先順位の高い課題を選択し、集中して取り組むことで、精度の高い解決ができるでしょう。
優先順位の付け方は、次のいずれかをおすすめします。
・組織としての目標達成の最も大きな障壁となっているもの
・取り組みやすいもの、小さな課題でも組織の根幹に関わる基本的なもの
前者は簡単には解決できないものですが、解決できれば劇的な効果が期待できます。後者は小さな成功体験を積むことで、従業員の意識を前向きに変えることができるでしょう。
5.解決方法の実行
組織課題の優先順位を付けたら、一つずつ解決方法を試しましょう。複数試すと、効果が出てもどの解決方法が効果的であったのかが把握できません。従業員の負担にもなるため、解決方法は一つに絞って集中して取り組む方が賢明です。実行してもすぐに効果が出ないことは多くあります。しかし、根気強く取り組みましょう。組織課題を達成するためには、小さなゴールをいくつも設定することも効果的です。少しずつでも「進んでいる」「成長している」と実感できるため、モチベーション維持につながります。さらに、成功体験を積み重ねることで達成感や自信も得られるでしょう。
6.検証と振り返り
解決方法を実行したら、どのような効果があったか、どのような結果になったかを検証します。原因の特定から解決方法の立案、実行までの流れを振り返り、良かった点や悪かった点、次に改善する点などを挙げましょう。そして新たな仮説を立て、次につなげることが大切です。
一度の実行で完璧に解決することは難しいものです。また、組織は少しずつ変化するものであり、過去に正しかったことが現在も正しいとは限りません。そのため、「仮説・実行・検証」というサイクルを繰り返し、常によりよい解決方法を模索し実践する必要があります。
Uniposには「組織の状態を効率的に振り返りできるアナリティクス機能」があります。組織課題の原因究明や解決に役立てることができるでしょう。
組織力向上のために管理職ができること

組織の課題を解決してよりよい状態にするには、管理職のマネジメントスキルが重要です。なぜなら管理職は経営層などの上層部と従業員の間を取り持つポジションであるからです。
上層部の意思を部下と共有し、部下の意見や行動を引き出すためにできることは多くあります。マネジメントスキルは組織課題の解決のカギとなるでしょう。
管理職としての自覚を持つ
管理職は自身が結果を出すことよりも、どうすれば部下とともに結果を出せるかを考えることが求められます。例えば、すべてを事細かに指示するのではなく部下にも考えてもらう、部下に気づきを与えるような対話をするといったことが必要です。
優れたプレイヤーから管理職になった方も多いかもしれませんが、プレイヤーの目線だけでは良い管理職とはいえません。管理職は組織のマネジメントの役割を果たさなければならないという自覚を持つ必要があります。
部下の主体性を引き出す
部下と課題を共有し、意見を積極的に取り入れることで、部下は「自分も役に立てる」「自分の話も聴いてもらえる」と感じます。その結果、管理職への信頼が増し、主体的に課題解決に取り組む動機となるでしょう。
また、部下の努力や成果を認めて給与に反映させるなど、部下の処遇や環境にアプローチすることもやる気につながります。
さらに、課題解決に向けた具体的な行動を示すことも一つの方法です。目指す結果を共有しただけでは、うまく動けない部下もいるでしょう。はじめのうちは具体的な行動やその頻度、タイミング、チェックすべきことなどを伝えておくことで、部下は行動が課題解決にどのように結びつくのかが理解できます。そうすることで、徐々に主体的な行動にもつながるでしょう。
部下と個別に関わる
部下の能力を最大限に引き出して課題解決に活かすためには、一人一人に適したアプローチが必要です。それぞれ適正や強みが違うため、面談やヒアリングは複数人まとめて行うのでなく、個別に行いましょう。大勢の中で意見を言いづらくても、1対1なら話しやすいという人もいます。部下は個別で丁寧に話を聞いてもらえることで、やりがいや信頼感が増すでしょう。
職場環境を改善する
職場環境が働きにくいものであれば、将来的に離職を考えることもありえます。当事者意識を持って組織課題に取り組んでもらうためには、良い組織にしたい、これからも頑張りたいと思ってもらえるような環境づくりも大切です。働きやすいオフィス環境整備・休暇制度の整備など、意欲を保つためにも職場環境を整えましょう。
事例を共有する
事例は結果に関係なく従業員と共有しましょう。成功例だけでなく失敗例も知ることで、一人ひとりの気づきにつながります。それぞれの気づきを共有できれば、さらなる気づきも得られるでしょう。Uniposには部下のモチベーション向上や連携の強化に役立つ機能があります。全社員が見られるタイムライン上で、従業員同士が称賛しあったり、少額のインセンティブをおくったりできます。モチベーションの向上や従業員の活発な交流につなげられる機能です。
活用シーン | 心理的安全性を高め、挑戦できる風土をつくる ピアボーナスのUnipos
組織課題の解決に役立つフレームワーク

組織の課題を解決するには、まず課題の把握が必要です。その糸口として、フレームワークが役立ちます。フレームワークによって課題を構成する要素を整理できるでしょう。
7S
7Sとは組織の重要な要素を以下の7つに分解して考えるフレームワークです。
1.Strategy:戦略
2.Structure:組織
3.System:社内システム
4.Skill:組織のスキル
5.Staff:人材
6.Style:社風
7.Shared Value:価値観
1~3は短期的な改善が可能なハード面で、3Sと呼ばれます。経営層などの上層部の意思決定によって、比較的簡単に変更や改善が可能です。
4~7は長期的な改善が必要なソフト面で、4Sと呼ばれます。3Sとは違い、変えるためには時間や労力が必要です。
見つかった組織課題が7Sのうちどれに当てはまるかを考える、7Sそれぞれに関する組織課題は何か議論するといった活用方法があります。7Sを実践することは、幅広い分野の課題を網羅的に見つけることに役立つでしょう。
SWOT分析
SWOT分析とは自社の外部環境・内部環境を以下の4つの要素から分析するものです。
1.Strength(強み)
2.Weakness(弱み)
3.Opportunity(機会)
4.Threat(脅威)
SWOT分析は、組織の課題や問題点の把握のほか、戦略策定やマーケティングの意思決定などを行うのに役立ちます。
PDCAサイクル
PDCAサイクルとは業務改善のためのフレームワークです。以下のサイクルを繰り返すことで継続的に問題解決を目指すものです。
1.Plan(計画)
2.Do(実行)
3.Check(評価)
4.Action(改善)
原因の特定から検証までのサイクルが大切であることは上でも触れましたが、それがまさにPDCAサイクルを表しています。一度実践して終わりではなく、何度も繰り返してより良い結果に近づけていくことが大切です。
組織課題を見つけて解決しよう
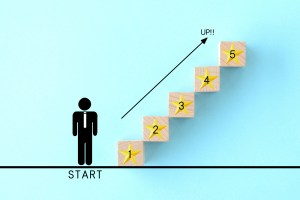
組織課題には既に顕在化しているものもありますが、認識されていない潜在的なものもあります。あらゆる課題を洗い出し、本質的に解決すべきものを把握することが解決のための重要なステップです。
見つかった課題を共有し、従業員の認識をすり合わせて解決につなげるには、管理職のマネジメントスキルが問われます。また、改善を繰り返して少しずつでも前進する意識も大切です。
根気のいる作業ですが、組織課題を乗り越え続けることで組織として成長できます。会社の現状に課題を感じている場合は、組織課題の把握から始めてみましょう。


