
サバティカル休暇ってどんな休暇のことなの?
サバティカル休暇は、導入したらどんなメリットがあるの?
働き方改革がメディアで大きく話題として取り上げられている今、休暇制度についても大きな変化が訪れています。欧米では一般的な長期休暇である、サバティカル休暇を取り入れようとする企業も増えてきました。
しかし、長期休暇を制度として導入するには、制度改定や長期休暇に対応できるように業務内容の整備や準備が必要となるので、導入を検討しつつも、今一歩踏み切れていない会社も多いようです。
そこで、この記事では、サバティカル休暇の基本的な情報から
・サバティカル休暇取得のメリット・デメリット(企業側・従業員側双方)
・サバティカル休暇導入する際の3つの注意点
・サバティカル休暇の導入事例
をご紹介します。
サバティカル休暇導入を検討している企業や人事労務担当の方は、特に導入の注意点等を参考にして、しっかりと導入前の整備や準備を進めてください。
1.サバティカル休暇とは?
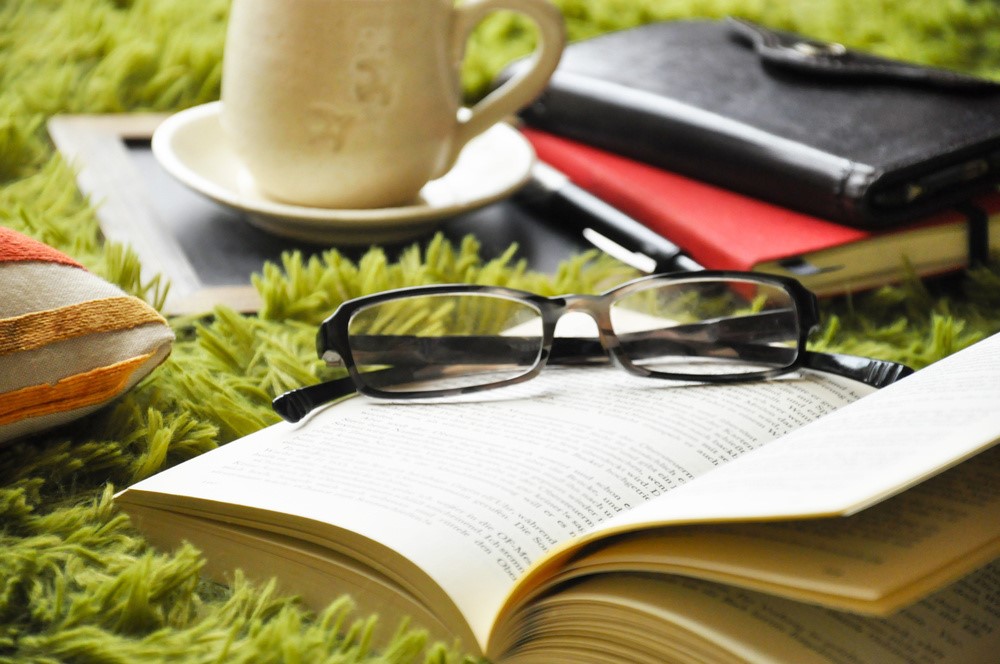
サバティカル休暇とは、所定の勤続年数を超えた社員が取得できる、使途に制限が設けられていない長期休暇のことです。英語でサバティカル(sabbatikal)の意味は、「研究休暇」となっており、「サバティカル」のみで長期休暇のことを指します。
法律で定められた休暇ではないため、各企業がそれぞれ自由に休暇制度を制定することができますが、一般的には、勤続年数が一定期間(3年〜5年以上、10年以上と定める会社もある)を超えた社員に対して、1ヶ月以上の長期休暇を与えるケースが多く、1年間という非常に長い期間休暇が取得できる会社もあります。
サバティカル休暇を有給にするか無給にするかは、会社判断で決めることができますが、完全無給では休暇の取得率が低くなるので、ある程度の支援金を支給する会社が多いようです。
また、サバティカル休暇は基本的に休暇中に何を行うことも制限されない自由な休暇ですが、休暇中に大学や専門機関において業務に関係する研究等を行うことがはっきりしていれば、補助金や援助金を支給する会社もあります。
1-1.サバティカル休暇が注目されている理由
すでに欧米先進国で導入されているサバティカル休暇ですが、経済産業省が後押ししていることもあり、日本国内の企業も積極的に取り入れるようになっています。
その理由ですが、近年クローズアップされている「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」に加えて、政府主導で行われている「働き方改革」により、働く時間と個人の生活の時間のバランスを取ることが重要視される時代になってきたことが大きいと言えます。
サバティカル休暇を導入することにより、心身のリフレッシュとともに、通常の勤務中にはできなかったスキルアップやキャリアアップのための自己研鑽の時間をたっぷりと取ることができるのは、働くスタッフにとっても、企業側にとってもメリットが大きいからです。
加えて、サバティカル休暇を導入することにより、リモートワークへのシフト、長期休暇中のスタッフのためにワークシェアリング制度を導入するなど、労働環境の流動化を促すという効果もあります。
1-2.日本の長期休暇取得の状況
日本人は働き過ぎだと言われ、過労死問題がマスコミで大きく取り上げられることも少なくないですが、実際に日本国内で長期休暇取得の状況はどうなっているのでしょうか。
厚生労働省『平成30年就労条件総合調査結果の概況:結果の概要』によると、
特別休暇制度のある企業のうち、1週間以上の長期休暇を導入している状況は、会社規模で比べると、
1000人以上/21.3%
300〜999人/18.9%
100〜299人/18.9%
30〜99人/12.8%
となっており、企業の規模が大きいほうが長期休暇が取りやすい現状がわかります。
また、1週間以上の長期休暇中に賃金を支給する企業の割合は、
全額支給/85.7%
一部支給/1.5%
無給/12.9%
となっており、有給の長期休暇がほとんどであることがわかります。
2.サバティカル休暇のメリット・デメリット

サバティカル休暇のメリットとデメリットを企業側、従業員側に分けてご紹介します。
2-1.企業側のメリット・デメリット
【メリット】
・介護や病気療養等の理由による退職を防ぐことができる
サバティカル休暇は自由に使える休暇なので、病気療養や介護などが目的であっても取得できますから、介護や病気療養等を理由とした退職を防止することができます。
勤勉なタイプで体調が優れないまま、持病を抱えつつ働いている人であれば、サバティカル休暇を利用して、十分に治療に専念してもらえます。
高齢化社会を反映して、親の介護等を理由に退職する人も増えていますが、サバティカル休暇を導入して長期休暇を取ってもらうことで、退職せずに職場復帰が可能になります。
|
【休職と長期休暇との違い】 休職とは、何らかの事由により業務に従事できない社員に対して、社員としての身分を保たせたまま、一定期間、労務の提供を免除または禁止する制度です。 主な休職理由としては、病気療養や海外留学など。最近では親の介護等を理由とした休職も増えてきました。 休職の場合、就業規則等に「休職期間満了までの間に復職できない場合は、期間満了をもって自動的に退職扱いとする」等の自動退職規定があれば、決められた期限までに復職ができなければ、休職期間満了となり退職することになります。 サバティカル休暇のような長期休暇制度を利用する場合には、退職はせず、休暇終了後に職場復帰することができます。 |
・企業のイメージアップが図れる
「ブラック企業」という言葉がありますが、福利厚生が充実し長期休暇が取れる会社は、「ホワイト企業」というイメージに繋がります。
就活中の学生の場合、就職した後、自分のやりたいことをする時間をたっぷり取るには退職しないとダメだろうと考えてしまいがちですが、サバティカル休暇のような長期休暇が取得できることがわかれば、会社選びの際にかなり好印象となるでしょう。
また、サバティカル休暇が定着すれば、業界誌などにも取り上げられて、さらにイメージアップすることもあるかもしれません。
【デメリット】
・長期休暇中に滞りなく業務を進めるための社内整備が必要
サバティカル休暇の期間は1ヶ月以上になることが多いため、その期間中の業務をどうするかがまず問題になります。1年間というような超ロングになる場合は、残される社員への業務の引き継ぎも、しっかりと行わなければなりません。
属人的な仕事のやり方が主流だった企業の場合は、サバティカル休暇導入をきっかけに、誰が仕事をしても同じ成果が出せるような仕組みを構築することをお勧めします。
・サバティカル休暇後のスムーズな仕事復帰のための社内整備が必要
サバティカル休暇を取得した人が休暇終了後にスムーズに職場復帰できるように社内整備することも必要です。
1ヶ月程度の休暇であっても、社内の雰囲気が変わっていたり、業務のやり方が改善されているケースは多いでしょう。1年もの長期休暇からの復帰となれば、「浦島太郎」のような状況になってしまい、疎外感を感じてしまうスタッフもいるかもしれません。
普段、年末年始やGW程度の休暇であっても、休暇明けの勤務は辛く感じるものです。スムーズに業務に復帰してもらうためのバックアップ体制はしっかりと整えておきましょう。
2-2.従業員側のメリット・デメリット
【メリット】
・十分な休養がとれてリフレッシュできる
サバティカル休暇の最大のメリットは、十分に休息を取ることができ、心身ともにリフレッシュできることでしょう。普段の休養では解消できなかった疲れやストレスが軽減できます。
趣味に没頭したり、海外旅行に行って知見を広げたり刺激を受けることで、新しい価値観が生まれることもあるでしょう。リフレッシュすることで働く意欲が復活し、仕事に対するモチベーションが上がります。
・専門知識の向上やスキルアップが図れる
「サバティカル(sabbatikal)」の元々の意味は、「研究休暇」です。サバティカル休暇であれば、大学などの教育機関に通って専門的知識の向上を図ることが可能になります。
サバティカル休暇の期間にもよりますが、海外への語学留学も可能になりますし、ワークショップなどに参加して貴重な体験をすることもできます。
専門的知識の向上、スキルアップによって、仕事に復帰後のキャリアップも望めるでしょう。
【デメリット】
・長期休暇中に価値観が大きく変化して職場復帰が難しくなるケースもある
サバティカル休暇中に、さまざまな経験をすることにより、それまでの価値観が大きく変わってしまう人もいます。長期休暇中に、自分の過去を振り返ることで、残りの人生をどう生きるかを考えてしまう人も少なくありません。
たとえば、発展途上の国へ旅行に行って衝撃を受け、これまでとは全く違う仕事がしたくなる人もいます。
このデメリットを回避するには、サバティカル休暇取得前に、しっかりと「休暇取得の目的」をはっきりとさせておくことが必要です。
3.サバティカル休暇を導入する際の3つの注意点

サバティカル休暇を導入する際の注意点をご紹介します。注意点は3点ありますが、2章の企業側のデメリットでもご紹介した通り、サバティカル休暇導入前の社内整備や準備が必要となります。
1ヶ月以上の長期休暇取得がスムーズに行われるように綿密に準備をするようにしましょう。
3-1.サバティカル休暇を取得しやすい環境を整える必要がある
もともと、日本の職場環境や労働環境は、長期休暇を取りづらい状況にあります。人手不足が深刻化している職場や、属人化した業務を行なっている場合は、特に「周りに迷惑をかけたくない」といった理由で、長期間の休暇を取得しない人もいます。
サバティカル休暇導入を成功させるには、まず全社で「休暇を申請する」ということに抵抗感のない社風や考え方に変えていくことが先決です。
場合によっては、役員や上司クラスが率先して長期休暇を取得して、部下クラスが長期休暇を取得してもいいのだ、と思わせることも大切です。
「休暇を取得しやすい環境」が整うまでは少し時間がかかるかもしれませんが、まずは社内の風通しを良くしていく体制づくりに着手しましょう。
3-2.サバティカル休暇中の業務をどう対応するかを考えておく
サバティカル休暇を取得する人間が欠けた状態でどう社内の業務を回していくか、誰が休暇取得者の業務を引き継ぐのか、など想定しておくことが必要です。
休暇の期間によっては、休暇取得者の業務を分担ではなく、一人で請け負う人が必要になるかもしれません。引き継ぎにかかる時間はどれくらいか?休暇中に緊急連絡しなくてはいけないケースはどんなケースなのか?など、シミュレーションをしっかり行いましょう。
3-3.サバティカル休暇復帰後の対応も考えておく
サバティカル休暇取得者が職場復帰する際のバックアップ対応についてもしっかりと考えておきましょう。1ヶ月〜1年近い長期休暇が終わって職場に戻る場合、休暇取得者と通常業務を続けてきた人との間には少なからずギャップが生まれます。
リフレッシュして充電が完了した状態にあり、新しい仕事にチャレンジしようと高揚感がある場合には、戻ってからやる仕事に物足りなさを感じてしまうかもしれません。逆に、長期休暇終了後で軽い抑うつ感を感じている場合は、活気のある職場にすぐになじめず、疎外感を感じてしまうこともあるかもしれません。
早く職場に慣れて、通常業務へと戻ってもらうためにも、休暇取得者と良く話し合い、無理のない復帰のロードマップを作成するようにしましょう。
4.サバティカル休暇の導入事例

日本国内で、すでにサバティカル休暇を導入している企業をご紹介します。
大企業ということもあって、休暇の期間も非常に長く、支援金や手当の支給があります。自社への導入の際の参考にしてください。
4-1.ヤフー株式会社
ヤフーでは勤続10年以上の正社員を対象に、2~3か月の範囲で取得できるサバティカル休暇制度を導入しています。自らのキャリアや経験、働き方を見つめなおし、考える機会をつくることで、本人のさらなる成長につなげることを目的とした休暇制度となっています。休暇支援金として基準給1か月分が支給されます。
参考:ヤフー株式会社 RECRUITMENT 制度・環境「休暇」
4-2.ソニー株式会社
ソニーのサバティカル休暇は、「フレキシブルキャリア休職制度」という名称で最長5年取得できます。
「ソニーでのキャリア展開を豊かにするため、配偶者の海外赴任や留学への同行で知見や語学・コミュニケーション能力の向上」を目的とする休暇で「ご自身の専門性を深化・拡大させるための私費就学」が理由であれば、最長2年の長期休暇が取得できます。
参考:ソニー 採用情報 人事制度「成長支援・キャリア実現のための施策」
4-3.株式会社リクルートテクノロジーズ
リクルートでは、勤続3年以上の社員を対象に、3年ごとに最大連続28日間取得できる長期休暇制度・STEP休暇を導入しています。心身のリフレッシュや、自己の成長機会のための学びに充てるなど、休暇の目的は自由となっています。休暇を応援する手当として一律30万円が支給されます。
5.まとめ
サバティカル休暇とは、所定の勤続年数を超えた社員が取得できる、使途に制限が設けられていない長期休暇のことです。
ここで、サバティカル休暇導入の際の3つの注意点を復習しておきましょう。
1.サバティカル休暇を取得しやすい環境を整える必要がある
2.サバティカル休暇中の業務をどう対応するかを考えておく
3.サバティカル休暇復帰後の対応も考えておく
まず、最初に手をつけることは、長期休暇を取得しやすい、風通しの良い社風へと変えていくことです。サバティカル休暇は制度だけ整えても、取得する人がいなければ絵に描いた餅になってしまいます。
サバティカル休暇導入を検討中の企業や人事労務担当の方は、この点に注意して、サバティカル休暇導入を成功させてください。


