
ビジネス書で話題に上っている「ティール組織」という言葉は知っているけども、わかっているのは、これまでのマネジメント方法とは違うアプローチで組織を機能させるという概要のみ。成功例は海外が多いようだし、ファシリテーターは著者本人だけで日本語の関連書籍も少なめです。それに、そもそも日本の組織では通用しないんじゃないか、などティール組織採用のハードルの高さを感じている人事担当者は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ティール組織についてよく知らない人・全く本を読んでない人でもよくわかる
1.ティール組織とは?
2.ティール組織が成功するのための3大要素
3.ティール組織のデメリット
4.組織がティールになるまでの5段階意識フェーズ
5.ティール組織に関した3大勘違い
6.ティール組織を取り入れている企業事例
をまとめました。
最後までお読みいただければ、
- なぜティール組織が世界で注目されるのか
- 自分の組織には取り入れ可能なのか
が把握でき、今後の組織運営の一案として検討・提案をすることができるようになります。また、参考ではありますが、最後にオススメ書籍として関連書を提示しましたのでご活用ください。
1ティール組織とは?
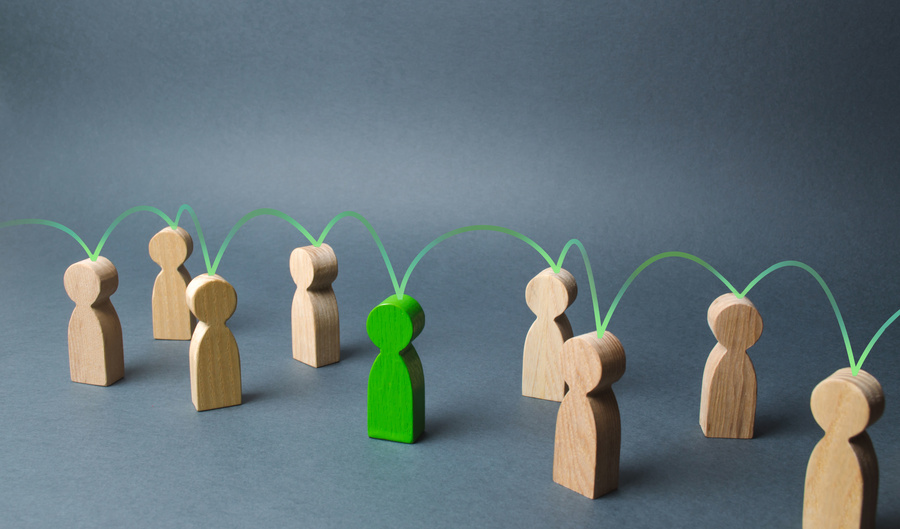
1-1.ティール組織の発案者
ティール組織の提唱者は、「ティール組織」の著者でもあるフレデリック・ラルー氏です。2014年にラルー氏が発売した本の中で、氏が「ティール組織」と名付けた、全く新しい組織モデルを構築した12組織が紹介され、その驚くべき成果を紹介したことがきっかけで、瞬く間に革新的なビジネス書として世界的ベストセラーになりました。日本での翻訳本は「ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現」として2015年に出版されています。
ラルー氏は世界最強のコンサルティング会社としても有名なマッキンゼー出身。そこでの経験を通じ、今世界に必要とされるのは論理でもなく、頭脳でもなく、競争でもない。長きに渡って共生できる未来的思考を持った組織なのではないかという考えに到達し、世界の様々な組織の発達段階を調査した結果、全く新しい組織階層として「ティール組織」という概念を生み出しました。
ティールとは色のことで、青と緑が混ざったような色をしています。これらはラルー氏による概念上の色分けです。各階層の詳細は第4章にて説明をしています。【参照:フレデリック・ラルー 公式ページ】
1-2.ティール組織の簡単な説明と特徴
ラルー氏が提唱するティール組織とは、私たちが今まで見聞きし、体験してきた組織・慣例・文化が根本的に違う、新しい組織のモデル(ひな型)です。特徴としては従来型の組織にあった下記のような
- ピラミッド式の上下関係
- 上下関係に関わる細かな規則や決まり事
- 定期的なミーティングや会議
- 売上目標や予算の設定
など、今までほとんどの組織で馴染みのある
- 組織構造
- 慣例・ルール
- 文化・社風・風土
のほとんどが撤廃されています。ビジネスの意思決定の権限・責任のほぼ全てが、経営者を含んだ管理者サイドから個々の従業員サイドへと譲渡され、組織と人材に革新的変化を起こすことができる「次世代型組織モデル」です。
ティール組織では、社内は全てが並列になります。それは、組織の全員が同じ細胞でできた、1つの目的を持った「集団(生命体)」や、同じ目的や志を持ったもの同士が集まる「共同体」に近いイメージです。その結果
- 管理者は不要になる→上司不在のフラットな関係性で仕事をする
- 全員が同じ目的のことをするので全員が同じ給与→それでもOKなら契約する
- 指示命令系統がない→対話メインで仕事が進行する
ようになります。
組織のあり方を根本的に覆す概念ですので、参加者全員に組織と仕事への意識変革が必要になります。ですので、ティール組織になることは、組織が変化するというよりは、組織が違う段階へシフトすること、と受け取る方が良いでしょう。
2.ティール組織が成功するための3大要素(=メリット)

ティール組織の三大要素と書きましたが、この要素はそのままティール組織の三大メリットでもあります。
1.セルフマネジメント
ティール組織でのセルフマネジメントとは、自主経営の意識を持ち、「全体の結果を出すために必要なだけの仕事量をあれこれ全部やる」ことに関した感覚とコミットメントの強さを指します。
ティール組織では、意思決定に関する権限と責任を全メンバーが持っています。その結果、メンバー全員が他人からの指示や承認無しで仕事の目標設定と動機付けをし、それによって組織運営がされます。
セルフマネジメントという言葉自体は従来型の組織でも使われてきており、それは「権限委譲」「組織構造の簡略化」などを意味しましたが、ティール組織にはそもそも部門がありませんので、簡略すべき組織も、委譲すべき権限も最初から存在すらしていません。固定した部門や役職がない代わりに、ティール組織では、状況に合わせて生まれる担当・階層・チーム・ルールがアメーバのように作られ、臨機応変に対応をします。
例えば、問題解決をする場合。
通常の組織では責任者に問題が起きてから報告があり、解決方法を責任者が指示してメンバーがそれに従います。もし問題が悪化してもそれは責任者の責任になります。ティール組織の場合は、メンバーの中で「問題になりそうなことに気づいてしまった人」が解決すべき課題を自らみんなに提案し、その問題や事情に詳しいメンバーからのサポートやアドバイスを参考にしながら、チームを作ってみんなで課題の解決に取り組みます。
問題の状況や進捗をシェアをしながら互いに意見を出し合い、最終的には最も賛同者の多い解決策を使って課題を解消していきます。みんなで決めたことですので、どういう結果でも、それが最善の結果であると受け止めます。このような臨時組織は、問題解決とともに自然解散し、デフォルトの状態に戻っていきます。
このような働き方は「組織に起きたことを自分のこととして考える」という発想がないと成立せず、セルフマネジメントの「セルフ」の中には、個人という自分と、組織体の一部としての広義な自分が含まれています。
2.全体性
「仕事場でも、ありのままの自分でいられる、仮面を被らないでも良い」という考え方です。著書ではホールネス(Wholeness)と表現されています。今までの組織論だと、どうしても会社にとって有用な部分だけを「是」とし、それ以外の部分は切り捨てる傾向があるため、役職に関係なく「会社での顔」「プライベートでの顔」の使い分けが必要でした。
ティール組織では、そのような個人の全体性を部分的にしか表現させないような環境は、組織が決めた役割に対して自分を整合させることに大きなエネルギーを消費することになるため、その人が持つ本来の力を発揮する以前に疲弊させる、甚大なエネルギーロスであるという考え方をし、リソースを十分に使えていないとみなします。
例えば、人間ですから
- 今日は体調悪いから家で寝ていたい
- 妻が出産だが、下の子がまだ幼いから1人にできない
- 夫婦の両親が入院して、お金も時間も、もう手一杯だ
- 下の子供が熱出した、なのに上の子が骨折した、もう無理
- 恋人に別れを切り出された、死にたい
など、仕事の能力とは関係なく、仕事をバリバリとやる気になれない・出来ないタイミングというのは誰にでもあります。従来型の組織では、そんな時でも「組織人としての仮面」をつけて、その人の全体的な状態を無視した組織の役割・組織の顔に自分を無理にでも押し込めることが組織人としての評価すべき態度とされてきました。
ティール組織では、そういう「やる気になれない自分」「いま頑張れない自分」もひっくるめて、そのままの状態で会社に来てもいいんだよ、という組織での在り方が許され、受容されます。その人は組織の一部なのだから、その人の全ても我々は受け入れる、という全体性への姿勢があらゆるシーンで貫かれます。その日は効率が悪くてもいい、そういう日もあるよ、お互い様だよねと互いにカバーし合って、労わりあうことができる状態の組織が全体性です。
イメージとしては、例えば足を捻挫した時、体の他の部分が筋力をカバーしながら歩きやすいように体全体でバランスを取って歩行しますが、そのように、本調子でない部分を互いに補完し合って組織全体のバランスを整えながら通常運営をするという考え方です。存在そのものを否定されないことにより、本人が安心感を持って組織に帰属できる上に、自分の全てを組織に持ち込めるため、結果的にダメージからの回復も早まるという利点があります。
3.組織の存在目的
ティール組織では「組織の存在目的に対し、自分らしく貢献できるかどうか」をシンプルに、しかし強く訴えかけてきます。従来型の組織では、自分の会社が競争で勝ち抜き・生き残ることが最大最高の存在目的であり、組織は常に生産性拡大をしながら生き残りをかけて戦い続けていました。しかし、それは組織の存在目的であり、個人レベルでの存在目的や「らしさ」は必要とされません。
ティール組織では、組織をひとつの生命体のようなものとみなすので「生き残り」の概念がありませんので、自らの存在のために必死に戦うという考え方そのものがありません。生命体と同じように、必要な時に誕生し、役割が終われば消滅するという自然の巨大なサイクルの1つとして組織を俯瞰しています。代わりにティール組織では、より精神的な希求、より大局的な存在目的が組織のテーマになります。例えば
- 自分たち(組織)が心から望んでいることは何だろう
- 自分たち(組織)は世界になにを提供できるか
- 自分たち(組織)独自の才能は何だろう
- 世界では何が障害になっているか、何に困っているのか
- どうすれば、組織の中でより自分らしく生きられるようになるのか
などの、「存在そのもの」に対する、より高次な発想と理想の実現が評価の対象になります。
上記の例を見ていただけるとわかる通り、組織と個人の間にあまり境界がありません。ティール組織では、個人の在り方と組織の在り方とがある程度シンクロしている必要があり、そのシンクロしている部分がその組織で働くモティベーションになります。別の言い方をすれば、この存在目的の合致が少なければ、または少なくなれば、自然とその人はその組織からは離れていきますが、それはお互いにとって最良最善のことなのです。
個人の存在目的と組織の存在目的が合致していれば、組織の中には自然と自分にとって心地の良い居場所が形成されます。組織と本人たちの目的が合致しているため、メンバーが望めば新しい仕事へチャレンジできる可能性もありますし、人によっては多才な技能をあらゆるところで使えます。やればやるほど、自分も組織も、そして社会も幸せになるポジティブな連鎖が起きます。
ティール組織にとっての存在目的は「それをすることで、あなたと組織が共に満たされるかどうか」が大命題であり、仕事という限定された枠組みを超越した、この世での自分の在り方そのものに対する方向性の合致が、かつての組織でいうところの「我々のミッション」となります。
部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら
3.ティール組織のデメリット

ここではティール組織のデメリットを紹介します。各項目で発生するデメリットと、その解決方法について説明します。
1.企業メンバーの高い意識と自主性がないと成立しない
ティール組織では組織のヒエラルキーを作らず、全メンバーに権限があることは説明しましたが、それらは全組織メンバーに「セルフマネジメント力」があってはじめて成立します。
ティール組織でメンバー各自が決めた生産目標を達成するためには、仕事の完成図をメンバー全員が把握し、その完成に向けてメンバー全員が責任を持って協力しながら行動する必要があります。2章3の組織の存在目的でも解説した通り、組織の目的が個人の目的と合致していれば、メンバー全員が目的のために邁進していくことができますが、このセルフマネジメントの質が下がってくると、生産効率が落ちていきます。
【デメリットの解決策】
解決策としては、パフォーマンス低下がある時点ですぐに臨時のミーティングを行い組織内での自分の存在目的を再確認してもらうサポートが必要になります。ミーティングは詰問したり責めるためではなく、
- なぜ個人のセルフマネジメントが機能しないのか?
- やる気が低下してしまうことが起きているのか?
のように、なぜセルフマネジメント力が低下しているのかを解明するためです。
セルフマネジメントの質が低下する理由は様々です。個人生活の背景などもよく把握し、やる気が下がってしまう個別の事情がある場合は暫定的に負担の少ないポジションに移動するなど、組織・メンバーともに全体の生命体として捉えれば、ラクに解決できることも多いでしょう。しかし、もしメンバーが
- 個人と組織の存在目的のシンクロが少ない
- 途中で個人の目的が変わってしまった
などの場合は自ら組織を去っていくことになりますが、それは結果として双方にとってのメリットになります。
このような齟齬は、採用の時点で十分な話し合いや、存在目的に対するすり合わせでかなり防げます。面談やプレゼンの時間・仮採用の時間をたっぷりとって、人物とその内面を観察してから採用を決定すると良いでしょう。
2.マネジメント(管理)をしない分、進捗が全然わからない
ティール組織は管理職が存在しないため、ピラミッド型組織と比べると、仕事の進捗や達成具合が見えにくいという特徴があります。定期的に生産性会議などで確認することは可能ですが、この会議自体も合議の上ですので強制管理ができません。基本的にティール組織では「マネジメント」「管理」はできないと思っておいた方が良いでしょう。
【解決策】
問題の解決方法はプロジェクト開始前・後で2通りあります。
①プロジェクト開始前
プロジェクト開始前には必ず生産性に関したミーティングがあるので、ここでしっかりとゴール設定をし、メンバー全員が完成図・数量・時期などの生産ゴールを明確にシェアできていることが大切になります。
②プロジェクト開始後
プロジェクト開始後はの進捗報告ですが、そもそもティール組織には報告をすべき上司が存在しないため、現場の実情は
- 仲良しさんならお互い知ってる
- 話さない人の進捗は全然わからない
ということになります。実質的なマネージャーおよび全体情報を管理できる者がいない状態で、全体の利益のためになる的確な判断を個人にさせるためには、その判断材料となる情報をできる限り開示しておく必要があります。例えば
- メンバーの出勤スケジュール
- 個別の生産状態
- 個別の売上げ状況
- 顧客数とコストの情報
- コミュニケーションができるボード
- 今メンバーが組織のどこにいるかなどのGPS情報
など、必要な情報がいくつでも・いつでも確認できる機能やツールを組織側が用意する必要があります。
また、ティール組織が横つながりであることを利用し、おしゃべりやお茶ができる場所やタイミングをなるべく多く設置し、問題解決のための臨時組織結成や、人員補完のためのお願いや提案などが気軽にできるシェア・ポイントをたくさん設けておくことで、組織が拡大して行ってもマネージャーが不在である問題がクリアできます。
3.承認プロセス(稟議書・印鑑・サイン)がないリスク
ティール組織のリスク管理方法は、改めて確認する必要があります。従来型組織の場合、
・稟議書
・委員会
・役員会
・回覧資料
などを通じて、何人もの確認や「承認」を経ないと重要な決定や判断がされることはないので、リスク管理という点では責任の所在が組織側にあり、非常に安全性の高いものでした。
ティール組織ではヒエラルキーが存在しないため「承認のための縦のプロセス」が存在しません。つまり、1人がやる!と決めたら通ってしまう企画がいくらでもあります。企画の遂行にはお金がかかりますし、場合によっては投資に近いような内容もあります。
ティール組織では組織の存在目的が個人の存在目的と大きくシンクロするとは言っても、組織のリソースを個人の思惑通りに動かすこととは違います。
【解決策】
まずは、組織メンバー全員の良識と判断力を全面的に信頼します。性善説的な考えではありますが、人は動物の本能として、自分が所属する場所で不利益が生じることを嫌います。同時に、ティール組織のような高次な組織目的と個人目的がシンクロするような場所では、自分の組織が損失を被るような事態は誰も望まないことも共通認識であると言えます。よって、信頼が最もリスクを遠ざけることになります。
その上で、2章で説明したティール組織の特徴であるセルフマネジメントを取り入れた承認方法を採用しましょう。具体的には、誰かが企画を立てた時点で、すぐにそれを全員に公開します。稟議を回す必要がないのですから、一斉公開してもなんら問題はありません。
その際、メンバーはその企画の良し悪し・採用不採用をジャッジするのではなく
- 自分たちの目的達成のために必要かどうか
- 専門知識のあるものは惜しみなく情報提供をする
- 自分の知っている情報がある場合は、提供をする
- 他に似たような企画があった場合は、それを開示する
のように、問題解決策をみんなで作り上げた時と同じような方法で、みんなで企画を育てていきます。メンバー全員のサポートを受けながら成長した企画書は、最終的により多くの人が納得した内容となり、通過をします。
これがティール組織では事実上の稟議になると言えます。これらのプロセスは臨時のミーティングを開いても良いし、ネット環境が良好なのであれば、スレッドを立てて自由に意見を交換しあうことも可能です。
部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら
4.組織がティールになるまでの5段階意識フェーズ

ここではティール組織の各成長段階を説明します。①の赤を起点として、もっとも階層が高い状態がティールになるように、組織の発達段階を5つの段階で表現しています。この階層はあくまで「ティール組織」の著者フレデリック・ラルー氏が提唱するものです、世界的な基準とは違います。しかし、どのようにして組織が各意識の発達段階に到達するかの理解に役立ちます。
全ての階層組織は、単一で存在しているわけではなく
- レッドとアンバーの間にあるがアンバー寄り
- グリーンとティールを大きくまたがっているが、まだグリーン的
- この仕事に関しては、オレンジ、あの作業はグリーンだ
など、いろんな側面が混ざりっているのが普通です。その中で、総合的に見る「うちの組織はオレンジに近いかな」などの見立てをするために使います。
|
名前 |
特徴 |
比喩 |
例 |
価値基準 |
得られるもの |
|
①レッド |
衝動的 |
狼の群れ |
ヤンキー |
欲求を満たす |
目の前の成果獲得 |
|
②アンバー |
順応的 |
軍隊 |
官僚 |
集団規範 |
スケールメリット |
|
③オレンジ |
達成的 |
マシン |
大企業 |
成果の追求 |
成果主義による結果・承認 |
|
④グリーン |
多元的 |
家族 |
スタバ |
人として大切に |
団体・個人として強くなる |
|
⑤ティール |
進化的 |
生態系 |
ー |
内なるものに従う |
セルフマネジメント・全体性 |
①レッド(衝動型)組織
|
①レッド |
衝動的 |
狼の群れ |
ヤンキー |
欲求を満たす |
目の前の成果獲得 |
世界最古の組織モデルです。10000年前からある古い形式であり、現在でもヤクザ・ヤンキー・チーマー・暴走族などはレッド組織を自然と構成します。海外ではスラム街などに多く見られます。
レッド組織のメンバーは「力こそが全て」という思考パターンを持ちます。そのため、この組織で自分の欲求を満たすためには、他のものよりも強くなければならないと考えます。この意識段階にいる組織メンバーは
- 組織メンバーは、常に「自分」の欲求のみを求める(欲しい→奪う など)
- 自分以外の全ての存在を脅威と見る(やるか・やられるか)
- 脅威を取り除くために力による支配をする(強い奴が正義)
- 1人の長が圧倒的な力で他を支配する(オヤジ・組長など)
- 恐怖と服従により組織の崩壊を防ぐ(脱会・脱チームへの制裁など)
- 常に自分より強いものに従うことで、安全な環境を確保する
- よそ者は脅威である可能性があるので、排除する
というパターンをとります。
レッドのメンバーにとって最も重要なのは「今」であるため、戦略性が低く、短期決戦でものを片付ける傾向があります。例えば、強さを証明するために戦略を練って長い戦いをするよりも、「今・この瞬間」に目があったもの同士で闘争をして勝つことの方が重要で価値があります。たとえ戦略を組む場合でも、2−3日〜数週間が限界で、長期的・戦略的な視野で取り組んでも成功しません。
②アンバー(順応型)組織
|
②アンバー |
順応的 |
軍隊 |
官僚 |
集団規範 |
スケールメリット |
アンバー組織は、権力と階級制度、官僚制度、秩序と統制などの概念を組織モデルに組み込んだもので、いわゆるヒエラルキー型・ピラミッド型組織のことです。世界の大半の政府機関・公立学校・宗教団体・軍隊がこのアンバー組織になります。
レッドでは「自分」にしか興味がなかった意識が、アンバーにくると「集団」にシフトしますが、自分たちの所属する組織以外には意識が及ばないため、組織メンバー(身内)以外に強い対抗心と敵愾心を抱く傾向があります。そのため、アンバー組織では
- 組織が個人の世界観になる
- 世の中は不変であるという前提がある
- リーダーには家父長的な権威がある(政治党のリーダー・宗教の教祖)
- ルールと規範で組織を維持する(戒律・法律など)
- 階級があり、階級は権力である(称号・勲章など)
- トップが考え、組織構成員が従う構図
- 組織ルールに従うことにより、安心と安定をえることができる
- 設定されたルールは固定され、踏襲する必要がある
- 構成員以外はルールを乱す可能性があるため、排除する傾向
などのパターンがあります。
アンバーでは、段階的な階級の確保=自分の安全なポジションとなるため、より安全な自分になるためには、自分より権威のある存在から承認をされる必要があります。これは承認欲求という行為につながり、人はこの欲求を満たすために組織が設けた基準やルールを積極的に守り、秩序ある行動を取るようになります。アンバーでは、これ以外の方法で承認がされることはありません。
また、ルールが踏襲されるという特徴があるため、100年単位で中・長期戦略を立てて運用することができます。ただし、この戦略を立てた時点から「世界が不変である」ことが前提なため、変化への対応は不得意です。
③オレンジ(達成型)組織
|
③オレンジ |
達成的 |
マシン |
大企業 |
成果の追求 |
成果主義による結果・承認 |
オレンジ組織は、プロセス・プロジェクト・研究開発・マーケティング・生産管理という工学的な視点を経営学に組み込み、社会的な成功を最終ゴールとする組織です。世界的に名の通ったグローバル企業や、国内大企業などに多く見られます。
レッド「個人」、アンバー「集団」からオレンジの階層までくると、基本的なピラミッド組織の形態は残しつつ、意識が「世界」に向くようになります。世界の中での自分、世界の中での仕事、世界の中での組織が発生し、その中で成功をしたいという意識と発想が出てくるため、世界的ビジネスリーダーが多く生まれる階層です。そのためオレンジ組織では
- リーダーは経営を工学的な視点から眺めている
- 組織そのものも工学的な視点で見ているため、人をパーツと見る傾向がある
- そのため、組織メンバーはマシンのように働く傾向がある
- 組織ゴールはトップが決める
- 組織目標達成と株主の利益分配が最重要課題
- ピラミッド型ではあるが、縦横に柔軟に伸びる形態
- 組織メンバーは自己目標を自由に決められる
- 実力主義なので階級突破が可能
- 物資的成功が最も評価される(金額・所有物・規模など)
トップが決めたゴールに向かい、中短期目標と長期目標を織り交ぜながら柔軟に達成を目指します。また物事には変化が起きることを理論的・体系的に受け入れているため、特定の成功パターンに固執しません。現状にとどまることよりも、リスクを恐れずにチャンレジをして、新しい発見をすることに対して高い評価をする傾向にあります。
④グリーン(多元型)組織
|
④グリーン |
多元的 |
家族 |
スタバ |
人として大切に |
団体・個人として強くなる |
グリーン組織は、オレンジ組織に多様性とステークホルダーの存在を加えたもので、組織の能力の最大化を目的とした組織です。ステークホルダーには様々な解釈方法がありますが、おおよそ組織メンバー以外の次のような存在を指します。
- 投資家
- 株主
- 債権者
- 顧客(消費者)
- 取引先
- 地域社会
- 行政・国民
このように、グリーンは、オレンジ組織のピラミッド構造を残したまま、より多様な特徴や技能を持つ様々な立ち位置のメンバーを内包させ、この関係者全員が幸せになることを希求する組織です。具体的にはダイバーシティを標榜する団体やその関連団体や組織がこれに当たります。
グリーンの意識発達段階までくると、人は「人生には仕事の成功や失敗以上に、もっと重要なものがあるのではないか?」と考るようになります。そのため、グリーン組織では
- 性別・人種・宗教・思想などのあらゆる違いを不自然に感じる
- あらゆる考えは平等に尊重されるべき
- 組織では従業員や社員のことを家族として大切にする(パーツから人へ)
- 組織は互いに支え合うことが自然だと考える(私たちは家族だから)
- みんなの組織だから、みんなで考えるようになる(権限委譲)
- 全ては話し合いで決める(コンセンサス)
- グリーン組織のリーダーは、サポート型になる
などの特徴が出てきます。
このような特徴を持つ組織に、スターバックスがあります。著書内にも紹介がありますが、スターバックスのテーマカラーはまさにグリーンです。スターバックスはスタッフとお客様の「居場所」であり、快適で心地よい空間として「ずっとここに居たいな」と思える場所であるべきだという理念があります。それがスタバ独特の「雰囲気」として愛され受け入れられ、今や世界中に帰るべき家(店舗)があります。スターバックスの理念の延長線上には「個人の人生を尊重し、企業の目標と重なりあう場所をお互いに探る」という特徴もあり、ティール的な要素も含まれたグリーンであることがわかります。【参照:スターバックス Our Mission Our Value】
良いことづくめのように見えるグリーン組織ですが、グリーン組織にある平等の概念が関係者全員の合意(コンセンサス)を取り付けるための障害になることもあります。その結果、貴重なビジネスチャンスを逃したり、問題の解決が遅延する傾向もあるため、企業の健全経営をするための障害にもなるのが事実です。この部分も、基本は組織メンバーでコンセンサスを取りながら、その組織独自の解決方法を生み出すことが課題になります。
⑤ティール(進化型)組織
|
⑤ティール |
進化的 |
生態系 |
ー |
内なるものに従う |
セルフマネジメント・全体性 |
ティール組織は「大志を抱いているが、野心的ではない人たち」の集団です。彼らの内側にある「大志」は様々ですが、それは彼ら自身の存在目的として、社会行動へと駆り立てる原動力(エネルギー)となります。この原動力(エネルギー)を最大限に発揮させて組織の力としても活用し、組織が社会ミッションを達成する原動力として使うというのがティール組織です。メンバーは組織を1つの生命体とみなし、その生命体の持つ集団の知・共同体としての知性に対して信を置きます。
ティール組織にはヒエラルキーが存在しないため、上司や部下といった概念がありません。組織の構成員は「メンバー」または「仲間」呼ばれ、創設者ですらも並列するメンバーの1人です。そのためティール組織では、
- メンバーは組織全体を1つの生命体とみなす
- メンバー全員が自立的で主体的で並列的ある
- メンバーは組織の存在目的を軸に、自分にできる最善の行動をする
- 仕事は常に、本当に自分がしたいことなのかを軸に考える
- やるべきことと、やりたいことが一致した時に全身全霊で仕事をする
- 自分がやると決めた仕事には権限と責任が発生する
- 必要な場合はアメーバ的に組織が出来、不要になったら解消する
- 問題解決は「当然するべきこと」であるため、合意は不要(反対者が存在しない)
- 合意ではなく、サポート・シェア・賛同により問題解決をする
など、今日まで多くの人が当たり前に信じてきた「組織」の概念を覆す事柄の連続です。
これほど多くの組織的構造からの解放と自由が与えられていても、ティール組織には出世や派閥の概念も存在しないため、争いが起きません。また、仕事には権利と責任がセットでメンバー全員に付帯しているため、権利の乱用もできません。
オレンジ組織では発見のようなイノベーションが評価されましたが、ティール組織では意識や概念そのものがより高次の階層へと次元上昇する「パラダイムシフト」が高い評価をされる傾向にあります。しかしながら、まだこの世に出てきたばかりの組織概念ですので、これといったビジネスモデルもなく、導入しても組織内で意識のシフトが起きるかどうかは未知数の状態です。ティール組織の事例に関しては6章で紹介をしています。
5.ティール組織に関した3大勘違い

この章では、ティール組織に関した誤解・勘違いについて説明します。2015年に翻訳本が発売され日本でも流行りだしたティール組織ですが、いまだにこれと言ったビジネスモデルがない上に、ファシリテーターも著者本人しかいないため、世界各地でいろんな勘違いがされている状態です。今回はその中でもとくに世界共通の3大勘違いを紹介します。
1.ティール組織は小型組織向きである
ティール組織の最も多いのが「小規模なところでしか使えないんでしょ?」という誤解です。著者のラルー氏が来日講演時にも「全然そんなことはない!」と言い切っているところから、あらゆる業種に適応できることが明らかになっています。
これらの誤解は、小規模オフィスや出来立てのベンチャー組織などでは、業務遂行のため、計らずも組織がティール組織化することが原因で、それが最もイメージしやすいからです。しかし、どのような規模であれ、仮に事務所に2人しかいなかっとしても、トップと部下という役職が存在する組織はティールではありません。
実際、著者が行った調査対象になった組織の従業員数は90人から4万人と幅広く、業種だけでなく規模についてもティール組織を構築する上では問題にはなっていないことが判明しています。
【参照:フレデリック・ラルー 「ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現」】
2.ティール組織という確立したビジネスモデルがある
これも誤解です。そのようなパチッとはめこむタイプのビジネスモデルは存在しません。
書籍『ティール組織』の中で事例として取り上げられた組織メンバーは全員、著者・ラルー氏から他組織の話を聞くまで、お互いの組織の存在すら知りませんでした。つまり、ティール組織というのは、ラルー氏をはじめとしたコーチやファシリテーターなどによってあらかじめセットされて施行したビジネスモデルなのではなく、それぞれの組織が自分たちにとって最善のことを考えて突き詰めて行った結果、似たような組織形態になったというわけです。
これだけ世界的に流行っているティール組織論ですが、発売から5年経過した2019年現在でも、「ティール組織とはこうあるべき」というビジネスモデルは存在していません。また、ティール組織論のなかで取り上げられた組織たちは、組織のティール化を目指していたわけではなく、自分たちの理想的な組織の在り方を目指してやり続けた結果、ラルー氏により「ティール組織」として取り上げられたことにも留意すべき点です。
3.現存する組織マネジメントの中で最も優れている
違います。階層式になっているので誤解しやすいのですが、ティール組織がその前の階層よりも優れていて、それよりも前の階層が劣っているというわけではありません。組織をどのように機能させて結果を出すかは、その取り扱う商品や環境によっても違います。
例えば、国内に内乱が起きている場合などは、5段階の①レッド組織が最も良く機能して結果をだします。大規模な戦争が起きた場合は②のアンバーが機能しないと負けてしまいます。部品生産や工業製品を画一的に素早く世界に行き渡らせたい場合には③オレンジ組織が最適です。このように、その組織が置かれている環境など様々な条件に組織を最適化することが大事なのです。
また、ティール組織は完璧なティールの条件を揃えている必要はなく、その組織イメージを決定付ける風土や組織構造がティール的かどうかで呼ぶ名称に過ぎません。どのような組織にも、オレンジやグリーン的な部分は残っていますし、たとえティール組織の中でも、オレンジ的、グリーン的な性質を持つメンバーは存在しています。
ティールは組織論とその考え方は大変に優れたものではありますが、全ての組織に対してベストというわけではありません。また、そのような完璧な組織モデルというのは、この世に存在しないと思っておいた方が良いでしょう。組織の変革や変容を希望する場合は、各カラー階層が持つ長所と短所を理解し、適宜に組み合わせて、強靭かつしなやかな組織に育てていく方が、結果的には他社の追随を許さない、オンリーワンの組織を構築することになります。
部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら
6.ティール組織を取り入れている企業事例

この章では、ティール組織として紹介されている12組織の中から2社を事例として紹介します。
【オランダ介護組織ビューゾルフ】
- 国:オランダ
- 運営内容:
高齢者の地域ケアをメインとした在宅介護ケアの団体
- 課題:
政府の財政難による資金圧迫で介護事業の細分化と分業化が進んだ。介護依頼者は毎回、新しい看護師に病状などを説明する必要がありケアそのものが成立しなくなった。このような背景の中、激務と対応人数の多さ、低賃金から、看護師離職率が激増した。
- 取り組み:
看護師が介護ケアの全プロセスを把握して責任担当をしたら、これ以上賃金を下げないでも必要なケアができるのではないか?という発案からスタートした。
- 成果:
現在、メンバー10,000人でマネージャー職ゼロ。構成員はバックオフィスと看護師。成功の鍵となったのは自社開発の専用アプリで
- 業務日誌
- 利用者の様子やケアの内容
- 作業内容と時間の自動計算と公開
- メンバーの生産性の自動計算と公開
- ケアプランの改定やその変更点の発表
- シフト作成
- メンバーの連絡
をし、可能な限りメンバーが自分の裁量で判断できるだけの情報開示をしたことにありました。もともとセルフマネジメント力が高い看護師という職業適正もあったと思いますが、以下の最低限の決まりごとだけで組織10,000人がトラブルもなく稼働しているという事実は、驚愕すべきでしょう。
|
ちなみに、一万人規模の企業というのは、日本だと商船三井や日立造船などの規模になります。また、ビューゾルフはメンバー満足度も高く、全オランダ企業の中で業種を超えて最も働きやすい職場として最優秀雇用者賞を受賞しています。
日本にはこのビューゾルフをモデルにした「ビューゾルフ柏」という介護ケア施設があり、それらの活動内容は日本の医療機関でもティール組織の事例としても注目をされています。
【参考:ビューゾルフ オランダ】
【参考:ビューゾルフ柏 ネイバーフッドケア】
【参考:ビューゾルフ柏 フェイスブック】
【参照:吉江悟 ビューゾルフ柏業績報告】
【アメリカ パタゴニア】
- 国:アメリカ合衆国
- 運営内容:
山岳・スポーツ用品をはじめとした世界的衣料メーカー
- 課題:
企業理念に沿った事業をするために日々、変革と革新をする。
*ティールを目指した結果に大企業になったわけではなく、ラルー氏の著書でティール組織であると紹介された。
- 取り組み:
開業当初は理念はなく、ただ衣料品を作る世界の下請けメーカーとして運営をしていました。途中から、時代に合わせて企業理念を変えていく企業風土にシフトします。パタゴニアは今までに3回、企業理念を変えています。
1994年 「環境危機に警鐘を鳴らし、解決に向けて実行する」
2002年 「最高の製品を作り、環境に与える不必要な悪影響を最小限に抑える。そして、環境危機 に警鐘を鳴らし、解決に向けて実行する」
2018年 「故郷である地球を救うためにビジネスを営む」
パタゴニアは企業理念が変わるたび、新しい企業理念に沿った商品開発と事業戦略に刷新し、自ら組織を生き物のように新陳代謝して来ています。
また、経営の透明性としてオープンブックポリシーが徹底しており、ほんとんど全ての数字が公開されています。また、資本主義の総本山であるアメリカ企業の中で、談合入札などを徹底拒否する会社としても国内外で評価をされています。
- 成果:
- コストがかかっても、地球のためになる綿花を育てて生地を作り、その賛同者による衣料品の購買で売り上げが落ちないなど、企業理念を支える根強いファン作りに成功
- 店舗で修繕と再利用をするリサイクルを推奨。新商品は持っているなら買わなくてもいい!という「Don’t buy this jacket」という自社製品の不買運動は有名。ファンと新規の賛同者たちに支持をされ、リサイクルユーズという新しい概念が消費大国アメリカに根付くきっかけとなり、「もったいない」「サスティナブル」の概念を衣料業界でいち早く行動に移している。
- 社内に保育園と幼稚園があり、家庭と仕事が分断されることなく長く働ける環境構築がある
【参考:パタゴニア 日本】
ティール組織を理解するためのオススメ書籍
|
【ティール組織 提唱者】 1.フレデリック・ラルー 「ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現」 最も最初に出版されたティール組織論。概念的であったり、心理学や神話、宗教など西洋の世界観全体と基礎知識がないと日本人には理解できない部分も多い。中盤からのティール組織論そのものから見る方がわかりやすい。
2.フレデリック・ラルー「[イラスト解説]ティール組織――新しい働き方のスタイル」 イラストによりわかりやすく解説が入ったもの。内容は1と同じだが、語り口調が多いのでよりわかりやすい部分が増えた。
3.吉原史郎 「実務でつかむ! ティール組織 "成果も人も大切にする"次世代型組織へのアプローチ」 日本で出されているティール理論の説明では、最もわかりやすく実践的。どうやったらティールが組織に根付くか、という視点からティール理論を解説している。
4.武井浩三 「自然経営 ダイヤモンドメディアが開拓した次世代ティール組織」 日本の企業にティール的な要素を入れた「自然(じねん)経営」という独自の概念を、セミナーでの対話形式で展開。ダイアモンドメディア内の一部で実際に採択された経緯などもあり、ティール組織論の採用を検討している担当者にとっては一読すべき価値がある。 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。ティール組織はまだ世界的にも新しい組織論として、非常に注目されていることがお分かりいただけたかと思います。
1.ティール組織とは?
2.ティール組織が成功するための3大要素
3.ティール組織のデメリット
4.組織がティールになるまでの5段階意識フェーズ
5.ティール組織に関した3大勘違い
6.ティール組織を取り入れている企業事例
の全項を通じて、ティールがなぜ世界で注目されるのか、取り入れてみる価値があるかどうかの手応えは感じていただけたと思います。自社の環境や人材の特徴などを鑑み、採択の検討の一助になれば幸いです。
部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら


