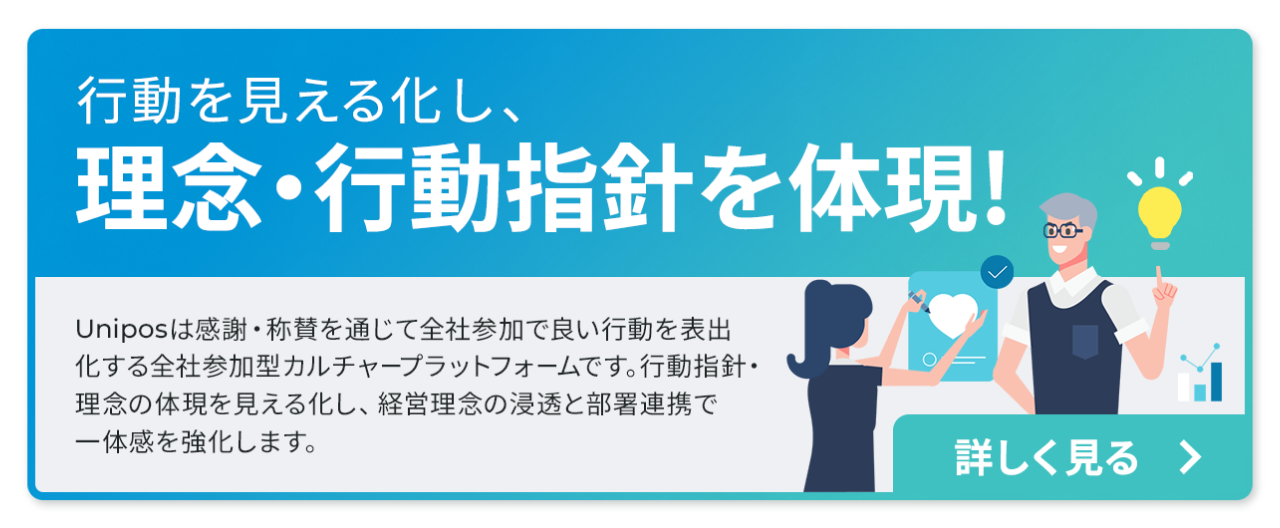変化の激しい現代社会において、社員の行動の判断基準となったり、組織の経営の判断基準となったりする「クレド」はますます重要視されています。
しかし、クレドを導入済みの企業は多いものの、活用がうまくいっていない企業もまた多いのが現状です。
そのため、クレド導入の予定がある企業担当者の方は「失敗したらどうしよう」と不安に思ってしまうでしょう。
そこで本記事では、よくある失敗例をもとに、クレド導入がうまくいかない原因とクレド導入を成功させるポイントを中心に解説します。
記事の最後では、クレド導入が上手くいかなかった実際の事例も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
1.クレドとは

そもそも「クレド(Credo)」とは、ラテン語で「信条」や「志」などの意味を持ち、ビジネスの場面では「企業における行動指針を簡潔に表した言葉」を意味します。
企業理念が「何のためにこの会社は存在しているのか」という存在意義や、「会社の大切にしている価値観はどのようなものか」という基本的な考え方を示す一方で、クレドはその存在意義や基本的な考え方をふまえ、「この会社で働く人々はどのような行動をとるべきか」をスローガンのように文章化したものです。
クレドは具体的かつ分かりやすい言葉で作られることが多く、社員が日々の業務を行う際の判断基準となったり、組織の大きな経営判断の基準となったりします。そのため、クレドは一度決めたら終わりではなく、会社の状況に合わせて柔軟に内容を変更するケースもあるでしょう。
クレドを適切に運用することで、一人ひとりの行動、そして組織全体に一体感を生み出すことが可能となり、会社は同じ方向へ進めるようになります。
なお、クレドについてのさらに詳しい説明は、以下の記事を併せてご覧ください。
参考:クレドの意味とは?クレドカードを作成する際の手順と導入事例
2.失敗例から学ぶクレド導入が上手くいかない5つの原因

まずは、クレド導入がうまくいかない原因を「作成」「浸透」とに分けて解説します。
2−1.クレドを作成する際の失敗原因
クレドを作成する際のおもな失敗原因は、次の2点です。
2−1−1.クレド導入の目的が明確になっていない
クレドをなぜ導入するのか、その目的や理由が曖昧なケースは意外にも多いものです。
「まわりの会社も導入に成功しているようだし、きっと自社で実施しても良い影響があるだろう」というケースでは、残念ながらクレド導入は失敗してしまいます。
- 今すぐ社員一人ひとりの意識を変えなければならない出来事があった
- 会社を背負えるような人材の育成をしたい
- これからも長く続く行動指針を決めたい
- これまでの行動を認めたうえで社員のさらなるモチベーションアップにつなげたい
クレドを作成する前に、このような目的や理由を明確にしておきましょう。
さらに、作成したクレドを公表する際にも、目的や理由と併せて伝えることが重要です。
明確な目的があるとわかったうえで公表されたクレドは、組織のクレドを受け入れようとする姿勢を助長させやすくなります。
2−1−2.経営陣だけでクレドを作成してしまう
クレドを作成する際に、経営陣の意見だけで内容を決定してしまうトップダウン方式では、社員の賛同を得られないまま終わってしまいます。
「結局のところ経営陣にとって都合の良い内容ばかりが盛り込まれていて、現場の感覚からは大きく離れたものになり社員がシラケてしまった」といった状況に陥るでしょう。
クレドは組織内のすべての人々のための行動指針となるものであり、本来は全員の理解が必要です。そのため、トップダウン方式ではなく、ボトムアップで社員の意見を十分に反映し作成するのが理想なのです。
経営陣がそうしたクレドの趣旨を理解し、「クレドの内容には極力現場の意見を反映させる」という意識を持てるかどうかが、クレドの導入の成功・失敗を大きく左右するでしょう。
2−2.クレドを浸透させる際の失敗原因
クレド浸透の主な失敗原因は、3点あります。
まず、クレドを浸透させるためには、次の5つのステップを考える必要があります。
STEP1:理解
→クレドの内容や言葉の意味を理解している
STEP2:共感
→クレドに共感し、取り組みへの意欲を持っている
STEP3:具体化
→具体的に自分が何をすべきかイメージできる
STEP4:実践
→クレドに沿った行動を実践している
STEP5:成果
→実践したことが成果となり、手応えを感じている
参考:失敗させない!飲食業のクレド経営ノウハウ③(クレド浸透編)
この5つのステップを踏まえ、クレドを浸透させる失敗原因を解説していきます。
2−2−1.クレド理解のための時間を割いていない
クレドを作成してはみたものの、社員にはそもそもクレドの存在自体を認識されていない、
またはクレドがあることは知っているが、内容までは知らないという失敗例があります。
このような状態は、クレドを決めることで満足して、浸透のための時間を割けていないことから起こるものです。
クレドを作成しただけで浸透するはずはありませんので、例えば、全社員が一同に会する理念共有会などの場でクレドについての説明・共有を行ったり、朝礼前に毎日唱和したり、さらにはクレドカードを作成し全社員に配布したりと、一定の時間をかけて何らかの対策を取る必要があります。
2−2−2.具体的な行動事例が提示されていない
組織の中でクレドの存在が周知され、社員もクレドに共感しているのにもかかわらず、なかなか浸透しないというケースでは、「具体的にどのように行動に移したら良いかがわからない」「イメージしている行動とクレドが合致しているか自信を持てず、迷いが生じている」などという状況が想定されます。
このような状況が解消されないままでは、「良いクレドが出来上がった」だけで終わってしまいます。
具体的にどのような行動がクレドに合致しているといえるのか事例を示すことや、実際にクレドにリンクした行動を評価する仕組みの導入などが求められるでしょう。
2−2−3.成果を共有していない
クレドを浸透させるには一定の時間がかかるため、経営層から見たときに「成果がでていないのでは?」「無駄な活動なのでは?」と捉えられてしまうことがあります。
そうすると、順調にクレド導入が進んでいる実感のある現場と経営層との間で認識の齟齬が生まれてしまいます。クレドは組織全体に一体感を生み出すものであり、一部が「失敗だ」と認識している状態では成功しているとは言えません。
そのため、クレドは作成時だけでなく運用中にも、随時進捗状況や成果を報告し、共有することが重要といえるでしょう。
3.クレドの失敗原因を回避し導入を成功させる4つのポイント

続いて、前章でご説明したクレド導入の失敗原因をもとに、クレド導入を成功させるポイントを解説します。
こちらも「作成」「浸透」とに分けて見ていきましょう。
3−1.クレドを作成する際のポイント
クレド導入を成功させるため、クレドを作成する際には「全体で内容を議論する」こと、「行動に移せる内容にする」ことの2点を守りましょう。
以下では、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
3ー1−1.全体で内容を議論する
クレド導入が決まったら、経営陣だけでなく現場のメンバーも含めて議論しましょう。
クレド導入を成功させるためには、経営層以外のすべての社員の意見が重要です。現場の声に耳を傾けることで、誰もが理解し共感できるクレドの作成につながるでしょう。
具体的には、全社員へアンケートを実施したり、直接意見交換ができる場を設けたりする方法があります。加えて、全体での議論の際には、クレド導入の目的や意義の共有が欠かせません。
会社側からの一方的な押し付けでクレド導入が決まったと捉えられないよう、目的や意義をしっかりと社員に説明してください。
目的や意義を共有したうえで全体でクレドの内容を議論できれば、社員も自らが考えて決めたことという意識を持つことができます。
3ー1−2.行動に移せる内容にする
クレドは具体的かつ分かりやすい言葉で、行動指針を示すために作成するものです。
漠然とした内容や実際に行動に移せないような内容ばかりが盛り込まれたクレドは、作成する意味がなくなってしまいます。
もちろん、組織が高い理想や希望を持って進むのは望ましいことですが、現実離れした内容を盛り込んでしまうと、まさに「絵に描いた餅」状態です。
クレドの本来の目的である「この会社で働く人々はどのような行動をとるべきかを示すこと」ができるよう、あくまで行動に移せる内容を反映し、クレドを作成していきましょう。
3−2.クレドを浸透させる際のポイント
クレドを無事作成させることができたら、次は浸透の段階です。
クレド導入を成功させるためには、「クレド理解・共感のための時間を割く」こと、「実践を評価する制度を導入する」ことの2点が大切です。
以下では、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
3−2−1.クレド理解・共感のための時間を割く
クレドを浸透させるには、最初のステップとしてクレドの理解・共感が欠かせません。
クレド理解・共感のための取り組みとして、多くの組織が実践しているのが「クレドカード」の作成です。クレドカードとは、名前の通りクレドの内容を記載したカードのことを指します。
クレドをカード化することで、社員は常に携帯できるようになるため、必要なときにすぐに内容を確認し、普段からクレドを意識しやすくなります。
参考:クレドの意味とは?クレドカードを作成する際の手順と導入事例
ただし、クレドカードを作成・配布しただけでは、本当にクレドへの理解や共感が深まっているかどうかはわかりません。
そのため、クレドカード以外にも、クレド理解・共感の取り組みは不可欠でしょう。
例えば、クレド導入の最初の段階で理念共有会を開催し、経営者自らが全社員にクレドについての想いを伝える取り組みや、毎日の朝礼・全社メールなどで繰り返しクレドを読み上げる・周知する取り組みなどが挙げられます。
3−2−2.実践を評価する制度を導入する
社員がクレドに共感し、具体的にどのような行動をとるべきかイメージが明確な状態になってきたら、実践を評価する制度を導入するのがおすすめです。
実践を評価する制度とは、いわゆる人事評価などにおいて、クレドに基づいた行動をしている社員をきちんと評価することを意味します。
実践の評価を効率的に行う方法として、社内SNSなどを活用するのもよいでしょう。
上司が部下を評価するだけでなく、社員同士でお互いの行動を評価することが可能となり、社員のモチベーション向上とクレドの浸透を同時に目指せるメリットがあります。
4.クレド導入が上手くいかなかった事例

インターネットメディア事業を行う株式会社キュービックでは、2016年から2019年の3年間で業績が4倍になるなど、順調に成長を続けていました。
しかし、一見安泰に映る状況ではあったものの、企業規模が大きくなるなかで「経営陣から社員へどのようなことを話しても伝わらない」状態となっていたそうです。
クレドの刷新・導入のほか、オフィスの移転やコーポレートサイトのリニューアルなど会社の方向性を次々とアップデートしていくことに対し、「経営陣の決定に納得できていない人がいるようだ」という声もあちらこちらで聞こえてきたといいます。
事業は右肩上がりの一方で、組織のコンディションは半年以上も不調な状態が続きました。
このような問題が起こってしまった最大の原因として、経営陣から社員への丁寧なコミュニケーションがなされていなかったことが考えられます。
クレドを刷新し導入する際には、その背景や意図、経緯などを社員と十分に共有しておらず、クレド導入などの過程に多くのメンバーを巻き込むこともしていませんでした。
同社はその後、さまざまな立場のメンバーとあらゆる方法でコミュニケーションを繰り返したことで問題を乗り越えることができ、「クレドが分かりやすくなった」という社員の声も聞こえるようになりました。
この事例から、クレド導入の際には、理解・共感のための時間を十分に割いて社員の疑問を解消することが非常に大切であることがわかるでしょう。
参考:ヒトに「本当の意味」で向き合い続ける──15年目の変革、そして守り続けるコアバリュー
5.まとめ
今回の記事では、クレド導入がうまくいかない原因と、クレド導入を成功させるポイントを中心に解説しました。
あらためて記事の内容を振り返ってみましょう。
・クレドとは「企業における行動指針を簡潔に表した言葉」のこと
・クレド導入がうまくいかない原因は、以下の5つ
<作成>
・クレド導入の目的が明確になっていない
・経営陣だけでクレドを作成してしまう
<浸透>
・クレド理解のための時間を割いていない
・具体的な行動事例が提示されていない
・成果を共有していない
・クレド導入を成功させるポイントは、以下の4つ
<作成>
・全体で内容を議論する
・行動に移せる内容にする
<浸透>
・クレド理解・共感のための時間を割く
・実践を評価する制度を導入する
・実際のクレド導入失敗事例から、特にクレド理解・共感のための時間を十分に割くことは重要だといえる
本記事を参考に、全社一丸となってクレドの作成・浸透に取り組み、組織の成長を目指しましょう。