
近年注目を集めているエンゲージメントについて、耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか。会社と従業員の双方向的な関係性を表すエンゲージメントは、会社の取り組みによって向上できます。しかし、どのようにマネジメントすればいいのかわからないという方もいるでしょう。
この記事では、エンゲージメントを向上させるメリットを紹介し、マネジメントを行う方法について解説します。エンゲージメントのマネジメント方法は複数あり、自社に合った方法を選ぶことが大切です。ぜひ参考にして、自社のエンゲージメントマネジメントに役立ててください。
エンゲージメントとは
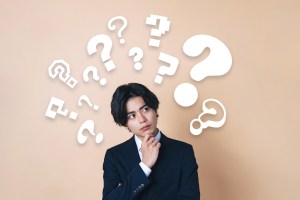
エンゲージメントとは、企業と従業員、顧客と企業など、双方向の強い結びつきを指す言葉です。経営や人事の領域では「従業員エンゲージメント」という言葉がよく使われ、従業員が会社に愛着心や貢献意欲を持ち、企業と従業員が双方向に信頼関係を築いている状態を指します。
従業員エンゲージメントとは、会社と従業員の関係性を表す言葉です。会社は理念やビジョンを従業員と共有し、従業員は会社に共感して貢献意欲を持つという、双方向性のある関係性を持つ状態は「従業員エンゲージメントが高い」と表現されます。会社と従業員が相互に影響を及ぼし合い、互いに存在を必要としながら成長できる関係を築いていくことを意味します。
エンゲージメント向上で会社と従業員のメリットが4つ!

従業員エンゲージメントを向上させることで、以下のメリットが期待できます。
- 従業員のモチベーションが向上し離職率が下がる
- 従業員間の情報共有が円滑にできる
- 組織が活性化し業績も向上する
- 会社に対する顧客エンゲージメントも強化される
エンゲージメントの向上は会社と従業員の双方にとってメリットがあり、サービスや製品を利用する顧客にとってもよい影響をもたらします。会社に関わるあらゆる方面でのメリットがあるといえるでしょう。
モチベーションが向上し離職率が下がる
会社はエンゲージメントの向上のために、企業のビジョンを従業員と共有し、待遇や職場環境の改善にも努めます。エンゲージメントが高い従業員は、仕事にやりがいを感じ、会社に貢献したいという意欲が高いです。
従業員は会社や仕事に対する理解を深め、自分の仕事に価値を見出せるようになります。仕事に自信やプライドを持つことで、モチベーションが高まり、離職率の低下が期待できます。会社にとっては、優秀な人材を流出させることなく確保でき、採用や育成にかかるコストも削減できるでしょう。
情報共有が円滑にできる
エンゲージメントが高い職場では、職場の腑に来や人間関係の改善が期待でき、従業員同士のコミュニケーションが活発になります。その結果、情報の共有や意見の交換などのコミュニケーションが活発になるでしょう。何気ないコミュニケーションが気軽にできれば、「理解してくれる人がいる」「自分の意見を尊重してくれる」いう安心感につながり、前向きな気持ちで仕事に打ち込めます。
日頃から円滑なコミュニケーションがとれる環境においては、業務上の情報共有や協力もスムーズにできるようになるでしょう。「確認したいけど話しかけにくい」「ピリピリした雰囲気で話しかけられない」という場面も減り、確認できなかったために起こる認識の齟齬や確認漏れなどを防げるでしょう。
組織が活性化し業績も向上する
エンゲージメントが高い従業員は、仕事に積極的に取り組み、組織全体の活性化につながります。自ら課題を発見し解決に努めたり、新しいアイディアを出したりするようになるでしょう。このような姿勢は、周囲の従業員にもよい影響をもたらします。触発される従業員が増えることで、組織全体の活性化も期待できます。
その結果、効率化や作業スピードの上昇、品質の向上などにつながり、業績の向上が期待できます。高いエンゲージメントが営業利益や労働生産性にプラスの影響をもたらすことは、研究でも明らかになっています。株式会社リンクアンドモチベーションの研究機関であるモチベーションエンジニアリング研究所と、慶應義塾大学大学院経営管理研究科/ビジネス・スクール岩本研究所の協同研究の結果が、以下で公表されています。
参照:株式会社リンクアンドモチベーション「モチベーションクラウド」
顧客エンゲージメントも強化される
従業員エンゲージメントとは、従業員が会社や仕事に強い愛着や帰属意識を持つことです。エンゲージメントが高い従業員は、会社や仕事に誇りを持っており、自ら考え行動します。よりよい商品やサービスを考えることで、それらをより魅力的なものに改善でき、顧客満足度の向上が期待できます。結果として顧客の満足度が高まり、新規顧客やリピーターの増加につながり、結果的に、業績の伸びが期待できます。
エンゲージメントをマネジメントする方法

エンゲージメントのマネジメントを行う方法には、以下の3つが挙げられます。
- リアルタイムマネジメントと環境整備
- エンゲージメントサーベイの実施
- 従業員の貢献の見える化
ここでは、それぞれの内容を確認しておきましょう。
リアルタイムマネジメントと環境整備
現状が明確であり、どのような対策を取ればいいかもわかっている場合は、リアルタイムマネジメントを行い改善に向けた対策を取りましょう。問題の要因が職場環境にある場合は、適切な環境整備を行います。
エンゲージメントサーベイの実施
現状がとらえられていない、何が課題なのか明確ではない場合、エンゲージメントを数値化して把握できる「エンゲージメントサーベイ」を行うことも一つの方法です。エンゲージメントサーベイとは、従業員が会社に対して持つエンゲージメントを調査して計測することです。従業員が会社や業務内容についてどのような感情を持っているかを分析することで、会社と従業員の関係性の強さを計測できます。
従業員の貢献の見える化
もう一つの方法として、従業員の努力や貢献を見える化して共有することで、会社全体のエンゲージメントをマネジメントし、高める方法があります。従業員同士のつながりが強まり、一人ひとりの行動が認められることで、会社全体の士気が上がり、組織が活性化します。ツールやインセンティブを活用することで、会社全体をまとめ、同じ方向を向いて努力することができます。
リアルタイムマネジメントと環境整備

エンゲージメントサーベイを行い従業員のエンゲージメントを計測することで、どのような対策を取ればいいかが見えてきます。「エンゲージメントに課題があると感じるが、取るべき具体的な施策が明確でない」という場合には、まずは課題の把握が重要です。課題が明らかになることで、必要な対策もおのずと見えてくるでしょう。
ここでは、エンゲージメントサーベイを行うために理解しておきたいステップと注意点を紹介します。
成功するエンゲージメントサーベイの6つのステップ
エンゲージメントサーベイを成功させるためには、以下の6つのステップを押さえておくことが大切です。
- 実施目的や注意点の共有
- ポイントを押さえた設問決定
- サーベイのスムーズな実施
- 結果分析と課題の明確化
- 課題解決のための人事施策の決定
- 持続的な改善のための再度サーベイ
ここでは、それぞれのステップごとに解説します。
実施目的や注意点の共有
エンゲージメントサーベイを行うには、従業員の協力が不可欠です。従業員には業務時間を削って質問に回答してもらうことになります。事前に実施目的やメリットを共有し、納得してもらった上でサーベイに臨みましょう。継続的にサーベイを行うと、日常的な定型業務として適当な回答を行う「サーベイ慣れ」が起こる可能性もあるため、目的はサーベイごとに伝えます。毎回の調査で正確なデータを得るための準備も不可欠です。
従業員が正直に回答しやすいように、匿名性を守ることについても説明しておく必要があります。その他の注意点があれば事前に伝えておき、スムーズに回答が集まるように準備しておきましょう。
ポイントを押さえた設問決定
エンゲージメントサーベイは、課題を明確にするために行うものです。そのため、調査の内容や範囲はある程度絞っておく必要があります。自社の現状から、課題がありそうな点をピックアップし、より詳細な課題が掴めるような設問にしなければなりません。設問の決定は、自社で行う場合と外部に委託する場合があります。自社で行う場合は、必要な情報を集められるというメリットがあります。しかし、担当者の負担が大きく、レポート作成に時間がかかる場合もあります。外部に委託する場合は、担当者の負担が少なく、わかりやすいレポートが得られるというメリットがあります。しかし、自社のニーズに合った設問を作成できない場合もあります。自社に合った方法を選んで実施しましょう。
サーベイのスムーズな実施
エンゲージメントサーベイへの回答方法も、自社の状況によって選ぶ必要があります。パソコン上での回答は、パソコンに慣れている人にとっては便利です。しかし、一人ひとりのパソコンがない場合や、パソコンを使い慣れていない従業員が多い場合は、操作の説明や理解に時間や手間がかかります。このような場合には紙に記入してもらう形式で調査を行うなど、実施の方法も検討しましょう。
結果分析と課題の明確化
従業員から回答を得たら集約・分析し、課題を明確にします。会社全体だけでなく部署ごとで分析することで、より詳細な人事上の課題が見つかることもあるでしょう。見つかった課題を顕在化している別の課題と照らし合わせて考えると、根本的な課題が見つかることもあります。
課題解決のための人事施策の決定
複数の課題が見つかった場合は優先順位をつけて、最初に取り組む課題を決める必要があります。そのうえで、解決のための具体的な施策を決定し、分析結果とともに会社全体に開示しましょう。結果についても従業員の理解を得たうえで、施策を行います。
持続的な改善のための再度サーベイ
施策を実施したあとも、エンゲージメントサーベイは継続的に行います。施策を実施しても、ねらい通りに課題が改善するとは限りません。施策の実施後、課題はどのように変化したか、どれくらい解決したか、新たな課題はないかなどを継続的に観察していく必要があります。一度サーベイを実施して終わりではなく、分析し施策を試し、効果を検証するというPDCAサイクルを回して、課題を改善していくことが大切です。
エンゲージメントサーベイについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にして取り組んでみてください。

エンゲージサーベイ実施時の注意点
エンゲージメントサーベイは、質問に回答する従業員と実施する担当者の双方にとって負担のかかるものです。手間や時間をかけて行う調査を有意義なものにするために、以下の注意点も押さえておきましょう。
- 従業員の負担にならないよう配慮してネガティブな反応を防ぐ
- フィードバックを行う
- 自社にあったタイミング・頻度で行う
従業員の負担にならないよう配慮してネガティブな反応を防ぐ
エンゲージメントサーベイを行うには、従業員の協力が不可欠です。業務の時間を割いて回答してもらうため、回答しやすい形式にする、短時間で回答できる質問にするという工夫が必要です。
従業員が「面倒だ」「意味がない」「よくわからない調査に回答させられる」とネガティブな反応を示すこともあるでしょう。拒否反応を防いで協力してもらうには、やはり事前の説明が重要です。実施する目的や匿名での調査であること、従業員にもメリットがあることなどを誤解のないように伝えましょう。従業員はただ回答するだけでなく、調査後に結果が開示されること、施策に活かされることなども合わせて伝えることで、調査への理解を得られることもあります。
フィードバックを行う
エンゲージメントサーベイを実施したら、集計・分析を行いスピーディーにフィードバックや結果の開示を行いましょう。時間を割いて回答した調査の結果について、従業員も気になるものです。エンゲージメントに関する課題について、従業員に関心や当事者の意識を持ってもらうためにも、フィードバックや結果の開示は有効です。今後の調査を形骸化させないためにも、迅速なフィードバックを行いましょう。
自社にあったタイミング・頻度で行う
エンゲージメントサーベイは定期的に継続して行うことは大切ですが、頻度についての決まりはありません。一般的な傾向としては、以下の2パターンが挙げられます。
- 年1回ほどの実施、設問数は50~70問程度
- 毎月、数か月に1回ほどの実施、設問数は1~10問程度
回答を行う従業員や、集計・分析を行う担当者の負担などを考えて、自社の状況に合ったタイミング・頻度で行いましょう。
従業員の貢献の見える化

業員の貢献が目に見える形で評価されれば、エンゲージメントやモチベーションの向上が期待できます。また、他の従業員も触発されてよりよい仕事ができるよう努力するようになれば、職場全体を活性化させるための重要な施策です。そのために有効な方法は、大きく分けて以下の2つです。
- 評価制度を充実させてインセンティブを与える
- 貢献を共有できるコミュニケーションツールを導入する
これらの方法を採り入れることで、貢献への評価が会社の風土として定着するでしょう。エンゲージメントを高めるサイクルとして、継続的な効果が期待できます。
評価制度を充実させてインセンティブを与える
明確な評価制度のある職場では、従業員のエンゲージメントを高めるうえで重要な役割を果たします。より貢献度の高い仕事をした従業員に対して、表彰や称賛などのインセンティブを与えることも、エンゲージメントの向上につながります。他の従業員に自分の貢献が周知されることで、「自分の仕事の価値が認められた」「これからも努力を続けよう」とさらなる意欲を持てるでしょう。周囲からの期待がモチベーションを高めることにもつながります。
以上のようなよいサイクルをつくるには、どのような点が評価されるかを明確にし、報酬や待遇にどのようにつながるかもクリアにする必要があります。加えて、評価が透明性を持って運用され、報酬や待遇に確実に反映されるものでなければなりません。
貢献を共有できるコミュニケーションツールを導入する
人事評価や表彰のタイミングだけでなく、日常的に貢献を共有する環境を整えることも重要です。エンゲージメントの適切なマネジメントに役立ちます。会社からの称賛のほかに、従業員同士が気軽に感謝や称賛を伝え合えれば、従業員同士の結束も固くなるものです。前向きなコミュニケーションは、やがて組織の風土として定着するでしょう。このような環境を形成するためには、新たなコミュニケーションツールを採り入れることが有効です。
こうした場面で役立つのが、全社参加型のコミュニケーションプラットフォームであるUniposです。Uniposでは、従業員や役員が部署や役職を越えてお互いに感謝や称賛を伝えることができます。やり取りはオープンな形式で行われるため、感謝や称賛はすべての従業員の知るところとなります。バックオフィス業務など、成果が見えにくい業務における貢献も共有されるため、会社へのエンゲージメントや従業員同士のつながりの強化が期待できるでしょう。自分の評価を振り返ることもできるため、モチベーションの向上や目標の設定にも活用できます。
Uniposを導入したメンバーズエッジカンパニーは約9割の従業員がエンジニアという会社です。多拠点でありテレワークの従業員も多いため、会社への帰属意識の低下や従業員同士のつながりが薄れることを危惧して導入を決めました。Unipos導入後は、感謝や称賛を伝え合うだけでなく、気軽なコミュニケーションを取るために日常的に楽しみを持って使われています。導入当初に将来的なビジョンとUnipos導入の目的を伝えたことも功を奏し、常に80%以上の利用率を維持しています。従業員同士の結びつきや会社へのエンゲージメントが強化され、いわば会社のインフラとして根付くことになりました。
テレワークでも「雑談」が生まれ、マネジメントに好影響 | 導入事例
まとめ

従業員と会社との結びつきであるエンゲージメントを向上させることで、モチベーションや生産性の向上も可能です。そのためには、現状を把握して適切な方法を選択する必要があります。課題が明確であればリアルタイムマネジメントや環境整備で対応できるでしょう。
また、エンゲージメントサーベイを活用して、課題をあぶりだすことも一つの方法です。前向きな雰囲気を会社の風土とするための取り組みを行うことも、エンゲージメントを底上げするためには欠かせません。エンゲージメントを向上させる方法は複数あるため、自社に合った方法で取り組みましょう。



