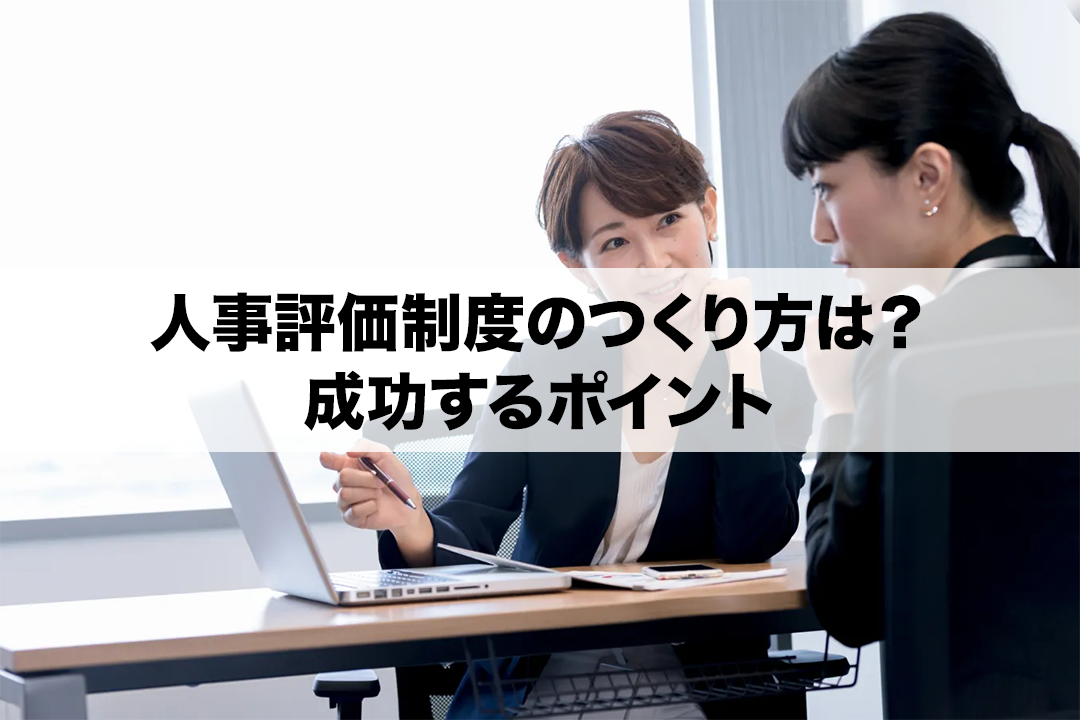
人事評価制度は成果を出した従業員を正当に評価する制度であり、従業員のモチベーションアップや生産性の向上のために重要です。制度の運用を成功させるためには、正しいつくり方を把握しなければなりません。
本記事では人事評価制度のつくり方や具体例などを解説します。
人事評価制度とは

人事評価制度とは、従業員の仕事内容や勤務態度、成果を評価し、昇給・昇格などに反映させる仕組みです。あらかじめ目標を設定し、一定期間ごとに仕事内容を目標と照らし合わせて評価します。
ここでは、人事評価制度の重要性や人事考課の違いを解説します。
人事評価制度の重要性
人事評価は、企業が求める成果を出した従業員や成長の見える従業員を正当に評価し、適切な処遇を与えることを目的とします。「努力して成果を上げれば評価される」と認識することで従業員のモチベーションは向上し、人材育成と企業成長に役立ちます。
人事評価制度により従業員は「会社が求めていること」を知り、「何をするべきなのか」を把握します。その結果、企業の成長につながる働き方が身に付くでしょう。
さらに人事評価制度では定期的な振り返りを行うため、自身のスキルや得意分野の確認に役立ちます。伸ばすべき強みや補うべき弱みを把握し、スキルアップを図れるでしょう。
従業員のスキルや得意分野を把握することで、適材適所の人材配置も実現できます。本来の能力を発揮できるポジションに配置すれば、高いパフォーマンスによる生産性向上も期待できるでしょう。
人事考課との違い
人事評価制度と似た制度に人事考課があります。両者に明確な違いはありませんが、人事考課とは主に給与や昇進を判断するものであるのに対し、人事評価は人材育成や能力開発などの目的も含み、より広い範囲で判断する点が異なります。
人事考課は社員の待遇決定を主な目的とした最終結果ですが、人事評価は社員の評価決定であり、運用しながら従業員の育成にもつなげていくものです。
人事評価制度の3つの要素(評価・等級・報酬制度)

人事評価制度は「評価制度」「等級制度」「報酬制度」という3つの要素で成り立ちます。
それぞれの役割をみていきましょう。
人事評価制度の要素1.評価制度:従業員の能力と成果と基準を測る手順
評価制度は、従業員の能力や実績を評価し、昇格や昇給を決定する制度です。従業員を評価するための基準や手順を定めます。従業員の能力や成績、勤務態度など、評価の対象となる項目は企業ごとに異なります。
客観的で公平な評価をするためには、評価制度の整備が欠かせません。どのような行動や勤務態度が評価されるのか、従業員と共有することが大切です。
評価制度では一方的な点数をつけるだけでなく、フィードバックも必要です。上司と部下の間で「できたこと」や「できなかったこと」を確認し、「課題とすべきこと」を確認する機会にすることで部下の成長を促せます。
人事評価制度の要素2.等級制度:能力と役割に基づく従業員の区分
等級制度は、従業員を能力・職務・役割などによって区分・序列化する制度です。等級ごとの権限を定めるためにも、等級制度が必要です。
等級により、評価制度や報酬制度が変わります。例えば、一般職から管理職になった場合、「リーダーシップ」や「部下の育成」といった項目が評価基準に加わるでしょう。
等級制度は従業員がより高い等級を目指すための指標となり、どのように成長していくかのキャリアプランを描きやすくなります。
人事評価制度の要素3.報酬制度:給与や賞与のルールとその効果
報酬制度は、給与や賞与、昇給などのルールを定める制度です。評価内容に応じ、昇給や賞与の額が決定されます。従業員の能力や等級に対し、公平な報酬額を支給するために欠かせない制度です。
報酬は給与と賞与、インセンティブに分けられ、インセンティブは金銭的な報酬だけでなく、表彰や旅行など「非金銭的報酬」を採用する企業もあります。
従来の報酬制度は年齢・勤続年数によって報酬を決定する「年功主義」が一般的でしたが、近年は成果により報酬額を決定する「成果主義」を採用する企業も増えています。
人事評価制度の種類

人事評価制度にはさまざまな方法があります。特徴やメリットを確認して、自社に合う方法を採用しましょう。
ここでは、人事評価制度でよく用いられる方法を3つ紹介します。
目標達成を中心にした評価方法.目標管理制度(MBO)
目標管理制度(MBO)とは「Management by Objectives」の略で、設定した目標に対する達成の程度から評価を判断する手法です。従業員が自ら目標を設定し、上司が目標達成に向けてサポートしながら達成度合いを評価します。
従業員自身が目標の設定から達成までを管理することで業務の道筋がわかり、業務効率が高まります。モチベーション向上にもつながるでしょう。設定した目標を達成するために業務量やスピードをコントロールすることを学ぶこともでき、自己管理能力の向上も期待できます。
ただし、従業員自身が目標を設定することで、高い評価を得るためにあえて低い目標設定をするという懸念が指摘されています。そのような運用にならないよう、注意しなければなりません。
活躍する従業員をモデルにした評価基準.コンピテンシー評価
コンピテンシー評価とは、自社で活躍する従業員をモデルにして評価基準を作り、人事評価を行う手法です。評価項目が具体的な人物の行動特性であるため、従業員が目標を把握しやすいのがメリットです。
スキルや能力だけでなく「成果を上げる人材がどのような行動をとっているか」に着目するもので、分析により効率的な人材育成を実現します。評価基準も明確であるため、評価者も公平に評価しやすいでしょう。
自社で優れた成果を上げる人材をモデル化するほか、企業理念や経営戦略などから独自のモデルを設定する場合もあります。
多角的な視点からの包括的な評価.360度評価
360度評価とは、上司だけではなく同僚や部下、自己評価も含めて幅広い視点から多角的に評価する手法です。
一般的な人事評価は上司から部下へ一方向の評価が行われますが、360度評価では異なる立場の複数人から評価が行われます。公平で多角的な観点から評価されるため、従業員の納得感を得やすいのがメリットです。
360度評価では自分の強み・弱みをさまざまな角度から確認できるため、人材育成の効果も期待できるでしょう。
効果的な人事評価制度のつくり方

人事評価制度をつくるには、目的の明確化や評価基準の設定など、複数の手順を踏む必要があります。手順は多く、初めから構築する場合はある程度の時間が必要です。
ここでは、効果的な人事評価制度をつくるステップを解説します。
組織的目的の明確化!成功の基盤
まず、人事評価を実施する目的を定めます。企業理念や行動方針をもとに、評価制度の運用で人材をどのようなに変えたいか、組織に活用したいかを考えましょう。
目的は従業員にも共有し、企業の目的・方向性を従業員にも理解してもらうことが必要です。
「会社はこのような人材を評価する」という目的を明確にすることで、従業員も努力すべき方向性を把握しやすくなります。
評価基準の設定!等級ごとの方針定義
次に、設定した人事評価制度の目的が達成されるよう、評価基準を設定します。等級ごとに評価の方針を定め、その等級に位置する人材に対して求める役割や期待する行動を細分化します。
評価基準は従業員が理解できるよう、わかりやすくすることが大切です。読み取りにくい基準は人により解釈が異なることにもなり、業務に対する取り組み方も変わってしまいます。従業員の立場から見て理解できる基準をつくり、共有することが必要です。
具体的な評価項目の選定!基準の適用
評価基準を作成したら、具体的な評価項目を設定します。組織の中期計画に沿って作成すると、計画の達成を推進できるでしょう。
必要な評価項目は企業ごとに異なり、同じ企業でも立場によって異なります。例えば、事務職であれば「正確性」、営業職であれば「交渉力」や「提案力」、管理職には「リーダーシップ」や「マネジメント能力」といった項目が必要です。
同じ項目でも、等級や立場によって求められるレベルは異なります。そのため、項目ごとにウエイトを設定することも大切です。一例として、「コミュニケーション」はすべての従業員で必要な項目ですが、営業や接客の業務ではウエイトを高く設定すべき項目といえるでしょう。
評価方法とルールの確立!明確な判断基準
評価項目に対する評価方法は、主に3つの方法があります。
- 業績評価
- 能力評価
- 情意評価
業績評価とは、与えられた役割により達成した成果を評価する手法です。営業職であれば売上目標の達成があげられます。評価としてわかりやすくモチベーションを高めやすいものの、業績評価のみでは目の前の成果のみに注力して人材育成など中長期的な視点が抜けてしまう懸念があります。
能力評価は業務を遂行するために必要なスキルや知識を評価する手法です。成果を出している人のスキルに着目し、それを身につけることを推進します。成果が目に見えにくい業務の従業員を評価しやすいのがメリットで、スキルアップに向けてモチベーションを高める効果があります。
情意評価とは、仕事への意欲や勤務態度を評価する手法です。事務など成果が可視化できない業務を評価できる点がメリットですが、項目の設定や正確な評価は難しいといえるでしょう。
評価項目に対する判断のルールづくりも必要です。一般的に「1・2・3・4・5」などの5段階評価が行われています。ルールづくりでは、評価の公平性が保てるようにすることが大切です。
ルールが決まったら、評価者を決定します。評価項目に基づいて適切に評価できる人材を選定することが重要です。
社内全体への周知!スムーズな評価の実施
人事評価制度が確立したら、従業員に周知します。周知を徹底せずに従業員の理解を得ないまま運用すると、制度を押し付ける結果になってしまいます。評価制度を十分に理解できない場合、業務遂行にあたっての方向性もみえないでしょう。
スムーズな評価を実施するためには、策定した人事評価制度を明文化し、従業員にわかりやすく伝えることが大切です。ただ文書を配布するのではなく、説明会を開催して説明を行い、従業員からの質問も受け付けて疑問を解消するようにしましょう。
評価の運用開始と検証!定期的な改善と向上
人事評価制度は策定と運用で完了ではなく、効果の検証と改善が欠かせません。また、経営の動向や従業員数の変動など、変化に合わせた見直しも必要です。
運用開始後は、従業員が制度を理解しているか、不満は出ていないかを検証します。定期的にアンケートを実施するなどして、評価制度が計画通りに機能しているかチェックしましょう。
人事評価制度を成功させるポイント

人事評価制度を成功させるためには、長期的視点で取り組むこと、運用可能性を考えることなど、いくつか押さえたいポイントがあります。
人事評価制度を成功させるためのポイントをみていきましょう。
定期的な修正・変更を行い、長期的視点で実施する
人事評価制度は運用後に工夫や改善が必要になることも多く、企業の成長や人員の変動で求められる制度の内容も変わってきます。はじめから完璧な制度を作ろうとせず、定期的に修正・変更を行いながら、長期的な視点で取り組むようにしましょう。
人事評価制度の運用では、企業戦略を推進し、成果を出すための事業計画と連動させながらPDCAを回す方法も効果的です。人事評価制度と事業計画を連動させることで戦略を行動に移すことができ、目標の達成を促すでしょう。
現実的に運用可能かどうかを考える
制度を設計するときは現場のリソースを念頭に置き、現実的に運用可能かどうか確認が必要です。理想ばかりが先行し、現実的な運用可能性を考えずに設計すると、スムーズな運用が妨げられる可能性があります。
一般的に、人事評価制度の運用では多くの業務が発生します。部下の設定した目標設定が適正かの確認や、評価シートの採点などさまざまな業務があり、上司の負担は大きいといえるでしょう。
評価面談も行わなければなりません。ただ評価の結果を部下に通知するだけでなく、一人ひとりにフィードバックを行う必要があります。
これらの負担を考え、運用工数をできるだけ削減する方向で設計することも必要です。
運用を効率化するために人事評価システムを導入するのもひとつの方法です。これまで紙やエクセルで行っていた評価をツール上で一元化することにより、作業を効率化できるでしょう。
ただし、システムの導入で従来の評価基準をすべて再現することは難しく、作り直さなければならない可能性もあります。
公正に評価する
人事評価制度を成功させるポイントは、公正に評価することです。評価は処遇に関わるため、評価結果が公正・公平でないと感じた従業員は仕事へのモチベーションを失うでしょう。人事評価制度を設けた目的の達成が難しくなります。
従業員の納得感を得るためには、運用前に周知を徹底し、制度の目的を浸透させることが大切です。運用後は、目標達成までのプロセス・進歩具合も可視化できるような仕組みも必要になるでしょう。評価シートの受け渡しだけではなく、評価について従業員が納得できるフィードバックも必要です。
従業員のモチベーションを高めるために役立つのが、ピアボーナスのUniposです。会社の行動方針に沿った行動や隠れた貢献などを評価し、従業員同士が称賛や感謝をおくり合うシステムです。
称賛を受け取った従業員は「日々の仕事を認められている実感」を得て、モチベーションが向上します。上司は部下の貢献を手軽に把握できるため、人事評価にも良い影響を与えるでしょう。
人事評価制度の注意点

人事評価制度は組織風土に合わせた設計も大切です。組織風土に合わない制度を構築すると、評価制度が形骸化する場合もあります。
例えば、成果主義の評価制度を導入しても、古くからある年功序列の仕組みが残ったままではうまく運用できません。
給与は原則として下げることはできず、年功序列制のもとで恩恵を受けてきたベテランの従業員がいる会社において成果主義を採用すると、若手の従業員は不公正感を覚えることもあるでしょう。
また、成果主義を採用する場合、成果が数字では表せない業務に携わる従業員や、成果を上げる過程で頑張る従業員を評価する仕組みを設けなければ、これらの従業員はモチベーションを下げる結果になります。
人事評価制度では、上司が部下を適切に評価するということも注意したい点です。定期的な評価面談を行わなかったり、形式的な面談で終わらせたりする対応では、評価制度は形骸化してしまいます。
人事評価は部下のこれまでの仕事を評価して終わりではなく、評価を通じて部下を育て、企業の成長につなげる役割があります。評価する側は、このような人事評価制度への理解を深めることが求められるでしょう。
人事評価制度の具体例

これから人事評価制度の見直しを検討している場合、成功事例が参考になります。ここでは、新しい人事評価制度の構築に成功した事例を紹介します。
さらに、人事評価制度だけでは解決できない課題を解消した企業の事例もみてみましょう。
ジョブ型雇用に基づく新たな制度を導入【富士通】
総合エレクトロニクスメーカーである富士通株式会社は、2020年4月、「ジョブ型人材マネジメント」の考え方に基づく新たな人事制度を一般社員に導入しました。一人ひとりの職務の明確化と職責の高さに応じた報酬により、従業員の主体的な挑戦と成長を後押しする制度としています。
具体的には、職責の高さを表す仕組みである「FUJITSU Level」を導入し、レベルに応じた報酬水準として、より高い職責へのチャレンジを促進しています。
さらに、2021年度から幹部社員に適用を開始している評価制度「Connect」を一般社員にも展開しました。社会・顧客へのインパクト・行動・成長を評価する国内外共通の評価制度です。
評価制度で拾いきれない課題を解決【ミュートス】
製薬会社向けのシステム開発を行う株式会社ミュートスは、エンゲージメントのサーベイツールで社内調査を行ったところ、「やりがい」と「承認」の項目が低いという課題が見えてきました。「自社製品への誇りが持てず、会社のビジョンが見えない」「自分が正当に評価されていない」と感じている社員が多かったということです。
自分自身が正当に評価されていないという課題に対して人事評価制度の改善も進めましたが、時間がかかり、評価制度では拾いきれないこともありました。そこで考えたのが、Uniposの導入です。
同社には協力的な企業風土があり、システムの導入はスムーズに進みました。人事評価制度で拾いきれない日常の出来事に感謝を伝えるという当初の目的は達成され、さらに期待した以上のコミュニケーションが発生したという成果も得られています。
また、導入から1ヶ月後にサーベイツールで測定してところ、エンゲージメントの「承認」スコアが目に見えて上昇していたということです。
人事評価制度の失敗例

人事評価制度の構築に失敗している事例もあります。人事評価制度が失敗するポイントは大きく分けて以下の2点です。
- 制度自体に問題がある
- 運用に問題がある
制度に問題がある場合、主に以下のような内容が考えられます。
- 評価が昇給・昇格に反映されていない
- 評価基準が不明確
- 自社の現状と乖離している
- 人材育成や業績アップに連動する仕組みになっていない
運用に問題があるのは、主に次のような場合があげられます。
- 制度の内容や目的が従業員に理解されていない
- フィードバックが十分に行われていない
- 経営層や管理職の取り組みが不足している
- 運用体制が整備されていない
- 人事評価エラーが起こっている
人事評価制度の失敗事例をいくつかみてみましょう。
(評価基準が曖昧で公平な評価ができなかった)
評価基準が明確にしなかったために、公平な評価ができなくなったという事例があります。基準が曖昧で評価者の主観や感情が入る余地を残したため、最終的な評価が評価者の判断に委ねられてしまったのです。不公平な評価になり、従業員の不満も大きくなってしまいました。
(評価結果が昇給・昇格など待遇に反映されなかった)
評価が待遇に反映させる基準が曖昧で、評価が高くても給与や賞与のアップに結びつかず従業員のモチベーションが低下したという事例があります。
ただ評価するだけの制度になり、従業員の目的達成に向けた意欲も半減してしまいました。
いくら高い評価を得ても、それに見合った処遇がなければ従業員の不満は高まります。給与や賞与への反映が難しい場合でも、モチベーションを高めるようなインセンティブなどの報酬は設定しなければなりません。
(フィードバックが行われていない)
ただ評価シートを渡すだけで、フィードバックを行わず、制度が形骸化したという事例もあります。人事評価制度の運用では評価結果のフィードバックが大切であり、結果を通知するだけでは人材育成や生産性向上など、人事評価制度の目的を達成できません。
従業員は評価の理由について知ることができなければ、評価に納得できないでしょう。事例では、その後の評価制度の運用がほとんど形骸化してしまったということです。
まとめ

人事評価制度は、成果を出した従業員を評価し、適切な処遇を与えることを目的とします。「成果を上げれば評価される」と認識した従業員はモチベーションを高め、仕事に対し意欲的に取り組むでしょう。公正な人事評価制度をつくることで生産性が向上し、企業の成長を実現します。
人事評価制度のつくり方は手順が必要であり、時間もかかります。まず目的を設定し、評価基準や評価項目を明確にすることが大切です。従業員への周知も徹底させましょう。運用では、効果を検証しながら改善を行い、目的を達成できる人事評価制度を構築してください。


