
「インセンティブ制度とは、具体的にどのような制度なのだろう?」
「インセンティブ制度の効果を知りたい」
あなたは今このようにお考えではないでしょうか?
インセンティブ制度とは、個人の仕事の成果によって報酬を与える制度です。
従業員や組織のモチベーション向上や活性化のために、多くの企業で導入されています。
かつてのインセンティブ制度は業績や売り上げに応じたものが目立ち、制度の対象も営業職や販売職など職種が限定的でした。
しかし近年では、インセンティブを金銭報酬に限定しないことで、あらゆる職種にも対応できる制度となっています。
当記事ではインセンティブ制度について、メリットやデメリットのほか、導入事例にも触れてどこよりも分かりやすく徹底的に解説してきます。
インセンティブ制度導入時のポイントやおすすめのサービスまで網羅していますから、当記事を読むだけでインセンティブ制度を理解し、導入すべきか判断できるでしょう。
インセンティブ制度とは?

インセンティブ制度とは、個人の仕事の成果によって報酬を与える制度です。
インセンティブ(incentive)という単語には「目標を達成するための刺激」という意味があり、インセンティブ制度は従業員や組織のモチベーション向上や活性化のために導入されています。
インセンティブの報酬は企業によってさまざまですが、広く知られているのは金銭報酬です。
金銭報酬は個人の仕事の成果が明確に分かる営業職や販売職での導入が多く、売上目標や契約件数の達成などによって報奨金が支払われます。
そのため、「インセンティブ制度=インセンティブ報奨金」と思いがちですが、近年では、インセンティブ制度の報酬を金銭に限定しない企業が増えています。
インセンティブ制度の報酬を金銭以外に設定することで、職種に関係なくすべての社員が制度の対象となります。
また、インセンティブ制度と混同されやすい類似制度として、ボーナスや歩合制があります。
|
インセンティブ制度 |
固定給とは別にもらえる報酬。 個人の業績・貢献度などによってもらえる。 報酬は金銭に限らず、表彰や副賞などさまざま。 |
|
ボーナス |
会社の業績に応じて、すべての従業員に支払われる。 個人の成果ではなく、会社の業績に左右される部分が大きい。 固定給の〇ヶ月分、または役職で金額が決まっている場合もある。 |
|
歩合制 |
個人の売り上げなどに応じて支払われる報酬。 基本給が低めに設定されていることが多く、給料が安定しない。 実力主義の要素が強い報酬制度でハイリスク・ハイリターンでもある。 |
インセンティブ制度は固定給が保証されていること、個人の成果で報酬が決定することが特徴です。
従業員によって受け取るインセンティブに違いが出るため、実力主義の要素が比較的強い制度と言えるでしょう。
インセンティブの種類

かつては金銭報酬が主流だったインセンティブ制度ですが、近年ではインセンティブは金銭にとどまりません。
会社ごとにユニークなインセンティブを設けているところもありますが、大きく分類すると次の4種類になります。
■報奨金制度
■表彰制度
■リーダー制度
■旅行などの副賞型制度
この章では、それぞれの制度について詳しく解説していきます。
2-1.報奨金制度
報奨金制度は、個人的な売り上げや成果に応じて金銭がもらえる制度です。
個人の成果を数字で表すことができる業種で多く導入されています。
報奨金制度のインセンティブは頑張れば頑張った分だけ収入が増えるため、モチベーション向上につながりやすい反面、従業員の間の給与に格差を生み出します。
【報奨金制度を採用している主な業種】
■不動産業
■自動車販売業
■販売業
■保険業
■美容系(美容師、エステサロンなど)
【報奨金制度のインセンティブ例】
①契約件数や売上金額に応じてインセンティブを与える
契約件数や売上につき、〇円または〇%がインセンティブとして支払われる仕組み。
販売する商品が高額な不動産業や長期契約の保険業で採用されることが多いのが特徴。
②目標達成率に応じてインセンティブを与える
四半期や半年など、期間ごとに設けた目標値の達成率によってインセンティブが変動する仕組み。
2-2.表彰制度
事務職や専門職など、成果が数値化しにくい職種にも対応できるのが表彰制度です。
表彰制度とは、個人やチームの業績だけでなく、日常的な努力や貢献などを褒め称える制度です。
コツコツ努力をしている人や縁の下の力持ちといった目立ちにくい従業員にスポットライトを当てることができます。
報奨金と比較してコストも抑えられることから、導入しやすい制度と言えるでしょう。
表彰内容は企業によってさまざまです。
一例を挙げると、
◎社内の活性化に役立つアイディアの提供
◎残業時間最少
◎顧客満足度
などがあります。
個人の頑張りを大々的に表彰することで、
◎「自分は認められている」という承認欲求を満たすことができる
◎「自分はやればできる」という自己肯定感のアップ
につながり、ますます「仕事を頑張ろう!」と意欲を高める効果が期待できます。
2-3.リーダー制度
リーダー制度とは、年齢や勤労年数に関わらず、リーダー職に就ける制度です。
チームやプロジェクトのリーダーとして業務により深く関われたり、まかされる仕事の範囲が広がったりします。
リーダー職になることで得られるメリットは、
◎自分の能力が認められることにより、承認欲求が満たされる
◎チームのメンバーから一目置かれる存在になれる
◎メンバーを統率する経験ができる
◎チームのメンバーが「次は自分がリーダーになれるように努力しよう」と良い競争心を持つ
などがあります。
リーダー制度は実力や努力次第で、誰でも平等にリーダーとなれる制度です。
さらにリーダー手当を支給するとより魅力的なインセンティブとなるでしょう。
モチベーションアップには役職を与えることが有効ですが、インセンティブとしては下記の理由により適しません。
|
【役職をインセンティブとして与えにくい理由】 ■組織のスリム化などで役職が減少傾向にある ■役職には人数制限があり、努力次第でポストに就けるわけではない ■一度与えた役職は基本的に降格できない ■役職を与えると固定給が上がり、企業のコスト負担が大きくなる ■役職は負担も大きいため、魅力的な目標ではなくなりつつある |
役職は長期的な成果や年功序列の要素で決まることが多く、人によっては魅力的なインセンティブと言い難いのが実情です。
ですから、若手社員のモチベーション維持や向上には役職ではなくリーダー職を与えることが最適と言えるでしょう。
2-4.旅行などの副賞型制度
インセンティブの報酬として、旅行や自社製品、休暇などの副賞をご褒美として与える企業もあります。
副賞型は従業員に直接的な利益をもたらすため、モチベーションの良い動機付けになります。
実際に株式会社エアトリが行ったインセンティブ旅行に関する調査では、7割以上の人がインセンティブ旅行の制度があれば仕事のモチベーションが上がると回答しました。
副賞型制度の魅力は、インセンティブ対象が個人または部署(チーム)どちらにも対応できることです。
個人でインセンティブを獲得した場合は家族旅行または個人旅行、チームで獲得した場合はチーム全員での旅行とする企業が多いようです。
詳しくは5章で説明しますが、個人成果を重視したインセンティブの場合は人間関係の悪化を招く恐れがあります。
副賞型は制度の内容次第で全職導入可能ですし、インセンティブの対象を部署ごととすることでチームワーク強化も望めます。
共に働く仲間同士が互い送り合うインセンティブ(ピアボーナス)を簡単に実現する「Unipos」の詳細はこちら
インセンティブ制度で従業員が得られる3つのメリット

インセンティブ制度の導入により、従業員が得られるメリットは次の3つです。
■目標が明確になり、モチベーション維持がしやすい
■成果が正当に評価される
■承認欲求が満たされる
それではさっそく、それぞれのメリットについて詳しくご説明します。
目標が明確になり、モチベーション維持がしやすい
インセンティブ制度には達成すべき目標が明確になるというメリットがあります。
私たち人間のモチベーションとは、その日の気分によって上下しやすいものです。
プライベートで悩みを抱えていたり、仕事が思うようにいかなかったりすると、やる気が削がれてしまうということもあるでしょう。
しかし、目に見えた目標があることで、「自分は何をすべきか」「どうすれば達成できるのか」を意識的に行動できるようになり、モチベーションが維持しやすくなります。
成果が正当に評価される
自分の働きや努力が正当に評価されると、誰だって嬉しいもの。当然モチベーションが上がります。
ただし、組織への貢献は必ずしも目に見える成果だけではありません。
◎契約は取れなかったが、次回につながる信頼関係を構築した
◎顧客から感謝をされた
などの将来的に成果となりそうな事案もあるでしょう。
また、業務上の直接的な成果とはなりませんが、間接的に成果へつながる貢献もあります。
例えば、
◎誰に対しても笑顔で接し、職場の雰囲気を明るくしてくれる
◎書類の整理を進んで行ってくれる
◎困っている人を積極的に助ける
などは誰もが働きやすい職場環境の土台となるものですが、評価につながりにくい側面もあります。
数字だけでなく幅広い貢献をカバーできるインセンティブ制度があると、日々の頑張りや能力をきちんと評価してもらえます。
承認欲求が満たされる
承認欲求は誰もが持つ「周りから認められたい」という欲求です。
組織が掲げるインセンティブを得ることで、周囲の人から公式に「目標を達成した人」と認められます。
これにより、承認欲求がストレートに満たされるのです。
承認欲求が満たされると、「自分はやればできる」という自信が付き、仕事にやりがいを感じます。
さらに上を目指して業務に励めるでしょう。
インセンティブ制度の導入で企業が得られるメリット

インセンティブ制度は従業員にとって3つのメリットがありましたね。
実はインセンティブ制度は従業員だけでなく、企業にとっても3つのメリットがあります。
企業のメリットは次の3つです。
■社員のモチベーション向上が業績アップにつながる
■優秀な社員の離職を防ぐ
■歩合給や固定給アップに比べてコストを抑えられる
それぞれ解説していきます。
社員のモチベーション向上が業績アップにつながる
インセンティブ制度は従業員の頑張り次第で得られる報酬です。
そのため、従業員は報酬獲得を目指して切磋琢磨します。
業績に直結する売り上げ目標を達成したり、業務効率を上げたりすることは組織の利益につながります。
優秀な社員の離職を防ぐ
従業員の離職理由として、「正当な評価が得られない」「自分は認められていない」などを挙げる人も少なくありません。
いくら頑張っても評価や待遇が変わらないのであれば、「頑張るのは無駄」「正当に評価してくれる会社を探そう」と考えるでしょう。
優秀な社員であればあるほど、正当な評価を必要とします。
インセンティブ制度は「努力を認める制度」「努力次第で追加の報酬が得られる制度」ですから、モチベーション低下や離職を防げる効果も期待できます。
歩合給や固定給アップに比べてコストを抑えられる
従業員のやる気を引き出すには、給与の引き上げやボーナスのアップなどの待遇改善が効果的なのは言うまでもありません。
しかし、現実問題として固定給や歩合給などのアップは厳しいと言わざるを得ません。なぜなら、一度上げてしまった給与は下げにくいものだからです。
インセンティブ制度は従業員の成果や貢献度などに対して、一時的に与える報酬です。必ずしも金銭である必要もないため、やり方次第ではコストを抑えて従業員のやる気を高めることができます。
共に働く仲間同士が互い送り合うインセンティブ(ピアボーナス)を簡単に実現する「Unipos」の詳細はこちら
知っておくべきインセンティブ制度のデメリット

インセンティブ制度は従業員・企業の双方にとってメリットがあることが分かりました。
とはいえ、何事にもデメリットはあります。
インセンティブ制度の注意すべきデメリットは、
■従業員の間でモチベーションに差が出る
■人間関係が悪化するリスクがある
■インセンティブの内容やルールなど細かな配慮が必要
の3つです。
失敗しないインセンティブ制度の設計には、デメリットをあらかじめ理解しておくことが大切です。
従業員の間でモチベーションに差が出る
仕事だけでなく、すべてのことに当てはまりますが、努力が必ずしも成果に結びつくとは限りません。
目標を達成のためにどんなに頑張っても思うような成果が得られないことがあります。
インセンティブ制度の内容が成果を重視するものの場合はその傾向が顕著になり、いつも同じ従業員がインセンティブを得ているということも。
インセンティブを獲得した従業員は高いモチベーションで業務にあたれますが、インセンティブ未獲得の従業員はやる気を失う可能性もあります。
努力がインセンティブに結びつかないことで、かえってモチベーションの低下を招く危険性があるのです。
人間関係が悪化するリスクがある
インセンティブ制度は個人の能力や成果を反映する意味合いが強い制度です。
インセンティブ制度の獲得条件が個人業績によるものの場合、同僚をライバル視してチームワークを阻害する恐れがあります。
インセンティブの評価基準を、商品の販売数としたケースで見ていきましょう。
企業の利益を第一に考えるなら、とにかく商品を販売することが重要です。
しかし、インセンティブに個人販売数が関わってくるとなると、次のようなスタンドプレーに走る従業員も出てきます。
◎商品の購入見込み客の共有をしない
◎自分が対応する時に購入させようとする
◎販売時に有効なノウハウを共有しない
その結果、チームのメンバー内で足を引っ張り合う形になり、「あいつとは仕事をしたくない」「自分勝手なやつだ」などと不信感を抱く可能性があります。
チームワークの乱れが人間関係を悪化させるだけでなく、業績にも悪影響を及ぼすリスクがあるのです。
インセンティブの内容によっては、成果を出そうとする従業員間の競争を激化させ、それが要因で職場環境が悪化してしまうことも考えられます。
5-3.デメリットを防ぐためには簡単に導入できない
先にご紹介した2つのデメリットを防ぐためには、インセンティブの内容やルールなどに細かな配慮が必要です。
◎一部の従業員だけが該当する制度にしない
◎個人だけでなく、チーム用のインセンティブも設定する
◎誰もが納得できる公平な評価基準にする
これらをすべて満たすためには、インセンティブ制度導入前の調査が重要になります。
従業員へのアンケートやヒアリングのほか、制度運用のシミュレーションも必須です。
そのため、自社でインセンティブ制度をゼロから構築するには、人的コストや時間がかかります。
インセンティブ制度の導入事例

実際にインセンティブ制度を導入し、良い効果を出している企業を3社ご紹介します。
6-1.従業員同士で称賛を送り合う!ピアボーナス制度「メルチップ」
フリマアプリの大手・メルカリでは、スタッフ同士がリアルタイムに感謝や称賛、さらにインセンティブとして少額の報酬(ピアボーナス)を送り合う仕組み「メルチップ」を導入しています。
メルチップとは、「mercari+Tip」の造語で「Go Bold」「Aii for One」「Be Professional」な出来事に対して、チャットアプリ上で気軽に感謝の気持ちを表せる仕組みです。
メルチップは毎週400ポイントずつ配布され、感謝や称賛などを伝えたい相手に送ります。
受け取ったメルチップは「1ポイント=1円」として毎月の給与とともに支払われるのが特徴です。
メルチップ制度導入後の社内アンケート調査では、満足度がなんと87%! 社員のおよそ9割が、5段階評価で満足度4以上とするなど、好評を得ています。
メルチップ導入で、スタッフ間のコミュニケーションが活性化だけでなく、評価をする際にも役立っているようです。
参考:
贈りあえるピアボーナス(成果給)制度『mertip(メルチップ)』を導入しました。
同僚から月60回「成果給」を受け取った人も!メルカリの「ピアボーナス」運用の裏側
ビジネススキルや健康増進プログラムも!ポイント制インセンティブ
45歳以上のベテラン社員を対象とした健康増進・能力向上プログラムをインセンティブとして設定しているのが、大和証券グループです。
2015年から導入されたこの制度は、ベテラン社員が対象と限定的ではありますが、実にユニーク。「ビジネススキル」や「マネジメントスキル」のほか、健康増進を目指すプログラムが用意されています。
これらのプログラムを受講または実践し、基準をクリアすれば、ポイントが付与される仕組みです。累計ポイントは、55歳以降の給与に反映されるというのも一風変わっていますよね。
健康増進プログラムには、3ヶ月間で1日平均1万歩でポイントが獲得できる「ウォーキングチャレンジ」などがあり、ポイント導入後には参加者が3倍に増えたそうです。
残業ゼロがインセンティブになる!「残業ゼロインセンティブ制度」
パーソルプロセス&テクノロジー株式会社の一部門であるワークスイッチコンサルティングでは、残業ゼロインセンティブ制度を導入しています。
この制度は文字通り、残業がゼロの社員に対してインセンティブを支給するものです。高い生産性を評価する制度のため、単に残業がゼロであれば良いというわけではなく、成果が出ていないと判断された場合にはインセンティブが得られないこともあります。
インセンティブの受給対象となるのは、毎月100名前後。同部門では、平均残業時間と受給社員数が反比例していることから、生産性向上の成果が出ていると考えています。
インセンティブ制度を導入するなら押さえておくべき3つのポイント

6章でもご紹介したとおり、一口にインセンティブ制度と言っても、企業によってインセンティブの内容は多種多様です。
魅力的なインセンティブの設定はもちろん大切ですが、制度をうまく機能させるには、導入前に次の3つのポイントを押さえておく必要があります。
①「なぜ導入するのか」を明確にする
②個人にとって魅力的なインセンティブを把握する
③インセンティブ制度の詳細を決定する
それでは詳しく解説していきます。
「なぜ導入するのか」を明確にする
まずは「なぜインセンティブ制度を導入するのか」、導入の目的や目標(目指すべき姿)を明確にしましょう。
導入目的が業績アップと顧客満足度の向上では、インセンティブの内容や判断基準も異なります。
多くの売り上げで業績に貢献したのに全社員の前で表彰のみでは、従業員のモチベーションの原動力とはなりがたいでしょう。また、判断基準が曖昧になりがちな数値化できない個人の頑張りに多額の報奨金を与えるのは、従業員の不平不満を生み出しかねません。
インセンティブ制度の運営には、一定のコストがかかりますから、コストに見合う成果が得られるかの検討も必要です。
個人にとって魅力的なインセンティブを把握する
インセンティブ制度は、個人の仕事に対するモチベーションを高めるものですから、従業員にとって魅力的なものでなければ機能しません。
2章で詳しくご紹介しましたが、インセンティブの種類は次の2つに分類することができます。
◎報奨金・副賞など金銭に結び付くもの
◎称賛や昇格など組織での立場に結び付くもの
どちらのインセンティブが最適であるかは、社内の雰囲気や従業員の状態から判断しましょう。
従業員の行動につながるような魅力的なインセンティブを把握するためは、導入前にアンケート調査やヒアリングが有効です。
インセンティブ制度のルールを明確にする
導入の目的とインセンティブが決まったら、制度の細かな条件をあらかじめしっかりと決めていきます。
①制度の対象者(個人またはチーム)
②インセンティブの内容
③インセンティブの獲得条件
④獲得の評価基準や評価方法
⑤制度の運営方法
インセンティブ獲得の条件や手続きなど、制度の一連の流れをシュミレーションし、持続的に運営が可能か検討することが重要です。
職種や部署で得られるインセンティブに差が出ないか、常に一部の従業員が獲得する状況にならないかを重点的にチェックしましょう。
従業員の間で不平不満が生まれないように、細かな配慮が必要です。
インセンティブ制度おすすめサービス3選
インセンティブ制度を導入する際に、すべてを自社で構築するのは非常に大変です。
7章のデメリットをご紹介した時にも触れましたが、インセンティブの内容やルールなど、細かな配慮が必要になります。
また、導入当初は新鮮で盛り上がりを見せても、だんだんマンネル化してしまう可能性もあります。仕事や職場環境に合わなくなる場合もあるでしょう。
これらのマイナス面は制度や手続きを簡素化することで払拭できます。
ここでは、インセンティブ制度として活用できるおすすめのサービスをご紹介します。
ピアボーナス・Unipos(ユニポス)

株式会社Uniposが提供するWebサービスです。
従業員同士が日頃の感謝や称賛のメッセージとともに、成果給(ピアポイント)を送り合える仕組みです。
主な特徴は次のとおりです。
■Slackなどのチャットツールから気軽に成果給や称賛が送れる
■働きがいやエンゲージメントを最大限高められる
■働き方・HR関連のアワードを多数受賞
■たまったポイントはAmazonギフト券など各社自由に設定できる
【主な導入企業】
株式会社メルカリ、ボルボ・カー・ジャパン株式会社、株式会社商船三井、パーソルテンプスタッフ株式会社など
公式サイト:https://unipos.me/ja/?utm_source=ongen&utm_medium=ownedmedia&utm_term=infeed&utm_content=wiu&utm_campaign=infeed_text
サンクスコレクト

旅行会社大手・JTBの子会社「JTB ベネフィット」が提供するインセンティブとして活用できるポイントサービスです。
主な特徴は次のとおりです。
■貯めたポイントは約10,000点の商品から交換可能
■サービスのカスタマイズが可能
■手間がかからず簡単に運用できる
【主な導入企業】
JTBグループなど約100社(2016年8月末現在)
公式サイト:https://thankscollect.jp/
インセンティブ・ポイント
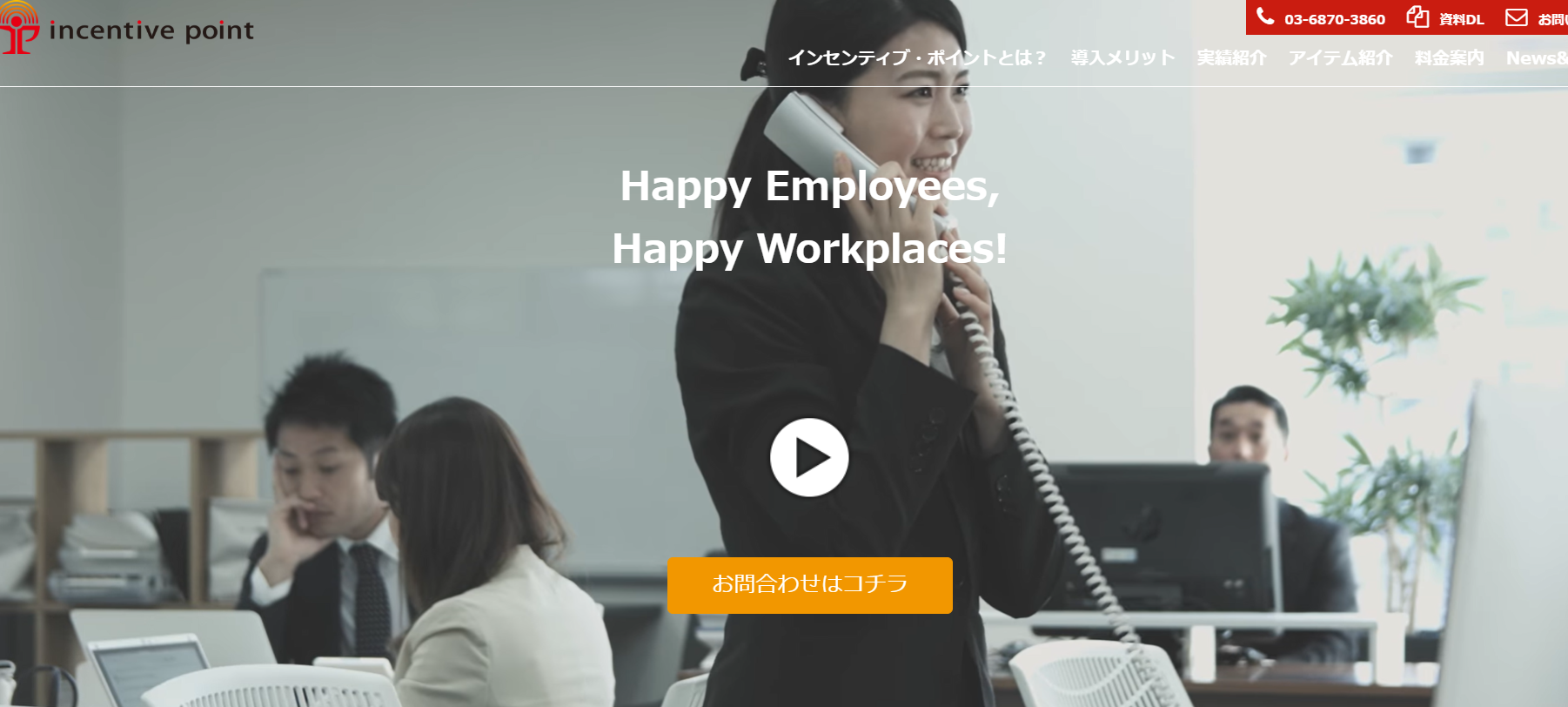
インセンティブ・ポイントは株式会社ベネフィット・ワンが提供する社内ポイントサービスです。
導入実績が約436社と多くの企業で採用されています。
主な特徴は次のとおりです。
■シンプルな仕組みで、簡単に社内ポイントプログラムを導入できる
■多種多様なアイテムとの交換が可能
■コミュニケーションをより活性化させるサンクスポイント機能搭載
■モチベーションや売上アップに貢献
【主な導入企業】
Soft Bank、Panasonic、SUNTORY、リンガーハットなど
公式サイト:https://bs.benefit-one.co.jp/incentivepoint/index.html
まとめ
インセンティブ制度は個人のモチベーションを高めるものです。
インセンティブの種類は報奨金以外にも、表彰やリーダー職などのポジションを与えるなどあり、どの業種・職種にも対応可能です。
インセンティブ制度によるメリットをまとめると、
従業員のメリット
■目標が明確になり、モチベーション維持がしやすい
■成果が正当に評価される
■承認欲求が満たされる
組織のメリット
■社員のモチベーション向上が業績アップにつながる
■優秀な社員の離職を防ぐ
■歩合給や固定給アップに比べてコストを抑えられる
となり、個人・組織の両方が多くのメリットを得られる制度であることが分かりました。
ただし、次のようなデメリットもあります。
■従業員の間でモチベーションに差が出る
■人間関係が悪化するリスクがある
■インセンティブの内容やルールなど細かな配慮が必要
これらのデメリットはインセンティブ制度の設定を配慮することで払拭できます。
インセンティブ制度をうまく活用して、誰もがやりがいを持って働ける職場を目指しましょう!


