
ナレッジマネジメントは、組織内でスムーズに情報を共有・活用するための手法です。
導入や活用が上手くいけば、業務効率化や人的コスト削減といった効果が期待できます。ただし、導入すれば必ず効果が出るというわけではありません。
本記事では、ナレッジマネジメントを失敗させないよう、ナレッジマネジメントの理論や活用事例について紹介します。
1.ナレッジマネジメントとは
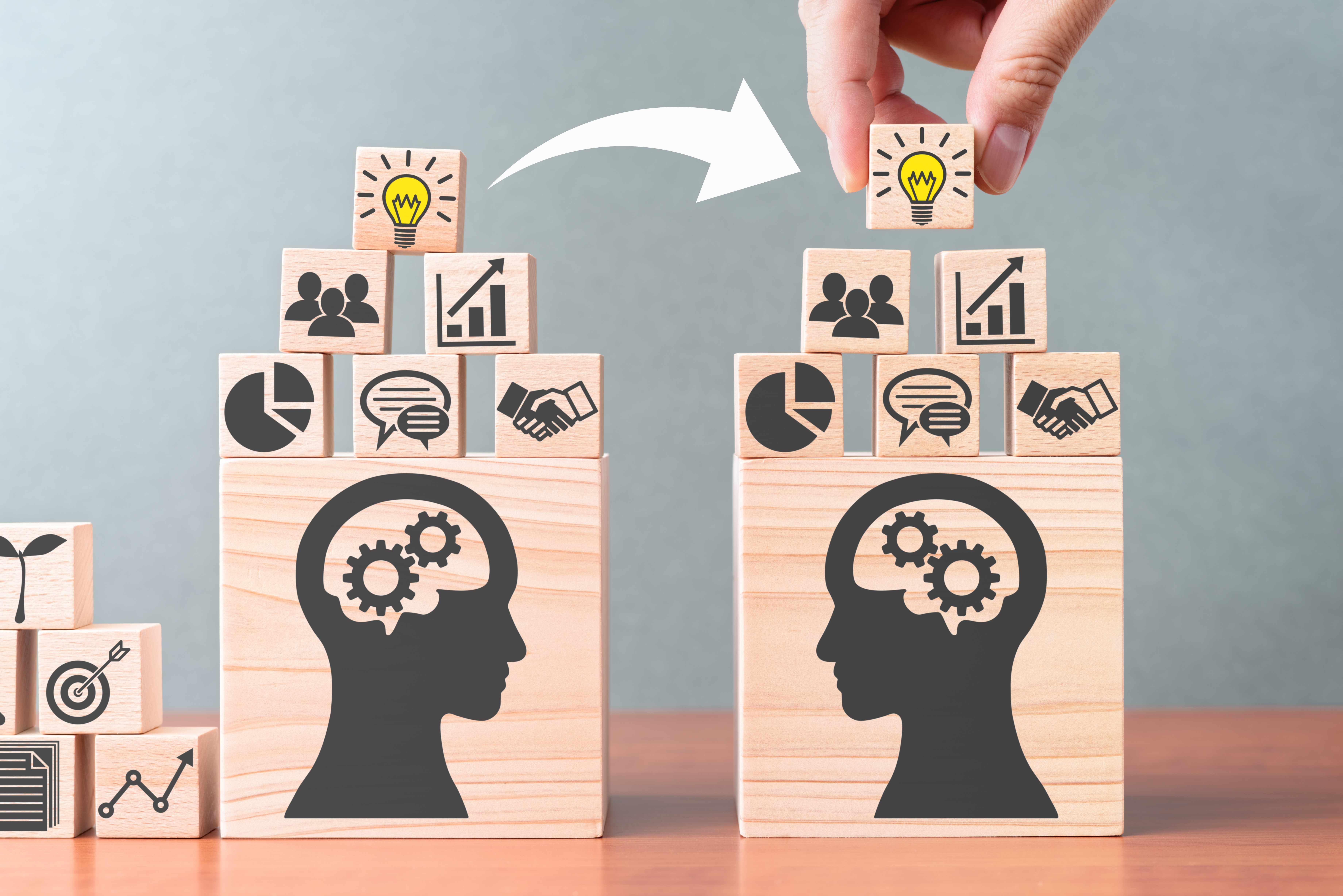
ナレッジマネジメントは、1990年代初頭に野中郁次郎によって発表された組織的知識創造理論とSECIモデルをもとにした、日本発の経営理論です。
現在では、世界の多国籍企業の約8割が実施しているといわれています。ナレッジマネジメントとは、企業全体の生産性を向上させるため、熟練工のスキルやベテランの経験知識など、個人のもつ暗黙知を企業内で共有し、新たな技術革新を促すという手法です。
暗黙知は、数字や言葉で表現しにくいものが多くマニュアル化されにくいため、個人の成果にはつながりますが、組織全体のスキルアップにつながりにくいという特徴があります。
そのため、暗黙知を形式知に変換して相互交換し合うことが重要となってくるのです。
そのために、
(1)情報の共有・見える化
(2)情報の知識化
(3)知識の活用・体系化
という3つのステップを踏みます。
形式知は、具体的な言葉や図表、数字で表現されるものなので、マニュアル化しやすく組織での共有も可能です。
ナレッジマネジメントの4つの手法
経営資本・戦略策定型
組織内の知識を多角的に分析し、経営に活用する手法です。
専用のシステムを導入して分析することが多く、競合他社や自社の事例を分析して役立てます。この手法を活用することで、業務プロセスの改善ポイントが見つかりやすくなります。
顧客知識共有型
業務の知識に加え、業務プロセスやその先を見通した知識を提供する手法です。
顧客優先を第一にした考え方で、顧客のクレームや意見に対応した方法などをデータベース化し、その事例に基づいてその後のトラブルへの対応や判断ができるという仕組みです。
部署による顧客への対応差を防ぐことができ、顧客満足度の向上につながります。
ベストプラクティス共有型
規範となるであろう社員の行動や思考を形式知にし、組織全体で共有することでスキルアップする手法です。
専門知識型
ネットワークを活用して組織内外の知識をデータベース化し、情報を効率よく提供するための手法です。
特に、情報システム部門やヘルプデスクなど、組織内外からの問い合わせが多い部署で活用すれば、問い合わせ業務の軽減や対応のスピードアップ、応対の質向上などに役立ちます。
社員の良い行動や思考を可視化する ピアボーナスⓇ「Unipos(ユニポス)」とは?
ナレッジマネジメントが注目されている背景
では、なぜこのナレッジマネジメントが必要とされるようになったのでしょうか。
高度経済成長時代に終身雇用モデルが確立し始めた頃、企業は長期的に人材を育成しようと新規採用者に対しさまざまな研修を行ったり、年功序列型の人事戦略を行ったりしました。
また、将来幹部候補となる総合型人材を育てようと、従業員にいろいろな経験を積ませます。数年おきの転勤や異動による、社内の幅広い知見の獲得などもそのひとつです。
従業員側も長期的な雇用を前提としていたため、ほとんどの場合は転職や失業を意識することなく働いていました。そのため、企業内で知識や技術を吸収することに集中できたのです。
その結果、長期で務める人材が多く、社内で自然にナレッジを共有しやすい環境となっていました。
平成に入ると、就職氷河期やバブル崩壊が起こり、終身雇用を前提とする雇用システムが変わり始め、働き方も大きく変化します。企業の規模に関わらず事業存続の危機が訪れ、人員の大量整理や事業再建などが行われるようになりました。
人員整理の対象となった人は再雇用を目指し、将来性に不安を抱えた人は転職を検討することが増えたのです。その結果、人材の入れ替わりが激しくなったことで、個人で抱えていたスキルや知識が共有されない、蓄積されないといった課題が見えてきました。
つまり、企業の財産として個人のスキルや知識も企業全体で管理・共有し、意思決定や生産拡大に活かしていく重要性がわかってきたのです。
さらに時代が進み、IT・情報化時代になると、行動や意思決定をスピーディーに行う必要が出てきました。
また、顧客ニーズの多様化に伴い、柔軟に適切に対応する力も求められるようになってきました。この時期、ナレッジマネジメントに対して誤解が多く生まれました。
例えば、ナレッジを集めるためにシステムさえ構築しておけばよい、ベテランが自らノウハウを共有したがらないなどです。
このような失敗を通し、個人でナレッジを登録したり活用したりすることを企業全体の目標にすることや、部門を問わず企業全体でナレッジの共有をする必要があることなど、ナレッジマネジメントに対する正しい理解が進み、広まっていったのです。
2.ナレッジマネジメントの目的

ナレッジマネジメントは、何のために知識を共有するのか、その目的をもつことが大切です。ここではナレッジマネジメントの目的の例を2つ紹介します。
組織内連携の強化
組織内にエンジニアと営業の組織があると仮定します。この場合、通常の業務だと連携をとることがあまりない部署同士を、ナレッジマネジメントによって情報を共有することで連携しやすくすることが目的として設定できるでしょう。
エンジニアの開発状況や人員体制を営業が把握しておけるため、どのような納期で開発が可能かなどを顧客に聞かれたときに即答できるようになります。企業の規模が大きいほど部署間でのリアルタイムな情報共有が難しくなる傾向です。
ナレッジマネジメントによって連携しやすくなれば、顧客の声を開発や営業に素早く活かし、新たな商品開発や改良のきっかけが生まれ、企業競争力の強化も期待できると考えられます。
業務改善や効率化
例えば日報を蓄積していけば、個人の業務改善にもなり、社員同士で共有すれば新たな課題や方法が見えてくるかもしれません。
資料作りがなかなか進まず困っていた社員が、先輩社員の作った資料をファイル共有機能で見て参考にすることで、資料の作成方法を学んだり作成時間を短縮したりすることにつながることもあるでしょう。
業務改善や効率化を目指すことで、短期間での高度な人材育成にもつながります。
3.ナレッジマネジメント導入時の注意点
ナレッジマネジメントを闇雲に導入し、目的もなく取り組んでしまうと、逆に損失が生じる可能性があります。
例えばナレッジマネジメントのツールを導入したものの、ナレッジマネージャーなどのリーダーは配置されておらず、現場に丸投げしてしまうケースがあります。この場合、何を蓄積し、どう活用すればよいのかがバラバラになってしまい、結局情報を残しておくだけになってしまうのです。
また、社員にナレッジマネジメント導入の目的が浸透していないと、ナレッジマネジメントのツールを使用してもらうことさえも難しくなってしまいます。
社員にとっては、これまでツールを利用せずとも日々の業務は回っていたため、まずツール導入の目的や意義を理解してもらう必要があるのです。
このような事態を防ぐためにも、ナレッジマネジメントは組織内で目的をはっきり共有したうえで導入するようにしましょう。
4.ナレッジマネジメントの基礎理論「SECIモデル」

SECIモデルとは
SECIモデルは、ナレッジマネジメントの中心となるフレームワークです。暗黙知を形式知に変換し、形式知を暗黙知に変換する場を作るために4つのステップで知識創造を行います。
SECIモデルの4つのステップ
共同化プロセス
最初のステップは「共同化プロセス」です。経験を通して、暗黙知を個人から個人に伝えるプロセスです。
例えば、トップ営業マンと営業回りをしたり、優秀なプログラマーとプログラミングをペアで行ったり、上司の指導を受けながら顧客対応をしたりといったことが挙げられます。
同じ組織のメンバーと同じことを同じ場で経験することで、言葉にできない知識や技術、経験を体で覚えながら体得します。
表出化プロセス
次は「表出化プロセス」です。共同化で得た暗黙知を、図や言葉などの形式知に変換する段階です。マニュアル化したり、動画や例を示したりといったことが考えられます。
暗黙知は主観的でしたが、表出化によって形式知になったものは、客観的で論理的な知識に変換されています。
例えば、グループ演習で知識のアウトプットをすることや、得られた知識を文章化して会議で報告すること、詳細に分析した手順や手法をフローチャート化するといったことが挙げられます。
連結化プロセス
その次に行うのは「連結化プロセス」です。変形した形式知を組み合わせ、新たな知識体系を作り出します。バラバラの知識が合体することで、より体系的な内容になり、表出化したときよりもより多くの価値創出に役立ちます。この段階ではまだ、形式知のままです。
例えば、社内データを組み合わせて整理し直すことや、成功した企画アイデアをもとに新しい企画の作成、複数のコンセプトをつないで大きなモデルを作り出すといったことが考えられます。
内面化プロセス
最後は「内面化プロセス」です。表出化で得た形式知を繰り返し練習することで、体にしみ込ませる段階です。形式知を繰り返し使うことで内面化し、暗黙知に変化していきます。内面化によって暗黙知化すると、熟成と深化により、より質が高まるのです。
例えば、新たに体系化した方法を業務に採用し、スムーズに業務をこなせるようにしたり、マニュアル化された作業を繰り返すことでマニュアルがなくても作業できるようにしたりするといったことが該当します。
このような4つのプロセスを絶えず繰り返すことで、知識が進化して絶え間ない創造が生み出されるのです。さらに、SECIモデルの4ステップを実践する場も定義されています。
共同化ステップに対応しているのが「創発場」。思いや経験などの暗黙知を共有する場です。
表出化には「対話場」が対応します。対話を通して、他者が暗黙知を理解できるように、知識や技術の聞き取りや説明を行う場です。プレゼンテーションやミーティングなどが当てはまります。
「システム場」は、連結化の場です。複数の形式知を持ち寄る場なので、対面はもちろん、組織内のチャットツールやSNSも有効です。
最後のステップに対応するのが「実践場」です。獲得した形式知を職場で実践します。通常の業務を行う場を表します。
5.ナレッジマネジメントの活用事例

ここでは、ナレッジマネジメントの活用に成功し、業績を伸ばした事例を紹介します。
富士ゼロックス
富士ゼロックスでは、プロトタイプや製品完成の段階になって、やっとユーザーに近い視点を持つ担当者の意見を反映できるという仕組みであったため、開発の最終段階になって設計の変更が生じ、開発期間が延長してしまうという課題がありました。
この課題を改善するため、技術者と各工程の設計者がお互いに交流し、互いの現場で培ったノウハウつまり暗黙知を獲得するために互いの現場を訪問し合ったのです。
このような取り組みを続けたことで、初期段階から全員が意見を出し、それぞれの領域で責任をもつ「全員設計」というコンセプトが生まれました。
さらに、獲得した暗黙知を整理するためのオンライン上の設計情報共有システムを開発し、設計者や技術者が自分たちのノウハウを言語化して記載し始めたのです。
しかし、記載された情報は全員が共有する必要があるとは限りません。そこで、各工程の上司が必要なものだけをピックアップし、登録するように改善しました。その選別された情報を実際に活用するため、さらに有用なものを選別して編集し、実際に使用できるようにしたのです。
また、「何でも相談センター」もナレッジマネジメントの成功事例として知られています。
営業部門に設置されており、営業からの問い合わせには何でも答えるための部署です。営業経験者が相談員として所属しており、1カ月に約2000件もの相談に答えています。
たらい回しにされることもないため、営業職は顧客からの相談に専門外のことでも答えることができるようになりました。
さらに、相談センターにはさまざまな知識が蓄積されることで、質の高いナレッジの源になっており、営業職のみならず相談員もスキルアップした状態で再び営業職に戻ったときに活用できるのです。
マッキンゼー
マッキンゼーには、Knowという独自のシステムがあり、日々蓄積されるナレッジを管理しています。マッキンゼーは、2万人の情報資産を蓄えているコンサルティングファームで、業務をプロジェクト単位で回しています。そのため、プロジェクトを通して得た膨大な量のナレッジを組織全体の資産とするための仕組みが必要不可欠なのです。
Knowを活用すれば、提案ごとに過去の事例を参照することができ、コンサルトは効率的に無駄なく業務に取り組むことができます。ナレッジの内容は、業界をけん引するプレイヤー情報や業界の市場規模、バリューチェーンなどになっており、フォーマットが統一されていることでより使いやすくなっています。
さらに、ナレッジ共有には報酬制が導入されており、進んで使いたくなる仕組みといえるでしょう。
これらの事例からわかるのは、ナレッジを共有する社内風土を整えることが成功に向けて大切だということです。マッキンゼーのように、具体的な報酬制度を導入するほか、共有頻度を人事評価に組み込むのも有効でしょう。
また、ナレッジの共有方法やフォーマットなどある程度決めておくことも成功のポイントといえます。富士ゼロックスのように、高性能なナレッジマネジメントツールを使うのも重要です。
シンプルなUIで設計されていることや、必要な情報をすぐに引き出せる強力な検索機能があることなど、利用者にとって気軽に使えるツールはナレッジ共有を身近なものにしてくれます。
6.ナレッジマネジメントのおすすめツール

導入の目的によって適切なツールは異なります。ナレッジの蓄積や共有を目的とするのであれば、「Knowledge Explorer」が適しています。
提案書や仕様書などの作成中に、必要な資料をAIがピックアップして通知で知らせてくれたり、他のユーザーが検索したときの行動や判断を可視化する機能や検索結果のドキュメントにコメントや評価をつけられる機能あったりと、ナレッジの活用に役立つ機能が充実しているのが特徴です。
「flouu」は、全文検索機能が優れており、ほしい情報をすぐに見つけることができます。リアルタイムでの情報共有が可能で、複数人が1つのドキュメントにアクセスして同時編集できます。オンライン会議にも適しているでしょう。
社内WikiやFOQの作成を目的とする場合、「IBiSE」が便利です。Q&Aを入力するだけで社内FAQが簡単に作成できるため、プログラミングの知識は必要ありません。部署をまたぐ情報共有や業務連絡もスムーズに行えるようになります。
また、3000社以上が導入している「Qast」は、ナレッジ経営実践用のツールです。テンプレートを使用した回答の投稿や、匿名での質問ができるため、気軽にナレッジを蓄積していくことができます。ナレッジへの貢献をスコアで可視化してくれるため、人事評価への利用も可能です。
ヘルプデスク業務の効率化を目的とするのであれば、「Freshdesk Support Desk」がぴったりです。内部チャットツールを使用することで、社内関係者間やオペレーター同士で相談することができ、ヘルプデスクの業務改善につながります。ナレッジ共有と自動化、分析という3つの要素により、よりスピーディーな顧客への対応が可能です。
ツールを活用しナレッジマネジメントを進めよう
これまでは対面で直接伝える、個別のファイルに残しておくといった方法で業務にかかわる情報を伝達してきました。その結果、うまく伝わりきらなかった暗黙知がたくさんあったのではないでしょうか。
変化の激しい時代だからこそ、暗黙知も形式知も共有し、人材育成や企業の成長促進に取り組む必要があります。ナレッジマネジメントを成功させるためにも、目的に応じたツールを選び、活用していきましょう。


