
1.傾聴とは?
傾聴とは、相手に寄り添い、相手の話の内容だけでなく、話し方や表情、姿勢、しぐさといった言葉以外の部分にも注意を払ったりすることにより、相手を深く理解するための聴く技術です。
もともとはカウンセリングやコーチングで使用されるコミュニケーション技法の一つでしたが、最近ではその効果からビジネス上でも必要なスキルとして、傾聴力と言われることもあります。
傾聴は、米国の心理学者でカウンセリングの大家であるカール・ロジャーズ(Carl Rogers)によって、「積極的傾聴(Active Listening)」として提唱されました。
ロジャーズは、自らがカウンセリングを行った多くの事例(クライエント)を分析し、カウンセリングが有効であった事例に共通していた聴く側に必要な要素を3つにまとめました。
その要素を含む聴き方が、傾聴になります。
3要素とは、「自己一致」、「共感的理解」、「無条件の肯定的関心」です。
■ロジャーズの3原則
1.自己一致 (congruence)
聴き手が、相手に対しても自分に対しても真摯な態度で、話が分かりにくい時は分かりにくいことを伝え、真意を確認する。分からないことをそのままにしておくことなく、自己と一致することを確認します。
2.共感的理解 (empathy, empathic understanding)
相手の話を、相手の立場に立って、相手の気持ちに共感しながら理解しようとする。
3.無条件の肯定的関心 (unconditional positive regard)
相手の話を善悪や好き嫌いの評価を入れずに聴くことです。
相手の話を否定せず、なぜそのように考えるようになったのか、その背景に肯定的な関心を持って聴きます。そのことによって、話し手は安心して話ができるようになります。
これら3つの要素は相互に影響しています。はじめに、聴き手が相手に対しても自分に対しても真摯な態度(自己一致)であれば、話の分からない部分を確認しながら、真意まで確認することができます。
それによって、相手の立場に立ち、相手の気持ちに共感しながら理解することもできるようになります(共感的理解)。
共感ができた上で、なぜそのように考えたか関心を持ち、評価を入れることなく聴くことができれば、話し手は安心して話を続けることができ、深い理解につながります。
参考元リンク1
傾聴とは|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト (mhlw.go.jp)
https://kokoro.mhlw.go.jp/listen/listen001/
参考元リンク2
傾聴とは?採用試験時に必要な傾聴の技法9つやもたらされる効果を紹介! | ITエンジニアの派遣なら夢テクノロジー (yume-tec.co.jp)
https://www.yume-tec.co.jp/column/training/4320
2.傾聴の目的、メリット

傾聴の目的は、『相手を理解すること』です。
傾聴を実践すること(相手を理解すること)のメリットは、ビジネスシーンにおいても注目されています。相手を深く理解することによって、ビジネス上では以下のメリットがあります。
① 信頼関係が構築されやすい
話を聴いてもらうことにより、自分の思っていることが理解、共感されたとき、話し手は聴いてもらえたことと、共感してもらったことで安心感が生まれます。
その時、話し手の問題がすぐには解決されなくとも、話をしたことやそこでのコミュニケーションが良いものであった体験は、職場の同僚や上司、部下との間の信頼関係を築くことに役立ちます。
② 信頼関係があるからこそ、業務が円滑に進む
信頼関係が構築されていない状況においては、普段の業務指示や何気ないやり取りでも、不安や嫌な気持ちになったり、モチベーションが上がらないことが起こりえます。
ただ、信頼関係が構築されている場合は、お互いの真意は確認できている前提ですから、仕事上の良くない報告や、困っているという相談も遠慮することなく行うことができます。
報連相がスムーズであれば、チームワークや仕事そのものの生産性も高くでき、業務が円滑に進むことが期待できるでしょう。
③ 話し手が自発的に整理、解決できる
人はさまざまな意見や悩みを持っていますが、具体的に言葉として表現できるレベルの思いもあれば、まだ人に伝わる程度にはまとまっていない考えもあります。
それを自力で言葉にし、把握することは簡単ではありません。傾聴を行うことで、話し手が考えてはいたものの、きちんと整理できていなかった事柄が整理できる場合があります。
話をしているうちに自己解決して、『あ、なんだ!こんなことか。』と思った経験は誰しも一度はあるのではないでしょうか。
聴き手が何か特別なアドバイスを行わなくても、話し手自身が自分の頭、自分の言葉で整理していくので、その後の行動が違います。
人は誰かから指示されるよりも、自分の考えで判断した事のほうが、エネルギーが発揮されるものだからです。この気づきを傾聴によって生むことができれば、あなたの同僚や部下の悩みも話し手自ら解決し、前向きに仕事に取り組むことができるかもしれません。
④ 相手の状況や悩みがわかるからこそ尊重できる
傾聴を行った場合に、話し手の悩みの根源にたどり着く場合があります。
最近だと、ニュースに対する受け取り方、働き方の考え方などは人それぞれです。個々人で異なる思想をよく理解せず、『〇〇であるべき!』などの発言をした場面で、パワハラにあたる可能性があるなど思いもよらぬ状況に陥る可能性があります。
もし、普段から周りのメンバーとの傾聴を行っている場合には、その人の考え方や置かれている状況(自宅で介護をしている、子供が入院中など)を知るきっかけにもなり、そういう背景が知れることで、チーム内での助け合いや発言の1つを取ってみてもコミュニケーションの質が上がり、互いに尊重できる関係が築ける可能性が高まります。
参考元リンク1
傾聴とは?傾聴の効果や種類、具体的な実施方法を紹介 | あしたの人事オンライン (ashita-team.com)
https://www.ashita-team.com/jinji-online/business/9335
参考元リンク2
傾聴とは? 意味、ロジャーズの3原則、実践方法8選、ビジネスで効果を出すには? - カオナビ人事用語集 (kaonavi.jp)
https://www.kaonavi.jp/dictionary/keicho/
3.傾聴の種類、具体的な実践例
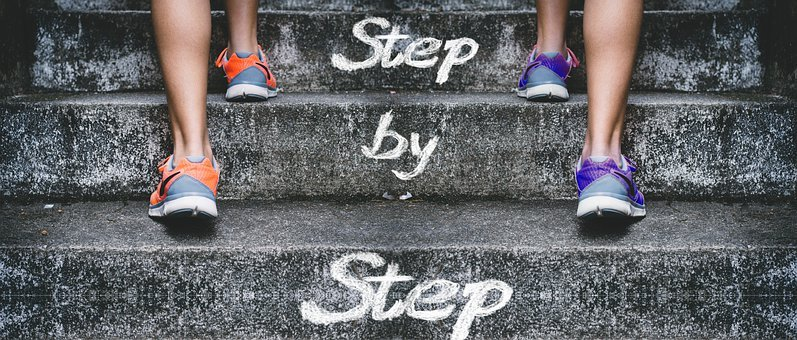
傾聴には3段階のレベルがあります。レベルによる違いと聴き手の態度、しぐさを説明していきます。Step1からStep3に向け、段階的にレベルが高くなります。
Step1:聴いていることを示す
傾聴の初期段階であるStep1は、聴いていることを示すレベルです。
聴き手の興味関心や意見を優先するのではなく、まずは話し手が考えている心の内を伝えやすいように、相手のために聴くことを意識します。
うなずく、相槌を打つ、視線をしっかり合わせる、姿勢を正すなど、興味を持って相手の話を聴いている姿勢を示します。そうすることで相手がリラックスして話しができる土台が作られていきます。
Step2:理解していることを示す
次に、ただ聴いているだけではなく、相手の言うことを理解していることを示します。
例えば、相手が言ったことを復唱する、要約する、言い換える、などして、内容を確認していきます。相手が感情を示しているなら、その感情に寄り添ったり共感を示したりすることも、「理解していることを示す」につながります。
話し手の言葉をオウム返しのように繰り返したり、別の言葉で言い換えたり、要約したりして理解を伝えます。
Step3:質問を通し、相手の思考を刺激する
最終はStep3です。ここが積極的傾聴の中でもっとも難易度が高いプロセスです。
「傾聴」とは、聴いているだけでは、話し手の気づき(次の行動)につながりにくい場合があります。気持ちが楽になる、スッキリした、などの効果はあるかもしれませんが、特にビジネスの場においては、相手に気づきがあり、次なる行動の有無が重要になります。
そのために、次の行動に繋げるための質問を投げかけながら、相手の思考プロセスを刺激していくことが大切になります。
聴き手は必要に応じて話し手の発言に言葉を添えたり質問を挟んだりすることで、話し手の思考を促すのです。
積極的傾聴は、聴き手側の真摯な姿勢に加えて、経験やテクニックも必要とされます。
参考元リンク1
積極的傾聴とは聴くだけではない!①積極的傾聴を実現する方法3ステップ | 信元 夏代のスピーチ術 (natsuyo-speech.media)
https://natsuyo-speech.media/speech-basic/communication-skill/activelistening1/
4.いろいろなきく

傾聴は、単に“きく”のではなく、相手のことをより理解するために、様々な“きく”があります。
(1)耳できく:相手の言葉に最後まで耳を傾け、理解する
傾聴では相手のいうことを、偏見を含まずに聴き、自分の価値判断で評価せず、否定的にならないことが求められます。
そのため、相手が沈黙したり、考えていたりする場合などは、できる限り待つ姿勢が望ましいとされています。
「耳できく」とは、相手が話すのを邪魔せず、安心感を与えて話を受け止める姿勢を示しながら、理解することを意味しています。
(2)目できく:相手の言葉以外の行動(姿勢、表情、しぐさ、声の調子など)に注意を払い、真意を汲み取る
傾聴で重要なのは、相手の表情や声の調子なども同時に見ることです。相手が本音で語っているかどうかを見ます。
相手のことを本当に理解しようと思えば、このような非言語的コミュニケーションにも配慮しなければなりません。
最近はオンラインでのコミュニケーションが多くなっていますが、画面はONにして、相手がどういう状態なのかを確認しながら実施するなど、傾聴にも工夫が必要です。
声は元気でもずっとうつむき加減で笑顔がない場合には、何か問題があるかもしれません。
(3)心できく:相手の言葉の背後にある感情も受け止め、共感を示す
言葉の裏側の気持ちを推測し、受け止め、共感を示すことが必要です。
部下は上司に対して、会社の愚痴を言いにくいものです。
そのため、「楽しく仕事しています」など、当たり障りのない言葉しかいわない場合もあります。傾聴では、本心はどうなのかを推測し、それを受容・共感することが求められます。
参考元リンク1
傾聴とは――意味と使い方、ビジネスの場で活用するメリットや効果は - 『日本の人事部』 (jinjibu.jp)
https://jinjibu.jp/keyword/detl/475/
5.ビジネスシーンでの傾聴の例

傾聴は、ビジネスシーンでも活用できます。例えば、お客様への傾聴です。
1.お客様への傾聴
傾聴の目的である『相手(お客様)を深く理解すること』は、お客様が本当に求めていることを理解することと同じです。
お客様の求めるもの(価値)が理解できれば、その価値をどのようにすればお客様へ提供できるかを考え、ビジネスを進めていくことができます。
あるセールスレディの成功例をご紹介します。
彼女は、徹底的に傾聴を重視した結果、男性が多いBtoCの営業会社で全国2位の営業マンと2倍の成績差をつけ、TOPセールスを上げました。
「相手を良く知り、相手が望む以上を提供する」ことが、セールスの王道だといいます。
彼女は、お客様へのプレゼンに入る前の1時間のうち、9割を傾聴しています。
重要視したポイントは、下記です。
① お客様の話を徹底して聴くと決める
② お客様のために、価値ある時間にすると意識する
③ お客様の話を徹底して聴く
④ 徹底的に共感しながら聴く
ここで、①と③は似ていますが、実はここが他の人との大きな差になっていると考えます。
話を前に“聴くと決める”、その上で実際(話をしている最中に)も徹底して聴く、ということを忘れずに、常にお客様のために、お客様の価値を意識しながら、共感をもって聴くということです。
お客様側も普段自分の話を熱心に聴き、共感を示す彼女のプレゼンだからこそ、内容の興味、好感、信頼は強くなり、真剣に耳を傾けるようになります。
それにより成約率の確率を上げ、他の営業マンの2倍以上のセールスを築くことができたのです。
傾聴は、社内の上司や同僚、部下といった周囲の人間関係でも効果を発揮します。
2.社内メンバーへの傾聴
冒頭ご紹介したビジネス上のメリットを享受すべく、最近は上司と部下の間で行われる1on1ミーティングを取り入れる企業が増えてきています。
1on1ミーティングを通じて、上司と部下のコミュニケーションができ、相談しやすい関係が生まれます。共感を示すことで、自分のことを大事にされていて、これからもこの会社に貢献したい!と思えるような従業員エンゲージメントの向上にもつながるでしょう。
1on1は、ティーチングでなく、コーチングと言われます。
コーチングは、単に知識や技術を教えるということでなく、部下自身が答えを導き出すサポートをするということです。
時間はかかるかもしれませんが、部下自身が自分の考えにより答えにたどり着くので、より主体的、かつ強く意識され、その後の行動変化も大きくなることが期待できます。
参考元リンク1
「傾聴」の効果的な活用事例:仕事や人間関係での事例9選と使い方 (life-and-mind.com)
https://life-and-mind.com/keityou-jirei-4972#i-4
参考元リンク2
1on1のコーチング・傾聴・承認など徹底解説 | Engagement Note | Talknote株式会社
https://news.talknote.com/inner-communication/1on1-coaching/
6.傾聴のやり方、ポイント

これまで、傾聴の意味・定義・目的・効果についてご紹介しました。この章では、傾聴の心構えと具体的な行動、ポイントについて、整理します。
■Step1:聴いていることを示す
<聴き手の心構え>
・相手の話に興味があり、しっかり聴く意思を持つ
→相手を理解することが目的であることを再度確認しましょう。“徹底して聴く”です。
<聴き手の姿勢、行動、言動>
・相手のほうに体を向け、顔や目を見るようにする。
→やりすぎない程度に自然な感じを意識しましょう。視線はあちこちに向けていると落ち着きがない感じが出てしまいます。アイコンタクトが苦手な場合は、襟元を見るのがオススメです。
・姿勢はやや前のめり気味
→普段、友人や家族と興味がある話題について話しているような姿勢です。思わず前のめりになる感じです。
・リラックスした雰囲気、柔らかい表情
→聴き手がリラックスしていると、話し手もリラックスして話ができます。傾聴する姿勢が強く出すぎると変な緊張の空気が出てしまうので、自然体で臨みましょう。
・話を否定しない、遮らない
→基本的なことですが、話し手の話を否定したり遮ったりしてはいけません。
・適度なうなずき、あいづち
→言わずもがな、聴いていることを示すために適度にうなずき、あいづちを打ちましょう。話し手は、反応があると聴いてくれていると安心します。例:なるほど、へぇー、ほう、そうなんですね、うんうんなど
・繰り返し
相手の発言を繰り返すことで、相手の話を聴いているという印象を与え、さらなる会話を引き出します。「〇〇で不安」と聴けば、『そうなんですね、〇〇が不安なんですね』と繰り返すなど。
・腕組みはしない
→警戒や拒絶を表すため、腕組みはしないようにしましょう。態度がそのまま相手との壁を作ってしまします。
・時計やスマホを気にしない
→癖で時計を何度も見ることや、スマホを触りながら聴く、というのもNGです。
・ミラーリング
→「ミラーリング」は、鏡のように相手と同じ動きをすることです。
姿勢や表情、しぐさ、声のトーンなどを相手と同調することで、相手に親密感や安心感を与えることができます。わざとらしくならないように、タイミングをはかったり、真似するポーズを左右反対にしたりするのがうまくミラーリングするコツです。
・待ってあげる、間(ま)をとる
→話を進めていくうちに、話し手が話に詰まったり、考えを巡らせたり、もしくは感情的になるケースがあるかもしれません。
そんなときも、聴き手は落ちつき、考えがまとまるのを待ってあげて、意識して間を取ることも必要です。急いで話を進めても相手の理解にはつながりません。
■Step2:理解していることを示す
<聴き手の心構え>
・聴いた内容を理解していることを話し手に示す
→話した内容が伝わっていると安心感、信頼が生まれます。聴き手から、理解されたことのフィードバックがあると、話し手は自分の話を他人の口から聴くことができます。それにより、客観視でき、気づきが生まれることがあります。
<聴き手の姿勢、行動、言動>
・相手の立場に立って、相手の気持ちになる
→聴いた内容が聴き手の考えと大きく異なることもあるでしょう。ただ、その場合も話し手の立場になって、どういう考え、気持ちかを良し悪しの評価でなく、関心をもって聴き、共感理解をしましょう。
・話をまとめ、言い換える
→聴き手は、話の内容を適宜まとめ、言い換えを行うことで、理解を示すことができます。
この手法は「パラフレーズ」と呼ばれます。ある程度話を聴いたら、その内容を自分(聴き手)の言葉に言い換えてみましょう。内容の認識をすり合わせたりして、話の内容をきちんと理解していることを示します。
もしも、そのまとめと言い換えに自信がない場合でも、それも含めて確認するとよいでしょう。
例えば、『これまでの話から、こういう理解をしましたが、あっていますか?』と素直に聴いて、言葉のニュアンスも含めて理解できれば、より深い共通理解につながります。
・バックトラッキング
→「バックトラッキング」は、「オウム返し」のことです。相手が話したことを繰り返すことで、しっかり理解してくれているという印象を与え、共感を示すことができます。
相手の感情に寄り添いつつ、一部を抜粋するように返すといいでしょう。返すという感覚というより、いったん受け止める感覚でしょうか。
バックトラッキングは、タイミングを誤ることや使いすぎると逆効果にもなります。使い方には注意しましょう。
■Step3:質問を通し、相手の思考を刺激する
<聴き手の心構え>
・質問を通して、話し手の思っていること、または話し手が本来希望している方向へ導く
→傾聴の中でもレベルが高い内容です。質問を通して、話し手がどう思っているのか(実は本人すら気づいていないケースもあります)を少しずつ明らかにしていくことです。これは聴き手からのアドバイスでなく、話し手のペースに合わせて、いくつかの質問を通して行います。
<聴き手の姿勢、行動、言動>
・アドバイスでなく質問する
→アドバイスは専門の見地から行うものです。傾聴は、アドバイスはありません。目的が話し手を理解することですから、話し手自身が自分をより理解するための質問を投げかけます。
例えば、その時どう思ったのですか?、これからはどうしたいと思っていますか?など。
こういった質問を行うことで、話し手の真意を確認することができるかもしれません。
・解決を急がない
→傾聴を行う際に、問題解決が目的でない場合もあります。単に話を聴いてもらいたかっただけ、あるいは、状況を伝えるだけのケースもあり得ます。
話し手が問題を抱えているケース、そうでないケース、何れにしても、相手の気持ちを尊重して、決して急がず、気持ちを丁寧に確認しながら聴くこと大事です。
・相手が次でできることを意識させる
傾聴を通して、話し手の問題や不安がすぐには拭えるものではありません。ただ、話の中で、話し手が次にできそうなことがあれば、次の質問をしてみることで、少しは解決の糸口が見えるかもしれません。
例えば、「この後何か始められそうですか?」、「今の状況を変えるきっかけはつかめましたか?」
これも聴き手のアドバイスでなく、話し手本人が意識的に思えれば、行動と解決が見えてくるケースもあります。
参考元リンク1
傾聴とは? 意味、ロジャーズの3原則、実践方法8選、ビジネスで効果を出すには? - カオナビ人事用語集 (kaonavi.jp)
https://www.kaonavi.jp/dictionary/keicho/
参考元リンク2
傾聴とは?採用試験時に必要な傾聴の技法9つやもたらされる効果を紹介! | ITエンジニアの派遣なら夢テクノロジー (yume-tec.co.jp)
https://www.yume-tec.co.jp/column/training/4320
7.傾聴を学ぶ方法
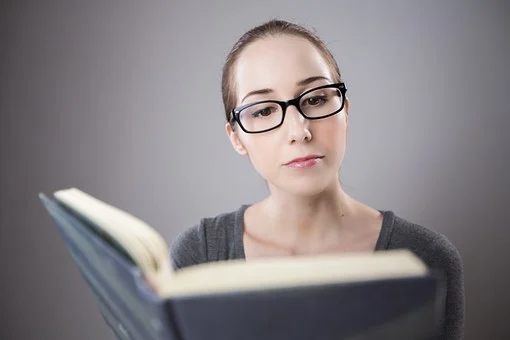
傾聴のスキルを身にける方法をいくつかご紹介します。
■方法1:社外セミナー、社内ワークショップへの参加
・社外セミナーへの参加(有料)
傾聴を本格的に学ぶ場合(人事関係の部署で、社内に傾聴を広めたいなど)は、
一般社団法人 日本傾聴能力開発協会 が提供する各種講座がオススメです。
オススメの理由は、傾聴の専門の協会であり、認定資格を取得できるからです。
目的に応じて、下記の講座を選択できますので、傾聴のプロ、組織内の傾聴のプロを目指す方には本格的に取り組めるメニューになっています。
・傾聴サポーター養成講座
3日コース:15.4万円(割引後)※認定あり
・傾聴1日講座
1日コース:5.1万円(割引後)※認定はなし、修了証はあり
他、傾聴心理士養成講座、講師養成講座など上級講座もあります。
参考元リンク1
JKDA一般社団法人 日本傾聴能力開発協会 – 傾聴の資格が取得できる傾聴の学校
・社内でのワークショップ形式での実施(無料)
外部でなく、社内でお金をかけずに実施する方法もあると思います。
各組織の管理職、リーダクラスのメンバを選び、ワークショップ形式で実施するやり方です。
傾聴は、座学で学ぶものでなく、実践、経験によって体得していくものと位置づけ、気の知れたメンバーで小さく始めるのもよいと思います。次第に、多くのメンバを巻き込めれば、それこそ社内の風通しを良くするきっかけにもなるかもしれません。
■方法2:書籍から学ぶ
まずは個人的に傾聴を学ぶ場合は、下記の書籍がオススメです。
書籍1:プロカウンセラーの共感の技術(杉原保史)
共感することの考え方、具体的な技術が、初心者にもわかりやすい言葉で書かれており、オススメです。傾聴の技術を学ぶためというのはもちろんですが、やさしい言葉使いと悩みへのアプローチから、読んでいる自分の悩みも少し解消されたような、読んでスッキリする良著です。
参考元リンク1
Amazon.co.jp: プロカウンセラーの共感の技術 eBook : 杉原 保史: 本
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00SH23QN6/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
書籍2:プロカウンセラーの聞く技術(東山紘久)
人とのコミュニケーションにおける基本的、かつ重要な心得が読みやすく書かれています。すぐに実践できる技術も記載されており、今後人との会話が楽しみになるかもしれません。
参考元リンク2
Amazon.co.jp: プロカウンセラーの聞く技術 eBook : 東山紘久: 本
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00VFM9C06/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
8.まとめ
傾聴は、お客様や社内メンバなど、周りの人々の気持ちに寄り添い、相手を深く理解するための聴くスキルでした。
今回ご紹介した傾聴のやり方やポイントを1つでも実践頂き、これまでよりも良い関係を築くことができれば幸いです。
良い関係から、周りのメンバやお客様がやりたいことの真意が実現し、人もビジネスも成長できることを祈っております。
最後までご覧頂き、ありがとうございました。



