
組織マネジメントとは、一言でいえば限られた経営資源を効率的に利用して、最大限の成果をあげるための経営手法のことです。
例えば「自分の会社がうまく行っていなくて悩んでいる」、あるいは「もっと会社を良くしたい」と感じているとき、有益なヒントを与えてくれるのが「組織マネジメント」です。
しかしながら「組織マネジメント」という言葉は漠然としています。
「組織マネジメントって、具体的には、どうやってやればいいの?」
と困っている方も多いでしょう。実際、組織マネジメントに取り組んでいるといいながらも取り組みが曖昧で、成果に結び付いていない企業は数多くあります。
そこでこの記事では、まず知りたい「組織マネジメント」の基本概念から組織マネジメントを行う上で習得すべきスキルまで、組織マネジメントのアウトラインをわかりやすくまとめました。
一読いただければ、既存の記事を読んでもわかりづらかった次の疑問が明確になるはずです。
・具体的に何をマネジメントするの?
・組織マネジメントすると何がいいの?
・必要なスキルは?
・行う前に知っておくべき注意点って?
“組織マネジメントがわかる”ようになれば、今日から現場で活かすことが可能です。さっそく続きをご覧ください。
1.組織マネジメントとは

組織マネジメントとは、組織を効率的に動かし成果を最大化するためのマネジメント手法のことです。
組織は、人材・システム・戦略など、さまざまな要素で構成されています。それらの管理がなされず無法地帯となっていたら、企業の目指す方向へ進んでいくことは難しいですよね。
そこで、組織の経営資源を適切に管理して、目的達成までのコストを最小化するのが組織マネジメントです。企業の経営陣はもちろんですが、現場を管理するマネジャー陣(管理職)にも求められる視点といえます。
具体的に組織マネジメントで管理するべき経営資源は、マッキンゼー・アンド・カンパニーが提唱した「組織の7S」というフレームワークを利用すると、考えやすくなります。
<組織の7S>
①戦略(Strategy)
②組織構造(Structure)
③システム(System)
④スキル(Skill)
⑤人材(Staff)
⑥スタイル(Style)
⑦価値観(Shared Value)
次項で詳しくご紹介しましょう。
毎日1分のマネジメント習慣で組織風土を改革するUniposとは?詳細資料ダウンロード
1-1.7つの資源(7S)のフレームワーク
7Sとは、7つのSから始まる資源を総称した言葉です。4つのソフト要素と3つのハード要素に分かれます。
<7つの資源(7S)>
|
|
項目 |
説明 |
|
ソフト
|
価値観(Shared Value) |
組織に根付いた価値観 |
|
スタイル(Style) |
組織文化、社風 |
|
|
人材(Staff) |
従業員の特性 |
|
|
ハード |
スキル(Skill) |
組織が持つ能力 |
|
戦略(Strategy) |
競争に勝つための方向性 |
|
|
組織構造(Structure) |
組織の分け方など構造上の特徴 |
|
|
システム(System) |
人事・会計などの仕組み |
7つの経営資源は、それぞれが相互に影響し合う関係にあります。組織マネジメントがうまくいっている会社では、それぞれの要素が補完し合い、強め合いながら目的達成へと向かっていきます。
「組織マネジメントとは、この7つの経営資源を適切に管理すること」とも表現できます。
2.組織マネジメントの目的は強い組織を作ること

組織マネジメントの目的を一言でいえば「強い組織を作ること」です。
強い組織の概念は企業によって異なりますが、ひとつには企業の目指す目標を達成し、変化に対応する柔軟性を持ち、困難に直面することがあっても打ち勝つ組織と定義できるでしょう。
組織マネジメント自体は、新しい概念ではありません。「人材を管理する」「社内システムを管理する」などと言い換えれば、多くの企業で従来から実施されてきたものです。
しかし、現在ではその難易度が上がっています。経済のグローバル化や労働人口の減少、従業員のライフスタイルの多様化などを通して、企業内で行われるあらゆるマネジメントが高度化しているためです。
具体的には、今までにない新たな課題に直面したり、人材管理が複雑化したり、それによって管理職の負担が大きくなったりしています。さらに、市場変化の加速化に伴い、組織変革のスピードも求められるようになりました。
こうした状況にある今、改めて組織マネジメントを見直す目的は複雑化・多様化するビジネス課題を組織の力で解決し、競争が激化する現代を企業が生き抜くためといえるでしょう。
3.組織マネジメントによって得られる成果

組織マネジメントで得られる成果は、組織を高度にコントロールできるということです。
前述の通り「組織マネジメント」という概念が指す領域は非常に広いものです。広義では経営そのものが組織マネジメントであるともいえます。
しかし、漠然と無意識的に組織マネジメントを行うのではなく、意図を持って組織マネジメントを実行していくことは、組織をより能率的かつ高レベルにコントロールすることにつながります。
組織が高度にコントロールできている状態では、具体的に次のようなメリットを享受することができます。
①目標の達成に向けて戦力集中できる
②市況の変化や未経験のリスクに素早く対応できる
③マネジャー(管理職)業務の効率化できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1.目標の達成に向けて戦力集中できる
事業目標を達成する上では「戦力の集中」が不可欠です。
マイケル・ポーターの『戦略の本質』では「トレードオフ」という概念が語られています。トレードオフとは「何を取って何を捨てるか」ということ。事業目標の達成においても限られた経営資源(=組織の7S)をどう配分し、どう活用するかが重要です。
組織マネジメントが行われていない企業では、そもそも自社がどういった経営資源を持っているのかが明確化されていないため、「何を取って何を捨てるか」の基準が曖昧になります。
組織マネジメントが適切に行われている企業では、目標の達成に向けて最も効率的な戦力配分が可能になります。つまり、戦力の集中が可能になり、事業目標を達成しやすくなるのです。
3-2.市況の変化や未経験のリスクに素早く対応できる
グローバル化をはじめとする市場環境の変化に伴い、「柔軟で素早い対応力」が求められる場面が増えています。例えば、下記のようなケースです。
・多様化した顧客ニーズに対応した商品の開発
・急激なステークホルダーの変化
・経験したことのない新たなリスクの発生
組織マネジメントが行われていない企業では、変化に瞬時に対応することができず、経営が傾くきっかけにもなりかねません。
日頃から組織マネジメントが行われている企業であれば、未経験のリスクや変化にも素早く柔軟に対応することができます。
3-3.マネジャー(管理職)業務の効率化できる
2.「組織マネジメントの目的は強い組織を作ること」でも触れた通り、企業が抱えるビジネス課題は多様化しています。マネジャー(管理職)の業務はより高度化し、業務量が増加していることは、実感として認識している方が多いでしょう。
例えば、下記のような悩みを感じたことはないでしょうか。
・ざまざまなタイプの部下が増えて業務管理をしきれない
・部下の価値観がバラバラで統率を取るのが難しい
・組織のチーム編成が最新の市況に合っていない
組織マネジメントが行われていない企業では、こういった組織が持つ問題に個々のマネジャーが対応する必要がありました。
組織マネジメントを行うと「企業の仕組み」として対処できるようになります。例えば、下記のような取り組みが組織マネジメントの一環となります。
・ワークライフバランスの取り組み制度を強化する
・1つの価値観を全従業員が共有する
・組織の構成を変更する
効率的な問題解決が可能になると同時に、マネジャーの業務量を大幅に減らすことができるでしょう。
毎日1分のマネジメント習慣で組織風土を改革するUniposとは?詳細資料ダウンロード
4.組織マネジメントを行うための必要スキル
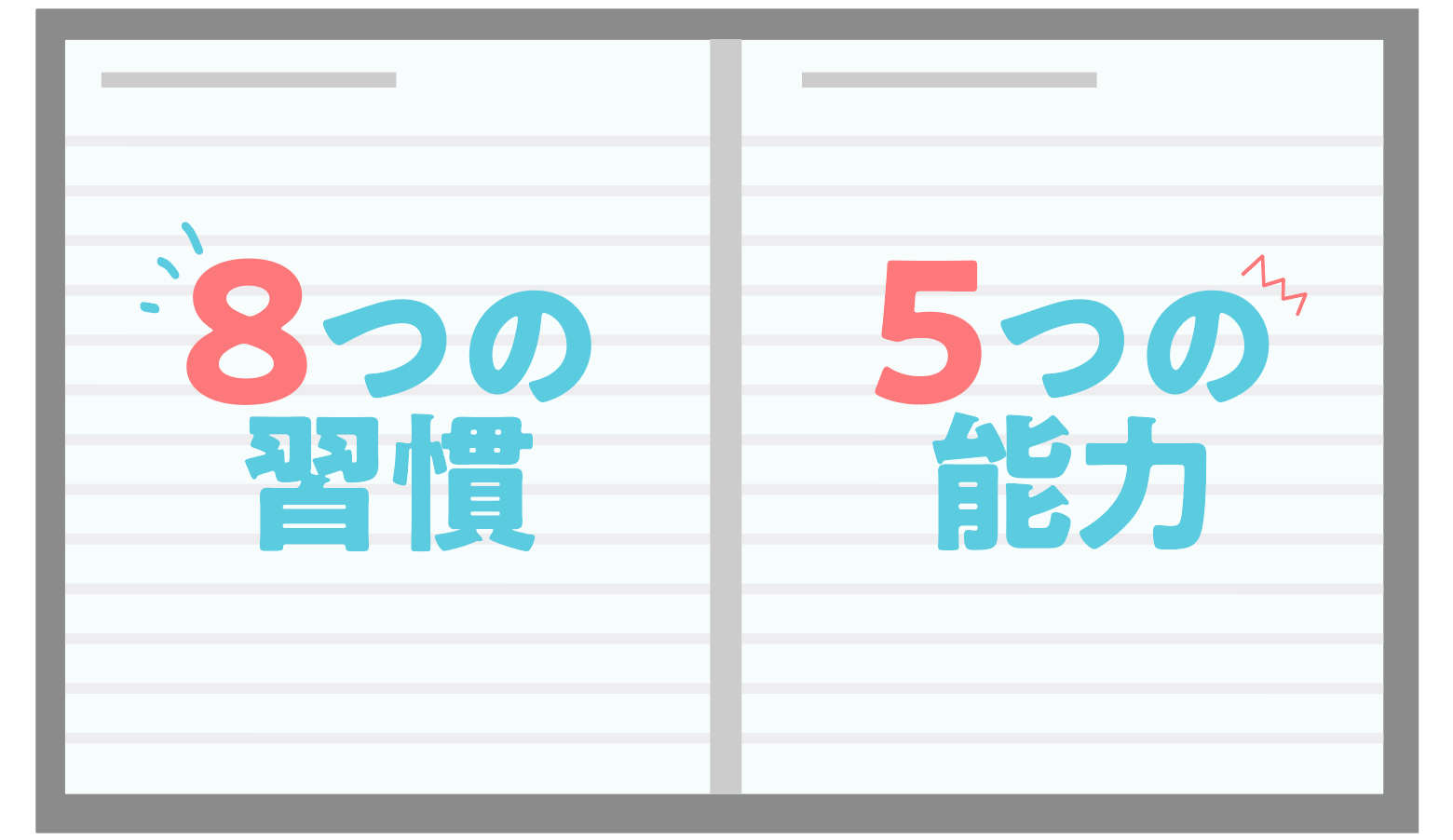
前章では組織マネジメントを行うことでどういった成果に繋がるかをご紹介しました。しかし、どんな人でも組織マネジメントをうまく活用し、実践できるわけではありません。
自社にとって最適な組織マネジメントを思考し、数多くある手法の中からより良いものを選択するためには、経営陣や管理職が必要な能力を身に付けている必要があります。
では具体的に、どんな能力を身に付ければ良いのでしょうか。ピーター・ドラッカーが説いた8つの習慣と5つの能力をご紹介しましょう。
4-1.8つの習慣
ドラッカーは、下記の8つを習慣とすべきだと説いています。
|
(1)なされるべきことを考える (2)組織のことを考える (3)アクションプランをつくる (4)意思決定を行う (5)コミュニケーションを行う (6)機会に焦点を合わせる (7)会議の生産性をあげる (8)「私は」でなく「われわれは」を考える 引用:P F ドラッカー『ドラッカー名著集1 経営者の条件』ダイヤモンド社,2006年 |
ドラッカー自身が出会ったさまざまな経営者のほとんどは、実は「いわゆるリーダータイプではなかった」といいます。
性格、仕事に対する姿勢、価値観、強み・弱みなどは千差万別でしたが、彼らが成果をあげたのは、この8つのことを習慣化させていたからだというのです。
私たちが組織マネジメントに取り組む上で、どのような態度で臨むべきなのか、ひとつの答えといえるでしょう。
4-2.5つの能力
さらに、成果をあげるためには、次の5つの能力が条件であるとドラッカーは述べています。
|
(1)何に自分の時間がとられているかを知ることである。残されたわずかな時間を体系的に管理することである。 (2)外の世界に対する貢献に焦点を合わせることである。仕事ではなく成果に精力を向けることである。「期待されている成果は何か」からスタートすることである。 (3)強みを基盤にすることである。自らの強み、上司、同僚、部下の強みの上に築くことである。それぞれの状況下における強みを中心に据えなければならない。弱みを基盤にしてはならない。すなわちできないことからスタートしてはならない。 (4)優れた仕事が際立った成果をあげる領域に力を集中することである。優先順位を決めそれを守るよう自らを強制することである。最初に行うべきことを行うことである。二番手に回したことはまったく行ってはならない。さもなければ何事もなすことはできない。 (5)成果をあげるよう意思決定を行うことである。決定とは、つまるところ手順の問題である。そして、成果をあげる決定は、合意ではなく異なる見解に基づいて行わなければならない。もちろん数多くの決定を手早く行うことは間違いである。必要なものは、ごくわずかの基本的な意思決定である。あれこれの戦術ではなく一つの正しい戦略である。 引用:P F ドラッカー『ドラッカー名著集1 経営者の条件』ダイヤモンド社,2006年 |
これらの能力は、持って生まれた才能ではありません。誰もが習得可能なものです。普通の人であれば、いかなる分野でも実践的な能力は身に付けられるとドラッカーはいいます。
組織マネジメントで成果をあげる第一歩として、さっそく今日から取り組んでみてはいかがでしょうか。
5.組織マネジメントで使われる手法リスト

組織マネジメントは、ある1つの手法を指した言葉ではありません。実際には、複数の手法を組み合わせながら実践していくものです。
そこでこの章では「組織マネジメントでよく使われる手法」をリスト化しました。組織マネジメントの手法選びのヒントとしてください。
|
手法 |
目的 |
|
①フィードバック分析 |
自らの強みを分析 |
|
②コア・コンピタンス |
自社の強みを分析 |
|
③SWOT分析/クロスSWOT分析 |
自社の強みと弱みを分析 |
|
④バリューチェーン分析 |
事業の流れから強みと弱みを分析 |
|
⑤PDCAサイクル |
継続的な業務改善 |
|
⑥PPM分析 |
複数の事業の位置づけを分析 |
|
⑦アドバンテージ・マトリクス |
事業ごとの特性を分析 |
|
⑧3C分析 |
市場・顧客、自社、競合のマーケティング分析 |
|
⑨5Fモデル |
競争環境の分析 |
|
⑩VRIO |
経営資源の競争力を分析 |
|
⑪TOC |
ボトルネックを探す |
|
⑫バランストスコアカード |
戦略を組織に浸透させる |
なお、これらは数多ある組織マネジメント手法の、ごく一部です。失敗しないためにも、実際に実践する前に押さえておきたい注意点を先に確認しましょう。
6.取り入れる前に押さえておきたい注意点
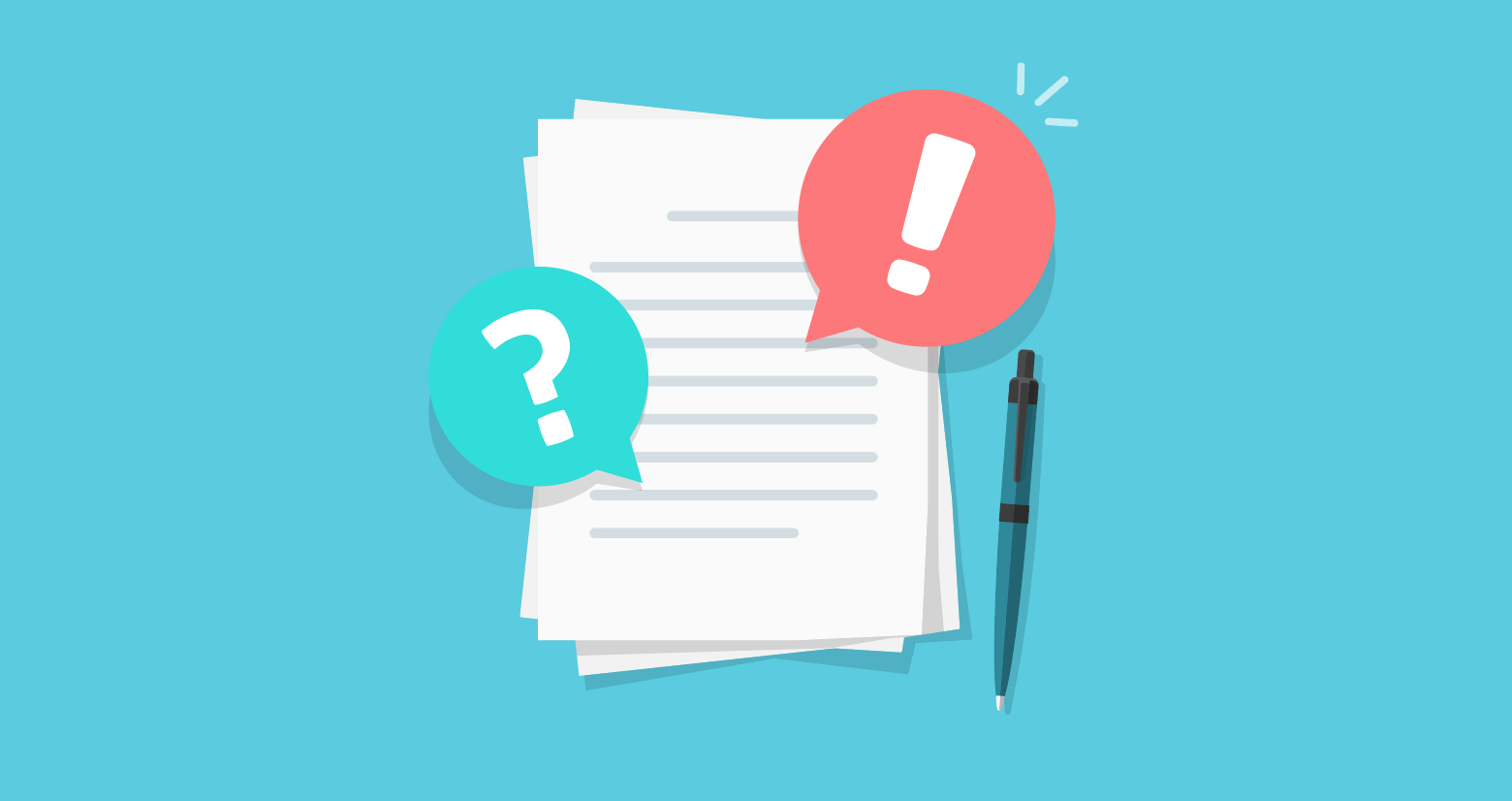
ここまでお読みいただいた方は、組織マネジメントの奥深さと、その無限の可能性にお気付きのことと思います。「組織マネジメントの視点を持って、今すぐに企業変革に取り組みたい」という方もいるでしょう。
本章では組織マネジメントを取り入れる前に押さえておきたい注意点を2つ、お伝えします。
6-1.目的を利益の追求としない
「企業は何のためにあるのか?」という問いは、今までに多くのビジネスパーソンが繰り返してきた哲学的な疑問です。ドラッカーは「顧客の創造である」と定義しています。顧客満足を通じて社会貢献した結果、企業は存続し得るのです。
もちろん、企業が利益をあげることは大切なことです。しかし、それ自体を組織マネジメントの目的としてしまうと、不正が起きるリスクや顧客ニーズに対応できずに淘汰される可能性が高まってしまいます。
「社会に貢献するためにはどうすれば良いか?」という大局的な視点を持って何をなすべきか考えていくのが組織マネジメントの本質です。
6-2.「人材」のマネジメントの優先順位を上げる
組織マネジメントを行う対象である経営資源は、7つあることをご紹介しました。近年、その中でも注目されているのが「人材(staff)」のマネジメントです。
ドラッカーは「仕事が生産的に行われても、人が生き生きと働けなければ失敗である」と述べています。「人材」は最大の経営資源であるともいえるのです。
現代では、少子高齢化社会による労働人口の減少やライフスタイルの多様化によって、優秀な人材を確保することが難しくなっています。
実際に、人材のマネジメントを通じて、組織変革を試みる企業が増えました。例えば、ヤフーは「組織開発」によって人材育成を行っている企業として有名です。
組織開発は目に見えにくい「人間的側面」から組織を良くするプロセスです。組織マネジメントのひとつの手法といえるでしょう。
詳しくは『組織開発とは?正しく理解して現場で実践するための定義・目的・手法』も合わせてご覧ください。
毎日1分のマネジメント習慣で組織風土を改革するUniposとは?詳細資料ダウンロード
7.組織マネジメントの理解が深まる名著3選
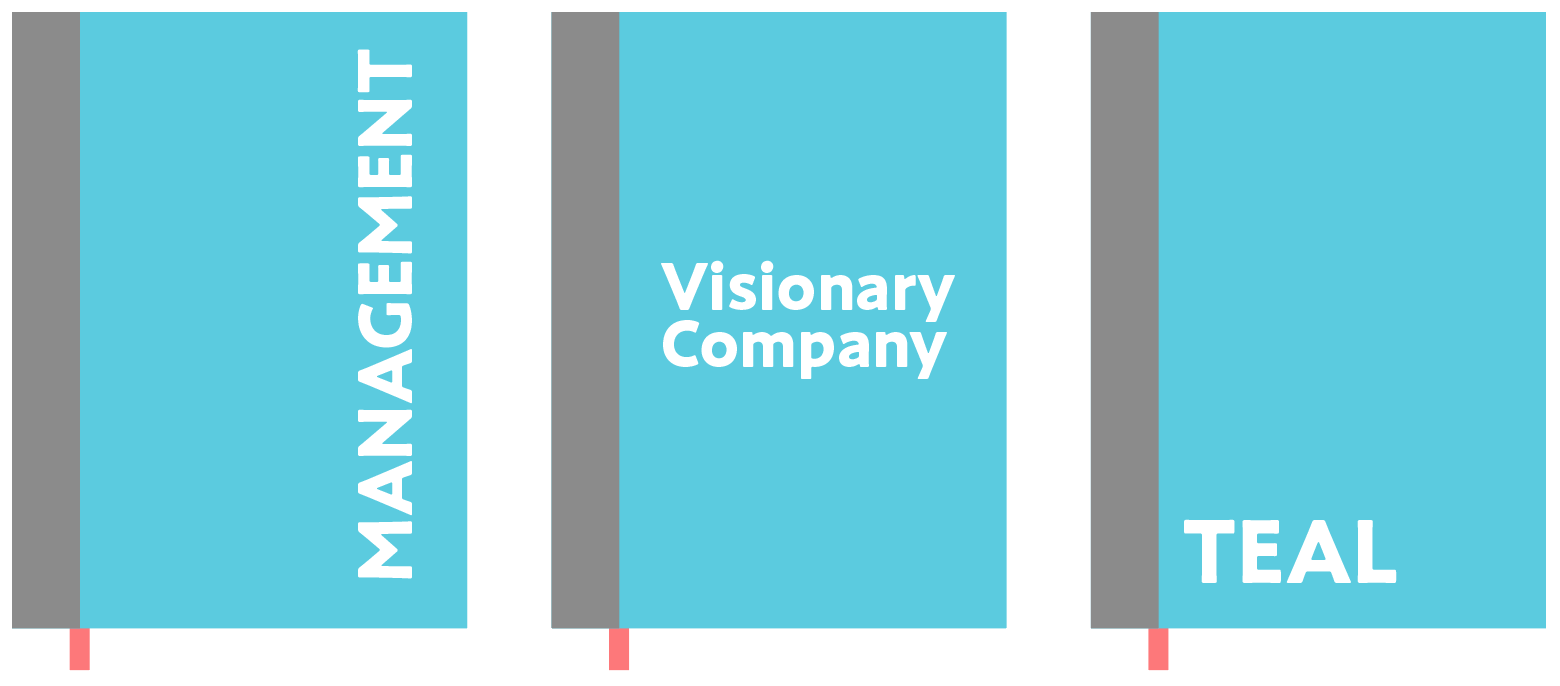
最後に、「組織マネジメントついての学びを深めたい」という方におすすめの名著を3冊、ご紹介しましょう。
7-1.『マネジメント』ピーター・F・ドラッカー
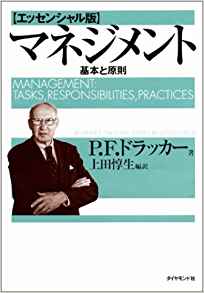
『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』 ピーター・F・ドラッカー
組織マネジメントについて、本質的な概念を知るための一冊として最適なのがピーター・F・ドラッカーの『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』です。
前述の通り、組織マネジメントの手法は多数ありますが、ドラッカーが説いているのは小手先の手法に左右されない、大局的な視点です。
「ハウツー本」というよりも、「組織マネジメントを行う上での哲学そのもの」を学ぶことができる名著として、多くの経営者に愛読されています。
過去に一度読んだことがある方も、マネジメントする立場になったタイミングで再読すると、新たな発見があることでしょう。
7-2.『ビジョナリー・カンパニー』ジム・コリンズ
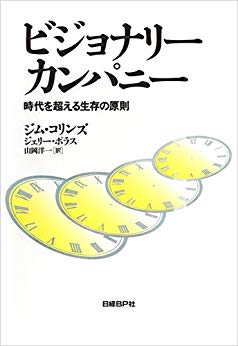
『ビジョナリー・カンパニー 時代を超える生存の原則』 ジム・コリンズ
組織マネジメントに取り組むときに熟慮が必要なのは、「何を変えて、何を変えないべきか」という選択です。それを考える上で大いに参考になるのが、ジム・コリンズの『ビジョナリー・カンパニー 時代を超える生存の原則』です。
この一冊の中には、業界トップを何十年も維持する超優良企業18社の創業からの歴史が詰まっています。つまり、成功企業がどんな組織マネジメントを行っていたのか、その事例が示されているのです。
具体的には、次の18社の事例を読むことができます。
|
3M、アメリカン・エキスプレス、ボーイング、シティコープ、フォード、GE、HP、IBM、J&J(ジョンソン・エンド・ジョンソン)、マリオット、メルク、モトローラ、ノードストーム、P&G、フィリップ・モリス、ソニー、ウォルマート、ウォルト・ディズニー |
この本を手もとに置きながら自社の組織マネジメントを考えることで、思考がより具体的・実践的になるはずです。
7-3.『ティール組織』フレデリック・ラルー

『ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』 フレデリック・ラルー
「最新の組織マネジメントについて学びたい」というときにおすすめなのがフレデリック・ラルーの『ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』です。
日本では2018年に出版され新世代の組織論として話題となり、『ビジネス書大賞2019経営者賞』を受賞しました。
ティール組織とは「進化型の組織」を指す言葉。その特徴は「管理しない」ことにあります。
上下関係も売上目標も予算もない、従来のアプローチとはまったく異なるやり方で圧倒的な成果をあげる組織が、世界中で出現しています。それらの組織で行われている組織マネジメントの手法が、この本で明らかにされています。
ティール組織は「次の組織モデルはこれだ」と、世界中で注目されている組織論です。これから組織マネジメントに取り組む人にとっては必読の一書といえるでしょう。
あの有名企業も導入!毎日1分のマネジメント習慣で組織風土を改革するUniposとは?詳細資料ダウンロード
8.まとめ
組織マネジメントとは、組織を効率的に動かし成果を最大化するためのマネジメント手法のことです。具体的には、7つの資源(7S)のマネジメントを指します。
目的は競争に負けずに長きにわたって生き残る強い組織を作ることであり、下記の成果が期待できます。
1.目標の達成に向けて戦力集中できる
2.市況の変化や未経験のリスクに素早く対応できる
3.マネジャー(管理職)業務の効率化できる
その手法は数多くありますが、適切な組織マネジメントを行うためには、経営陣や管理職が必要なスキルを兼ね備えていることが不可欠です。ドラッカーはそのスキルを「8つの習慣」「5つの能力」といった形で説いています。
組織マネジメントを取り入れる際には、目的を利益の追求しないこと、人材マネジメントの優先順位を上げることに留意してください。
より学びを深めるためには、下記の3冊を読むことをおすすめします。
1.『マネジメント』ピーター・F・ドラッカー
2.『ビジョナリー・カンパニー』ジム・コリンズ
3.『ティール組織』フレデリック・ラルー
ぜひ、あなたの所属する企業でも組織マネジメントを取り入れて、より良い組織への変革の一助としてください。社会に貢献し、従業員がイキイキと働ける組織ならば、リスクや変化にさらされたとしても、揺るがぬ強さで生き残っていけることでしょう。
毎日1分のマネジメント習慣で組織風土を改革するUniposとは?詳細資料ダウンロード


