
日本で、年功序列制度に代わり、一般的になってきている成果主義。
メリットがある一方で、社員のモチベーションに直接影響を与えるデメリットも指摘されています。諸刃の剣とも言える成果主義をうまく活用する方法はあるのでしょうか。
今回は、成果主義の意味、メリットとデメリット、成功事例と失敗事例、導入時の注意点をご紹介します。読者の組織にあった今後の人事評価制度検討のヒントになれば幸いです。
1. 成果主義とは
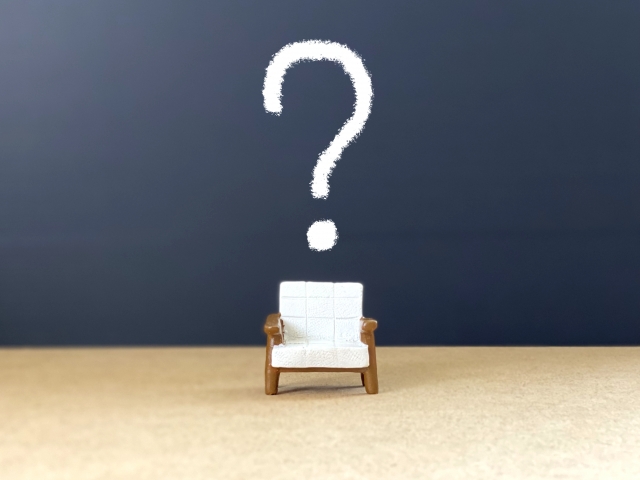
・成果主義の意味
成果主義とは、仕事の成果とそこに至るまでの過程を評価し、昇進や昇給を決めていく人事評価制度です。
もともと日本では「年功序列」の人事制度が一般的でしたが、バブル経済崩壊後の1990年代後半以降に企業間競争が激しくなり、年功序列から成果主義へシフトしていきました。
年功序列の評価基準は勤続年数や年齢ですが、成果主義の評価基準は仕事の成果、および成果までのプロセスです。成果主義では、勤続年数や年齢に関係なく、成果に応じた昇進、昇給が可能です。
・日本で広まった背景
日本で成果主義が普及した背景は、大きく2つです。
(1)業績悪化によるコスト削減の必要性
バブル崩壊後の1990年代以降、それまで安定して成長を続けていた企業においても、業績の悪化によりコスト削減が必要になりました。
中でも大きなコストを占めていたのが人件費です。
年功序列の場合、成果と給与が直接関係していないために、業績が悪化している場合も勤続年数が長い社員が多いほど人件費の割合が増加する問題が出てきました。
その問題を解決すべく、成果を上げたところに給与(人件費)を充てる合理的な手法として成果主義が注目されました。
(2)雇用形態の多様化
終身雇用が一般的だった以前に比べ、転職などの人材流動のスピードが早くなり、派遣社員や契約社員といった雇用形態が多様化しています。
そういった状況から、勤続年数や年齢だけでは適正に人事評価を行うことが難しくなり、別の合理的な評価方法が必要だったことも、成果主義が普及した背景の1つです。
‐参考リンク‐
成果主義とは――年功序列や能力主義との違い、メリット・デメリットや事例の解説 - 『日本の人事部』 (jinjibu.jp)
成果主義のメリットとデメリットとは?うまく浸透させる方法 | ピポラボ | ピポラボ (cydas.com)
2. 日本の成果主義の現状

・成果主義を取り入れている企業の割合
日本で『成果主義』という言葉が注目されたのは、1993年ころのことでした。
国内大手の電機メーカーである富士通株式会社が、成果主義人事を導入したからです。そして今なお、成果主義を導入する企業が増加傾向にあります。
成果主義を導入している割合について、独立行政法人経済産業研究所のペーパーによると、2012年では70%以上の企業が成果主義を導入していると示しています。
また、2004年に厚生労働省が行った調査でも「個人業績を賃金に反映させる」企業の割合は規模計で53.2%でした。
従業員数によって、その割合にはバラツキがあり、従業員数300~999人の企業では73.6%、従業員数1,000人以上の企業では83.4%という結果でした。
企業規模が大きくなるほど、「個人業績を賃金に反映させる」企業の割合が高い結果となりました。現在においても、大企業を中心に成果主義の導入が進んでいる傾向にあります。
‐参考リンク‐
成果主義の導入で失敗しないためのポイント5つ~メリット・デメリットから解説~ (2020年12月24日) - エキサイトニュース(4/15) (excite.co.jp)
・成果主義の問題点
現在の日本で起きている成果主義の問題点をご紹介します。
時代の潮流に沿って、成果主義の人事制度を導入したものの、諸々の課題やデメリット(後述)によってやり切れず、もとの人事制度に戻るケースがあります。
(1)評価基準のあいまい性、評価結果に対する不満
評価を行うにあたり、評価者と被評価者の認識があっていないケースがあります。
定量的な成果以外にも、定性的成果の程度に関する事項、目に見えない範囲での貢献度について、人事制度の評価方法では十分でない場合や評価者の裁量にゆだねられる部分があるためです。
また、他社員との相対的な比較により、不公平感が生まれているケースもあります。結果モチベーションが低下し、離職する可能性を高めてしまうことも否定できません。
(2)残業時間の増加
思うような成果が出ていない場合は、自らの評価を上げるために残業時間を増やして対応しようとします。企業全体として、残業時間の増加により人件費が上がる能性があります。
(3)必ずしも努力が成果に結びつかない
残業時間の増加とも関係しますが、社員の頑張りが成果に結びつかないケースもあるため、成果主義の人事制度自体に不満を感じ、離職するケースがあります。
(4)メンタルヘルスの不調
行き過ぎた成果主義によって職場環境が悪化し、従業員のストレスが高まることで、メンタルヘルスに悪影響を及ぼすことがあります。職場のメンタルヘルスが問題となり、2015年には労働安全衛生法でストレスチェックが義務付けられました。
しかし、令和2年度(2020年度)の「過労死等の労災補償状況」によれば、精神障がいによる労災請求件数は2,051件であり、2015年の1,515件から増加しています。
‐参考リンク‐
成果主義とは――年功序列や能力主義との違い、メリット・デメリットや事例の解説 - 『日本の人事部』 (jinjibu.jp)
3.成果主義のメリット、デメリット

・成果主義のメリット
成果主義のメリットは、4つあります。
(1)人件費の適切な配分と削減
成果主義は仕事の成果(業績)によって、人件費が増減する仕組みです。それ故、人件費の適切な配分と業績を伴わない場合の削減が可能になります(年功序列の場合は、社員の高齢化により人件費は増加する)。
(2)モチベーションが維持、向上
成果をあげることがそのまま昇給や昇格などのインセンティブにつながるので、社員のモチベーション維持、向上に役立ちます。結果、企業全体の業績アップも期待できます。
(3)優秀な人材を留保、採用できる
成果主義であることは、優秀な人材にとっては魅力的に見えます。能力を適正に評価し、自身の成長が期待できるためです。
そのような人材が社員である場合は、流出(離職)を防ぐことに役立ちます。採用活動においては、成果主義であることをアピールすることによって、優秀な人材を獲得しやすくなります。
(4)業務効率化の推進
仕事の成果を高めるには、プロセスを見直して業務効率化を図ることも重要になってきています。
近年は働き方改革が進み、残業時間を厳格に管理する企業が増えてきています。これにより、労働時間を増やすことなく成果を上げる考え方が推奨され、社員が自発的に業務効率化に取り組むようになり、結果組織全体のパフォーマンス向上につなげやすい、というメリットがあります。
・成果主義のデメリット
成果主義のデメリットは、5つあります。
(1)不公平感のない評価基準の設定が難しい
成果主義では、仕事の成果を客観的に評価できる基準を設定する必要があります。
部署によって長期的・短期的に結果が出るところや、定量的には成果が見えにくい部署もあります。企画・事務・研究といった職務に当たる社員に対して、どういう観点で客観的な評価を行うかの基準を設定することは簡単ではありません。
評価結果によっては、社員のモチベーションに大きな影響を与えるため、不公平感のない設定の検討が必要です。
(2)人事評価の負荷が増える
成果主義では、納得感のある基準を設けることが重要です。
それと同時に、社員個別に評価が必要となるため、運用にかかる負荷は年功序列の評価制度に比べ大きなものになります。
社員と上司の関係性だけでなく、チーム単位や組織単位で、評価結果のすり合わせを行うなど、複数の評価者で評価している企業もあります。
評価者が増えると現場の負担も増えますし、とりまとめを行う人事部門の負担も大きくなる可能性があります。
(3)離職率の上昇、採用コストの増加
仕事の成果が人事評価に直結する成果主義では、社員は高いストレス状況に置かれます。
人により、それがモチベーションの維持向上に作用するケースもありますが、期待した成果が出ない社員の場合は、給与の減少や降格になり、強いストレス状態となる場合があります。
その結果、転職する社員が増えることや、人材確保のための採用コストが増大する可能性があります。
(4)組織連携の不足、チームワークの低下
成果主義では、個人的な成果へのこだわりが強くなり、組織やチームとしての成果をないがしろにするケースが懸念されます。
具体的には、顧客(案件)の奪い合い、ノウハウや情報を共有しない、後輩を育成しないなどです。
その結果、チームワークが低下し、組織全体の連携が悪くなることで、組織の成果(業績)が最大化されない結果となります。
(5)能力の出し惜しみ(ラチェット効果※)
能力の出し惜しみとは、成果達成のために社員が自らの能力をセーブすることです。
成果主義では、定期的に成果を出し続けることが求められています。そのために、以下のメカニズムによって、能力の出し惜しみが生まれます。
① ある年の目標設定を100(単位は何でも構いません)に設定し、社員Aは110の成果を上げ、目標達成した。
この時、次の年の目標設定は、110を基準として、より高い成果が求められます。かつ、そうでなければ成果として認められません。
② 次の年の目標設定を120に設定し、社員Aは125の成果を上げ、目標達成した。
この時、次の年の目標設定は、125を基準として、より高い成果が求められます。かつ、そうでなければ成果として認められない。次の年に続く……
このように、社員が頑張れば頑張るほど、目標値が上がっていき、自らの首を絞める結果となります。
社員としては処遇を最大化するためにはどうしたらよいかを考えるようになるので、最終的に、目標値をできるだけ抑え(セーブして)それを少しだけ上回る成果を出し続けることが合理的と考えるようになります。
この結果、社員は自らの目標値を過少に設定し、能力を最大限出すことなく、業務を行うことになります。
※高い個人目標を達成したことでそれが最低ラインとなり、翌年はより高い目標を課される一方向性の流れをラチェット効果といいます
‐参考リンク‐
成果主義とは――年功序列や能力主義との違い、メリット・デメリットや事例の解説 - 『日本の人事部』 (jinjibu.jp)
成果主義とラチェット効果 - ゼミのページへようこそ (hatenablog.com)
4.成果主義の成功事例、失敗事例

成果主義を導入した結果、成功した事例と失敗した事例を2つずつご紹介します。
・成功事例1:花王
成果主義を導入し、成功している企業として、花王の例をご紹介します。
花王は、成果主義を導入するもっと前の1965年から、社員の能力開発支援に力を入れはじめていました。
まだ一般的には年功序列制度が当たり前だった時代に、社員がモチベーションを持って仕事に取り組めるような目標管理も導入しています。
その後、改良を加えながら制度を充実させ、2000年ごろには現行の成果主義の制度が整えられました。
花王の成功のポイントを一言でいうと、成果主義のデメリットを補う対応を行っている点にあります。
花王の社員(管理職を除く)は、主任クラスから一般社員まではフィールド(職種)ごとに役割等級に分かれています。社内では「職群制度」と呼ばれているそうです。
成果主義のデメリットの1つである評価基準を設けにくい点をこの制度によって補っています。
例えば、結果が出るまでに期間を要する研究部門は、長期的視点での研究成果も評価に含むこと。また、生産部門は単に結果だけではなく、習熟レベルを評価に加味するなどして職群ごとに社員にとって納得感のある評価観点を設定し、評価を行っています。
‐参考リンク‐
成果主義のメリットとデメリットとは?うまく浸透させる方法 | ピポラボ | ピポラボ (cydas.com)
成果主義の成功例からわかる成果主義の導入メリットとデメリット | 成果を自動的に最大化するSFA「Senses」 (mazrica.com)
・成功事例2:武田薬品工業
武田薬品工業は、1997年に成果主義を導入しました。同時期は、世界の大手製薬会社が次々と合併・吸収を繰り返している状況で、グローバルで戦うための構造改革が必要だったという背景がありました。
武田薬品工業の成功のポイントは、トップラインの意識改革と評価の透明性でした。
経営陣にも目標管理を課すだけでなく、全社一体となって制度改革を行いました。評価方法について、透明性と納得性にこだわった評価制度を目指し、社員からの理解を得た結果、売り上げ利益ともに大きく成長しています。
‐参考リンク‐
成果主義の導入成功例と「成果主義に頼らない」働き方 – ビズパーク (jinzaii.or.jp)
・失敗事例1:富士通
富士通は、1993年ごろに他の会社に先駆けて成果主義を導入しました。
当時の成果主義の仕組みは、各社員が目標設定を行い、上司がその目標の達成度を評価するものでした。
この仕組みの問題点は、達成度のみで評価が決定することでした。結果、社員自身が難易度の低い無難な目標ばかりを設定し、チャレンジ度の高い目標や新規性の高い目標、中長期的な目線で企業を成長させるような会社が求める目標が生まれなくなっていきます。
その後、この評価制度は廃止されることになりました。
・失敗事例2:マクドナルド
日本マクドナルドは2006年に成果主義を導入し、その一環として定年制を廃止しました。
導入の目的は、「若手社員を伸ばし実力本位の企業文化を構築すること」でした。
同時に、定年制や年功序列制度を廃止するなど根本的な人事・賃金体系の変更を行い、実力本位の社風を明確に打ち出しました。
しかし、いざ導入してみると、ベテラン社員が自分の成果を優先するがあまり、後進の人材育成をしなくなり、若手の人材開発に問題が生じました。その結果、日本マクドナルドは成果主義を見直し、定年制を復活させました。
‐参考リンク‐
成果主義は日本に合わない?企業の失敗事例から学ぶ成果主義のすすめ | あしたの人事オンライン (ashita-team.com)
5.自社で成果主義を導入する際の注意点

自社で成果主義を導入する場合の注意点は、次の3つです。
・導入方針と具体制度内容を明確にする
成果主義を導入する背景や目的などの基本方針、および運用で困らないための制度設計が重要です。
ここでのポイントは、社員にとって透明性と納得感があるかどうかです。
何を基準(評価観点)に、どのようなタイミングで評価されるかの詳細や、評価結果に応じて給与がどの程度変わり、昇格条件は何かなどが具体的に明文化されている必要があります。
さらに、部署間や職域に応じて納得感のある個別設定が必要なことも忘れはなりません。
年配の社員については、成果主義へのシフトに大きな抵抗を示す可能性があり、そういった社員に対しても、慎重に説明責任を果たすことが重要です。
成果主義による評価の合理性や制度内容を周知し、改正について社員に納得してもらえるよう努めなければなりません。
成果主義は、人事評価、報酬、人事異動、人材開発、採用戦略など、人事制度の全般に影響する可能性が高いため、人事制度を総合して不整合がないかを最終確認する必要があります。
・評価者のトレーニング
成果主義の導入において失敗する要因の1つが評価の不透明感です。
評価基準を明確にしても、評価者が適切に評価できなければ公正さを保つことはできません。
実際に評価を行うのは人間なので、人によるバラツキや、先入観が入ってしまい、本来期待していた運用にならない可能性があり、事前の対応が必要となります。
対応としては、評価者のトレーニングや研修を行う方法が有効です。
制度内容や評価方法についての理解を統一し、一定レベルでの評価ができるように指導します。
人事異動や昇格などで評価者が入れ替わる場合もあるため、研修やトレーニングを定期的に実施する必要性も考慮しておくとよいでしょう。
・企業文化を踏まえて多面的に評価する
結果として定量的に見えるものは成果主義の上では扱いやすい対象です。
一方、すぐには業績につながらないが重要な仕事もあります。例えば、リスクを回避するために行った分析作業、将来的な重要顧客への提案活動、後進への育成、ノウハウの見える化などです。
現時点の成果としては見えにくいが、組織として重要な取り組み、過程(プロセス)を評価対象に含めることが必要となるでしょう。
成果主義の評価項目は、シビアかつ冷たいものになりがちです。そういう状態の中で、企業独自の項目として何を設定するかが企業の文化や強みと言えるでしょう。
‐参考リンク‐
成果主義とは? 年功序列との違い、背景や目的、特徴、メリット・デメリット、導入時のポイントや注意点などについて - カオナビ人事用語集 (kaonavi.jp)
6.まとめ
いかがでしたでしょうか。
これまで記載した内容を簡単にまとめます。
- 成果主義とは、『仕事の成果と過程を評価し、昇進や昇給を決めていく人事評価制度』
- 日本で広まった背景は、業績悪化によるコスト削減の必要性、雇用形態の多様化
- 成果主義は、70%以上の会社で導入されており、規模が大きいほど導入割合は高い
- 現状の問題点は、評価基準のあいまい性、評価結果に対する不満など、導入後に元の人事制度に戻るケースもあり
- 成果主義のメリットは、人件費の配分と削減、モチベーションの維持向上、人材の確保、業務効率化
- 成果主義のデメリットは、評価基準の設定が難しい、人事評価の負担増加、離職率の上昇、組織連携が不足する、能力の出し惜しみ
- 成果主義を導入する際の注意点は、導入方針と具体制度内容を明確、評価者のトレーニング、企業文化を踏まえた多面的評価
現状日本の成果主義の実態について、アメとムチのような扱われ方をされているケースがあります。成果を出せば昇給昇格があり、成果がでない場合は減給降格が待っています。
しかし、成果主義の本来あるべき姿は、成果を上げた社員を適切に評価し、努力に報いることです。会社側は、社員が最大のパフォーマンスを上げるために必要な環境や人間関係(コミュニケーション)、制度設計を整えます。
成果主義という手段を使い、社員が生き生きと働き、会社側も持続的に成長できることが重要ではないでしょうか。
今回は、成果主義の意味、メリットデメリット、成功事例と失敗事例、導入時の注意点をご紹介しました。
成果主義について、読者の皆さまの組織に合った形での採否や、今後の進め方の検討材料として頂ければ幸いです。
人事制度について、年功序列or成果主義のどちらか、というものではないと思います。
実際に、年功序列の仕組みから、徐々に成果主義の要素を既存の人事制度に馴染ませ、浸透させていく形をとっている企業もあります(ハイブリット型、とも呼ばれます)。
成果主義のメリットを享受できるような仕組み作りについて、現在の制度や立ち位置を踏まえつつ、ベストミックスな形を考え始めてはいかがでしょうか。
‐参考リンク‐
成果主義とは――年功序列や能力主義との違い、メリット・デメリットや事例の解説 - 『日本の人事部』 (jinjibu.jp)
成果主義とは | メリット・デメリットや失敗しない導入方法を徹底解説 | ボクシルマガジン (boxil.jp)


