
「サーバント・リーダーシップ」という考え方が注目を集めています。
リーダーシップはなじみのある言葉だと思いますが、サーバントという単語はあまり知られていないかもしれません。
本記事では、サーバント・リーダーシップとはどんな意味なのか、なぜ今組織に求められているのかについて解説します。
1.サーバント・リーダーシップとは?
 まず、サーバント・リーダーシップの定義や特徴について説明します。
まず、サーバント・リーダーシップの定義や特徴について説明します。
サーバント・リーダーシップについて知ることで、これまでのリーダーシップとの違いについても理解できるでしょう。
サーバント・リーダーシップの「サーバント」とは「使用人」という意味です。使用人の仕事は主人のために奉仕すること。つまり、サーバント・リーダーシップとは「組織やチームのメンバーに奉仕・支援するタイプのリーダーシップ」のことを指します。
2.サーバント・リーダーシップの特徴
 サーバント・リーダーシップをより深く理解するためには、逆のタイプのリーダーシップを考えるとわかりやすいでしょう。
サーバント・リーダーシップをより深く理解するためには、逆のタイプのリーダーシップを考えるとわかりやすいでしょう。
サーバント・リーダーシップの対極に位置するのは、カリスマ型リーダーによる「支配型リーダーシップ」です。
カリスマ型リーダーのマネジメントは「部下に命令して仕事をさせる」というスタイルです。
部下が意見することもあるかもしれませんが、基本的にはカリスマ型リーダーが物事を決定し、部下は命令された業務を忠実に遂行します。
カリスマ型リーダーシップに対して、サーバント・リーダーでは一方的に命令して部下を動かすことはしません。
サーバント・リーダーはチームメンバーを信頼し、協力しあいながら組織全体を成長させます。
仕事の進め方などかなりの部分をメンバーに任せ、チームがパフォーマンスを発揮するための“支援”に徹します。
このスタイルがサーバント(使用人)と呼ばれる所以です。
支配型リーダーシップが、1人のカリスマ型リーダーを頂点として、多くのメンバーがリーダーを支えるピラミッド構造になっているのに対し、サーバント・リーダーシップでは、大勢のメンバーをリーダーが支える逆ピラミッドの構造になっています。
サーバント・リーダーシップでは、上に立つのはリーダーではなくメンバーなのです。
このように説明すると、中には「それは単に弱腰なだけではないか」「部下の言いなりになっているのではないか」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、サーバント・リーダーシップは決して「言いなり」ではないのです。
サーバント(使用人)という言葉で誤解を招きがちですが、サーバント・リーダーシップにおいて組織やチームの目指す方向を定めるのはリーダーの役割です。
ミッションやビジョンはリーダーがしっかりとメンバーに示し、その上でメンバーがそれぞれの個性を生かしてパフォーマンスを発揮できるよう支援すること。
それこそがサーバント・リーダーシップの本質なのです。
NPO法人日本サーバント・リーダーシップ協会では、「サーバント・リーダーシップの10の属性」として、以下の要素を挙げています。
・傾聴
サーバント・リーダーシップでは、しっかりと「聴く」ことが重要です。
傾聴することでメンバーの考えを引き出し、メンバーが能力を発揮できるサポートの方法を考えます。
・共感
傾聴するために重要なのが共感です。
一方的に話をしたり考えを押し付けるのではなく、相手の気持ちに共感し、理解を示すことがサーバント・リーダーシップに求められています。
・癒し
カリスマ型リーダーはメンバーから恐れられることも少なくありません。
しかし、恐れはメンバーを萎縮させ、意見を封じ、能力を下げてしまうことにつながります。
サーバント・リーダーはメンバーに癒しを与え、パフォーマンスを引き出すことに努めます。
・気づき
メンバーが能力を発揮できるよう、チームはもちろん、他部門や組織全体をよく見て、そこから得た「気づき」をマネジメントに活かしていくことが重要です。サーバント・リーダーシップには視野の広さが求められます。
・説得
意見の相違が生じた際、職位によってメンバーを服従させるのではなく、話し合いによって説得することが大切です。
・概念化
物事の本質を抽出して伝える「概念化」の能力を高めることで、チームメンバーとのコミュニケーションはより円滑化されます。
組織やチームが何を目指すのか、ビジョンを伝える上でも概念化は必要です。
・先見力、予見力
将来、起こりうる事柄について予見する力がサーバント・リーダーには求められます。
先を読むことで、今どうするべきかがわかるからです。予見力はチームメンバーを支援し導くのに必要な能力です。
・執事役
執事とは、主人のために奉仕する者であり、主人からの信頼を得て大切な役割を任される者です。
サーバント・リーダーは執事のようにメンバーに寄り添い、メンバーのためになる行動をとります。
自分自身よりもメンバーの利益に満足を感じられることが、サーバント・リーダーの資質の1つです。
・人々の成長に関わる
チームメンバーの成長を促進するのも、サーバント・リーダーの大事な役割であり能力です。
メンバー1人ひとりの個性やスキルを理解し、成長を促します。
・コミュニティづくり
メンバーが円滑にコミュニケーションし、成長できる環境をつくるのもサーバント・リーダーの役割です。
NPO法人日本サーバント・リーダーシップ協会によると、支配型リーダーシップに従うメンバーは主に恐れや義務感で行動し、リーダーの機嫌を伺いながら、自らの役割や指示内容だけに集中するとされています。加えて、リーダーをあまり信頼しておらず、結果として自己中心的な姿勢を身につけやすくなってしまうのだといいます。
サーバント・リーダーシップに従うメンバーは、主に「やりたい」という気持ちで行動し、やるべきことに集中して、工夫できるところは工夫しようとします。
また、リーダーのビジョンを意識して動き、リーダーを信頼し、周囲の役に立とうとする姿勢を身につけやすいのです。
参考:https://www.kaonavi.jp/dictionary/servant_leadership/
参考:https://www.thelion-mag.jp/_/dl/gat/ServantLeadership.pdf
参考:参考:https://www.servantleader.jp/
3.サーバント・リーダーシップが求められる理由
 サーバント・リーダーシップは最近生まれた考え方というわけではありません。
サーバント・リーダーシップは最近生まれた考え方というわけではありません。
考え方そのものは何十年も前から存在していましたが、近年になって特に注目を集めるようになったのです。
なぜ今、サーバント・リーダーシップが求められるのか。サーバント・リーダーシップの歴史を紐解いてみましょう。
サーバント・リーダーシップの歴史
サーバント・リーダーシップは、教育コンサルタントのロバート・グリーンリーフ氏が1970年代に提唱した考え方です。グリーンリーフ氏はAT&Tのマネジメント研究センターでセンター長を務め、マネジメントや教育について研究を行った人物です。
また、マサチューセッツ工科大学スローン・スクールやハーバード・ビジネス・スクールの客員講師も務め、ダートマス大学やヴァージニア大学でも教鞭をとるなど幅広く活躍しました。
グリーンリーフ氏は自身の経験を通して「サーバント・リーダーシップ」という考え方を提唱し、著書となる『サーバント・リーダーシップ』を執筆しました。
マサチューセッツ工科大学のピーター・センゲ教授は同書を「リーダーシップを本気で学ぶ人が読むべき一冊だ」と高く評価し、経営学者のピーター・ドラッカー氏はグリーンリーフ氏について「私が出会った中でもっとも賢い人である」と称賛しています。
正解のないVUCA時代にこそ必要
では、なぜ1970年代に提唱されたサーバント・リーダーシップという考え方が、今あらためて注目されているのでしょうか。
それは、現在が「正解のない激動の時代」だからです。
現代のような時代のことを、Volatility(変動性・不安定さ)、Uncertainty(不確実性・不確定さ)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性・不明確さ)の頭文字をとり「VUCA」と呼びますが、サーバント・リーダーシップはVUCAの時代にこそ必要な考え方なのです。
逆にいえば、これまではサーバント・リーダーシップではなく、支配型リーダーシップの時代が長く続いていました。特に日本の会社組織では顕著で、部下は上司の命令に従って業務をこなし、上司は職位で部下を統制していました。
支配型型リーダーシップで部下を統制するピラミッド型の組織が必ずしもよくないということではありません。
20世紀の大量生産・大量消費時代は、モノをつくればつくった分だけ売れる時代でした。
モノを大量につくることこそが「正解」だったのです。そうした状況では生産効率をできるだけ上げられるよう、支配型のマネジメントが適することもあるでしょう。支配型のマネジメントは命令系統がはっきりしており、やることが決まっていればスピードを上げやすいからです。
しかし、VUCAの時代は違います。
インターネットの普及もあり、趣味嗜好は多様化・細分化しました。モノをつくっても売れるとは限りません。
「これさえやっておけばいい」という絶対の正解が存在しない時代になったのです。
VUCAの時代では、恐れず挑戦し、仮に失敗したなら、そこから学びを得て前に進んでいくしかありません。
そうした状況では、カリスマ型リーダーが1人ですべてを決めるのは非効率です。1人では考え方の幅にも限界があり、多様化する価値観に追いつけないからです。
多様化する世界で成果を出すには、チームにも多様性が必要です。いろいろな考えや価値観を持つメンバーが自由に意見を出し合い、思わぬアイデアが生まれる環境を作ることが重要です。
そのためには、多様なメンバーの個性を十分に発揮させてやれるリーダーが必要です。支配するのではなく、協調と奉仕でチームのポテンシャルを引き出せるリーダーーーすなわち、サーバント・リーダーです。
参考:https://www.kaonavi.jp/dictionary/servant_leadership/
参考:https://www.thelion-mag.jp/_/dl/gat/ServantLeadership.pdf
参考:https://www.servantleader.jp/
4.サーバント・リーダーシップのメリット
 サーバント・リーダーシップには多くのメリットが存在します。ここでは、サーバント・リーダーシップのメリットについて説明します。
サーバント・リーダーシップには多くのメリットが存在します。ここでは、サーバント・リーダーシップのメリットについて説明します。
・コミュニケーションの円滑化
誰しもが自由に意見を戦わせ、尊重しあえる環境をサーバント・リーダーが作ることで、チームの雰囲気はよくなります。そのようなチームコミュニケーションは普段から良好かつ円滑なものになるでしょう。
・エンゲージメントが高まる
サーバント・リーダーがチームの個々人に働きかけ、個性を尊重して成長を促すことで、メンバーはチームに所属することを心地よいと感じられるようになります。その結果、現在のチームや組織こそが自分の居場所だと確信し、エンゲージメントが高まることが期待できます。
・様々なアイデアが生まれる
サーバント・リーダーはメンバーの多様な個性を生かして、健全な議論が生まれやすい環境を作ります。その結果、チームメンバーからは多様なアイデアが生まれることでしょう。
・心理的安全性が高まる
心理的安全性の高いチームとは、他者から攻撃を受けることなく自分の意見を言えたり、失敗を恐れず挑戦できたりするチームのことです。心理的安全性の高いチームは生産性が高く、ビジネスでも大きな成果を上げられます。サーバント・リーダーシップを取り入れることで、より心理的安全性の高いチームを作れるでしょう。
5.サーバント・リーダーシップのデメリット
 良いことだらけに思えるサーバント・リーダーシップですが、デメリットもあります。
良いことだらけに思えるサーバント・リーダーシップですが、デメリットもあります。
・指示待ち人間には向かない
サーバント・リーダーシップはメンバーの意見を尊重し、チーム内で健全に議論できる雰囲気を醸成します。
その結果、多様なアイデアが生まれ、ビジネス課題を解決に導けるのです。裏を返せば、言われたことだけをやっていたいという“指示待ち”のメンバーはサーバント・リーダーのもとで力を発揮できません。
・向いていない職種や環境もある
サーバント・リーダーシップは多くの職場で有効ですが、かといってすべての環境に適しているわけではありません。
職種や業種によっては、サーバント・リーダーシップを適用しない方がいい場合もあります。
たとえば、決まった作業をルーティーンでこなすことが求められるような環境であれば、サーバント・リーダーシップはむしろ生産性を下げてしまうかもしれません。職場によってはオペレーティブなマネジメントが適していることもあるのです。
参考:https://www.kaonavi.jp/dictionary/servant_leadership/
参考:https://www.thelion-mag.jp/_/dl/gat/ServantLeadership.pdf
参考:https://www.servantleader.jp/
6.サーバント・リーダーシップを取り入れている企業事例
 サーバント・リーダーシップを導入したことで生産性が向上したり、業績によい影響が出たりした企業の事例を紹介します。
サーバント・リーダーシップを導入したことで生産性が向上したり、業績によい影響が出たりした企業の事例を紹介します。
「サーバント・リーダーシップのメリットはわかったけれど、実際にどんな効果が出るのか具体的に知りたい」という方はぜひ参考にしてください。
スターバックス
グローバルに展開するコーヒーショップのスターバックスは、サーバント・リーダーシップをいち早く導入し、成果を上げている企業でもあります。
スターバックスを大きく成長させた元CEOのハワード・シュツル氏は、「社員を大切にする」という哲学のもと組織づくりを行ってきました。
たとえばアメリカで初めてすべてのパートタイマーを対象に正社員と同じレベルの健康保険を適用したり、全社員を対象にストックオプションを導入したりしました。
シュルツ氏の言葉に「会社が社員を支える」というものがありますが、これはまさにサーバント・リーダーシップの考えに通じるといえます。
シュルツ氏の右腕として知られるハワード・ビーハー氏も、ロバート・グリーンリーフ氏の著書を社員に勧めるなど、サーバント・リーダーシップを社内に啓蒙していたそうです。
そんなスターバックスにも危機が訪れたことがありました。2007年頃、スターバックスは急拡大の反動で売上が落ち、窮地に陥ります。
このとき、シュルツ氏は業績を回復するため、リストラなどの厳しい判断に追い込まれます。
自身の持つ哲学と、経営者としての判断の矛盾に苦しみながら、シュルツ氏は最後まで従業員を守るために戦いました。たとえば株主から健康保険の中止を求められましたが、シュルツ氏は応じなかったといいます。
その後、スターバックスは見事に再生を遂げ、世界トップのコーヒーショップとして現在もブランドを確立しています。
スターバックスの現場では、スタッフが自律的に動き、柔軟に接客をこなしています。
また、「スターバックスで働いていること」に誇りを持ち、どの店舗でもエンゲージメントが高く保たれています。こうしたスターバックスの雰囲気は、まさにサーバント・リーダーシップが浸透した職場の特徴と合致しています。
資生堂
サーバント・リーダーシップを導入し、資生堂を再生させたことで有名なのが池田守男氏です。
化粧品最大手の資生堂ですが、90年代後半、経営危機が訪れます。それまで大量生産、大量消費で商品を販売してきた資生堂は、大きな方向転換を迫られることになったのです。
そこで新たに代表取締役に就任したのが池田守男氏でした。
池田氏は「店頭を起点とした経営改革」を方針として打ち出します。具体的には、「お客様が第一なのだから、お客様と接する店頭こそが資生堂の中でもっとも重要である」という考え方です。
それまでの資生堂はピラミッド型の組織で、頂点に社長がおり、続いて本社や研究所、そして支社長、営業担当、最後に店頭のビューティー・コンサルタント(販売員)という序列でした。
池田氏はこのピラミッドをひっくり返し、トップに店頭とビューティー・コンサルタントを据えたのです。
それはすなわち、「社長や本社、営業担当は、店頭とそこで働くビューティー・コンサルタントを最大限支えるべき」という考え方への転換でした。「会社が社員を支える」という奉仕の精神は、まさにサーバント・リーダーシップといえます。
この他にも、現場のコミュニケーションを重視した改革など、サーバント・リーダーシップの考え方を次々に導入していった池田氏の手腕により、資生堂は高いブランド力を手に入れ、化粧品業界のリーディングカンパニーとしての存在感を取り戻したのです。
参考:https://souken.shikigaku.jp/1647/
参考:https://servant.style/shiseido/
参考:https://www.kaonavi.jp/dictionary/servant_leadership/
参考:https://www.thelion-mag.jp/_/dl/gat/ServantLeadership.pdf
7.サーバント・リーダーシップ導入時の注意点
 サーバント・リーダーシップを導入する際、注意したい点もあります。
サーバント・リーダーシップを導入する際、注意したい点もあります。
それは、「まず組織のトップこそがサーバント・リーダーシップの精神を持つべき」ということです。
前段で紹介したサーバント・リーダーシップで成功した企業は、いずれもトップがサーバント・リーダーシップを理解し、率先して実践していました。
サーバント・リーダーシップは逆ピラミッド型の組織であり、通常なら最上位に位置するトップが最下位となってメンバーを支えなければいけません。トップ自身がまず周囲を支援する姿勢を打ち出さないと、逆ピラミッドの土台ができず、サーバント・リーダーシップはいつまでたっても浸透しないのです。
もう1つの注意点は、「だからといってトップダウンで一方的に導入を進めてはいけない」ということです。サーバント・リーダーシップを導入したいがゆえに、メンバーに十分な説明をすることなく導入を急ぐのはサーバント・リーダーシップの精神に反しています。トップが丁寧にビジョンを語り、メンバーの理解と協力を得て推進することが大切です。
参考:https://www.thelion-mag.jp/_/dl/gat/ServantLeadership.pdf
8.サーバント・リーダーシップを実践する方法
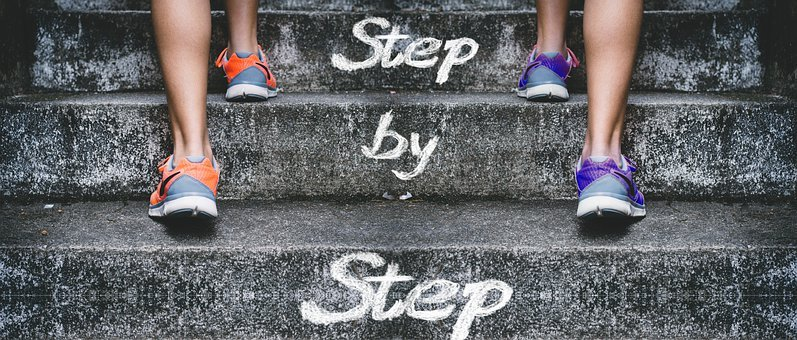 では、具体的にどのようにサーバント・リーダーシップを実践していけばいいのでしょうか。いくつかのポイントについて説明します。
では、具体的にどのようにサーバント・リーダーシップを実践していけばいいのでしょうか。いくつかのポイントについて説明します。
リーダーは自身を省みる
サーバント・リーダーは常に自分自身を省みる姿勢を持つことが重要です。自身の成長なくしてメンバーに奉仕し続けることは不可能です。メンバーの成長にコミットし、良い職場をつくるためには、まずリーダー自身が成長することが不可欠です。
仕事を押し付けるのではなく、自分自身も役割を果たす
メンバーに仕事を任せることと、単に仕事を押し付けることは違います。メンバーが能力を発揮してパフォーマンスを出せるように、サーバント・リーダー自身もしっかりと役割を果たす必要があります。
ビジョンを設定する
サーバント・リーダーの重要な役割の1つが、ビジョンを設定することです。
支配型リーダーシップと異なり、サーバント・リーダーシップではチームで協力して目標に向かいます。その際、ビジョンが提示されていなければメンバーは何を目指せばいいのかわからず、パフォーマンスを落としてしまいます。
そうならないよう、リーダーはビジョンを明確に示すようにしましょう。
チームに感謝する
サーバント・リーダーは常にチームに感謝する姿勢でいることが大切です。
感謝の気持ちを伝えることで、チームの心理的安全性は向上し、メンバーはさらにパフォーマンスを発揮できます。また、リーダー自身が率先して感謝を示すことで、メンバー同士にも感謝や称賛の文化が根付き、チームはよりよい雰囲気になっていくでしょう。
参考:https://www.thelion-mag.jp/_/dl/gat/ServantLeadership.pdf
9.サーバント・リーダーシップのおすすめ本2選~さらに学びたい方へ~
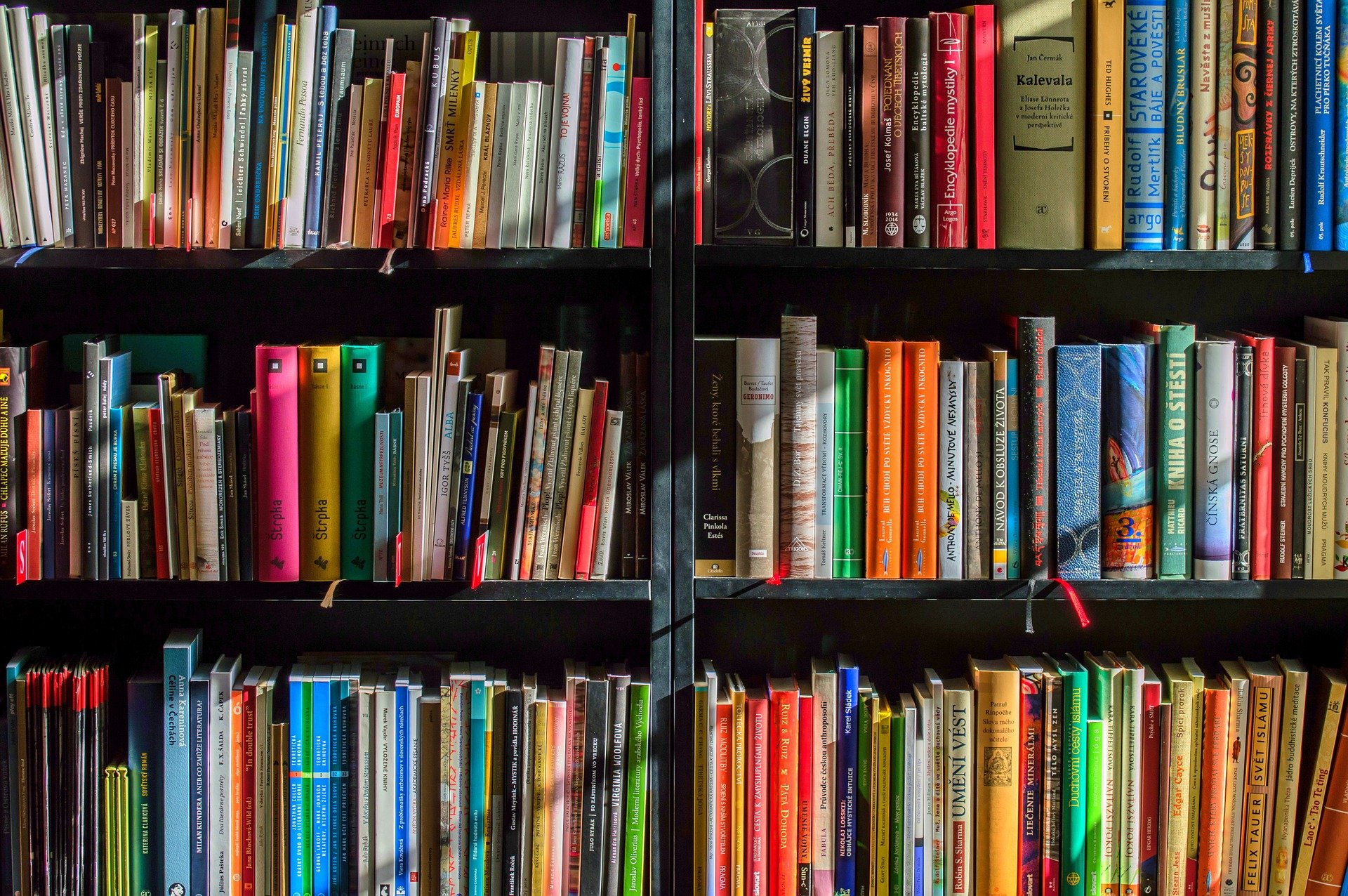 サーバント・リーダーシップについてもっと詳しく知りたい、専門的に学びたいという方には以下の書籍をおすすめします。
サーバント・リーダーシップについてもっと詳しく知りたい、専門的に学びたいという方には以下の書籍をおすすめします。
『サーバント・リーダーシップ』(ロバート・K・グリーンリーフ)
サーバント・リーダーシップの提唱者でもあるグリーンリーフ氏の著書。1977年に米国で刊行されて以来、常にサーバント・リーダーシップの教科書です。
刊行から40年以上がたっても、その内容は輝きを失うことなく、今も多くの経営者にとっての必読書として知られています。サーバント・リーダーシップを学びたいなら、まずはここからといえる1冊です。
『サーバント リーダーシップ入門』(池田 守男(共著) 金井 壽宏(共著))
サーバント・リーダーシップの企業事例でも紹介した資生堂の元代表取締役・池田守男氏が記したサーバント・リーダーシップに関する書籍です。
また、共著の金井 壽宏氏はリーダーシップ研究の第一人者として知られている人物です。
日本で初めてのサーバント・リーダーシップ実践に関する書籍であり、実践者ならではの視点で書かれた内容からは多くのヒントが得られるでしょう。
参考:https://www.servantleader.jp/book
まとめ
サーバント・リーダーシップは奉仕型のリーダーシップであり、かつて主流だった支配型リーダーシップとは様々な点で大きく異なっています。
正解がないVUCAの時代にこそ求められている考え方です。
サーバント・リーダーシップを導入することで、チームのコミュニケーションが円滑になったり、チームの心理的安全性が高まったり、組織へのエンゲージメントが増したりするなど様々なメリットが生まれるでしょう。
より組織を成長させるために、サーバント・リーダーシップの導入を検討してみてはいかがでしょうか。


