
チームビルディングとは、メンバーの能力を発揮し、かつチームという集団で見たときのパフォーマンスも高まるようにチームをつくることです。なぜチームビルディングが必要か、またどのように実施していくのか説明します。
チームビルディングとは?

チームビルディングとは、メンバーの能力を十分に発揮し、チーム全体のパフォーマンスが高まるようなチームをつくることです。なお、チームと混同しがちな言葉に「グループ」があります。グループは単に集団を意味する言葉で、目標や目的を共有しているわけではありません。一方、チームは目標や目的を共有し、各自の役割を果たしつつも協力し合う組織を意味します。
チームビルディングは、次の目的で実施されます。
- 業務上の目的を達成するため
- リーダーとしてのスキルを育成するため
- チームパフォーマンスを向上するため
基本的にチームは、特定の業務を遂行するためにつくられます。たとえば別企業とのコラボレーション企画をするときなら、プロジェクトチームを作成して業務にあたると効率よく仕事を進められるでしょう。パフォーマンスが高まるチームであれば、プロジェクトが成功しやすくなるだけでなく、多大な成果を期待できます。
また、チームは一時的につくられた団体です。部署のように恒常的に存在する団体ではないため、試験的な取り組みに対して活用できます。年齢的には若手・新人にあたる人材をリーダーに抜擢し、リーダーシップを磨く実践的な場にすることもできるでしょう。
チームとしての成果を上げることも、チームビルディングの目的です。一人ひとりのスキルや特性に注目し、相乗効果が生まれやすいように配属・サポートすることで、1+1が3にも4にもなるようなチームづくりを実現します。
チームビルディングのメリットとは?

チームビルディングには、次のメリットがあります。
- 企業のビジョンを共有できる
- 短期間で社員を育成できる
- 業務のパフォーマンスが向上する
- 社員が企業に愛着を感じる
- 社員の働きやすさが向上する
チームとして業務に取り組むとき、各メンバーは、チームをけん引するリーダーから繰り返し企業ビジョンについての話を聞くことになります。普段の業務ではあまり企業ビジョンについて触れる機会がない職場でも、臨時的に作成したチームのなかでは繰り返し触れることになるでしょう。メンバー個々に企業ビジョンが浸透し、自然と企業ビジョンに沿ったものの考え方や判断をするようになります。
また、チームビルディングは高効率の社員育成の場でもあります。チームのリーダーが次世代リーダーとしての経験・スキルを獲得するだけでなく、他のメンバーも主体的に業務に取り組むことで、各自の持つポテンシャルを発揮できるようになるでしょう。
チームとしての活動により、社員が仕事に対する意識を変革する可能性もあります。するようにいわれたからするのではなく、課題を自分で見つけ、会社にとって良いと思われることに自発的に取り組むようになるのも意識変革のひとつです。
また、会社にとって良い行動をすることが、自分にとって良い行動をするのと同じように感じられるようになるかもしれません。このような感情の同化が起こると、一層、企業に愛着を感じるようになります。
チームによりお互いの理解が深まることもメリットです。チームとしての業務をとおし、メンバーの個性を理解することで、お互いを尊重する気持ちも生まれるようになります。お互いが尊重し合う環境は心地のよいものです。メンバー各自が心理的安全性を感じられるようになり、よりリラックスした状態で働けるようになるでしょう。
チームビルディングによってチームの成果を最大化する方法

チームビルディングをおこなうことで、企業に対して愛着を感じやすくなり、また生産性の向上やメンバー各自の育成、モチベーションアップなどのメリットが得られます。しかし、チームビルディングさえすれば、常にこのような多大なメリットを得られるわけではありません。
場合によっては1+1が2にもならないことや、チームメンバー間に亀裂が入ること、企業への愛着を感じるどころか離脱を促進することなどもあるでしょう。チームビルディングを実施し、なおかつチームの成果を最大化するためにも、次のポイントに注目することが大切です。
- チームメンバーの関係を強化する
- 高すぎない目標設定
- メンバーの適性に注目したチーム編成
同じ目標を持って同じ業務に取り組むだけでも、チームメンバーの関係はある程度強化できます。しかし、業務を一緒にするだけでは、個人的な信頼関係は生まれにくく、仲間意識も育ちにくいと考えられます。
チームビルディングにおいては、業務をする以外の行動も大切な要素です。とりわけチームメンバーの関係を強化するための取り組みも、欠かせない要素として注目できるでしょう。たとえば業務時間外に食事をすること、カジュアルな話し合いの機会を定期的に持つこと、ゲーム的な要素のあるアクティビティに取り組むことなどでも、関係を強化できます。
また、現実的な目標を設定することも大切です。目標を高く持つことは良いことではありますが、どう考えても実現不可能なことや、運などに左右される要素を含む場合には、真剣に取り組む意欲が薄れてしまうかもしれません。
とはいえあまりにも容易に実現できる目標では、メンバーはやりがいを感じられず、仕事に対するモチベーションを失うこともあります。高すぎず低すぎない目標を設定することも、チームビルディングを成功させるためのポイントといえます。
メンバーの適性に注目したチーム編成も大切です。今までの仕事の取り組み方や性格などから、ポジティブなケミストリーが起こるようにメンバーの組み合わせを考えます。また、組み合わせだけでなく業務分担にも、メンバー個々の適性を反映することが必要です。チーム編成に問題があるときは、パフォーマンスが低下するだけでなく、社員間で不和が生じ、業務や企業に対しての不満が高まる可能性もあります。チーム編成後にミスマッチがわかったときは、速やかにメンバーの入れ替えなども実施し、適切にチームが機能するように調整していきましょう。
チームビルディングを行う上での注意点

チームビルディングを実施する際、次のような問題が生じることがあります。
- メンバーのスキルや適性が活かされない
- メンバーがモチベーションを維持できない
- チームが機能しない
メンバーのスキルや適性が活かされていないときは、チーム編成に問題があります。ただし、普段の業務から判断している社員のスキル・適性は、かならずしもチームでも同様に発揮されるのではありません。ほかのチームメンバーとの相性や相乗効果もあるため、必要に応じてメンバーを入れ替えることも検討してみましょう。
また、メンバーがモチベーションを維持できず、本来の能力を発揮できないケースもあります。たとえば「したくない仕事をさせられている」と感じるメンバーが多いときは、モチベーションは維持できないでしょう。いやいや仕事をするため、本来の能力を発揮できなくて当然です。
このような事態を回避するためにも、企業ビジョンだけでなくチームとしてのビジョンを浸透させることが必要になります。チームのビジョンとメンバー各自の目標とリンクさせ、チームの業務が他人事ではなく「自分事」としてメンバー個々が認識できるようにしましょう。
また、メンバーがモチベーションを維持できない理由として、自由度が高すぎる可能性も考えられます。メンバーの主体性を育むためにある程度の決定権を与えることは大切なことですが、業務進行や意思決定のすべてをメンバーに丸投げしてしまうのはおすすめできません。
メンバーは「リーダーの代わりに自分たちが仕事をしなくてはいけない」と考えるようになり、やらされ仕事として受け止める可能性があります。リーダーには、最初に業務の大枠を示すだけでなく、チームメンバーの個人の判断力にも委ねつつ、要所要所で的確な指示をすることが必要です。
また、メンバーの個性を理解し、業務へポジティブに反映するためにも、メンバーの意見をヒアリングすることも重要です。どのような仕事をしたいのか、どこに目標を置くとモチベーションを持って働けるのかなど、丁寧にメンバーの意見を聞き、チーム編成や業務進行に反映していきます。
チームビルディングの評価指標と測定方法

適時評価をおこないながら、チームビルディングを進めていくことが大切です。また評価を定期的におこなうことで、チームによって得られている効果を測定し、より良い成果に結びつけるためにチーム編成や業務の在り方を調整できるようになります。
なお、チームビルディングの効果を評価するための評価指標は、各自の立場によっても異なります。若手メンバーと中堅メンバー、管理者、経営者の4者の立場における評価指標と、効果の測定方法について見ていきましょう。
若手メンバー:主体性を促す
チームメンバーのなかでも若手メンバーに対しては、主体性を持って業務に取り組めたかどうかが評価の主な指標となります。チームで活動することにより、主体性を発揮できたか、受け身ではなく自分の意見を伝え、適切に行動したかが問われます。
また、チームのなかに内定者が含まれている場合も同様です。まだ社員ではないという引け目から、積極的な姿勢を示さない内定者もいるかもしれません。しかし、主体性を持って業務に取り組む人材であれば、仕事に対しても早めに順応でき、個人が持つスキルを十二分に発揮できるようになるでしょう。
主体性を持って仕事をしているかどうかは、インタビューなどの方法で測定できます。若手メンバーや内定者を対象にインタビューを実施し、仕事への姿勢や、したいのにできていないことなどを丁寧に聞き出しましょう。定期的にインタビューを実施することで、メンバーがチームにより成長した点・成長できていない点を分析できるようになります。
中堅メンバー:リーダーシップの育成
中堅メンバーも、チームビルディングによりポジティブな変化を見せます。若手とかかわることでリーダーシップスキルを育成したり、計画的にビジネスを推進するスキルを獲得したりできるでしょう。
中堅メンバーの成長も、定期的なインタビューによって測定できます。また、インタビューから、自分自身だけでなくメンバーの役割や立ち位置、貢献度などを的確に捉えているかもチェックできるでしょう。
リーダーには、単に集団を率いるだけでなく、メンバー各自を正確に評価することも求められます。次世代リーダーとしての能力を修得しつつあるのか、適時評価しましょう。
インタビューを定期的に実施することが難しいときは、アンケートも有効な測定材料になります。課題に感じている点や成果が得られた点、メンバー各自に対する意見などをアンケートに取り、リーダーや管理者としての能力が育っているか判断します。
管理者:チームの体制づくり
チームメンバーだけでなく、チームの管理者も評価の対象となります。メンバーにビジョンや目標を浸透させているか、また、チームの目標をどの程度達成しているかなどが評価基準になるでしょう。
適切なチームづくりをすることで、チームの目標に到達しやすくなるだけでなく、管理者の指示もとおりやすくなります。管理者そして企業にとって優れたチームにするためにも、管理者の体制づくりを評価することが大切です。
管理者への評価測定も、アンケートやインタビューをとおして実施することが一般的です。また、一方的に管理者を評価するのではなく、管理者がほかのチームの管理者と経験や課題を共有する機会を設けることも、チームビルディングに有益なことといえます。
経営者:ビジョンの発信
経営者にとっても、チームビルディングを評価することは大切なことです。優れたチームビルディングがおこなわれているなら、チームが機能しやすくなり、売上などの目に見える形で成果を得られるようになります。また、会社のビジョンが浸透するだけでなく、社員の企業への愛着が強まり、離職者が減少する効果も期待できるでしょう。
また、優れたチームはほかの社員に対しても影響力を持ちます。チームビジョンや企業ビジョンの発信にもつながり、企業価値の増大も期待できます。
タックマンモデルによるチームビルディングの5段階
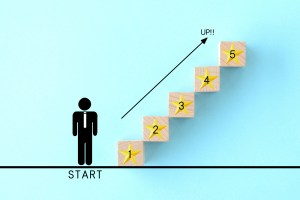
チームビルディングの課題に対処するためには、丁寧なチームづくりが必要です。タックマンモデルとは、チームの成長を5つの段階に分け、1つずつ丁寧にステップアップしてチームとしての成熟を目指すモデルです。
タックマンモデルを活用することで、チームが現在どのような段階にあるかを正確に把握し、目標を達成できるチームへと育成していくことが可能になります。タックマンモデルの5段階と、段階を進めるためのプロセスについて見ていきましょう。
タックマンモデルによるチームビルディングの5段階
- 形成期
- 混乱期
- 統一期
- 機能期
- 散会期
1.形成期
チームが始まる段階を「形成期」と呼びます。メンバーがお互いの個性や能力について理解していない状態で、チームの目標もあまり浸透していません。
メンバー個々はお互いに興味を持ち、遠慮はしつつも少しずつ相手を知ろうと考えています。チームとして次の段階(混乱期)に進むためには、お互いの理解を深めることが必要です。
2.混乱期
「混乱期」とは、チームがお互いについて徐々に理解をし始めたものの、考え方の違いなどから混乱が生まれやすい段階のことです。役割分担や指示系統がまだ明確に決まっていないことから、チームとしてはあまり機能していません。
意見の違いが対立を生むのも、この時期です。対立ではなく、お互いがお互いの意見を尊重するディスカッションが生まれるようになると、次の段階(統一期)に進みます。
3.統一期
「統一期」とは、チーム全体に固有のまとまりが生まれ始める時期です。自然にチームとして行動できるようになりますが、まだメンバーが個性を発揮する段階には到達していません。
統一期には、チームビジョンや目標、メンバー各自の役割などは確立し、チーム内で共有されています。団結して課題解決しようとする動きも見られるようになるでしょう。チーム内で各自が個性を発揮できるようになると、次の段階(機能期)に進みます。
4.機能期
「機能期」とは、チームとしてのまとまりと個性が両立する時期です。前段階ではチームとしてのまとまりはあったものの、まだメンバーがお互いを様子見する段階であったため、個性を発揮することが難しい状態にありました。
しかし、徐々に心理的安全性を確立すると、メンバーが自分の意見を率直に伝えられるようになり、個性を発揮しつつもチームとしての団結力を失わずいられるようになります。また、個性を発揮できるようになったことで、メンバーのチームに対する信頼が増し、団結力も前段階より強まります。
機能期は、5段階のなかでチーム史上最大のパフォーマンスを発揮できる時期です。機能期を長く維持するためにも、リーダーは個々のメンバーをケアし、チームとしてのパフォーマンスを高める取り組みをしなくてはいけません。
5.散会期
「散会期」とは、チームが解散する時期です。よいチームだったとメンバー各自が名残惜しく思うならば、チームビルディングは成功だったと判断できます。

チームメンバーの特性を理解し、タックマンモデルに基づいたチームビルディングを実現するには、次の3つに留意することが必要です。
- チーム目標の明確化
- メンバー役割の明確化
- メンバーの価値観の尊重
チームビルディングの成功は、いかに混乱期や統一期を短縮して早期に機能期に到達し、可能な限り機能期を長引かせることにあるといえます。チーム目標を明確にすると、混乱期の短縮が可能です。またメンバーの役割を明確にすると、指示系統が機能しやすく、機能期へ到達するまでの時間を短縮できます。
メンバーの価値観を尊重し、心理的安全性を確立することも、早期に機能期へ移行するために欠かせないポイントです。チームのまとまりも大切ですが、個性も大切です。各自の個性を尊重できるチームに仕上げるためにも、タックマンモデルを活用して、チームのパフォーマンスを最大化していきましょう。
チームの発展段階に合わせたリーダーシップスタイルとは?

リーダーには、チームの発展段階に合わせて適切な方法でリーダーシップを発揮することが求められます。
チームメンバーがお互いについてあまり理解していない形成期では、リーダーはメンバーの相互理解を深める場をつくり、コミュニケーションを生み出すために積極的に働きかけなくてはいけません。また、リーダー自身がメンバーの個性や強みを理解し、伸ばすためのサポートもおこないます。
混乱期はメンバーの個性がぶつかる時期でもあります。リーダーはかじ取り役を務め、お互いが誤解なく相手を尊重できる場をつくることが必要です。
統一期には、チーム全体のまとまりを強化するための取り組みをリーダーが率先しておこないます。機能期にはリーダーはメンバー個々のケアに注力し、メンバー各自が満足できる状態で、チームとしての業務に取り組めるようにサポートします。
チームビルディングの成功に必要なコミュニケーションスキルとは?

チームビルディングの成功には、メンバー各自のコミュニケーションスキルが欠かせません。各自が積極的にコミュニケーションを取ることで、チームとしての団結力が生まれるだけでなく、お互いの能力や価値観を尊重できるようになります。
また、リーダーもコミュニケーションスキルを発揮することが求められます。業務を丸投げせずに、お互いの意思を反映しつつ、丁寧に進めていくことが必要です。
コミュニケーションの一貫として、ピアボーナス制度の導入も検討できます。ピアボーナス制度とは、お互いへの感謝の気持ちを見える形で贈り合う精度です。チームビルディングの成功だけでなく、メンバーのモチベーションの維持にも役立ちます。ピアボーナス制度の導入については、ぜひUniposにご相談ください。
チームビルディングの成功事例

チームビルディングにおいて成功した事例から、チームビルディングのコツを学べます。たとえばある飲食事業者では、社員数の増加によりコミュニケーションが希薄になり、チーム間の理解がなかなか進まないという状態が見られていました。
そこでSNSによるコミュニケーションツールを導入したところ、情報共有だけでなくコミュニケーションの活性化も進みました。社員同士が打ち解けられるようになり、チームの機能性も高まっています。
また、ある企業では、他部署や他チームとのコミュニケーションが機能せず、常に社内が混乱した状態にありました。そこで会社全体をチームとして捉え、社員全員が利用できるコミュニケーションツールを導入したところ、社内規範が浸透し、各自の役割認識が高まるという効果を得られています。
職場のコミュニケーションを見直してみよう

チームビルディングの成功は、メンバー間やリーダーの積極的なコミュニケーションにかかっています。職場のコミュニケーションを今一度見直し、必要に応じてチャットサービスやSNSなどのコミュニケーションツールを導入することも大切です。
また、ピアボーナス制度の導入も、メンバー間のコミュニケーションの活性化に役立ちます。優れたチームは、企業の発展に欠かせない要素です。ぜひチームビルディングに注目し、企業成長を持続していきましょう。