
初めまして、Uniposの川村と申します!
僕は新卒からピアボーナスⓇ「Unipos(ユニポス)」を提供するUnipos社で働き、間もなく4年目を迎えようとしています。
昨年12月末までの計1年半ほど、UniposのSDR(インサイドセールス)チームでマネージャーを務めていました。Unipos SDRは立ち上げ時には自分を含め2名ほどのチームでしたが、事業成長と共にメンバーが増え、最終的には5名体制のチームになりました。
新卒3年目で4名のマネジメントを任された僕ですが、チームを率いる特別な経験やスキルを持っていたわけではありません。当然ながら人が増えたことでマネジメントの壁にぶち当たり、成果を出せず大いに悩みました。
ただどうせやるからには最高のチームを作りたい!と、それでも諦めずもがき続けた結果、最終的には商談数が前年比4倍まで向上するという、上半期の目標を大きく上回る成果を残すことができました。
チームづくりは一朝一夕にはいきません。チームづくりの大変さを身をもって知ったからこそ、今回の僕の経験が組織づくりに悩める皆さまに何かお役に立てる部分があるのではないか?そう考え、今回この記事を書くことにしました。
この記事はチームや組織のリーダーはもちろんですが、組織をより良くするために少しでも何かしたい!そう思っている全ての方に向けて書いています。
チームづくりは一人の強力なリーダーによってなされるのではなく、メンバー1人ひとりの考え方や、日々のちょっとした言動から作られる。このことを僕は、後にお話する「THE CULTURE CODE」を通したチームづくりを実践する過程で強く実感したからです。
より良いチームづくりを模索する皆さまに、本記事が何かしらのヒントになれば非常に嬉しいです!
メンバーの増加と高い目標値。チームをどう動かせばいいのかわからなかった。

SDRチームを立ち上げた新卒2年目当時、僕以外のメンバーはインターン生が1名のみ。マネジメントにはそれほど苦労していませんでした。
ところが3年目の4月から、新卒メンバーが一気に3名も増加。組織が大きくなり、それに合わせて目標も引き上げられました。一気に増加したメンバーのマネジメントに、高い数値目標。なかなか成果が出せず、どうしたらいいか数ヶ月ほど悩み続けました。
もともと社内にSDRという業務自体がなく、SDRチームを立ち上げたのも自分自身。どうしたら成果の出るUniposSDRチームを作れるのか、社内に相談できる人もあまりいなくて、頭を抱える日々が続きました。
そんな苦しい状況のなか徐々に見えてきたチームの課題は「メンバーは皆やる気に溢れ、個々人の能力も優秀だが、チームの目標数字を達成することへの意識が弱い」というものでした。
課題が見えたのはよかったのですが、僕自身も3年目、決して経験が豊富なわけではありません。「やばい!自分自身、それほど経験もない。あれやこれやと色々指示をして、トップダウンで成功に導ける自信もない。どうすれば自律的なメンバーを育てて、チームの目標を達成できるのだろう。」
課題を解決するために具体的にどんなことをして、どうメンバーを動かせばよいのか。まったく分からず、途方に暮れていました。
でもやっぱり、最強チームを作りたい
「メンバーとリーダーが一体になって、自律的に動きながら、継続的に成果を出せるチーム」
これが僕の理想とする最強のチームです。最強のチームは最高の成果を出すと信じてます。
もともとチームづくりに関心があり、どうせやるなら理想のチームを作りたいという気持ちを強く持っている方でした。辛い状況でも諦めず試行錯誤を続けることができたのは、その想いがあったからだと思います。
ここからどうやったら最強チームを作れるだろうか?まずはいくつかの本を手に取り、打開策を探しました。
例えば、読んだ本の一つにタックマンモデルという組織づくりのフレームワークがあります。それは、チームの成長を「形成期」「混乱期」「統一期」「機能期」「散会期」という5つの段階に分けて取り組んでいくものです。
なかでも、重要と言われているのが混乱期をどう乗り越えるかです。そのような時期に、リーダーに求められるのは、メンバー間の正しい衝突をチームの中にもたらし、本音で意見や価値観の違いをぶつけ合い得る環境を作り出すことです。
その後、チームを再構築することで、より一層強くしていくということがこの「混乱期」の狙いです。
しかし、メンバーと年次もそこまで変わらず、そうした方法を好まない僕自身の性格を考えて、合わないなと思いました。とはいえ参考になることも沢山ありましたので、その中から実践したこともあります。
これだ!と思えるものに出会うまで様々なところから知識を得て、取捨選択を繰り返していました。
では、もっと平和的に、再現性のある組織の作り方はないか?

そんな中出会ったのが私の組織づくりのバイブル、ダニエル・コイル著『THE CULTURE CODE-最強チームをつくる方法-』です。
この本は同僚との他愛のない会話の中で「この本、組織づくりにおすすめだよ!絶対気に入ると思う。」と言ってもらったことがキッカケで、すぐにAmazonで購入しました。(余談ですが、Cultureの語源となったラテン語「Cultus」。これは「Care(気に掛ける)」という意味だそう。)
読んだ瞬間、これが自分が求めていた友好的な組織づくりの方法だと感じました。特別なスキル、能力、経験など必要とせずとも、誰もが組織をこんなにも変革させられるのだと感動しました。
本書では最強組織の事例を多数紹介すると共に、そうした組織に必要な要素を徹底的に研究しています。成功事例のみならず、組織を破壊するような人間をこっそりチームに派遣して、その後どうなるのかを観察した実験なども取り上げられていて、非常に興味深いです。
例えば、そのうちの一つに「腐ったりんごの実験」というものがあります。
とある組織に、ニックという男性が派遣されました。ニックは、わざと怠けたり、周囲を暗くしたり、性格悪く振る舞ったりすることで、組織を恣意的に壊すことに務めました。そうすると、必ずニックが所属するチームのパフォーマンスは30〜40%低下することがわかりました。
しかしながら1チームだけ、ニックがどう頑張って組織を悪い方向に導こうとしても全くパフォーマンスが落ちないチームがありました。
なぜそのチームだけパフォーマンスが落ちなかったのか?様々な角度からそのチームを調査した結果、原因はなんとジョナサンという、なんの変哲もない1人のメンバーだったのです。
ジョナサンは、飛びぬけて何か凄い能力を持っているわけではありませんでした。ただ彼は、いつも穏やかな態度を絶やさず、メンバーが発言した際にはその意見に熱心に耳を傾け、「君ならどう思う?」と他のメンバーにも意見を求めることが常でした。
彼はニックの否定的な意見や振る舞いを前にしても、変わることなく普段どおりの穏やかな態度を貫き「君ならどう思う?」と他のメンバーにも意見を求め続けました。
ジョナサンは「強いリーダー」という像からはかけ離れているものの、研究の結果そうしたジョナサンの小さな行動がチームに安全、安心な環境を提供していることがわかったのです。ジョナサンによって安全、安心な環境が守られたことで、チームはニックの悪影響を受けることなく、パフォーマンスも低下せずにいられたわけです。
この事例から、組織は強いリーダーやたった1人の英雄によってつくられるのではなく、メンバー1人ひとりの日々の考え、ちょっとした言動によってつくられるのだということを知り、感動を覚えました。
最強チームを作る上で必要なことは3つだけ
そんな『THE CULTURE CODE』が提唱する、最強チームをつくる原則は以下の3つです。
・ 安全な環境
・弱さを見せる
・共通の目標を持つ
たったこれだけです。とてもシンプルじゃないでしょうか?
1つ目の「安全な環境」は、チーム内のつながりを強固にし、チームの帰属意識やアイデンティティを育てることに繋がります。
2つ目の「弱さを見せる」は、互いに弱さを見せあうことで、チームの信頼関係をつくり出します。
最後に3つ目の「共通の目標を持つ」ことで、チーム内の共通の価値観を作り上げ、目的意識の高い組織を作り上げることが出来ます。
実際にこの3つを徹底的に意識した具体的な施策を実行していくことで、僕のチームは大きく変わっていきました。
最強チーム3原則を踏まえて実践したこと
本書を読んですっかり感動し、確信を得た僕は、素直に最強チームを作るために必要なことは3つだけと信じて、本書の事例等を参考に様々なことを実践しました。その中から、特にこれは実践してよかったなと思えるものをご紹介します。
1. 安全な環境
1-1. まずは自分が徹底的にその人の存在を承認する
「まず今のあなた自身を認めているよ。」と面談の場で伝えていました。
こう言うと中には「え、今のままでいいって、成長しなくてもOKってこと?」と思われる方もいるかもしれませんが、それはもちろん違います。
チームが成果を出すためには、メンバー1人ひとりの成長が必須です。
ただ、メンバー1人ひとりには当然それぞれの性格があり、得意・不得意もあります。僕としては、そうして個人がありのままで持っているものを、まず大事にして欲しかった。
「できない」「足りない」部分を補う、欠点を克服していくのももちろん成長だけど、その一方で「ありのままの自分でいいよ」と認めてもらえることで「もっとこうした部分を伸ばしていきたい!」「こういうことをやっていきたい!」という、ポジティブな気持ちからの成長意欲を持ってもらえるのではないかと考えたからです。
それはかつて僕自身が「これができない、アレができない」と欠点を克服する成長にばかり囚われ、ポジティブな気持ちからの成長意欲がなくなり、非常に辛い想いをした経験があったからです。
だから「まず1人の人として、そのままのあなたでいいよ、『変わらなければならない』ことは1つもないよ」とメンバーに伝え、その上でメンバー自身が望むキャリアや成長を支援するようにしていました。
また、何かメンバーが成果を出したときは「すばらしい!」「最高!」と言いながらハイタッチも交えて称賛していました。
はじめは皆恥ずかしがっていましたが、少しずつ慣れてくるとメンバー同士も相互に褒めあったり、Slack上で「すごい!」「おめでとう!」といった言葉を掛け合う頻度が増えていきました。
1人の人間としてありのままでいいと伝えること、メンバー同士が互いを承認し合うようになることで、チームの空気は目に見えて明るくポジティブになっていったと思います。
1-2. 何かあれば守るぞ、という覚悟と行動を示す
SDRチームはUniposに興味を持ってくださったお客様に電話を掛け、Uniposがどの様にお役に立てるのかを探るため、組織状況や課題を詳しく伺います。
そうした中、互いの行き違いなどが原因で、お客様からご指摘をいただくこともゼロではありませんでした。そんな時は僕がすぐに出ていき、メンバーに代わって対応すると決めていました。
誰でもミスや失敗はします。
社会人になりたて、かつお客様に電話を掛けること自体が初めてのメンバーばかりでしたが、日々精一杯業務に取り組んでくれていました。そんな中、不慣れな経験からミスや失敗をした時リーダーが助けてくれず、全て自分で対処せねばならないとなったらどうでしょうか。メンバーは萎縮して、失敗を怖れる様になり、そのあと新しい挑戦や改善をしにくくなってしまうのではないでしょうか。
ミスや失敗をしても大丈夫。何かあったら自分が守る。だから安心して働いて、思い切ってチャレンジして欲しい。複雑な対応が発生した時はすぐに自分が出ていくことで、それを伝えられるのではないかと思っていました。
実際、そうした態度を示し続けることで、はじめは電話することに抵抗を覚えていたメンバーも、徐々に安心して業務に取り組んでくれるようになったと思います。そしてメンバーが安心して働くようになるにつれ、チームには自発的な改善・工夫が増えていきました。
1- 3. 接触回数を増やし、メンバー同士でも互いの相互承認を促進する
チームで毎日必ずミーティングをしていました。
輪になってお互いの顔を見ながら誰かを否定することなく、会話の回数を増やし、接触機会を最大限作ることに努めました。時には「PCを閉じよう!」と呼びかけて、それぞれの話や共有事項に耳を傾けて、質問をしたり意見を出してもらうような環境を作っていました。
多くのIT企業では、各人が手元でPCを開いてミーティングを行うのが基本ではないでしょうか。PCを閉じて相手の話に耳を傾けると、普段よりもずっと相手の細かな変化に気が付きますし、発言の意味をより深く理解することができます。
たまにこうした工夫を取り入れることで、メンバー同士が互いに対して、より丁寧な関心を向けられるようになったと思います。
2. 弱さを見せる
2-1. 弱さは、まずリーダーが見せる
できていないことは強がらず「俺もできないから一緒に協力してほしい。一緒に解決していこう。」と伝えていました。
また、定例会議の最後に一言コーナーを設け、そこで日常の失敗や、他愛のない話、業務上の失敗も率先して共有していました。
リーダーや上司と言えど同じ”人間”なので失敗することもあるよね、と理解してもらえたように思いますし、何よりメンバー自身も、失敗を共有しやすい環境を作れていたのではないかと思います。
3. 共通の目標を持つ
3-1.適切な目標設定(KPI/KGI)と背景を説明する
当初は商談数をKPIにしていたのですが、各メンバーが具体的な改善行動を取りにくいという状況が発生してました。なぜなら、商談を構成する要素が複雑化しているため、何から着手していいか分からなくなってしまっていたからです。
より適切でシンプルなKGIやKPIに近づけるべく、思い切って商談数をKGIとし、架電数・通電数・通電率をKPIに変更することにより改善行動を促しました。
そうすることで、メンバーが以前に比べて、積極的に各KPIをどう改善するべきなのかという意見を発信してくれるようになったと思います。また、そのKPI設定自体が適切なのかといった議論もチーム内でできるようになりました。
3-2. 数値計測を自動化する
共通の目標を常に可視化するために、Salesforceのレポート機能、ダッシュボード機能やスプレッドシートを活用して、KPIやKGIの実績と目標が自動で最新の状態で管理できるようにしていました。
デイリーMTGではこういったレポートやダッシュボードを全員で見ながら数字の進捗を確認していました。目標数字を何としても達成してやろうという意識付けの助けになっていたと思います。
3-3. 目標設定の背景を伝達し、チームのObjectiveを設定する
上記のような数字だけのコミュニケーションだと、何の目的ためにこの数値を追いかけているかが伝わりづらいので、我々のObjective(チームの存在目的)を言語化し伝達していました。
単に「商談をとる」とかではなく、Uniposのビジョンやミッションを実現するために我々はどういう領域に責任を担っているのかを伝えることを大切にしていました。我々のチームは「Unipos事業全体の最適化へ貢献する、良質商談の定常供給集団になる」とObjectiveを設定していました。
これはモチベーション向上に大きく影響を与えると思います。業務レベルの抽象度で仕事を捉えてしまうと、メンバーによってはモチベーションを保つのが難しい可能性があります。なので、我々が業務を通して成し遂げたい理想の姿をチームの中で言語化しておくことを大切にしていました。
★Uniposもこまめに活用
手前味噌になってしまいますが、自社のプロダクトUniposにはかなり助けられました。
些細なことから大きなことまで僕は何かにつけメンバーにUniposを送っていて、こまめに感謝・称賛を伝えることが、安全な環境を醸成するのに一役買ってくれました。
Uniposを送るときには行動自体を称賛するだけでなく、できるだけI(アイ)メッセージを用いて、自分自身がどのように嬉しかったのか、どんな風に感謝しているのかを伝えるように工夫していました。



更に嬉しかったことは、メンバー同士もとても活発にUniposを送り合っていることでした。メンバー同士が互いに認め合い、信頼し合うことで、チームのつながりはより強くなっていったように思います。
「Unipos」の詳細資料ダウンロードはこちらから
実践する上でのポイント
ここでは僕が具体施策を行っていくにあたって、大切にしていたポイントを紹介します。
1.3ヶ月間継続できるかどうか
最強のチームを作りは一朝一夕に成し遂げられるものではありません。それが故に、チームづくりのために何かしらの取り組みをすると決めたら、ある程度の期間続けることがとても大事だと思っています。
過去の経験から、やろうと決めた取り組みが途中でうやむやになり消滅、といったことを繰り返すと、チームには「新しいこと始めても、どうせ中途半端になっちゃうんじゃ…」と半ば諦めるような空気が流れることを知っていました。こうした空気感の中で、チームが良くなっていくのは困難です。
具体的な施策や行動をチームで実施するときには、「これを3ヶ月間続けられる工数があるか?インパクトがあるか?」を自分とチームに問うて意思決定をしていました。
2.迷っているなら、実践して振り返る
意外と考えればいろんな施策が出てきます。そんなときに、本当に意味があるのか?成果に直結するのか?と迷いが出てくることもあると思います。
その迷いを抱くことは健全ですが、勇気を持って一歩を踏み出さなければ何も変わりません。
まずはやってみる、それでもやっぱりチームに良い影響がない、成果が出ないということであれば、またその時考えれば良いと思うのです。
完璧を目指すのではなく、目の前の課題に着手することが何よりも価値のあることだと思います。
「目標達成への意識が弱かった」チームが歴代商談記録を3度も更新

最強チーム3原則に沿った実践を続けることで、チームは変わっていきました。「チームの目標を達成することへの意識が弱い」。当初抱えていたそんな課題も、気付けば全員が強い目標達成の意識を持ち、自律的な行動を起こせるチームに変わっていたのです。
Unipos SDRの歴代記録を塗り替える商談数を達成した時のことは忘れられません。達成するかしないか、ギリギリの状況の中チーム一丸となって走り抜け、達成した瞬間メンバーの1人は号泣しました。僕も泣きたいくらい感動していましたし、チームの成長を実感できて本当に嬉しかったです。素晴らしい瞬間でした。
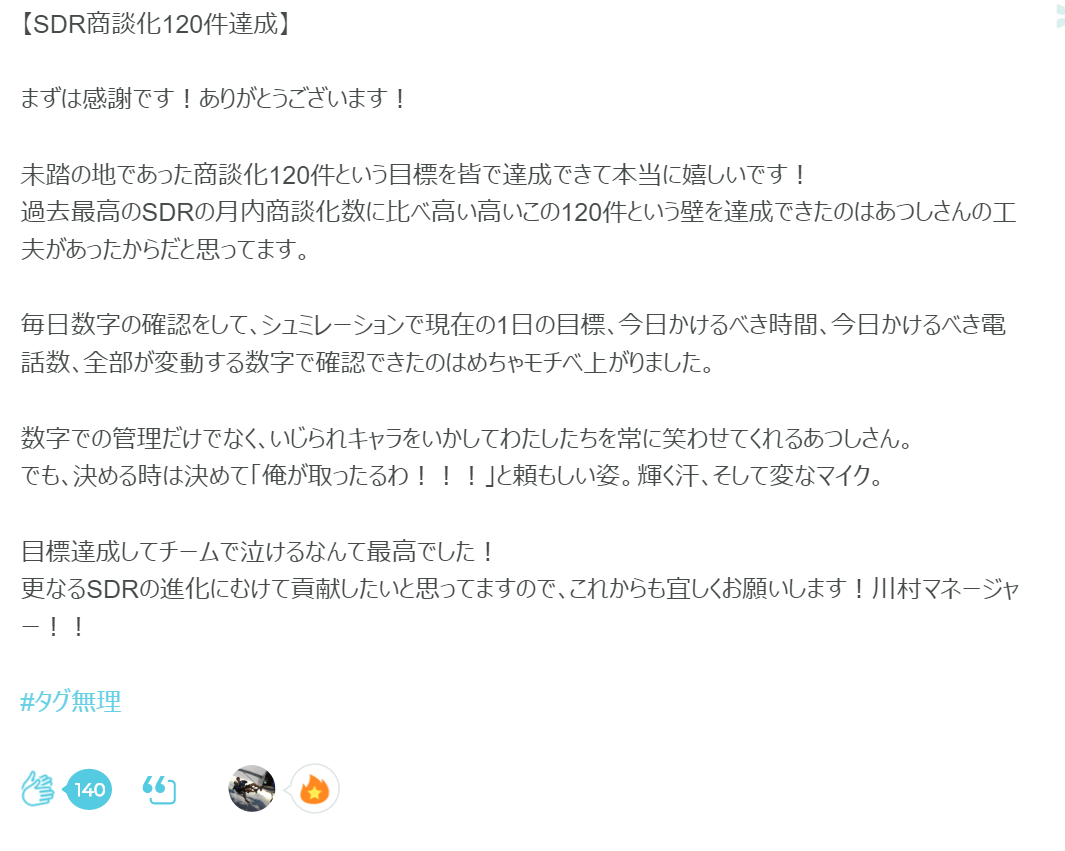
「Unipos」の詳細資料ダウンロードはこちらから
そして改めて僕らのチームの変化を定量面・定性面から振り返ってみると、以下のようにまとめられるかなと思います。
定量的
・ 商談数は前年比の4倍(商談数ギネスを3度更新)に向上
・ チーム全員の生産性/稼働量(架電数)の各指標が約6倍に向上
・上半期トータル商談数目標達成
定性的
やはり、目標達成への意識が弱かったチームが強い目標意識を持ち、メンバ―1人とりがその達成に向け、自律的に行動できるようになったことが一番大きな変化です。
ここが変わることで、僕らのチームは成果を出し続けるチームに生まれ変わることができたと思います。
メンバーが目標達成のため、自ら動き実行してくれた取り組みの一部をご紹介します。
- 架電数の向上を図るため、「Dialpad」というIP電話ツールの導入を提案・実行
- 架電の稼働量を向上させるため外部パートナーの方々との強力体制を構築
- 展示会の名刺管理のより良い方法を考案し、実際のオペレーションに組み込む
目標達成のために今どんなことをすべきか、どのような改善が必要か、常にメンバー1人ひとりが考え実行したこれらの取り組みは、チームの成果を上げるのに大きく貢献してくれました。
そしていつの間にか、他部署や他企業の方々からまでも「SDRっていつも雰囲気いいよね!業務大変そうなのになんで?」と言われるようになり、実際にメンバーからも「このチームで働けてよかった」と言ってもらえるようになりました。
それだけでも凄く嬉しいのに、その内のメンバーの1人が「次のSDRチームのリーダーをやりたい」と言ってくれた時には本当に涙が出るくらい嬉しかったです。そのメンバーは現在、本当に僕のあとにチームを引継ぎ、Unipos SDRの新たな歴史を築いてくれています。
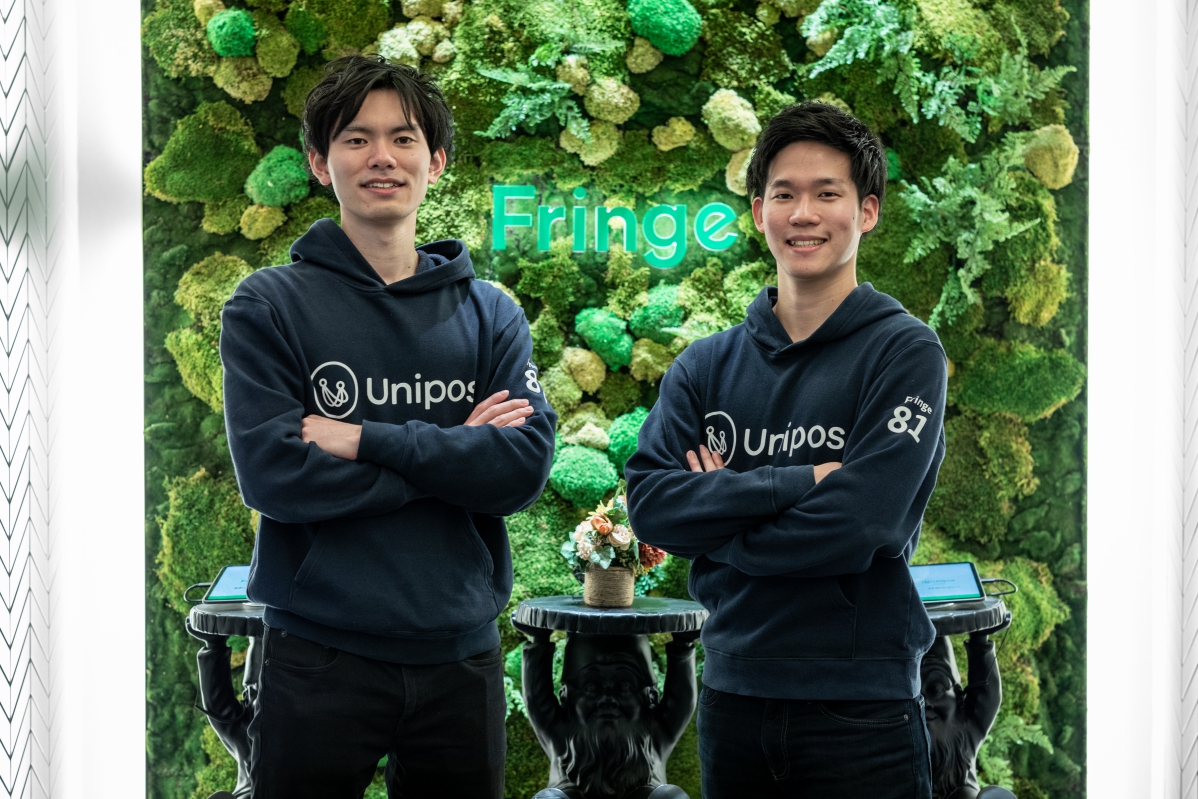
最後に
ここまで読んでいただきありがとうございました!
改めて、SDRを最強のチームにすべく一緒に駆け抜けてくれたメンバー、これまでいろんなことを教えてきてくれた先輩方に感謝します。
今もチームづくり、組織づくりについて、先輩をはじめ様々な方と話をしますが、やはり全てに効く正解はないと思っています。様々な方法やノウハウの中からそのチームや個人の特性に合わせてカスタマイズするのが基本で、実践・検証が絶対的に必要です。
少しでもこの記事に共感いただけたら、お伝えした3つの原則やポイントを参考に「自分のチームでは何ができるだろうか?」を考え、チームで議論していただくことほど、僕にとって嬉しいことはありません。
最後に、チームはリーダーのものではなく、みんなのものです。
今回の経験を通して、僕はこのことを何よりも学びました。
だからどうか、チームの中ではあなたが「誰」であるかということよりも、「何」をするかということを大事にしてください。
僕は今新たに、Unipos社・親会社Fringe社も含めたFringeグループ全体を自分のチームとして捉えた時、どうしたら最強チームを作れるのか、そんな新しいチャレンジに向かって歩み始めています。
まだまだ未熟な僕ですが、これからもより良いチーム・組織をつくるべく、試行錯誤していきます。
皆さまも一緒に、それぞれの場所で、最強チームを目指し続けていきましょう!


