
事なかれ主義について調べているあなたは「もしかして、ウチの会社って事なかれ主義…?」と不安に感じているのではないでしょうか。
例えば、こんなお悩みはありませんか。
・業務上の問題に気付いても、見て見ぬふりをする部下がいて困っている
・会議で積極的に発言する社員が少ない
・最近の若い世代は、当事者意識が希薄だなと感じる
実は、こういった悩みが発生するのはごく自然なことです。一社にしがみつかなくても多様な働き方が容認されるようになった現代では、従業員の当事者意識が希薄になり、事なかれ主義が増えるのは当然の流れといえるでしょう。
このまま放置すれば、事なかれ主義が企業文化として定着してしまい企業の弱体化を招くのは時間の問題です。
その前に何としても職場の事なかれ主義を防ぐアプローチを行う必要があります。加速する職場の事なかれ主義にブレーキをかけ、事なかれ主義の対義である「当事者意識・我が事感」を醸成する人材マネジメントに注目が集まっているのはそのためです。
この記事では、まず職場の事なかれ主義について徹底的に分析します。
・事なかれ主義とは?その特徴は?
・事なかれ主義に陥る人の心理状態とは?
その上で、事なかれ主義の予防に効果的な対応策を解説します。当事者意識を高める取り組みの先進企業として「メルカリ」の事例を取り上げながら、どうすれば職場の事なかれ主義をなくすことができるのかを明らかにします。
最後まで読んでいただければ、事なかれ主義をあなたの職場から遠ざけることができます。そして、会社の問題を自分事として捉えて動く強いチームづくりの秘訣がわかるでしょう。さっそく続きをご覧ください。
1.事なかれ主義とは波風立てない消極的な態度のこと

事なかれ主義とは、「いざこざがなく、平穏無事に済みさえすればよいとする消極的な態度や考え方(デジタル大辞泉)」を指す言葉です。
一見「何が悪いの?」と感じる人もいるかもしれません。しかし実は多くの問題をはらんでいます。
“物事を平穏無事に済ませようとすること”自体は決して悪いことではありません。
例えば、職場で意見が対立したときに「ここはいったん自分が引いた方が全体のためになる」と考え、相手の意見を容認する——といった経験のある方もいるでしょう。
しかし、事なかれ主義者の場合、平穏を求める目的が「自分の地位を守るため」「自分がやっかいごとに巻き込まれないため」など利己的であることが、大きな特徴です。
詳しくは次章で解説します。
2.事なかれ主義者の3つの特徴

事なかれ主義の人の特徴を3つに分けて、詳しくご紹介します。
2-1.特徴①保身に走る
1つめは「保身」の意識が強いことです。自身の評価が悪くなることや、地位が脅かされることを何よりも嫌います。
例えば、事なかれ主義の人は、業務上のミスに気付いても申告せずに、誰かが指摘するまでそのまま放置することがあります。ミスのせいで、自分の評価が下がることを恐れているのです。
2-2.特徴②当事者意識が希薄
2つめは「当事者意識」が希薄であるということ。身近で起きている問題に当事者として対応するのではなく、どこか他人事のように眺めているところがあります。
例えば、会議でディスカッションが行われていても、積極的に参加しようとしません。AかBかと意見を求められても「どちらでもいい」という態度です。
2-3.特徴③消極的で行動力に欠ける
3つめは「消極的」で行動力に欠けるということです。行動を起こして波風が立つのが嫌なので、できる限り何もしないでやり過ごそうとする省エネ体質なところがあります。
例えば、自ら新しいアイデアを提案したり、改善策を考えたりすることがありません。基本的に、いつもと同じ業務を淡々とこなすことを好みます。
3.職場で起きる問題の事例

事なかれ主義の人には3つの特徴があることがわかりました。では、職場での事なかれ主義は、どのような問題を引き起こすのでしょうか。実際に職場で起きた事例をご紹介しましょう。
3-1.ケース①部下が事なかれ主義で仕事に責任を持たない
1つめのケースは上司目線での事例です。
|
部下が事なかれ主義で、当事者意識が薄く何を話しても他人事のような顔。ミスが発生していても気付かない振りをしたり他の人に事後処理を押しつけたり、チームの士気も下がるので困っている。 |
この事例では、部下が事なかれ主義のため、ミスに気付いていてもスルーしています。さらに、自分さえ良ければ良いという考えに陥っており、全体の利益を考えることができないため、チームの士気を下げてしまうのです。
まとめると、事なかれ主義によって次の2つの問題が起きています。
①ミス発覚の遅れ
②チームのモチベーション低下
3-2.ケース②上司が事なかれ主義でトラブルを解決してくれない
1つめのケースは部下目線での事例です。
|
上司が事なかれ主義で、チーム内でトラブルが起きているのに見て見ぬ振り。人間関係が悪化してギスギスしているのは明らかなのに何もしてくれない。直接何度か訴えたのに、変わらなかった。 |
この事例では、上司がチームの問題を見て見ぬ振りをしています。「やっかいごとに巻き込まれたくない」という気持ちが強いようです。部下たちにとって、改善を訴えても対応してもらえないという失望は、信頼問題に関わります。
また、この上司は単に問題を先送りにしているだけなので、時間の経過とともに解決は難しくなっていくばかりです。
まとめると、事なかれ主義によって次の2つの問題が起きています。
①部下からの信頼感の損失
②社内の問題の先送り
以上、ケース①とケース②に共通していえることは、職場の事なかれ主義はミス・トラブルの発覚や対応を遅らせるとともに、社内の雰囲気を悪くするということです。
4.職場で事なかれ主義に陥っている人の心理
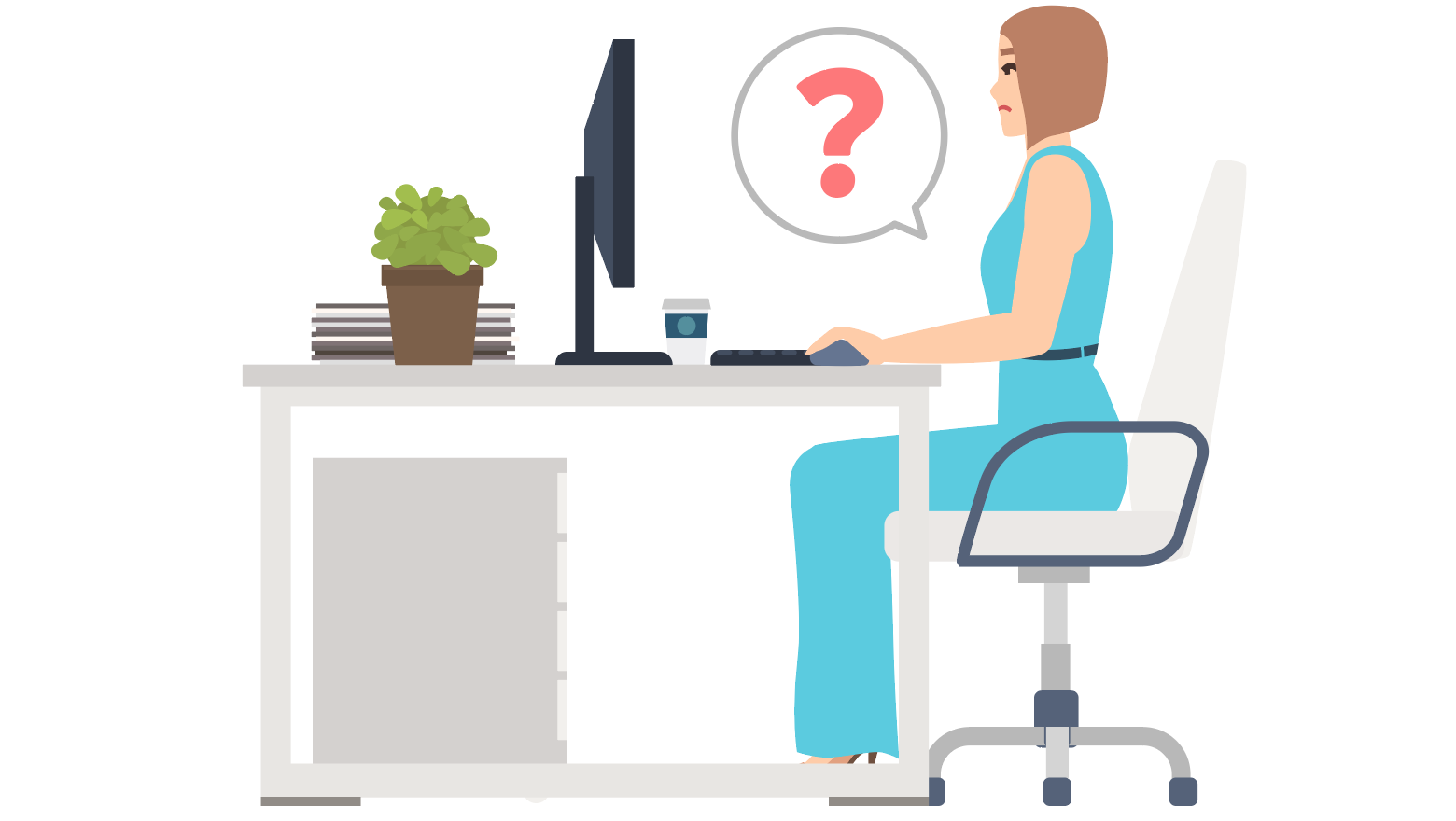
職場で事なかれ主義な態度を取る人は、どうしてそうなってしまったのでしょうか。もちろん、元々の性格による部分もあります。しかし、多くは職場環境に依存しているのです。
つまり、もともと事なかれ主義ではなかった人が、職場での経験を経て、事なかれ主義へ変わってしまうことがあるということです。
職場に事なかれ主義の人がいる場合、まずはその人の資質を責めるのではなく「事なかれ主義にならざるを得ない要因が、職場環境にあったのでは?」と振り返ることが大切です。
そのヒントとして、事なかれ主義に陥っている人がどんな心理状態にあるのか、見ていきましょう。
4-1.心理①声を挙げて損するのが嫌
1つめは「声を挙げて損するのが嫌」という心理状態です。職場で下記のような経験をすると、陥りやすくなります。
・新たな提案をしたら、その業務が全部自分に降りかかって大変な思いをした
・問題点を指摘したことがきっかけで人間関係が悪化した
・失敗を正直に申告したら不当な人事評価を受けた
このケースでは、最初は善意で「会社のために」という思いで声を挙げています。ところが、その純粋な気持ちが踏みにじられる経験をすると、その失望感から事なかれ主義に転じやすくなるのです。
4-2.心理②険悪なムードを恐れて萎縮している
2つめは「険悪なムードを恐れて萎縮している」という心理です。職場で下記のような経験をすると、陥りやすくなります。
・やむを得ないミスを上司から強い口調で叱責された
・トラブルが起きたとき犯人捜しが始まってチームの雰囲気が悪くなった
・問題が起きたとき同僚が不機嫌になり当たり散らされた
このケースでは、険悪なムードになったことが心に強いトラウマを残しています。「もう二度とこんな思いはしたくない」という恐怖心から、事なかれ主義になびきやすくなります。
4-3.心理③組織・チームとしての目的意識が持てない
3つめは「組織・チームとしての目的意識が持てない」という心理です。職場で下記のような経験をすると、陥りやすくなります。
・会社の問題に一生懸命に取り組んだのに評価されず失望した
・上司の言動から自分はただの駒としか見られていない無力感を感じた
・会社が大きくなりすぎて仕事をしている実感が持てない
このケースでは「やりがい」が感じられないことが、仕事に対する姿勢に影を落としています。「どうでも良い」という投げやりの態度から、事なかれ主義へと陥っていきます。
5.職場の事なかれ主義を防ぐ4つの対策

職場での経験によって、誰しもが陥る危険性のある「事なかれ主義」。事なかれ主義を職場からなくしていくために、どんな対策をしたら良いのでしょうか。
具体的な4つの対策をご紹介します。
5-1.失敗をマイナス評価に直結させない人事評価
1つめの対策は「失敗をマイナス評価に直結させない人事評価の導入」です。「失敗がバレると評価が悪くなる」と強く感じさせる職場では、多くの従業員が事なかれ主義へ傾きやすくなります。
減点評価(業務上のミスや目標未達などのマイナスを減点する)ではなく、加点評価(目標達成や会社への貢献などのプラスを加点する)の方が、事なかれ主義の予防という観点からは有効です。
最近では、GEが有名な人事評価モデル「9ブロック」を廃止したことが話題となりました。世界では、加点評価への移行どころか、従来の評価制度そのものを廃止する動きがあることは、特筆すべき点です。
5-2.チームの成果を個人の成果とする仕組み
2つめの対策は「チームの成果を個人の成果とする仕組み作り」です。
「自分さえ良ければいい」と従業員が利己的な視点に陥るのを防ぐためには、チームの評価が個人の査定に反映される仕組みが大変有効です。
日本国内では2000年頃から「成果主義」がもてはやされました。しかし、成果主義には「個人の成果につながらない業務には、事なかれ主義的な勤務態度の従業員が増える」というデメリットがあります。
現在では「個人評価+チーム評価」のダブルで行う人事評価を採用する企業が増えています。従業員が「チームの利益」「会社の利益」を考えられるように導くことができるので、事なかれ主義の予防に効果的です。
5-3.心のつながりを可視化する制度
チームワークへの興味が薄く他人事感が強いチームの空気を変えるためには、心のつながりを可視化する仕組みの導入が効果的です。
特におすすめなのが「ピアボーナス」です。ピアボーナスは、従業員同士が感謝の気持ちをボーナス(お金)を贈り合うことで表現できる制度です。
Google、メルカリ、VOLVOなど、人材マネジメントに力を入れる企業が続々と導入したことで話題になりました。
ピアボーナスは、目に見えなかった「感謝の気持ち」をボーナスとして可視化できることが特徴です。「自分は仲間から認められている」という実感を得やすくなる効果があります。
やりがいが感じられずに事なかれ主義に陥っている人にとって、「この企業で働く意味」を改めて見いだすきっかけとなるはずです。
5-4.安心して発言できるチーム環境の整備
上司からの強い叱責やチームが険悪になることを恐れる傾向が強い人が事なかれ主義から抜け出すためには、安心して発言できるチーム環境を整備する必要があります。
トラブル・失敗の報告や改善案の提言は、時にネガティブなニュアンスを含むこともあるでしょう。マイナスの発信であっても安心して行うことができる関係性を、日頃から構築しておくことが大切です。
そのために役立つのが「心理的安全性」の考え方です。心理的安全性とは、「ネガティブな反応が予想される行動をしても、このチームであれば大丈夫」と信じられるかどうかを意味する指標のことです。
心理的安全性を高めることは、事なかれ主義を遠ざけることにつながります。心理的安全性の詳細や高める方法については『心理的安全性を測定する方法とGoogleに学ぶ心理的安全性の高め方』をご覧ください。
6.事なかれ主義を“我が事感”に変えるメルカリの取り組み事例

「事なかれ主義」の真逆にあるともいえるのが、「我が事感」というフレーズです。我が事感をキーワードに組織づくりを行っているメルカリの事例をご紹介します。
急成長を続けるメルカリは、月に多いときで50名ものメンバーがジョインします。
その中で「会社が大きくなっても、遠くにいるメンバーのことを知り、興味を持ち、会社で起きていることに我が事感を持ち続ける組織であってほしい」(株式会社メルカリ HRグループ 高橋寛行氏)という思いから、数々のコミュニケーション施策が運用されています。
<メルカリのコミュニケーション施策の一例>
|
シャッフルランチ |
メルカリ全社員からランダムに組み合わせた5〜6名のチームでランチを行い、他部署交流の場として活用 |
|
TGIM |
毎月1回・月曜日に開催される軽食をつまみながら親睦を深める場 |
|
Global Donuts |
ドーナツを食べながら日本のメンバーと海外のメンバーが交流し互いへの理解を深める |
|
メルチップ |
ピアボーナスツール「Unipos」のweb・アプリを使って感謝の言葉にちょっとしたボーナスを乗せお互いに送り合う |
組織として具体的な制度を準備することで、事なかれ主義とは対極のチームを作る試みは、多くの企業にとって参考になるのではないでしょうか。詳しくは「メルカリメンバーが会社の出来事に“我が事”感を持つ理由」をご覧ください。
7.まとめ
事なかれ主義は「 いざこざがなく、平穏無事に済みさえすればよいとする消極的な態度や考え方」を指す言葉です。
事なかれ主義者には、下記の特徴があります。
①保身に走る
②当事者意識が希薄
③消極的で行動力に欠ける
職場の事なかれ主義を放置しておくと、問題の先送りやミス発覚の遅れ、チーム内の信頼感やモチベーションの低下を引き起こします。
そこで対策として、下記を行いましょう。
①失敗をマイナス評価に直結させない人事評価
②チームの成果を個人の成果とする仕組み
③心のつながりを可視化する制度
④安心して発言できるチーム環境の整備
メルカリでは「事なかれ主義」の対極にある「我が事感」をキーワードに、さまざまな施策を行っています。ぜひあなたの会社でも、事なかれ主義を遠ざけるための試みをスタートしてみませんか。
今まで突破できなかった壁を容易に飛び越えられるような、強いチームへの第一歩が始まります。


