
企業が成長するために、役立つ手法として知られている「1on1ミーティング」。
海外はもちろん、日本においてもヤフーが1on1を導入したことにより、注目が高まりました。
なかには「自社でも1on1を実践してみたい」と思っているものの、やり方がわからないという人もいるのではないでしょうか。
そこで、この記事では1on1の概要やヤフーが実践した1on1のやり方について解説します。
1.そもそも1on1とは?

ビジネスシーンにおいて1on1はよく耳にする言葉ですが、具体的にどのようなものなのでしょうか。ここでは、1on1の概要について見ていきましょう。
1on1の概要
1on1とは、その名前の通り上司と部下が1対1で行う定期的なミーティングのことをいいます。
一般的には、ティーチング・コーチング・フィードバックなどの要素を使い分け、部下に対してアプローチを行っていきます。
1on1は短時間の面談を高い頻度で実施することが基本です。企業によっても異なりますが、おおむね15~30分程度の時間を設けるケースが多くみられます。
頻度は毎日・毎週・毎月などさまざまです。多くの場合は週に1回、少なくとも月に1回は実施します。
1on1の目的
1on1は対話を通じて部下自身に気付きを促し、能力を引き出すことが主な目的です。
リラックスできる雰囲気のなかで日々の業務における成果や失敗について共有し、フィードバックの場を設けます。
簡単にいうと、仕事で成功したこと、反対に失敗したことを上司が聞き出し、そこから「何を学び、得たのか」のを引き出すことを重視しています。
日々仕事に追われているとその対応だけで手一杯になり、その仕事から何を学習できたのかがわからなくなってしまうものです。
学習したことを言語化しないまま日々を過ごしていても、個人の成長スピードはあまり上がりません。このような事態を防ぎ、社員の成長スピードを上げるために1on1が活用されます。
部下の成長機会を作り、生産性向上や信頼関係の構築などを目指すうえで1on1は非常に有効なアプローチ方法と言えるでしょう。
評価面談との違い
1on1について調べているときに「評価面談とどう違うのだろうか」と疑問を持つ人もいるでしょう。1on1も評価面談も、上司と部下が1対1で対話することに違いはありません。
しかし、両者は実施する目的や頻度に違いがあります。前提として、評価面談では上司が主体となることが基本です。
部下に対して一方的に評価を行い、目標や進捗について確認することが主な目的となります。部下が持つ仕事への課題や悩みなどは面談の場で重視されません。
一方、1on1では部下が主体です。評価や業務管理を目的とした評価面談とは異なり、1on1は部下の成長をサポートすることを目的としています。
1on1を通じて、上司は部下がどのような課題や悩みを抱えているのか、また将来像を描いているのか把握し、それを支援します。
つまり、1on1は上司と部下が対話し、フィードバックを通じて一人ひとりの個性や能力を引き出す場として活用されるのです。
また、実施する頻度も大きく異なります。評価面談は通常、四半期や半期に1回行うケースが多いでしょう。
一方、1on1は最低でも月に1回は実施します。四半期や半期に一度では、なかなか部下が持つ悩みや課題をリアルタイムで把握できません。
すると、問題の把握と解決が遅れ、生産性が低下する原因につながります。
1on1のように高頻度で対話する機会を設けることで、行動改善のサイクルスピードが向上します。その結果、部下が成功体験を積みやすくなり、人材育成や生産性向上につなげられるのです。
1on1はより密接にコミュニケーションを行い、信頼関係の構築や業務改善を図るために有効です。
日本における1on1の歴史
もともと1on1はアメリカ・シリコンバレーが発祥だとされています。
シリコンバレーには優秀な人材が集まっており、激しい人材の争奪戦が繰り広げられていました。そこで、優秀な人材が他社に流出しないよう、人材の育成や囲い込みをするための手段として1on1を導入するようになったのです。
やがて日本にもその概念が広がり、日本企業ではヤフーがいち早く1on1を導入しました。1on1の活用によってヤフーは業績を大きく伸ばすことに成功し、多くの企業から注目されるようになったのです。そして、2010年代にはその人材育成手法が広く浸透したといわれています。
2.ヤフーの1on1について

有名企業のヤフーで導入されている1on1のメソッドは、ビジネスシーンで大きな注目を集めました。
そもそも、なぜヤフーは1on1を導入したのでしょうか。ここでは、ヤフーが1on1を導入したきっかけや、具体的な内容について見ていきましょう。
ヤフーが1on1を導入したきっかけ
ヤフーが1on1を導入したのは、2012年に人材戦略のひとつとして始まったことがきっかけだといわれています。
当時スマートフォンが台頭し始め、ヤフーのビジネスは過渡期を迎えていました。
PCの領域では地位を築き上げていたものの、変化をしていかなければならないという危機感を持ったといいます。
そこで、ビジネスの在り方を大きく変えて「今後ヤフーは人材開発企業としてやっていく」という方向性を定めました。
そして、変革のなかで「社員同士のコミュニケーションはきちんと取れているのか」という疑問が浮上したのです。
ヤフーでは業務においてさまざまなITツールを活用し、それをコミュニケーションの手段としてきました。
しかし、チャットを通じたやり取りが多くなるなど「情報伝達はできていても上司と部下との交流が希薄になっているのではないか」という問題意識が生まれたのです。
そこで、新たな取り組みの一環として、1on1を導入したとされています。
ヤフーの1on1の内容
ヤフーでは上司と部下が週に1回、30分間対話する「1on1ミーティング」を導入し、全社に浸透させていきました。
ヤフーの1on1は始めから全社横断で始めたわけではなく、人事責任者とその周辺の一部社員から始まった取り組みです。
具体的には、キャリア心理学の手法をベースに「あなたは将来どのような仕事をしたいのか」「そのためには今どうすべきか」といった問いかけを繰り返し、メンバーがそれに答えるというやり取りを実施しました。
コミュニケーションは対話を中心としつつ、ノンバーバルも含めたものです。もともとは人事部主導で始まったプロジェクトでしたが、外部の専門家も交えてヤフーに合うカリキュラムを組み立てていきました。
ブラッシュアップを行い、管理職の1on1のスキルやフォーマットを向上させ、徐々に文化として浸透させることに成功したのです。
3.ヤフーが1on1を導入したことによる効果

ヤフーでは1on1を導入したことで、さまざまな変化があったといいます。組織にどのような効果や変化があったのか、詳しく見ていきましょう。
強みを生かしたチーム設計
ヤフーでは、1on1によって上司と部下の相互理解を深め、部下の隠れた能力ややる気を引き出すことが大きな狙いでした。
つまり、人材育成が主な目的です。深刻な人材不足が叫ばれるなか、社員の能力を引き出し、適切に成長させることは企業の喫緊の課題と言えます。
1on1はこのような課題の解決に大きな効果をもたらしました。1on1を導入することによって上司と部下のコミュニケーションが活性化し、より関係が深まりました。
その結果、自己開示をしてくれる人が増え、チームでビジョンを共有できるようになったといわれています。
従業員一人ひとりへの理解が深まったことにより、個人の強みを生かせるチームづくりができるようになったのです。
社内コミュニケーションの改善
いくら社内に優秀な人材をそろえても、コミュニケーションが不足した状態ではさまざまな問題が生じるものです。
ヤフーでは1on1を取り入れ、コミュニケーション不足を解消しました。定期的に1on1を実施して対話の場を設けることで、部下は意思や悩みを相談することができます。
日常のミーティングではなかなか話しにくい些細なことも、1on1であればフランクな雰囲気のなかで伝えることが可能です。これにより、コミュニケーションが活性化し、その結果業務における混乱やトラブルが減少しました。
それにともない、業務効率の向上効果も得られたようです。
1人ひとりの貢献を見える化→1on1の対話の質向上! ピアボーナスⓇ「Unipos(ユニポス)」とは?
4.ヤフーの1on1のやり方や進め方

ヤフーではどのように1on1を実施しているのか、具体的にチェックしていきましょう。
ヤフーが1on1を実践するときのルール
ヤフーでは1on1を実践するにあたり、いくつかのルールを設けています。
たとえば「1対1で行う」「トップダウンで行う」「相手のために行う」というルールです。
加えて「週に1回30分間行う」「メンバーの意見を十分に聞く」「次のアクションを決定する」というルールが定められています。
ヤフーの1on1の具体的なやり方
ヤフーでは上記のルールをベースに、4つの要素から成る1on1を実践しています。要素の内容は「コーチング」「ティーチング」「フィードバック」「学びの確認」です。
それぞれどのようにして行うのか、各要素の詳しい内容と1on1の流れについて見ていきましょう。
まず「コーチング」では、上司から話題を振るのではなく、部下が「その瞬間に感じていること」を話してもらいます。
実施する際は「今日は何を話そうか?」という投げかけからスタートすることが基本です。
部下が話し始めたら、上司は口を挟まずに傾聴します。何か意見を言いたくなっても、我慢して耳を傾けることがポイントです。そして、聞いた内容に対してアドバイスをするのではなく「それでどうするのか」と部下自身が考えるように促します。
上司が答えを示すことは、結果として部下の成長を妨げてしまいます。部下の考えを引き出すことが、コーチングの役割なのです。「ティーチング」では、部下が知らないことを教えていきます。
たとえば、社内の経費精算の仕方がわからない場合などにやり方を指導するというものです。
ティーチングとコーチングは混同されがちですが、役割が異なります。
一例として、仕事の進め方がわからないなど、解決方法が複数あるものを教えるのはコーチングとなります。
両者を混同しないように注意し、適切に使い分けましょう。「フィードバック」は、部下の行動とその結果を確認し、全体の調整をすることが目的となります。
上司と部下との見え方に差が生じていないか、確認しましょう。差がある場合は、その内容を伝えて差を縮めます。その際、部下自身が気づいていない要素を伝えることが重要です。
また、部下が自分を知るきっかけを作り、改善点に気づくように促す必要もあります。「学びの確認」では、部下が行動したあとに何を感じたのか、素直に話してもらいます。
「今回の仕事を通じて何を学べたのか」「次にどう生かせるのか」と深掘りしていきましょう。
たとえば、プロジェクト完了後に振り返りを行わず次の仕事に着手してしまうと、何が良くて何が悪かったのか、理解することができません。
学びの確認のプロセスを踏むことで、振り返りを行い成長へとつなげられます。
ヤフーでは、振り返りの際に「この一週間どのように仕事をしていたのか」という質問からスタートすることが多いようです。
部下が「これをしていたと答えたら、上司は「そのなかで成功したことはあったか」と深掘りします。そして、部下が「これに成功した」と答えたら「なぜうまくいったのか」と話を膨らませていくのです。
こうしたやり取りを上司が意識的に行えるかどうかが、部下の成長に大きく影響するポイントとなります。
5.1on1をマネジメントとして生かす方法

ヤフーの1on1は、事業を活性化させるための有効なヒントが多く詰まっています。それでは、その1on1を自社のマネジメントにどう生かすことができるのでしょうか。
1on1をマネジメントとして生かす方法について見ていきましょう。
部下のキャリアを見据えた指導・育成
部下の指導・育成は、マネジメント業務における重要な要素のひとつです。1on1を導入することで、部下のキャリアや将来を見据えた指導・育成に生かすことができます。
企業のさらなる成長や目標達成を目指すには、部下の主体性が求められます。部下が自主的に物事を考えられるよう、周りがサポートする姿勢が重要になるのです。
1on1では上司はあくまでもサポートする立場であり、問題の解決方法は部下自身が見つける必要があります。
自分で問題を解決できれば自然と自信がもてるようになり、効率的に成長を促すことができます。
従業員の離職防止
企業にとって何としても避けたいのが人材の流出でしょう。
日本では、少子高齢化にともない、深刻な人手不足が叫ばれています。多くの企業において、人材流出を避けるため従業員のエンゲージメントを高めることが求められているのです。
1on1はこうした離職防止にも役立ちます。1on1で対話の機会を設けることで、上司は部下の事情や悩みをより深く理解することができます。
その結果、一人ひとりの事情に配慮した働き方を提案できるようになり、エンゲージメントの向上につなげられるのです。
また、1on1によって従業員は自身の成長を実感できる機会を得られ、モチベーション維持の効果も期待できます。
現代は個々に合うマネジメントを行い、その人の能力を最大限に生かすことが求められます。1on1によって交流や成長を促進させ、人材の流出リスクを減らすことができるでしょう。
組織全体のパフォーマンスの向上
企業が成長するためには、社員同士のギャップをいかに埋めるかが重要です。なぜなら、上司と部下との間に大きなギャップがあると、適切な人材配置やチーム設計が難しくなるためです。
企業の成長にとって、適材適所の人材配置は欠かせないものといえます。
1on1を導入することで、部下は上司に疑問や悩みなどを速やかに相談できます。対話によって部下への理解が深まり、効果的に人物像のギャップを減らしていくことができるのです。
ギャップが埋まれば、個々の適性や能力にマッチする仕事をアサインできるようになります。その結果、個人の成長に留まらず、組織全体のパフォーマンスアップにつなげられるでしょう。
1人ひとりの貢献を見える化→1on1の対話の質向上! ピアボーナスⓇ「Unipos(ユニポス)」とは?
6.ヤフーの1on1について学べる!書籍「部下を成長させるコミュニケーションの技法」について
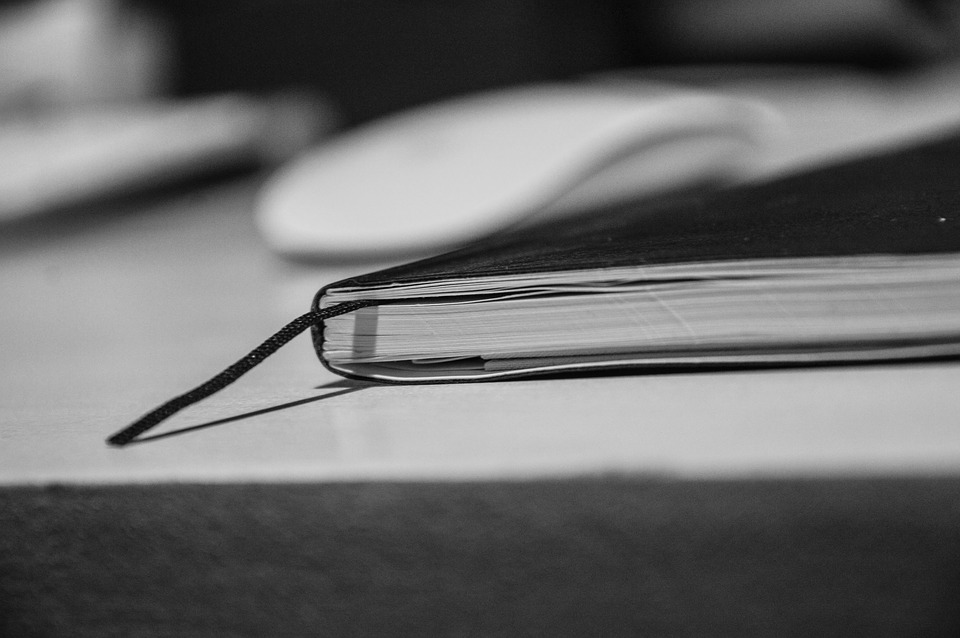
ヤフーの1on1についてより具体的に学びたい場合は、本間浩輔氏の著書「ヤフーの1on1部下を成長させるコミュニケーションの技法」を読んでみることがおすすめです。
この本は、ヤフーにおける1on1の導入方法や注意点について解説されているものです。漫画や専門家との対話などを盛り込み、1on1についてわかりやすく解説されています。
なぜヤフーが1on1の導入を決めたのか、その背景や人事観について詳しく知ることができます。
導入時にぶち当たる壁や実践における細かいノウハウなども網羅的に解説されており、これから新規に1on1を導入しようと考えている企業は大いに参考になるでしょう。
人事や組織の責任者など、1on1について理解を深めたい人は読んでおきたい一冊です。
1on1を導入して組織を活性化させよう
1on1は上司と部下が1対1で行う、気軽な対話の場です。なお、1on1は目標管理や進捗管理が主な目的ではなく、部下のフォローアップに重点を置いた取り組みです。
高頻度かつ短時間の対話を実践することによって、上司は部下への理解を深められます。それにより、部下の成長だけではなく、ひいては企業の成長にもつなげることができます。
ヤフーの事例や関連書籍などを参考にし、自社で1on1を導入して組織の活性化を図りましょう。


