
良い組織文化への変革は、どんどん変化していく時代や社会に対応し、持続的に発展していくために欠かせない要素です。しかし、ただ変革すればよいというものではありません。
心理的安全性が確保された状態で行うことで浸透し定着していくのです。
この記事では、組織文化変革の重要性と、心理的安全性の必要性について解説します。
1.組織文化とは?

そもそも組織文化とは、いったいどういったものでしょうか。
組織文化とは
組織文化は「組織カルチャー」とも呼ばれ、組織内で共有される信念やルールを示した言葉です。企業の成長につなげるための内容であることが重要なので、成長をじゃまするような組織文化であれば変革する必要があります。
従業員や組織の経験や競合の状況、市場変化などの影響を受け、変化したり成長したりしながらだんだんと作り上げられていくという特徴をもっており、組織として判断をくだすときのベースとなるものです。
組織文化の種類
ミシガン大学のロバート・クインたちが開発した組織文化の診断フレームワークでは、組織文化を4つのパターンに分類できます。ただし、この4つはあくまでも一例であり、1つだけでなく複数に該当する場合もあると捉えてください。
- 1つ目は「家族文化」です。フレンドリーで一体感のある温かい雰囲気や仲間意識が特徴で、コミュニケーション開発や組織への参加に価値を置き、社員同士や経営者と社員の連帯感があります。
- 2つ目は「イノベーション文化」です。創造や変革を大切にしており、社会の変化に敏感に反応することができます。
- 3つ目は「官僚文化」です。組織の統制と安定を重要視しており、適時性や効率、画一性に価値を置いています。お互いに監視し合うことで息苦しさを感じやすい一方で、安定性があるのがメリットです。
- 4つ目は「マーケット文化」です。市場競争に勝つことを大切にしており、収益性や目標達成など厳しい要求を社員に対して行います。
組織風土や社風との違い
よく似ている言葉に「組織風土」や「社風」があります。組織風土は、能力主義か年功序列か、個人主義か全体主義か、安定志向か上昇志向かといった、仕事への価値観やモチベーションに関わる心理的環境要因に影響を受けて形成された組織の価値観です。そのため、外部からの影響を受けにくいです。
一方組織文化は、就業規則や経営理念、会社の判断基準などに影響を受けた組織独自の行動原理を表す言葉です。そのため、経営層などの意図的にデザインすることもできます。
社風は、従業員が感じている組織の特徴や雰囲気であり、感覚的・主観的なものです。組織風土や組織文化に大きな影響を受けやすいです。
組織文化の重要性
では、なぜ今組織文化が重要視されているのでしょうか。
組織内に良い文化があれば、課題の発生率が下がります。仮に課題が生じたとしても、企業として重視すべきことが根付いていれば迅速かつ自発的に解決に導くことができるのです。その結果、より円滑な企業活動が期待できるでしょう。
また、場当たり的に解決に取り組むより費用面で考えても効率的です。さらに、はっきりした組織文化があることで、会社の方向性を理解した従業員は、信頼と安心のもとで会社に貢献することができます。
組織文化をビジネスに活用するメリット
組織文化をビジネスに活用することで、さまざまな効果が期待できます。
例えば、会社の方向性や求める行動が明確になるため、従業員が同じ方向を目指して進むことができ、一体感のある組織づくりが可能です。
また、会社のためにできることを考え自発的に行動できる従業員が増えます。自発的な行動によってモチベーションが高まるため、仕事のやりがいを感じやすい職場づくりにもつながるはずです。
トラブルの発生時や意見が割れたときには、組織文化に立ち返ることで、スピーディーに意思決定も進んでいきます。
参考:【ONE TEAM Lab】組織風土と組織文化、社風の意味や違いとは?それぞれの関係性も解説
2.良い組織文化をつくるのに必要な心理的安全性とは?

良い組織文化をつくるには、心理的安全性が重要といわれています。心理的安全性とは一体どのようなものでしょうか。
心理的安全性の定義
心理的安全性は、1999年に組織行動学のエイミー・C・エドモンドソン教授によって提唱された心理学用語で、何を言ってもどんな指摘をしても、受け入れてもらえるような職場環境を意味しています。
例えば、組織内で伝統の否定や空気を読まない発言をしたとしても、評価が下がったり拒絶されたりせず安心して誰に対しても発言できる状態であり、ただ仲の良い職場という意味ではありません。
アメリカのGoogle社は、この提唱を受けて効果的なチームについての研究を進め、効果的なチームの要素として最重要なのが心理的安全性だと結論づけました。
心理的安全性を高めるメリット
心理的安全性が高まると、従業員にとっても組織にとってもメリットがあります。
従業員にとっては、責任感や関心をもちやすいというメリットがあります。自分の意見を発言しやすく尊重してもらえる環境のため、積極的にチームに関わろうとするようになり、責任感や関心が高まるのです。
前向きな気持ちで集中して取り組んでいくことで、仕事に対するストレスが緩和され、生産性も上がります。
組織にとっては、多様性に富んだ人材が集まりやすくなるのがメリットです。価値観の多様性が認められるため、あらゆる能力や個性の発揮や議論の深まりがしやすくなります。
価値観の異なる人同士で対話をすることで、新たなアイディアも生まれるでしょう。自分の能力や個性が十分に生かせる環境のため、仕事へのやりがいも生まれ、離職率や退職率の低下にもつながります。
さらに、建設的な議論が行える環境のため目指す方向性がはっきりします。そのため、スピーディーな目標達成が可能です。
心理的安全性が低いことによるリスク
心理的安全性が低いと「無知と思われるのではないか」「じゃまをしているのではないか」「ネガティブと思われているのではないか」「無能と思われるのではないか」といった4つの不安を伴うようになります。
すると、自分の失敗を認めなかったり、常に自分を隠して働いたりするようになるのです。
心理的安全性が低いと、組織全体にも影響が出てきます。社員同士の意見交換が気軽にできなくなります。なぜなら、意見を言っても否定されたり人間関係が悪化したりするからです。
例えば、新たな事業案を思いついても、伝えることに不安感があると意見を伝えることができなくなります。仕事の裁量権が感じられなくなり、モチベーションの低下にもつながります。また、働きにくいと感じた人材の流出も考えられるでしょう。
伝えにくい意見の中には、ミスやトラブルに関する報告も含まれます。連絡や報告が不十分だと、トラブルの未然防止や適切な対処ができなくなったり、隠蔽体質の組織になったりといったリスクにつながります。
心理的安全性が低いことによるリスクを踏まえても、良い組織文化をつくるには、対人関係を気にせず意見しあえる環境づくりが大切といえるでしょう。
3.組織文化の改革プロセス

組織文化の改革は言葉にするのは簡単ですが、いざ実行し成果を出そうとすると、非常に難しいのが現状です。どのような視点であれ、組織の変革は70~80%の確率で失敗するという専門家もいるほどです。
熱意があっても、結果が伴わないというケースは少なくないのです。では、どうすれば成功できるのでしょうか。まずは変革は「人」にかかっていることを意識することです。ツールや技術の導入による変革を目指すのではなく、従業員の考え方や行動の現状と、目指したい姿や組織の在り方とのギャップを埋めるための計画を立てることから始めます。
そして、新しい文化を築くには実現力が欠かせません。これらのことを踏まえたうえで、組織文化の変革プロセスについてみていきましょう。
1:現状と目標を数値化する
企業文化がどんなものであっても、そこには従業員の価値観や行動が反映されています。そのため、基本的な価値観とその価値観を支えている行動について見極め、明確化する必要があります。良い結果につながった要素も入れてみましょう。そうすることで、何を変えるべきかが見えてくるのです。
次に、どのような組織文化にしたいのかをしっかり考えて定義します。特に、企業が急激な成長を遂げているタイミングだと、従業員の増加に伴って組織文化を個人で解釈するようになるリスクがあります。
そうなってしまうと、ゴールが不明瞭になり、成功への妨げとなってしまうのです。最初にじっくり時間をかけて目指す方向性を明確にしておくことは、この後の過程をスムーズに進めるのに役立ちます。
このとき、アンケート調査などを使って数値設定することが重要です。数値化すれば、到達できたのか、変化の程度はどのくらいかがはっきりわかります。
改革前と改革後の差を明示することは、組織文化の変革において欠かせないプロセスといえます。
2:目指す組織文化を言語化する
次に、数値化した組織文化を言語化し、従業員に向けて発信します。このとき大切なのが、どのような言葉に落とし込むかということです。「挑戦しよう」「主体的に行動しよう」といった表現だと、自社における挑戦とはそもそも何なのか、主体的にとはどんな姿なのかが明確に伝わりません。
具体的にどういう姿を目指すのかが、従業員にはっきり伝わるように表現することで、組織全体に組織文化が浸透しやすくなるといえます。
3:発信する
言語化ができたら、管理職で止まることなく社員までしっかり届くよう、伝え方を工夫していきましょう。例えば、社長がメッセージを発信するときに必ず出てくる、上司と部下の会話の中に日常的に使われるなど、口癖のように使われることをゴールとし、意識して発信し続けます。
また、新しい組織文化の内容について従業員が熟慮できる機会となるような対面ワークショップや、事業や全社レベルでの全員参加の会議などのコミュニケーションも有効です。
さらに、社内SNSやメール、イントラネットなどを使ったコミュニケーションなら、従業員にとってもフィードバックしやすい仕組みといえます。このようなコミュニケーションを通して、組織文化の新たな枠組みがどのように社内で広がっているかを評価することもできます。
このプロセスで大切にしたいのが、従業員に教えるというスタンスではなく従業員の組織文化に対する理解を深めるというスタンスで関わることです。そのためには、一方的に押し付けるのではなく、従業員が疑問を出したり価値観を理解して普段の業務に結びつけたりするのをサポートしなくてはなりません。組織文化を発信する側の意識が大切なのです。
4:定着のために仕組み化する
新しい組織文化を定着させるためには、評価や個人の目標設定などのルールを設計する仕組み化を、最終段階で行うのがポイントです。
「発信する」の過程において、日常の中で意識的に新しい組織文化に基づいて行動しているタイミングで仕組みを整えていくことで、無意識で行えるようになってきます。
仕組み化する方法としては、例えば組織文化に基づいた行動やそれによる結果が得られれば、周囲からの評価によって報酬として反映されるなどの方法があります。
心理的安全性向上の実践者に学ぶ、組織の巻き込みに成功した施策をご紹介!|詳細はこちら
4.組織文化を改革した企業事例
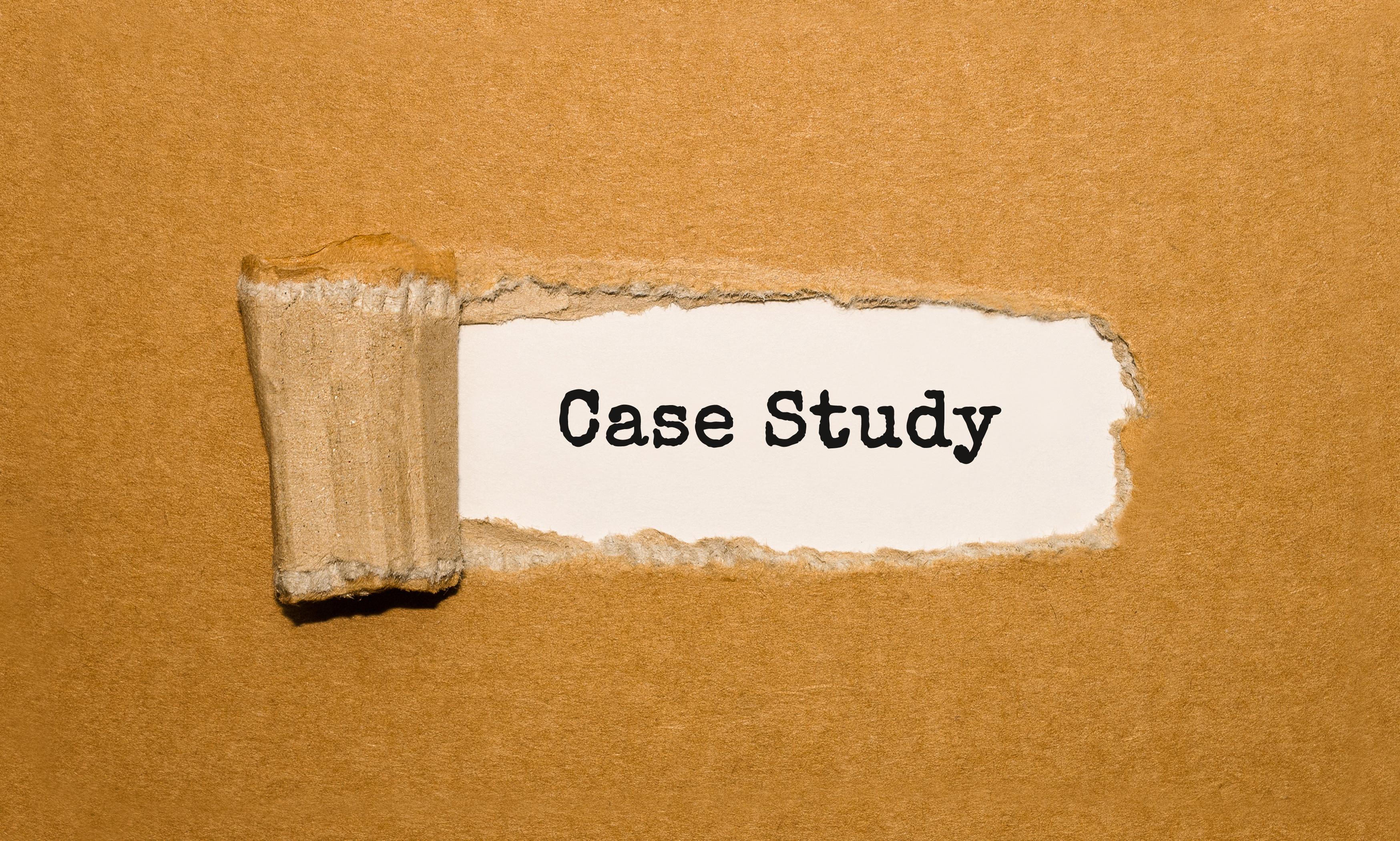
長期的な視点で組織文化をつくっていくには、文化的な資産を蓄積していくことが大切です。
ここでは、組織文化の改革に成功した企業事例を紹介します。
称賛文化の醸成を下支えに売上UP「株式会社カクイチ」
明治19年創業の株式会社カクイチは、称賛文化の醸成を下支えに、売上前年比132%増という成果を出した企業です。
ガレージや物置、倉庫、太陽光発電パートナー、農業支援技術の開発や提供といった事業を展開しており、全国に28の営業拠点と3工場、77店舗のショールームがあります。
そのため、他拠点の従業員同士もしくは他部署の従業員同士でのコミュニケーションがほぼとれておらず、職場で認められる機会も少ないという課題がありました。インセンティブ制度だけでは、従業員の承認欲求を満たすのに限界があると考え、ツールを使用してお互い言葉で称賛し合う文化の導入を決めたのです。
年齢層が高く、IT環境がほぼ整っていなかったため、まずはITに長けている人やコミュニケーション力の高い人を中心に、従業員同士で感謝の言葉とインセンティブをSNSのように気軽に送り合える「Unipos」を活用した改革に取り組みました。
シンプルな機能だったため、ガラケーを使用していた社員でもすぐに馴染み、活発に利用する姿が見られるようになりました。また、営業所が離れて直接集まることが難しくても、ツール上でコミュニケーションを取り合うことで、これまで伝わらなかった感謝の気持ちが見える化されるようになったのも成果のひとつです。
カクイチ社では、Uniposの少し後にSlackを導入。先にUniposを導入し、発信することや感謝を言う「感謝体質」ができあがっていたからこそ、慣れないSlackというビジネスチャットツールを入れても、ポジティブな発信をしようという意識ができていました。
コロナ禍でもその土台があったことで、自然発生で各拠点が鼓舞し合い、会社の売上目標よりも上の目標を自分たちで立て、競い合いが始まりました。このように「健全な対立」が生まれ、負けた拠点も勝った拠点を称える自律した組織になっています。
まさしく、組織の心理的安全性が高まったことで、より良い組織文化醸成につながった事例であるといえるでしょう。
参考:創業134年、ITリテラシーゼロ企業がDXに成功。称賛文化に変身、そして売上前年比132%へ
過去の組織崩壊から復帰「Goodpatch」
Goodpatchは、事業の新規立ち上げやプロダクトの改善などを支援するデザインカンパニーです。かつて組織崩壊した際に、心理的安全性の喪失や大量の従業員退職といった経験をしました。
この経験から、人と組織に向き合い続けることで、組織文化の維持が成り立ち事業成長につながるのだと痛感されたといいます。そこで、よりよい組織文化への変革を目指し「Unipos」を導入することにしたのです。
Uniposを使用する前は、普段業務では関わらないメンバーがどういう仕事をしているのかが見えにくかったり、カジュアルなコミュニケーションがとりにくかったりといった課題がありました。Uniposは文字で感謝などポジティブなメッセージを送り合うことができるため、これらの課題にアプローチできるようになったのです。
実は、もともと社内では「バリュートロフィー」という施策があり、よい行動をコアバリューに結びつけて称賛していました。しかし、運用がうまくいかず定着しないまま使われなくなってしまったのです。
Uniposも同じように称賛し合えるツールですが、その内容が可視化されいつでも閲覧できるため、これまで見えなかった多様な貢献が見えるようになってきました。このことは、飽きずに定着し使い続けてもらうための要素になっています。
さらに、月1回のオンラインイベントで同時にメッセージを送り合う機会を設けるなど、使用する良さや手軽さを実感してもらう機会を設けたのも定着した理由といえるでしょう。
このように日々の貢献の可視化や、リモートワークで会えなくても人となりがわかるようになったことで、組織の心理的安全性が高まり、従業員エンゲージメントのスコアも偏差値70前後を維持できる状態になりました。
参考:組織文化を重視する“Goodpatch流”Uniposの使い方
組織改革を成功させよう
リモートワークによって直接的なコミュニケーションが取りにくかったり、部署や拠点を超えたコミュニケーションが難しかったりといった課題を抱えている企業では、心理的安全性を高めることが組織改革において重要です。
組織改革の4ステップをもとに、心理的安全性の高い組織改革を目指して取り組んでみませんか。



