
少子高齢化社会で企業の人材不足が深刻化し、定着率を上げることが課題となっている企業は少なくありません。定着率を高めるには、労働環境の改善や柔軟な働き方の採用などが求められています。
本記事では、人材が定着しない理由や定着率を上げる方法について解説します。
従業員の定着率とは?

従業員の定着率とは、従業員が入社してから一定期間内でどれくらいの割合で在籍しているかを表す指標です。従業員の在籍期間が長いほど、定着率の数値は高くなります。
期間の設定は企業によりさまざまですが、1年間で計算することが一般的です。
ここでは、日本の定着率の現状と計算方法、離職率との違いについて解説します。
日本の離職率は13.9%
厚生労働省の調査によれば、2021年の離職率の平均は13.9%です。この数字から、日本の定着率は86.1%ということがわかります。
また、新入社員の就職3年以内の離職率は、新規高卒就職者が35.9%、新規大学卒就職者が31.5%と、3人に1人が離職しているという結果が出ています。新入社員の離職率の高さが、定着率全体を下げる要因になっているといえるでしょう。
参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します
定着率の計算方法
定着率の測定開始日は企業によって異なり、年度初めの4月を起算にするのが一般的です。また、測定する期間は年単位で、データの使用目的に合わせて長さを決めます。
定着率の計算式は、以下のとおりです。
定着率(%)=(入社者の合計-退職者の合計)÷入社者の合計×100
例えば、4月に20人入社し、翌3月までに5人退職している場合、計算式は(20-5)÷20×100で、定着率は75%です。
定着率が高いほど働きやすく、労働環境が良いことを表しています。
離職率と離職率の違い
定着率のほかに離職率という言葉もあります。離職率とは、従業員が一定期間でどれだけ退職しているかを表す指標です。定着率を反対から見たもので、両者を合計すると100%になります。定着率が80%であれば、同じ期間の離職率は20%です。
定着率が高ければ労働環境が良く働きやすいという指標になり、優良企業であるというアピールにもなるでしょう。反対に、離職率が高いと人材の流出が多い会社という印象になります。
離職率については、以下の記事が参考になります。

人材が定着しない理由とは?

定着率が低く人材が定着しない理由は、会社によって異なります。例えば労働環境が悪い、人間関係が良くないといった理由によって、従業員の離職率が上がることが一般的です。
また評価制度が明確でない、休暇が取りにくいといった体制の不備に問題がある場合もあります。
ここでは、人材が定着しない理由についてみていきましょう。
職場環境が悪い
残業が多い、仕事量が多いなど労働環境が悪いと、離職率が高くなり人材が定着しなくなります。働き方改革で残業を減らす会社は増えているものの、長時間勤務が常態になっている会社は少なくありません。
残業するのが当たり前という風潮があったり、上司や先輩が残業しているため帰れないという状況があったりすると、ストレスが多くなり離職につながる可能性が高くなるでしょう。
離職が増えて人材が不足すると、残された従業員の業務量が増える結果にもなります。過剰な業務を抱えることでより残業が増え、プライベートの時間がなくなることでストレスは大きくなるでしょう。さらに離職につながるという悪循環に陥ることにもなります。
職場の人間関係が悪い
職場の人間関係も、会社の定着率に影響します。人間関係の悪化は転職理由の上位にあり、定着率を下げる大きな原因です。
上司や先輩との関係が良くない、パワハラ・モラハラがある、社内コミュニケーションが図れないといった事情があると、業務もうまく進められません。働きにくい環境になり、離職を決意する従業員も増えるでしょう。
複数の従業員が働く会社では、人間関係のトラブルもありがちです。従業員の自治に任せるのではなく、会社側も何らかの対処をすることが求められます。
評価制度の基準が不明確
評価基準が曖昧で、正当な評価がされていないと感じると、離職につながりやすくなります。明確な基準がなく上司の主観が入りやすい評価制度では、従業員の不満も大きくなるでしょう。
評価基準が明確でない、そもそもどのような基準なのかが公表されていない場合、従業員は正しく評価されているのか判断しにくくなります。
成約の獲得など目に見える数字が出る業務であれば評価もわかりやすいものの、数値化しづらい業務で納得できる評価基準がない場合、評価されていないと感じる場面もあるでしょう。
頑張る人ほど自分の働きを適切に評価してほしいと感じます。評価されないのであればモチベーションが下がり、より自分を評価してくれる会社への転職を考えるでしょう。貢献度の高い人材の離職は、会社にとって大きな痛手です。
人事評価の問題については、以下の記事で詳しく解説しています。

休暇が少ない・有給休暇が取りにくい
休暇が少ない、有給休暇が取りにくい環境も離職につながりやすく、人材は定着しません。近年はライフワークバランスを重視する人も増え、休みにくい会社は敬遠されます。有給休暇は労働者に保障された権利であり、取りにくい状況は従業員にとってストレスとなるでしょう。
有給休暇の申請をすると忙しさを理由に拒否される、仕事を抱えているため取得したくても申請できないという状況は、離職を招く原因となります。定着率が悪く人材が不足すれば、ますます有給を取得しにくい状況になるでしょう。
人材育成の制度が整っていない
教育制度が整っておらず、スキルアップの機会がない会社も定着率が下がります。成長できない会社と感じ、早めの転職を考える従業員も出てくるでしょう。入社したときに十分な教育や指導を受けられないと、仕事がうまくできず、誰に相談したらいいかわからないという状況にもなります。
現場で働きながら覚えるという指導方針では、迅速なスキルアップは期待できません。なかなか仕事を覚えられず戦力にならない状態では、生産性の低下も招くでしょう。
定着率を上げる方法

定着率を上げるには、自社の定着率が悪い理由を解明し、改善していかなければなりません。残業時間が長いなど労働環境が悪い会社は働き方改革で労働環境の改善に努め、柔軟な働き方を取り入れることも必要です。
人事評価制度の整備や、社内コミュニケーション活性化の取り組みも求められるでしょう。
従業員の定着率を上げる方法を解説します。
労働環境を改善する
残業が多く長時間勤務が原因で定着率が悪い場合、労働環境の改善に努めましょう。残業期間の上限を決めたり定時に退社する日を設けたりして、残業の削減を行います。従業員の勤怠状況を常に把握し、長時間勤務の実態があれば業務の割り振りを考えるなど改善に取り組みましょう。
長時間勤務を是正する方法のひとつに、IT化による業務の効率化があげられます。ITのシステムやツールを導入して業務の自動化・書類の電子化などを行うことで、作業にかける時間を減せます。人材不足で1人の従業員に過剰な業務負担がかかっているといった状況を改善し、残業を減らせるでしょう。
近年はグローバル化が進み、外国人を積極的に雇用するなど人材が多様化している傾向にあります。多様な人材を採用することで人材不足を解消し、1人の業務負担を減らして労働環境の改善を図ることもできるでしょう。
有給休暇を取得しやすくすることも大切です。従業員の取得状況を調査し、積極的に取得されていない状況があれば取得を奨励するか、取得しやすいシステムをつくることも考えましょう。
また、仕事の進捗状況を自分で管理する属人的な働き方ではなく、チームで業務を共有することで、有給休暇を取得しやすくなります。
柔軟な働き方を取り入れる
定着率を高めるには、柔軟な働き方を取り入れることも必要です。家庭の事情などで通勤が難しくなった場合でも、働き方を選択できれば勤務を継続できる可能性があります。
柔軟な働き方として、次のような雇用形態があげられます。
- 出退勤時間を選べる
- 完全在宅勤務
- 一部在宅勤務
- シフト制
- フレックスタイム
- コンプレストワークウィーク
在宅勤務ができる業種であれば、リモートワーク制度の導入を検討してみましょう。出退勤の時間を調整できるシフト制やフレックスタイムの導入もおすすめです。自分のライフスタイルに合わせて勤務時間を変更できることで、仕事とプライベートの両立も図りやすくなり、ワークライフバランスを実現します。
コンプレストワークウィークとは、1週間の所定労働時間は変えず、1日あたりの就業時間を長くして休日を増やす勤務形態です。例えば、週40時間労働で通常は1日8時間×週5日勤務の場合、1日10時間にして週4日勤務にすれば休日を3日に増やせます。
業務内容に応じ、対応可能な働き方を取り入れていきましょう。働き方の選択肢が多くなることで従業員は働きやすい環境を手に入れることができ、定着率も高まります。
人事評価制度を整備する
人事評価制度の基準が曖昧なことで従業員に不満がある場合、見直しを検討しましょう。評価が正当でないと、待遇や労働環境が良くても離職の理由になってしまいます。
人事評価制度は、昇進・昇格の判断や給与査定を行う際の指標になり、評価基準に曖昧であると従業員の処遇に影響が出てしまいます。人事評価の基準が不明確で主観が入りやすい場合、成果以外の年齢や勤務年数・上司との関係性といった要素が評価に入り込む可能性があるでしょう。
適正な評価を受けられないと、仕事に熱心に取り組んでいる従業員ほどモチベーションを下げてしまいがちです。
客観的な評価が期待できる評価方法として、360度評価があげられます。360度評価とは、上司だけでなく同僚や部下も評価者となり、多角的に評価する方法です。評価者1人の場合は主観に偏る可能性はありますが、複数人から評価されることで、より客観的で公平な評価を可能にします。
複数人の評価によって、従業員の業績・スキルだけでなく、職場内での人間関係やチームへの貢献度なども把握できます。複数の関係者が評価を行うことで従業員も評価結果に納得し、受け入やすくなるでしょう。
社内コミュニケーション活性化の取り組みをする
人間関係の悪化で離職が多い場合、社内コミュニケーション活性化の施策を考えましょう。社内コミュニケーションの活性化は従業員が楽しく働けるだけでなく、業務を円滑に進めて生産性の向上にもつながります。
社内コミュニケーションを活性化させる方法はさまざまで、主に以下の方法があげられます。
- 社内報
- 社内イベント
- リフレッシュスペースの確保
- 社内チャットなどコミュニケーションツールの活用
社内報で社内の出来事など情報を伝えることで従業員同士の話題となり、コミュニケーションを促します。
社内イベントは職場を離れ、従業員同士がリラックスした雰囲気で触れ合える場所です。他部署の従業員とも交流ができるでしょう。
また、社内にリフレッシュスペースを設ければ、休憩時間に従業員同士のコミュニケーションが生まれます。
社内SNSやチャットツールなどのコミュニケーションツールは、メールに比べて気軽にコミュニケーションがとれる手段です。社内報は一方通行の情報ですが、社内SNSは従業員同士が双方向で情報のやり取りをできます。より社内コミュニケーションを活性化できるでしょう。
社内コミュニケーション活性化に役立つのが、ピアボーナスのUnipos(ユニポス)です。ピアボーナスとは、従業員同士で称賛や報酬をおくり合うシステムです。従来のように上司が部下を評価するのではなく、業務の成果や貢献に対して従業員同士がお互いに評価をし、少額のインセンティブをおくり合います。
Uniposはこのピアボーナスにより、従業員同士の交流を促し社内コミュニケーションを活性化させます。Uniposの利用率が高い職場では「コミュニケーションをとりやすくなった」という感想が多く、離職率低下につながっています。
従業員のスキルアップを支援する
教育制度が整っていないと、従業員は成長できません。長く勤務してもスキルが身につかず、望むキャリアプランを描けないのであればモチベーションが低下するでしょう。成長意欲のある従業員は転職を考えることにもなります。研修や資格取得制度などを導入し、従業員が成長できる体制をつくることが大切です。
人材育成の教育手法は現場で先輩社員が指導するOJTや座学研修、従業員自身が積極的にセミナー受講やeラーニングに取り組む自己啓発があげられます。
教育制度を設ける際は、キャリアパスを明確にしましょう。キャリアパスとは、社内でキャリアを積み、成長していくための道筋を表すものです。どのような業務経験を積み、どれだけの能力を身につければ目標とするキャリアに到達できるかを示します。
キャリアパスで成長の道筋が明らかになれば、従業員は成長のプロセスをイメージでき、モチベーションを高めるでしょう。
キャリアパスを明確にすることで、段階ごとに必要な知識やスキルも明らかになります。キャリアパスに沿ったカリキュラムを組むことで、各段階に適切な計画の策定ができるでしょう。
従業員エンゲージメントを高める
定着率を上げるには、従業員エンゲージメントの向上も大切です。従業員エンゲージメントとは、従業員が会社の方向性に共感して会社に愛着と信頼を持ち、貢献したいと考える意欲を指します。
従業員エンゲージメントの高い従業員は会社で長く働きたいと考えるため、定着率も上がるでしょう。
従業員エンゲージメントを高めるには、企業理念やビジョンを浸透させ、共有することが必要です。そのためには、繰り返し周知・共有していくことが求められます。経営トップ自ら従業員に語りかけ、周知させていきましょう。
個々人が尊重される環境も、従業員エンゲージメントを高めます。働きを称賛されることで、従業員の貢献意欲も高まるでしょう。
上司は部下の頑張りを称賛し、意見を受け入れていくことで従業員エンゲージメントが高まります。表彰制度を設け、定期的に表彰する場をつくるのも効果的です。称賛文化を醸成するのに役立つのが、Unipos(ユニポス)です。感謝や称賛の投稿は従業員同士でオープンに見ることができ、拍手機能によりワンクリックで称賛ができます。称賛の投稿はポジティブな体験となり、モチベーション向上にも役立つでしょう。ポジティブな体験が増えることで称賛し合う風土が醸成され、エンゲージメントの向上が期待できます。
早期離職が多い場合は採用基準や体制の見直しも
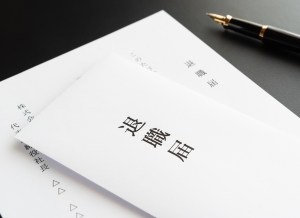
新入社員や中途社員の早期離職が多い場合、採用のミスマッチが原因の可能性が高いでしょう。採用のミスマッチが起こるのは、主に以下の原因があります。
- 企業の良い面ばかりを強調している
- 採用基準が不明確で面接官により判断が異なる
- 求める人物像が明確でない
- 入社後のサポートが不十分
会社説明会などで自社の良い部分ばかりを伝えると、採用のミスマッチが起こりやすくなります。会社の課題や実態も伝えていかなければ、入社後に「思っていた会社と違う」ということにもなるでしょう。
また、採用基準が明確でないと判断が面接官ごとに異なる可能性があり、ミスマッチを生みやすくなります。
求める人物像が明確でないことも、ミスマッチが起こる原因のひとつです。人物像が明確でないために、自社に合わない人材を採用してしまう可能性があります。
入社後のフォローが不足したために、仕事がうまくできなかったり、働くこと自体に不安を感じたりすることもあります。早期退職につながりやすくなるでしょう。
特に中途採用者は経験があるからとサポートを怠ると、離職の原因になります。中途採用者は経験や実績があることで、これまでのやり方を押し通そうとする可能性があるためです。
周囲とのずれが生じ、職場に馴染めずに離職する可能性があるでしょう。中途採用者は前職と企業文化や社風の違いにストレスを感じることも少なくありません。新入社員と同じく、十分なサポートが必要です。
採用のミスマッチで早期離職が増えると、採用にかけた時間と費用が無駄になります。新入社員が頻繁に入れ替わると、毎回教育を行うのも現場の負担になるでしょう。生産性を落とすことにもなります。
このようなミスマッチを避けるためにも、採用計画や基準、選考方法などこれまでの採用プロセスを見直すことが必要です。
まとめ

人材不足の悩みを抱える企業は多く、定着率を上げるための方法が求められています。定着率が悪い原因は、労働環境が悪い、人間関係が良くないなど会社によって異なります。まずは自社の状況を確認し、原因を見極めましょう。
原因に応じて、業務の効率化や社内コミュニケーションの活性化などさまざまな対策があります。採用後の早期離職が多い場合は、採用方法や採用基準を見直しましょう。
社内コミュニケーションの活性化や従業員エンゲージメントの向上には、Uniposを利用してみるのもひとつの方法です。従業員の定着率を高め、会社を成長させましょう。


