
従業員が人事制度に向ける不満はさまざまですが、その中でも多いのが「人事評価制度」に対する不満です。
実に「62.3%」が勤め先の人事評価制度に不満を抱えているというデータがあります。

【調査概要】調査期間:2018年2月7日(水)~2018年2月12日(月)有効回答:1532人(全体)調査方法:インターネット調査(日経BPコンサルティング調べ)
参考:「人事評価制度」に関する意識調査|Adecco
いうまでもなく、従業員が人事制度に不満を抱えてモチベーションが低下している状況を放置するのは危険です。組織崩壊を招く可能性さえあります。
そうなる前に、従業員の不満対策を行い人事制度への満足度を向上させることが必要です。
本記事では、「不満の中身」とその原因を理解し、適切な対策を行うために必要な情報を解説します。
- 具体的に何が不満なのか?
- 不満を抱く原因とは?
- どんな対策をすれば不満は解決する?
- 人事制度の不満に対処する上で注意すべきこと
これらの情報は、人事制度を通して組織をもっと良くしていきたいと願う方のお役に立てるはずです。さっそく、従業員の気持ちから紐解いていきましょう。
目次
非表示
]- 1. 【10の不満】従業員が人事制度に感じる不満ランキング
- 1-1. 評価基準が不明瞭(62.8%)
- 1-2. 評価者の価値観や経験によってばらつきが出て、不公平だと感じる(45.2%)
- 1-3. 評価結果のフィードバック、説明が不十分、または仕組みがない(28.1%)
- 1-4. 自己評価よりも低く評価され、その理由が分からない(22.9%)
- 1-5. 評価結果が昇進、昇格に結びつく制度ではない(22.0%)
- 1-6. 評価結果が昇給に結びつく制度ではない(21.4%)
- 1-7. 会社の定める評価指標が現実に即していない(20.6%)
- 1-8. 評価指標が成果のみで、プロセスへの評価がない(17.5%)
- 1-9. 評価指標に上層部の意向は反映され、一般社員は反映されない(14.4%)
- 1-10. 実績に対する評価より、年功序列が優先される制度である(9.2%)
- 2. 人事制度の不満を放置すると起きる問題
- 3. 人事制度に不満が出る3つの原因と対策方法
- 4. 人事制度の不満へ対処する際の注意点
- 5. まとめ
1. 【10の不満】従業員が人事制度に感じる不満ランキング

冒頭でご紹介した通り、Adecco Groupが2018年に実施した「人事評価制度」に関する意識調査によれば、【62.3%】の人が勤務先の人事制度の不満を抱えています。
実に「6割以上の従業員」が不満を感じているのです。あなたの会社の社員数で計算してみると、リアルにその多さが実感できるのではないでしょうか。
その具体的な不満は以下の通りとなっています。

出典:Adecco Group「人事評価制度」に関する意識調査
順に詳しくご紹介しましょう。
1-1. 評価基準が不明瞭(62.8%)
2位に20ポイント近い差をつけて、1位となっているのが「評価基準が不明瞭」です。
例えば、以下の企業では「評価基準が不明瞭」という不満が出やすくなります。
- 評価基準が上層部の暗黙知となっていて明文化されていない
- 明文化はされているが従業員に開示されていない
- そもそもハッキリとした評価基準が存在しない
従業員から見て透明性の低い評価基準は、そのまま不満に直結していることがデータから読み取れます。
1-2. 評価者の価値観や経験によってばらつきが出て、不公平だと感じる(45.2%)
2位は「評価者の価値観や経験によってばらつきが出て、不公平だと感じる」です。
1位の「評価基準が不明瞭」は、“評価基準の存在”への不満といえます。一方、2位の不満は“評価基準の運用”に対しての不満という色合いが強くなります。
例えば、
- 評価基準はあるが、評価する人によって解釈が変わる
- 厳しく評価する人と甘く評価する人がいて不公平
…というシチュエーションが考えられます。
「ゴマすりばかりしている同僚が高評価で、上司に嫌われている自分は低評価」のように、人間関係の好みが反映されていると感じる場合も、この不満に入るでしょう。
1-3. 評価結果のフィードバック、説明が不十分、または仕組みがない(28.1%)
3位は「評価結果のフィードバック、説明が不十分、または仕組みがない」です。
例えば「考課査定が行われた後、昇給・降格などの結果のみ通知される」という企業は、意外と多いものです。
評価結果の内容についてのフィードバックが不十分だと、従業員に「適切な評価が行われているのだろうか?」と不信感を抱かせてしまいます。
「評価した“後”のコミュニケーションがいかに大切か」を改めて実感させられる不満といえるでしょう。
1-4. 自己評価よりも低く評価され、その理由が分からない(22.9%)
4位は「自己評価よりも低く評価され、その理由が分からない」です。前述の3位の不満と類似していますが、「低い評価の理由がわからない」というのが特徴です。
人事制度に対して非常に強い不満を抱くきっかけとなるのは「自分が低く評価されたとき」です。
「なぜ、この評価なのか?」という問いに対して、納得できる答えが得られないと、従業員は不満を募らせていきます。
「本人の自己評価」と「企業側の評価」のギャップが大きい上に納得感がなければ、それは不満のタネとなります。
1-5. 評価結果が昇進、昇格に結びつく制度ではない(22.0%)
5位は「評価結果が昇進、昇格に結びつく制度ではない」です。これは、人事制度の「設計」の問題といえるでしょう。
人事制度は【①等級制度 ②評価制度 ③報酬制度】の3本柱から成り立っています。

【②評価制度】が、昇進や昇格について定めた【①等級制度】と連動していなければ、それは従業員の不満になります。
詳しくは後ほど「3. 人事制度に不満が出る3つの原因と対策方法」で解説しますが、「人事制度の3本柱をいかにバランスよく設計するか」の重要性が示唆されています。
1-6. 評価結果が昇給に結びつく制度ではない(21.4%)
6位は「評価結果が昇給に結びつく制度ではない」です。
これも、5位の理由と同じく人事制度の設計上の問題です。人事制度の3本柱のうち【③報酬制度】が、昇給について定めた制度です。
【②評価制度】と【③報酬制度】が連動していなければ、「せっかくがんばって高評価を得たのに、給料は変わらないのはおかしい」と、従業員は不満を抱きやすくなります。
1-7. 会社の定める評価指標が現実に即していない(20.6%)
7位は「会社の定める評価指標が現実に即していない」です。
例えば、以下のケースが考えられます。
- 現実的に達成不可能な目標を提示される
- 評価指標が創業時のまま改定されておらず古い
- 業務上の成果を上げることと評価指標を満たすことが連動していない
1位の不満理由として「評価基準が不明瞭」がありました。
一方、この7位の不満理由からは、たとえ評価指標が明確に提示されていても、それが現実に即していなければ不満の原因となることがわかります。
1-8. 評価指標が成果のみで、プロセスへの評価がない(17.5%)
8位は「評価指標が成果のみで、プロセスへの評価がない」です。
この不満は、2018年の調査時点では8位という結果ですが、これから増加する可能性があります。というのも、人事制度のトレンドが「成果主義型」から「役割主義型」へと変遷しているからです。

成果にフォーカスした人事評価よりも「どんな役割を担ったか」という行動プロセスにフォーカスした評価制度を導入する企業が増加しています。
そのような人事制度の導入を自社の魅力としてアピールする企業も多く、新卒社員〜若手社員の間では、「成果主義=古い、役割主義=新しい」という認識が生まれつつあります。
今後、この傾向はさらに強まっていくことが予想されます。
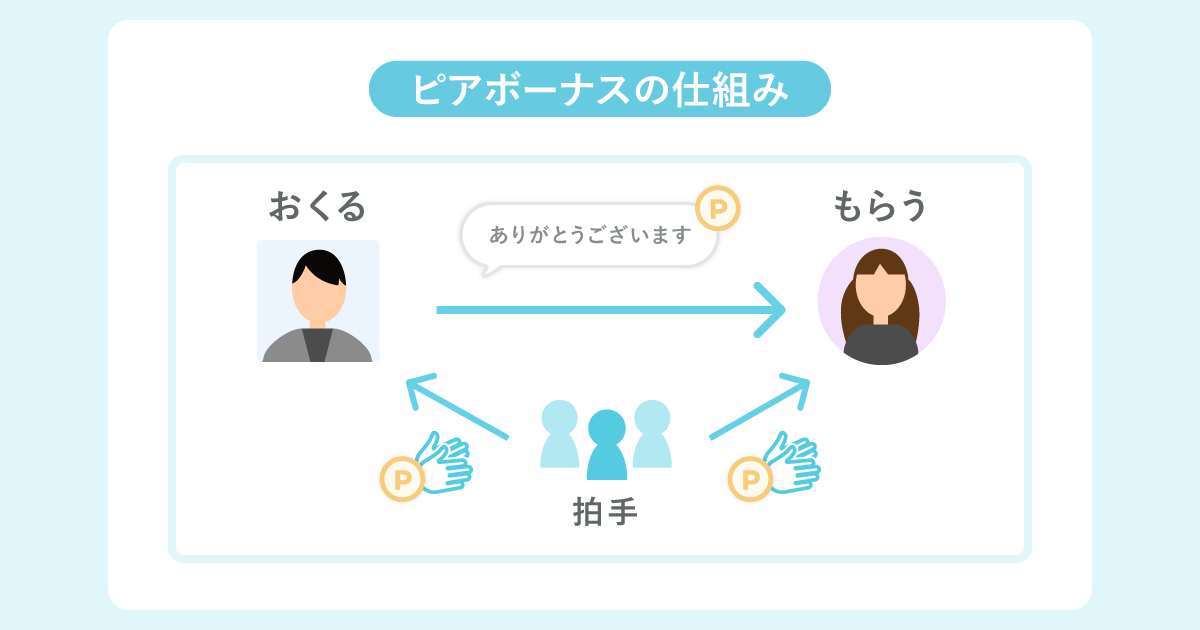
1-9. 評価指標に上層部の意向は反映され、一般社員は反映されない(14.4%)
9位は「評価指標に上層部の意向は反映され、一般社員は反映されない」です。
この不満理由も、8位の「プロセスへの評価がない」と同じく、人事制度トレンドの変遷とともに、増える可能性があります。
従来の評価制度では「上司が部下を評価する」のが一般的でした。しかし、それでは限界があるとして、同僚や部下など他の従業員も評価する制度(「360度評価」などと呼ばれます)が注目を集めています。

※さらに詳しく人事制度のトレンドについて知りたい方は「人事制度2020年代の最新トレンド傾向と事例3社に学ぶ取り入れ方」 も併せてご覧ください。
1-10. 実績に対する評価より、年功序列が優先される制度である(9.2%)
10位は「実績に対する評価より、年功序列が優先される制度である」です。
数は減りつつありますが、それでもまだ、年功序列を基本とする人事制度を継続している企業も多くあります。

年功主義型の人事制度が主流だった1970年代は団塊世代の大卒〜入社の時期にあたり、成果主義型が台頭する1990年代は就職氷河期世代の大卒〜入社の時期にあたります。
長年、企業に貢献してきた自負のあるベテラン社員は、年功序列が優先されるのは当然と考えるでしょう。
一方、若手社員・中堅社員は、成果主義型から役割主義型へと変遷する社会の中で社会人経験を積んでいます。年功序列には不満を抱きやすい傾向があります。
以上が、人事評価制度に従業員が抱えている10個の不満です。今まで気付けていなかった「従業員視点」が、得られたのではないでしょうか。
参考:Adecco Group「人事評価制度」に関する意識調査
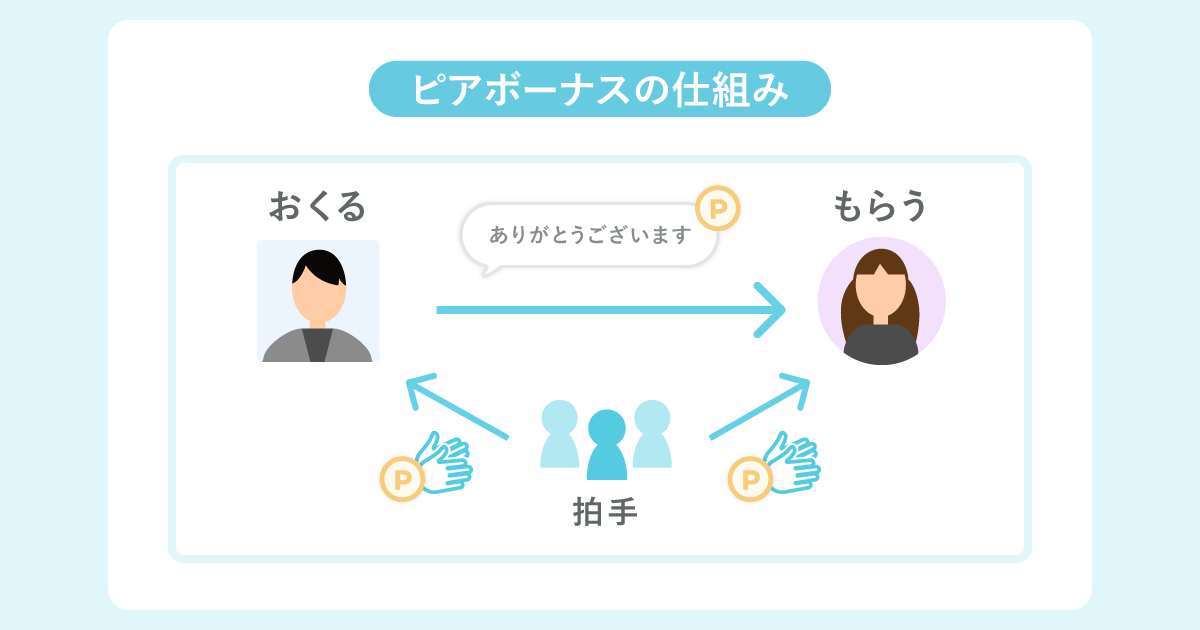
2. 人事制度の不満を放置すると起きる問題

従業員は、人事制度にさまざまな不満を抱えていることがわかりました。それらを放置したら、企業はどうなるのでしょうか。
本章では「人事制度の不満を放置すると起きる問題」にフォーカスしたいと思います。

順に解説しましょう。
2-1. 不満を抱えている従業員のモチベーションが低下する
まず、不満を抱えている従業員のモチベーションが低下します。
実は、不満を口に出している段階では、まだ救いがあります。「何とか現状を変えたい」という意欲が、「不満を口に出す」という行動を引き起こしているからです。
しかし、不満を抱えた状態が続くと、やがて仕事に対してのやる気が失われていきます。
- 不満を伝えてもどうせ変わらない
- がんばって働いても評価されないならムダだ
- 必要最低限の労力しか使いたくない
…といった具合に不満が意欲を損なわせ、やがて勤務態度に表出していきます。
そうなればパフォーマンスが下がりますので、成果は出にくくなります。成果が出ないとさらにモチベーションは下がり…と負のスパイラルの始まりです。
2-2. 不満が伝染し組織全体の生産性が低下する
不満を抱えた従業員のパフォーマンスが低下すれば、組織の生産性は下がりますが、影響はそれだけではありません。怖いのは、不満の伝染による組織全体の生産性低下です。
人事制度への不満を、たった一人の従業員が抱えていることは少ないものです。潜在的に複数の従業員が、同じような不満を抱えています。
そのため、ある従業員の勤務態度が悪くなれば、そこから不満の伝染が起こりやすくなります。それぞれが少しずつ抱えていた「人事制度が不満」という思いが、増幅していくのです。
職場の雰囲気は悪くなり、チームワークが悪化して、組織全体の生産性が低下していきます。
2-3. 離職率が高まり優秀な人材の流出が始まる
最終的には、離職率が高まり優秀な人材の流出が始まります。
「意欲がなく雰囲気の悪い職場は自分に合わない」と感じる従業員たちが、転職を考えるのは当然です。このタイミングで、より魅力的な人事制度をアピールする企業に出会えば、退職を決意する人も出てくるでしょう。
やがて離職率が高まり、優秀な人材が組織から姿を消します。組織の生産性はさらに低下しますので、悪循環が止まらなくなります。
この段階に陥ってからの立て直しは難しく、組織の弱体化が進めば存続さえ危うくなる危機的状況です。
こうなる前に、人事制度の不満を解決する手だてを打ちましょう。
3. 人事制度に不満が出る3つの原因と対策方法

人事制度の不満から組織崩壊が起きるのを防ぐために、本章では「人事制度への不満を解決するための具体的な対策」をお伝えしていきます。
記事の前半で「従業員が人事制度に感じる不満ランキング」をご紹介しましたが、10個の不満をグルーピングして分析すると、以下の通り3つのグループに分類できることがわかりました。
|
不満 |
グループ |
|
評価基準とその運用に原因があるグループ |
|
評価にまつわるコミュニケーションに原因があるグループ |
|
人事制度の設計に原因があるグループ |
つまり、人事制度に不満が出る原因は次の3つに集約されるのです。

それぞれの対策方法をご紹介します。
3-1. 原因①評価基準とその運用
1つめは「評価基準とその運用」に問題があるケースです。
<具体的な不満理由>
- 評価基準が不明瞭
- 評価者の価値観や経験によってばらつきが出て、不公平だと感じる
- 会社の定める評価指標が現実に即していない
- 評価指標が成果のみで、プロセスへの評価がない
- 評価指標に上層部の意向は反映され、一般社員は反映されない
対策として、以下を実施してください。
①評価基準・評価方法の適切性・妥当性を見直す
②評価基準を明文化し社内へ情報公開する
③評価者向けの評価方法マニュアルを作成し研修を行う
評価者によって評価に違いが出てしまうことを「評価エラー」と呼びますが、評価基準・評価方法の設定が抽象的であるほど、評価エラーが起きやすくなります。できる限り具体化することが必要です。
評価基準は、組織全体に浸透している必要があります。明文化して、社内へ共有しましょう。オープンな運用を心掛けることが大切です。
さらに、評価をする「評価者」用のマニュアルを作成して、評価方法に関する研修を行いましょう。どのようなシーンで評価エラーが起きやすいのかなどをレクチャーし、評価する側の成長を促します。
組織全体で正しい評価が行われるよう導くことで、不満の軽減を図っていきましょう。
3-2. 原因②評価にまつわるコミュニケーション
2つめは「評価にまつわるコミュニケーション」に問題があるケースです。
<具体的な不満理由>
- 評価結果のフィードバック、説明が不十分、または仕組みがない
- 自己評価よりも低く評価され、その理由が分からない
人事評価制度は、「評価者が評価を実施する」というステップだけ行っても、機能しません。評価の結果を従業員に対してフィードバックするからこそ、成長を促すことができるのです。
対策として「評価した結果を、本人へどのようにフィードバックするのか」をルール化しましょう。
例えば「フィードバック用の評価シートを作成する」「シートを元に上司と部下が半期に1度・1時間の面談を行う」など、具体的な制度として仕組み化しておきます。
その際には「なぜこの評価なのか」を客観的な事実に基づいて明確に説明することが重要です。
明確な説明が難しい場合は、評価基準の方に問題が隠れているかもしれません。評価基準を「評価後に、明確な根拠を説明できる評価基準になっているか?」という視点で、見直してみましょう。
3-3. 原因③人事制度の設計
3つめは「人事制度の設計」に問題があるケースです。
<具体的な不満理由>
- 評価結果が昇進、昇格に結びつく制度ではない
- 評価結果が昇給に結びつく制度ではない
- 実績に対する評価より、年功序列が優先される制度である
対策としては、人事制度の構成要素である【①等級制度 ②評価制度 ③報酬制度】が、相互にバランスよく連携しているかどうか、全体的な見直しが必要になります。
例えば、長年の企業の歴史の中で人事制度の部分改定が重なり、アンバランスになっている箇所はないでしょうか。あるいは、業務内容の変化とともに評価制度のみが進化して、等級制度や報酬制度の変更が追いついていない面はないでしょうか。
従業員にとって「評価の結果が報酬に反映されるかどうか」「昇級に結びつくかどうか」は、とても重要なポイントです。制度の一部分に着目するのではなく、大局的な視点で人事制度全体をチェックしましょう。
※さらに詳しく人事制度の設計について知りたい方は「人事制度を設計する手順とは?会社を成長させる戦略的やり方と注意点」 も併せてご覧ください。
4. 人事制度の不満へ対処する際の注意点

最後に「人事制度の不満へ対処する際の注意点」を2つ、お伝えしたいと思います。
4-1. 一部のモンスター社員(クレーマー)に振り回されない
1つめは「一部のモンスター社員(クレーマー)に振り回されない」ことです。
人事制度を構築する上で、従業員の「真の声」に耳を傾けることは非常に重要です。しかしながら、中には「不満を言うこと自体が目的」になっているモンスター社員が混ざっていることがあります。
大元をたどれば、人事制度の役割は「企業が目指す方向へ従業員をマネジメントすること」にあります。モンスター社員の不満に振り回されて、企業としての軸がブレては本末転倒です。
あくまで経営理念に基づいて、ときには企業としての姿勢を毅然と示すことも必要になります。
「真の声」と「モンスター社員の声」を正しく聞き分けることには、人事担当者としての高度なスキルが求められます。誤った判断をしないよう、丁寧なヒアリングを繰り返し十分な情報収集を行って、実態の把握に努めてください。
4-2. 大局的な視点で対応する(満足度上昇のみを目的としない)
2つめは「大局的な視点で対応する」ことです。より具体的にいえば「従業員の満足度上昇のみを目的としない」ということです。
人事制度には「アメとムチ」の一面があります。ごく端的にいえば、企業の業績に貢献した従業員は報酬が上がり、そうでない従業員は下がるという仕組みです。
組織にとってマイナスとなる不満は排除すべきですが、仮に従業員の満足度のみを追求する姿勢で人事制度を改革すれば、今度は業績とのバランスが取れなくなるリスクが出てきます。
常に経営方針と照らし合わせつつ、大局的な視点で組織の全体像を捉え、業績と従業員の満足度のバランスが最適化されるポイントを探っていきましょう。
5. まとめ
従業員が人事制度に抱く不満のうち、多いのは「評価制度」に対する不満です。【62.3%】が評価制度に対して不満を抱えているというデータがあります。
不満を放置したときに考えられるリスクは、以下の通りです。

不満の原因は、次の3つに大別されます。

原因別に、次の対策を行うことで、従業員の不満を軽減させることができます。

注意点として、 一部のモンスター社員(クレーマー)に振り回されないこと、大局的な視点で対応する(満足度上昇のみを目的としない)ことを心掛けてください。
人事制度の「不満の中身」に具体的に着目してみると、今までとは違った視点で、自社の人事制度を見つめなおすことができます。ぜひ、従業員の不満軽減を通して組織の生産性を高め、企業成長の原動力としていきましょう。


