
「心理的安全性(Psychological Safety)」とは、組織の中でメンバーそれぞれが、気兼ねなく自分の意見や気持ちを発信できるかどうかを表した概念のことです。
例えば私たちは以下のように、人からどう思われるか不安に感じることがあります。
- 上司とは反対の意見を言いたいけれど、言ったら評価が下がるのではないか
- 失敗して迷惑をかけたら、チームのメンバーに嫌われるのではないか
- 会議の内容が理解できないけれど、質問したらバカにされるのではないか
“心理的安全性が高い環境”とは、このような不安を感じることなく、メンバー同士で全員が何でも気兼ねなく発言、質問できるチームの状態を指します。
「心理的安全性が高いチームは成果を出しやすい」ことが研究により明らかになり、「心理的安全性の概念を取り入れたい」と考える経営者やマネジャーが増えています。
しかし、心理的安全性について正しく理解している人は、ほんの一握りです。
多くの人が「心理的安全性」という言葉の表面的なニュアンスだけを捉えて、【心理的安全性の高い組織=ぬるい組織】であると勘違いをしています。
例えば、
- プレッシャーがなく精神的に安心できる職場
- アットホームで厳しさのない雰囲気
- スタッフの仲が良く結束力の高いチーム
これらは、心理的安全性の本質とは異なっています。誤った解釈では、心理的安全性による本来のメリットを組織にもたらすことができません。
そこでこの記事では、以下を重点的に解説します。
①心理的安全性とは?勘違いしやすい本来の意味
②心理的安全性を人材マネジメントに取り入れるメリット
③心理的安全性を高める方法
最後までお読みいただければ、心理的安全性の概念を深く理解でき、チーム内外のパフォーマンス向上にも繋がるでしょう。
関連記事:心理的安全性とは?高める5つの方法とメリットを解説
心理的安全性が注目を集める理由
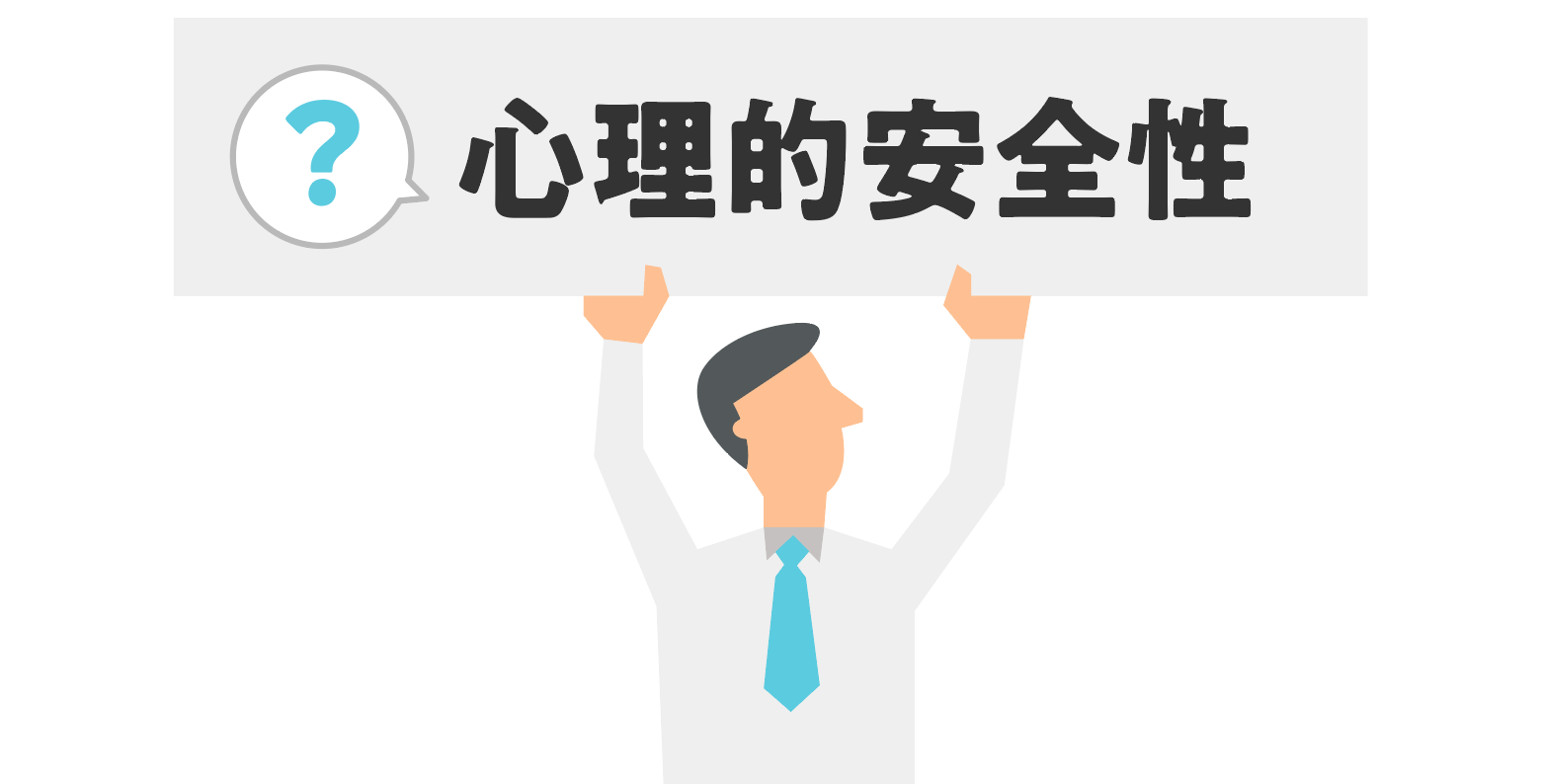
ハーバード大学教授により提唱され、Googleの調査により注目を集める
チームの心理的安全性という概念は、ハーバード大学のエイミー・C・エドモンドソン教授が1999年に発表した論文「Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams」の中で初めて提唱されました。
そこでは、心理的安全性とは「対人リスクをとるのに安全な場所であるとの信念がメンバー間で共有された状態」と定義しています。
その後、心理的安全性が注目を集めるようになったのは、Googleが生産性の高いチームの共通点を発見すべく約4年の歳月をかけて実施した調査「プロジェクト・アリストテレス」にて「心理的安全性は、チームの生産性を高める上で最も重要な要素である」という結論が発表されたためでした。2015年のことでした。
▼チームの効果性に影響する因子(重要な順)
Googleの調査によれば、生産性の高いチームには上記の5つの要因があり、この中で圧倒的に重要なのが心理的安全性だというのです。
「心理的安全性」を軸に比較した場合、チームには以下のような明確な違いが見られたそうです。
心理的安全性の高いチームのメンバーは、Google からの離職率が低く、他のチームメンバーが発案した多様なアイデアをうまく利用することができ、収益性が高く、「効果的に働く」とマネージャーから評価される機会が 2 倍多い、という特徴がありました。
優秀な人材ばかりが集まる世界有数の先進企業が出したこの結論に、世間は大きく注目しました。
選りすぐりの人材が集まるGoogle社にとって、生産性を決定付ける上で最も重要なのは、メンバー1人ひとりの能力よりも「心理的安全性」だというのです。
すなわち、個の力が圧倒的に強い状態よりも、チームの「心理的安全性」が高い状態のほうが、パフォーマンス向上に繋がるということです。
心理的安全性が高い組織とは
「心理的安全性」のある状態とは、4つの対人リスクを感じずにすむチームの状態
冒頭でもお伝えした通り心理的安全性とは、「組織の中でメンバーそれぞれが、気兼ねなく自分の意見や気持ちを発信できるかどうか」を表した概念です。
エドモンドソン教授は「対人リスクをとるのに安全な場所であるとの信念がメンバー間で共有された状態」と定義しています。
ここでいう「対人リスク」とは、具体的に以下4つです。
|
心理的安全性に関わる4つの対人リスク |
例 |
|
無知だと思われる不安 |
「自分だけ質問したら、無知だと思われるかもしれない」 |
|
無能だと思われる不安 |
「失敗したら、無能だと思われるかもしれない」 |
|
ネガティブだと思われる不安 |
「他の人の意見を批判したら、ネガティブな人格だと思われるかもしれない」 |
|
邪魔だと思われる不安 |
「手伝ってほしいと頼んだら、邪魔だと思われるかもしれない」 |
心理的安全性が高い環境では、これらの不安を感じずに済むため、堂々と質問したり、チャレンジしたり、反対意見を言ったり、支援を求めたりできます。
逆に心理的安全性が低い環境では、不安が障壁となって、本来は組織にとって必要な言動であったとしても、抑制されてしまいます。
不安が大きいほど心理的安全性は低く、不安が小さいほど心理的安全性は高くなるという関係性にあります。

心理的安全性の概念を理解する上で重要なのは、心理的安全性とは
「対人リスクを取れるかどうか(=不安を感じずに行動できるかどうか)」を表した指標であり、
心理的安全性が低いと組織にとって不利益なことが起きるという事実です。
具体的にどのようなことが起きるのか、次項で事例をご紹介します。
心理的安全性が低い組織の弊害とは
エドモンドゾン教授は著書の中で、心理的安全性が低い組織の悲劇として2003年のコロンビア号の空中分解事故におけるNASAを挙げています。
コロンビア号が空中分解する前、NASAにはコロンビア号の問題に気付いたエンジニアがいました。メールで直属の上司に報告したのですが、取り合ってもらえませんでした。
直属の上司は、上層部に報告することなく、自分のところでエンジニアの報告を止めてしまいました。
その後、エンジニアは幹部が出席する定例会議で報告しようかと迷います。しかし、懸念を口にするのは、NASAではキャリアをふいにすることにほかならないと思い、話すのをやめてしまったのです。その結果、7名の宇宙飛行士が犠牲となる大事故に発展してしまいました。
後に、エンジニアは定例会議で懸念を述べなかった理由を、以下のように語ったそうです。
「そんなことはできませんでした。
私がいるのはピラミッドのずっと下のほう……。
そして彼女(幹部)ははるか上の人ですから」
また、エンジニアからの報告を上層部に報告しなかった直属の上司は、次のように述べています。
たびたび言われていたのです。
「自分よりはるかに地位の高い人に意見を具申するなどもってのほかだ!」
このように、心理的安全性の欠如によりミスの報告が遅れたり、懸念事項を早い段階で指摘することが難しくなったりします。よく似たことが日常茶飯事で起きている企業も多いのではないでしょうか。
心理的安全性という概念は、このような悲劇を防ぐためにあると理解しておきましょう。
心理的安全性が「高い職場」「低い職場」の特徴
ここで、心理的安全性が「高い職場」と「低い職場」の特徴をまとめておきましょう。
|
心理的安全性が高い職場 |
・率直に本音で議論ができる ・厳しいフィードバックを与えることができる ・反対意見が歓迎される ・失敗を恐れずにチャレンジができる ・革新的なアイデアや斬新な意見が活発に生まれる |
|
心理的安全性が低い職場 |
・事なかれ主義の雰囲気が流れている ・会議で沈黙がよく起きる ・空気を読むことが求められる ・同調圧力が起きやすい ・新しい意見や他の人と違う意見が潰されやすい ・トップの意見に合わせるイエスマンが多い |
この表から押さえておきたいポイントは、心理的安全性が高い状態≠プレッシャーや責任感が低いという点です。
むしろ、心理的安全性が低い職場の方が、プレッシャーや責任感が低いケースもあります。心理的安全性が極端に低くなると、チームメンバーは何もせず何も言わなくなるからです。
逆に心理的安全性が高い職場では、厳しい議論や難しいチャレンジが可能になり、チームメンバーはプレッシャーに強くなる傾向にあります。
「心理的安全性」と「信頼」「尊敬」の違い
心理的安全性は、チームメンバーが信頼し合い、尊敬し合っているときに生まれます。その意味では、心理的安全性の中には、信頼と尊敬が含まれていると言って良いでしょう。
ただし、学術的には「信頼」「尊敬」は2者の関係性にあるもの、エドモンドソン教授が提唱した「心理的安全性」はチームや組織といった集団レベルの現象、という違いがあります。
|
信頼・尊敬 |
2者間の関係性 |
|
心理的安全性 |
集団レベルの現象 |
つまり、信頼や尊敬は、ある2人の従業員の間に存在するものです。一方、チームの心理的安全性は、従業員個人ではなく、チーム・部署・組織など集団単位に存在するものです。
例えば、「従業員Aさんの心理的安全性が高い」という言い方はせず、「●●部署の心理的安全性が高い」という言い方をします。
心理的安全性を高める4つのメリット

心理的安全性を人材マネジメントに取り入れたいと考える企業が増えています。
組織の心理的安全性を高めるメリットは、大きく分けて4つあります。
①イノベーションが促進される
②問題解決がスピードアップする
③組織が間違った方向へ進むのをくい止められる
④離職率の低下に繋がる
順に解説します。
イノベーションが促進される
1つめのメリットは、イノベーションが促進されるという点です。
心理的安全性が高い職場では、斬新な意見を発信しやすくなります。「こんなことを言ったら、変に思われるのでは?」という不安がないので、一見奇抜に思えるようなアイデアもミーティングで共有しやすくなるのです。
従来なら「前例がない」「コストがかかる」「実現できるわけがない」などと一蹴されていた意見も拾い上げることができるため、差別化された革新的な製品やサービスが生まれやすくなります。
問題解決がスピードアップする
2つめのメリットは、問題解決がスピードアップするという点です。
多くの人は「トラブルはできるだけ避けたい」という心理が働いて、問題に気付いても正面から向き合うことができません。時間が経過し、問題が大きくなってからようやく解決に乗り出すので、対応が後手に回りがちです。
心理的安全性が高い職場では、問題に気付いたらその場で声を挙げ、すぐに解決に向けて行動する従業員が増えます。
結果、問題解決のスピードがアップして、トラブルや変化に強い組織を作ることができるのです。
組織が間違った方向へ進むのをくい止められる
3つめのメリットは、組織が間違った方向へ進むのをくい止められるという点です。
組織とは、結束力が高いほど良いとも言い切れません。その結束力があだとなり調和を乱す異論は唱えづらくなって、組織が間違った方向へ突っ走ってしまうことがあります。
心理的安全性が高い職場では、各従業員は、自分の感じたままを発言できます。組織の空気感に抑圧されて、自分の意見を飲み込む必要はありません。
たとえ相手が自分の上司や企業のトップだったとしても、間違っていると思ったときには、率直に伝えることができる。それは、組織が間違った方向に進みそうになったときのブレーキ機能となります。
離職率の低下に繋がる
4つめのメリットは、離職率の低下に繋がるという点です。
心理的安全性が低い状態の場合、
・わからないことがあっても聞きづらく、業務の進捗が遅れる
・新しい意見や他の人と違う意見が潰されやすいため、会議で発言しづらくなる
といったことが生じてしまいます。
一方、心理的安全性が高い職場では疑問点や相談事、懸念事項などを気軽に伝えやすいため、個人および組織の成長を促進することができます。その結果、社員がリーダーシップを発揮しやすくなり、自己効力感の向上や離職率低下にも繋がります。
課題はマネージャーの負担増

心理的安全性は、組織力を高める上で大変メリットの多い概念です。しかしながら、心理的安全性の高い組織を作る上では、課題も存在します。
心理的安全性は、自然に高まることはありません。心理的安全性を高めるためには、マネジャー(チーム・リーダー)の在り方がカギを握ります。
マネジャーの態度、部下との接し方、コミュニケーションの量などが、チームの心理的安全性に直結するからです。
特に、心理的安全性が低いチームから高いチームへと変革していく時期においては、マネジャーの負担が増えるばかりで、心理的安全性を高める成果の手応えが、感じにくいかもしれません。
心理的安全性は、チーム内のコミュニケーションによって徐々に高まっていくものです。即効性を求めるのではなく、じっくり取り組む余裕が必要です。
心理的安全性の高め方
では具体的に、心理的安全性を高めるためには、何から始めたらよいのでしょうか?
「チームメンバーが対人リスク(=無知・無能・ネガティブ・邪魔と思われる不安)を感じない状態を作る」、これが心理的安全性を高めるということだとすれば、鍵を握るのは「マネージャー」の存在です。
メンバーから高める努力をすることももちろん無駄ではありませんが、チームリーダーが心理的安全性を壊すような言動を繰り返していたら、なかなか心理的安全性は高まりません。
なので、まずはチームのマネージャーが心理的安全性の重要性を理解し、高めるための言動を増やしていくことが重要となります。
本家Googleではどんなことをしているのか?
心理的安全性の高いチームを作るために、全世界共通のマネジャー研修が行われ、チームの心理的安全性を高めるさまざまな仕組みが導入されています。
Googleのマネジャー研修内容は非公開ですが、Googleのホームページで公開されているのが「心理的安全性を高めるためにマネージャーにできること」という資料です。心理的安全性を高めるために何をしたら良いのか考える上で、有益なヒントが詰まっています。
また、Googleが導入している仕組みの一例を下記表にまとめました。
|
1 on 1 |
マネジャーは週に1回1時間、必ず全メンバーと個人面談する |
|
ピアボーナス |
チームメンバー同士が感謝の気持ちを込め、ボーナスで贈り合う。日本の代表的なピアボーナスⓇサービスは「Unipos」などがある。 |
|
ライフ・ジャーニー |
人生のターニングポイントにおける[①行動 ②その意図 ③味わった感情]をチームメンバーと共有する |
マネジャーがチームづくりをリードしながら、それを補強する仕組みを導入しているのが、Google流のやり方といえるでしょう。
明日から始められる!心理的安全性を高める実践方法
では、マネージャーがすぐに始められる心理的安全性を高める方法には、どんなものがあるのでしょうか?
マネジャーがチームに弱みをさらけ出す
リーダーは常に強く、決断力に溢れていなければならない。
そんな常識は薄れつつありますが、とはいえ「弱みをさらけ出す」ということには抵抗感があったり、難しさを感じているマネージャーも多いのではないでしょうか。
そこを一歩越え、まずリーダーから「わからないことはわからない(無知だと思われる不安)」「できないことはできない(無能だと思われる不安)」と言うことで、チームの雰囲気は一気に変わっていきます。チームの雰囲気や無言のルールは、リーダーの言動によって影響を受ける部分がとても大きいからです。
そしてそれはもちろん「開き直る」ということではありません。
自分の無知や無能をさらけ出し、その上で皆に協力を求め、解決策を探る。何かわからないことやできないことがあっても、隠さなくていい。その分は皆で考え解決していこうという姿勢をチームに浸透させることが目的です。
マネジャー(上司)自身が自己受容する
先の述べた「弱みをさらけ出す」と連動するのが「自己受容」です。
弱みをさらけ出す上で大切なのは、欠点も含めて、自分自身を認められているかどうかです。そうした自己受容がないと、弱みをさらけ出すことはなかなか難しいですし、苦痛でしかならなくなります。
マネージャー自身が自分と向きあい、ダメな自分も受け入れられてこそ、弱みを他者に見せ、そこから前向きな解決策を探ることができるのです。
※心理的安全性を高めるための具体的な方法については「心理的安全性の高いチームの作り方!今すぐ使える8つの実践方法」 にて詳しく解説しています。こちらはマネージャーに限らずメンバーから始められる実践アイディアも多数取り上げているので、ぜひ合わせてご覧ください。
自身のチームの心理的安全性を測定する7つの質問

ここで気になるのが「自分のチームの心理的安全性は、現状どのくらいなのだろうか?」ということではないでしょうか。
チームの心理的安全性を測るには、サーベイやツールなど様々な手段がありますが、エドモンドソン教授によれば、以下7つの項目を問うことで、ある程度のチームの心理的安全性レベルを把握できるようです。
1.チームの中でミスをすると、たいてい非難される。
2.チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。
3.チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある。
4.チームに対してリスクのある行動をしても安全である。
5.チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい。
6.チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない。
7.チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる。
まとめ
心理的安全性とは「組織の中でメンバー一人ひとりが、気兼ねなく自分の意見や気持ちを発信できるかどうか」を表した概念です。
心理的安全性が高い職場は社員同士で信頼関係がある状態のため、反対意見を率直に伝えたり、失敗を恐れずにチャレンジしたり、助けを求めたりすることが可能になります。
逆に心理的安全性が低い職場では、人からマイナスの評価を受ける不安によって行動が起こせなくなり、組織が間違った方向へ進んでしまうリスクがあります。
心理的安全性を人材マネジメントに取り入れることには以下のメリットがあります。
①イノベーションが促進される
②問題解決がスピードアップする
③組織が間違った方向へ進むのをくい止められる
④離職率の低下に繋がる
一方、デメリットとしては、心理的安全性の高いチームが作れるかどうかはマネジャーの手腕にかかっており、マネジャーの負担が大きくなる点が挙げられます。
心理的安全性をいち早く人材マネジメントに取り入れたのがGoogleで、Googleのホームページではそのマネジメント方法の一部が公開されています。心理的安全性の理解を深めるために、一読しておくと良いでしょう。
さらに詳しく心理的安全性について知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。




