
「一体感の醸成」とは、それぞれが別の方向を向きまとまりの無い状態だったチームや組織を、時間をかけてひとつにすることを意味します。
組織においてこの「一体感の醸成」がなぜ必要かというと、以下のような効果を生み出すからです。
一体感の醸成が進むと…
・コミュニケーションが活発になり、職場の雰囲気が良くなる
・会社への連帯感が高まり、従業員の主体性が生まれる
・ 働くモチベーションが上がり、生産性が向上する
・組織が活性化し、売上や利益が向上する
最終的には、業績アップや、従業員満足度(ES)向上にもつながります。
一方で、「一体感の醸成」が上手く行っていない組織では、次のような状況に陥りがちです。
・なんとなく社内の雰囲気が良くない
・社員同士のコミュニケーションがあまりなく、モチベーションが低い
・最低限の仕事だけしていれば良いという、受け身の従業員が多い
もしあなたのチームがこのような状況にあるなら、それは危険信号です。
従業員のモチベーションが低いということは、生産性のレベルが低い状態にあり、さらに離職する可能性が高まっている危険性があります。
現状を打開し、良いチームを作り上げたいなら、ぜひこの記事を読むことをおすすめします。
この記事では、「一体感の醸成」を深く理解するために、以下の内容を説明します。
◎「一体感の醸成」が示す意味
◎「一体感の醸成」が必要とされる状況
◎「一体感の醸成」で得られるメリット
◎「一体感の醸成」を進める3つの方法
◎「一体感の醸成」を進める4つの企業事例
一体感を醸成すると得られるメリットは、職場の雰囲気が良くなるだけではありません。従業員に主体性が生まれたり、モチベーションや生産性が向上したり、売上や利益が向上したり…、良い影響がどんどん生み出されていきます。
本記事を最後までお読みいただければ、チームに一体感を作り出す方法が分かり、早速自社内でも取り入れる準備ができていることでしょう。ぜひ参考にしてみてください。
1. 「一体感の醸成」とは一体感を作り出すこと

「一体感の醸成」という言葉を初めて聞いたとき、「なんだか難しそうだな」と思った方もいるかもしれません。しかし難しく捉える必要はなく、単に「一体感を作り出すこと」という意味です。
「醸成」という言葉の本来の意味は、お酒や醤油などを作る工程で原料を発酵させることです。そこから転じて、ある状態や気運などを徐々に作り出すことという意味もあります。
つまり「一体感の醸成」とは、まとまりの無い状態のチームから、時間をかけて一体感を作り出すことを意味します。
それでは、なぜ職場には一体感の醸成が必要なのか、原点に立ち返ってみましょう。
2. 一体感の醸成が必要とされる状況

同じ目標に向かって仲間が主体性を持って進んでいく組織づくりには、一体感の醸成が不可欠です。なぜならば、一体感のない職場では数々の「良くない状態」に陥りがちだからです。
職場の一体感がないと、以下のようなことが起きます。
◎職場でのコミュニケーションが不足し、雰囲気が良くない
◎働くモチベーションや生産性が低い従業員がいる
◎会社の方針や指針が現場まで浸透していない
◎他部門との間に壁があり、あいさつも少ない
◎主体的に動けず、指示を待つ社員が多い
◎会社にあまり興味がなく、最低限の働きしかしない従業員がいる
このような状態が続くと、従業員のモチベーションも生産性も上がらないため、売上や利益を上げることができず、最悪の場合は業績にも悪影響を及ぼします。
もしあなたの職場でも上のような状態が続いているなら、一体感を作り出す施策を考えてみた方が良いでしょう。一体感を高めていくと、次のようなたくさんのメリットがあります。
3. 一体感を醸成すると得られるメリット
チームの一体感を醸成すると、職場の雰囲気が良くなるだけでなく、従業員のモチベーションや生産性が上がり、最終的には業績を押し上げる効果まで期待できます。

3-1. コミュニケーションが活発になり雰囲気が良くなる
同じ職場で働く仲間との一体感を感じられるようになれば、コミュニケーションが活発になり、職場の雰囲気が明るくなります。信頼関係を築ければ、画期的なアイデアも出やすくなり、課題を一人で抱え込まずに相談できるようになります。
同じ目標に向かって進むチームの一員として、従業員同士が助け合い、役割分担をしながら仕事を進めていける環境を実現できます。
3-2. 会社への連帯感が高まり主体性が生まれる
一体感が深まり、チームの目標や会社の経営方針などを理解することで、自分もチームの一員であるという連帯感が生まれてきます。
連帯感が生まれると、自分が会社のためにできることは何かを考えたり、自分の存在意義を見出したりするようになり、主体性が生まれます。今まで受け身で言われたことしかしなかった社員が、自主的に動ける社員へと変化します。
3-3. 働くモチベーションが上がり生産性が向上する
一体感を感じながら働ける職場では、働くモチベーションが上がり、より前向きな姿勢を持って仕事に取り組めるようになります。
集中して仕事に取り組むことができるため、生産性が向上し、労働時間削減にもつながるでしょう。また、同じチーム内にモチベーションの高さが伝播し、職場やより良い環境に変化していきます。
3-4. 組織が活性化し売上や利益が向上する
一体感の醸成により組織が活性化すると、顧客へのサービスの質も向上します。顧客へのサービスがより良いものになれば、顧客満足度が上がります。
その顧客がリピーターやプロモーター(商品やサービスを勧めてくれる顧客)になれば、売上や利益向上にもつながります。
職場の雰囲気が良くなる→連帯感や主体性が高まる→モチベーションや生産性が上がる→売上や利益が向上する、というステップで一体感の醸成が進んでいけば、最終的には、会社の業績アップや従業員満足度(ES)の向上にまで発展する可能性を秘めているのです。
4. 一体感を醸成する(高める)方法

一体感を醸成することで生み出せるメリットについて理解できたでしょうか。組織のあちこちで一体感の醸成が進めば、会社全体に良い影響を与え、顧客にも良いサービスを提供できるようになり、業績も向上します。
ここからは具体的な方法について見ていきましょう。一体感を醸成するには3つの方法があります。
会社を良い方向に導くためにも、これらの方法を実践してきましょう。
【一体感を醸成するための方法として注意したいこと】
一体感の醸成は、ある程度の時間をかけて行うものです。従業員を仲良くさせるには「飲み会を開催すれば良い」「派手なキックオフミーティングを開催すれば良い」では済みません。
確かに、従業員同士が仲良くなるきっかけ作りにはなるかもしれません。しかし会社が用意した器では、お祭りイベントで終わってしまい、翌日には元通りです。
従業員の納得感を引き出しながら、自発的に動くように仕掛ける必要があります。
4-1. 会社の理念やビジョンを従業員に浸透させる
あなたの職場の従業員は、会社の経営理念やビジョン、行動指針を理解した上で働いているでしょうか。一体感が十分に醸成されている組織では、経営者はもちろん従業員もしっかり「何のために働くか」「自分がするべきことは何か」を理解して働いています。
例えばクレドカードなどで、経営理念やビジョン、従業員のミッション、行動指針などを広く浸透させれば、従業員全員が同じ方向を向くようになり、一体感や連帯感を生むことができるのです。
また、従業員が仕事を進める上で迷いが生じた時にも、その内容に合った行動を取ることができます。
企業理念や行動指針についてより深く理解したい方には、以下の記事もおすすめです。
→ 行動指針とは?企業理念・行動理念との住み分けと作り方&定着方法
→ クレドの意味とは?クレドカードを作成する際の手順と導入事例
従業員同士の人間関係が冷めているようでは、一体感は生まれません。従業員同士のコミュニケーションが密になり、お互いの信頼関係をうまく構築できれば、同じ組織で働く仲間としての一体感が生まれます。
もちろんトップダウンで人間関係を良くさせようとしても限界があります。例えばSNSやチャットツールを導入するなど、時間をかけてコミュニケーションを活性化させる仕組みを導入する方法が良いでしょう。
社内コミュニケーションについてより深く理解したい方には、以下の記事もおすすめです。
→ あなたの会社は大丈夫?社会心理学者スタイナーが説く社内コミュニケーションの重要性
なかなか組織に一体感が生まれないのは、会社の業績などに興味がなく、自分事と感じていない社員が多いことが原因かもしれません。それを自分事にできれば、社員が連帯感や責任感を感じ、自発的に行動できるようになります。
会社にもっと興味を持ってもらうためには、会社の情報を開示して社員と共有する方法が最適です。売上の進捗や業界のトレンドなどを管理職だけでなく一般の従業員にも共有するのです。
自分の働きが会社の経営に影響している実感があれば、従業員の働きぶりや組織に対する思いも変わってくるでしょう。
会社情報の透明化について興味がある方には、以下の記事もおすすめです。
→ ティール組織とは?5つの組織タイプとメリット・事例・おすすめ書籍
ここからは、一体感を醸成することを目的に行われた実際の企業事例を4つ紹介していきます。
大規模な投資が必要な事例もありますが、すぐに取り組みを始められる事例もあります。自分の組織にはどのように導入できるか、イメージしながら読み進めてみてください。
5-1. クレドカードで会社の考えを従業員に浸透(常磐興産株式会社)
 出典:常磐興産株式会社
出典:常磐興産株式会社
クレドカード(企業の信条や行動指針を記したカード)を全従業員に持たせ、会社の方向性や思いを浸透させる取り組みは、リッツ・カールトン、ジョンソン・エンド・ジョンソンなどが有名です。ここでは、スパリゾートハワイアンズを手掛ける常磐興産株式会社の事例を紹介します。
スパリゾートハワイアンズは、2011年の東日本大震災で壊滅的な被害を受けながらも、炭鉱時代の「一山一家」の精神をバネに復興を遂げました。「一山一家」とは、同じ山で働く人はみんな家族であるという考え方です。
<一体感の醸成のために実施したこと>
・ビジョンやミッション、行動指針を記したクレドカードを全社員に配布
・ミッションは「世界一”ワクワク”する楽園を目指す」という内容
<結果>
・迷ったときはクレドカードを見て、原点に立ち戻れるようになった
・何のために働いているのか、従業員が意識できるようになった
会社と従業員が同じビジョンやミッションを共有することで、一体感の醸成が進んだといえる事例です。
参考:DIAMOND online「上からの指示がなくともお客様を助けられた理由は創業時の「5つの精神」にあった」/キャリマガ「おもてなしのプロを育てる!常磐興産・ハワイアンズ流の人財育成術」
5-2. 感謝を送り合うツールで一体感スコアが大幅改善(株式会社マクロミル)
 出典:株式会社マクロミル
出典:株式会社マクロミル
マーケティングリサーチのリーディングカンパニーである株式会社マクロミル。同社は担当領域が異なる部門の間で、従業員の一体感が薄れていることに悩んでいました。それを解決したのが、ピアボーナスⓇ「Unipos」というツールです。
Uniposは、従業員同士が感謝・称賛の言葉と少額のインセンティブを送り合える仕組みです。
<一体感の醸成のために実施したこと>
・リアルタイムで感謝の気持ちを送り合える「Unipos」を導入
<結果>
・Uniposを通じて、感謝のメッセージが飛び交うようになった
・成果やスキルに対する承認欲求が満たされ、社員の働きがいが醸成された
・「一体感」のスコアが大幅に改善された
ツールを導入することで、従業員同士のコミュニケーションが活性化し、ES調査での「一体感」「連帯感」のスコアが5~10ポイントも上昇したそうです。
部門内の人間関係が良好になった他、他部門のメンバー同士がランチに行くなど、新たな交流も生まれました。
参考:Unipos「ES調査での「一体感」スコアを大幅に改善したマクロミルのUnipos活用事例」
5-3. 情報共有で従業員の意欲を引き出す(サイボウズ株式会社)
 出典:株式会社サイボウズ
出典:株式会社サイボウズ
業務改善をサポートするクラウドサービスなどを手掛ける株式会社サイボウズ。同社製品のグループウェアが透明な組織運営を推し進めるツールであることもあり、同社の社内でも情報の透明化がかなり進んでいます。
<一体感の醸成のために実施したこと>
・サイボウズの自社製品であるグループウェアを使って、グループでさまざまな情報を共有
・「サイボウズ式」編集部では、通らなかった企画も、赤入れ原稿も、全て共有
<結果>
・なぜ企画が没になったか、原稿のどこに赤が入れられているのか、必要な時にチーム全員が見られるようになった
・情報格差がなくなり、働くチームメンバーの意欲を引き出せた
・編集長が出社していなくても、業務が回るような仕組みが生まれつつある
・大人数の従業員が、共通の目的に向かって連携を取って動けるようになった
・指示を待つのではなく、より主体的に、意欲的に動くようになった
情報共有を積極的に行うことで一体感が生み出され、従業員みんなが共通の目的に向かえるようになったそうです。さらに、規模が大きくてもスピーディーに連携を取れる組織を実現しています。
参考:NIKKEI STYLE「サイボウズのチーム力に学ぶ 意欲を引き出す情報共有」
5-4. 社員参加型で新オフィスを作り上げた(CBRE株式会社)
不動産賃貸・売買仲介サービスを主軸として事業展開しているCBRE株式会社は、関西支社の移転プロジェクトにあたり、従業員の一体感を醸成するようなオフィスづくりを目指しました。
<一体感の醸成のために実施したこと>
・新しいオフィスのあり方を、社員参加型で話し合って決めた
・移転プロジェクトに、社員全員が関与した
・社内外のコミュニケーションを促進するためのスペースを設置した
・社員の健康に配慮し、スタンディングデスクを導入した
<結果>
・89%の社員が、新しいワークスタイルは従来のものより好ましいと回答した
・78%の社員が、生産性が向上したと回答した
移転後のアンケートで、89%の社員が以前よりもワークスタイルが良くなったと回答しています。さらに、生産性の向上を感じている社員も多い結果となりました。
この事例の一番のポイントは、社員が関与して新しいオフィスの内容を決めたという部分です。一体感の醸成はトップダウンではなかなか進みづらいものです。社員自ら行動することが、社員の自発性を生み、会社やチームの連帯感や一体感を生んだ好事例ではないでしょうか。
参考:ニュースリリース「CBREが特別レポート「組織の一体感を醸成するワークプレイス」を発表」
6. まとめ
本記事では、
◎「一体感の醸成」とは何か
◎一体感の醸成が必要な状況
◎一体感の醸成を行うメリット
◎一体感を醸成する3つの方法
◎一体感を醸成した4つの企業事例
についてお伝えしました。
軽くおさらいをしてみましょう。
一体感の醸成が進むと、以下のようなメリットを生み出すことができ、組織がより良いものになります。

一体感を醸成する(高める)方法としては、以下のような方法があります。
◎会社の理念やビジョンを従業員に浸透させる
◎従業員同士の人間関係をより良くする
◎会社の情報を開示して社員と共有する
そして、これらを体現している4つの企業事例を紹介しました。
一体感は、単に職場の雰囲気を良くするものではありません。従業員のモチベーションを引き出し、生産性や主体性を向上させ、最終的には売上や業績アップにも寄与する大切な要素といえます。
逆に、一体感のない会社は、生産性や主体性、モチベーションが低く、離職率も高い傾向になるでしょう。そのような状態では、売上や利益向上、業績拡大を目指していくのは難しいと言わざるを得ません。
職場の雰囲気を変えて一体感を作り出したい方は、今回説明した3つの方法や4つの企業事例を参考に、施策を行ってみてはいかがでしょうか。

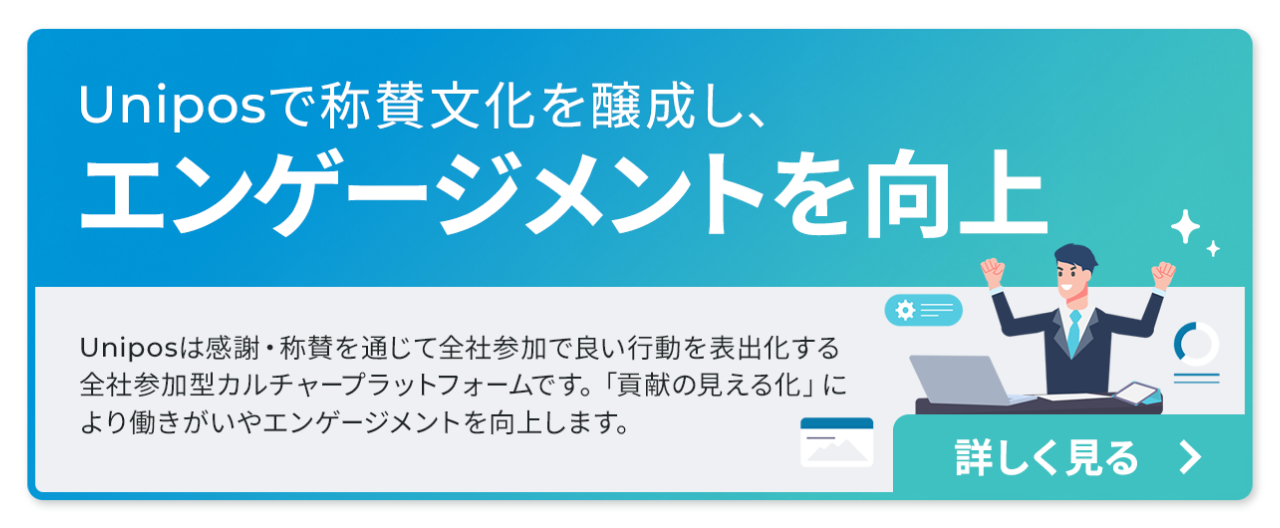
 出典:
出典: